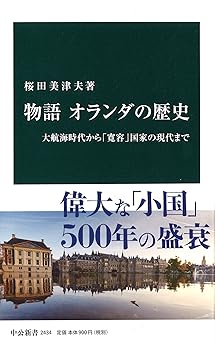レンブラント
17世紀中期のネーデルラントの画家。市民文化の勃興を背景として活躍。
オランダ(ネーデルラント)は16世紀の末に、スペインからの長いオランダ独立戦争の結果、ようやく1609年、事実上の独立を達成してネーデルラント連邦共和国となった。そのオランダの事実上の独立とほぼ同じ頃に生まれ、17世紀に活躍し、近代油絵を完成させたと言われる画家がレンブラントである。
レンブラント Rembrandt 1606~69 はライデンの製粉業者の家に生まれ、アムステルダムに出て画家の修行をつんだ。ライデンに戻って画家としてたち、豊かな商人や市の幹部から肖像画の注文を受けて肖像画を描いた。その一つ、『トゥルプ博士の解剖学教室』(1632)で評判をとり、再びアムステルダムに出て肖像画家として活躍した。
レンブラントの活躍は、17世紀のライデンやアムステルダムなどのオランダの商業都市が急成長し、市民に支えられた文化が生まれたことを意味していた。同時にそのころオランダはドイツで始まった三十年戦争、イギリスのピューリタン革命の動乱の影も及んでおり、政治的には不安定な状態が続いていた。
ここには6人の人物がいる。後ろに立つ無帽の召使いを除き、5人が組合幹部であるが、彼らの所属宗派がすべて判っている。左から、カトリック、メンノー派、カルヴァン派(議長)、レモンストラント派、カトリックである。組合幹部が所属宗派を異にしながら、真剣に輸出品の品質管理をしていることがこの絵から見て取ることが出来る。オランダはカルヴァン派の主流派(厳格な予定説を主張)が権力を握っていたとはいえ、同じカルバン派の分派であるメンノー派(穏健派)、レモンストラント派(寛容派)も加わり、カトリックも排除されていなかったという当時のアムステルダムが宗教的対立を越えて商業利益を追求する社会だったことが感じられる画面となっている。<桜田美津夫『物語オランダの歴史』2017 中公新書 p.77>
レンブラント Rembrandt 1606~69 はライデンの製粉業者の家に生まれ、アムステルダムに出て画家の修行をつんだ。ライデンに戻って画家としてたち、豊かな商人や市の幹部から肖像画の注文を受けて肖像画を描いた。その一つ、『トゥルプ博士の解剖学教室』(1632)で評判をとり、再びアムステルダムに出て肖像画家として活躍した。
レンブラントの活躍は、17世紀のライデンやアムステルダムなどのオランダの商業都市が急成長し、市民に支えられた文化が生まれたことを意味していた。同時にそのころオランダはドイツで始まった三十年戦争、イギリスのピューリタン革命の動乱の影も及んでおり、政治的には不安定な状態が続いていた。
「光と影の画家」
レンブラントは若くして肖像画家としての名声を確立したが、次第に単なる肖像画では飽き足らないものを感じるようになり、大画面に大胆な構図で、光と影を際立たせる独特の画風を生み出していった。1642年にアムステルダム市の射手組合から注文を受けて、射手たちの群像を描いた『夜警』を制作したが、注文主の組合員から誰が描かれているのか分からないという不評を買い、酷評された。そのため一挙に注文が減り、生活は困窮、妻や子にも死なれて貧民窟で暮らすという晩年となった。それでも創作は止めず、油絵・水彩・銅版画(エッチング)、デッサンなど多数の作品を残した。それらの作品は、絵画が装飾ではなく、真実を見つめて表現するという芸術であることを見事に示しており、レンブラントの絵画が近代絵画の出発点であると評価されるようになった。またレンブラントは、その成熟期の画風から「光と影の画家」と言われるが、その生涯もまさに光と影が交錯していた。(引用)このようにして生まれた新興オランダは、何よりも商人の国であった。土地が狭く、資源にも恵まれないオランダにとっては、貿易こそが何よりの繁栄の手段であった。・・・したがって、芸術の担い手も、君主や教会ではなく、もっぱら富裕な市民階級であった。レンブラントが最初画家として大きな成功を収めることができたのは、絢爛たる衣装や豪奢な金銀飾りなどの描写が、劇的な構図とともに市民たちの趣味に叶ったからにほかならない。しかしながら、まさに同じような理由によって、レンブラントがいっそう内面的なものの表現に向かって行った時、市民たちは彼の芸術に背を向けたのである。レンブラントは、そのような市民たちの趣味をよく知っていたに違いない。それでも彼は、自己の表現を変えようとはしなかった。・・・<高階秀爾『名画を見る眼』岩波新書 p.84>
『織物組合の見本検査人たち』
この作品は、1662年にレンブラントが描いた集団肖像画の傑作の一つ『織物組合の見本検査人たち』である。描かれているのはアムステルダムの織物組合で、重要な輸出品である織物の品質検査をしている検査人たちが、鑑賞者の側からもう一人の人物――おそらく重要人物であろう――が部屋に入ってきたことに気付いた、まさにその一瞬を捉えている。ここには6人の人物がいる。後ろに立つ無帽の召使いを除き、5人が組合幹部であるが、彼らの所属宗派がすべて判っている。左から、カトリック、メンノー派、カルヴァン派(議長)、レモンストラント派、カトリックである。組合幹部が所属宗派を異にしながら、真剣に輸出品の品質管理をしていることがこの絵から見て取ることが出来る。オランダはカルヴァン派の主流派(厳格な予定説を主張)が権力を握っていたとはいえ、同じカルバン派の分派であるメンノー派(穏健派)、レモンストラント派(寛容派)も加わり、カトリックも排除されていなかったという当時のアムステルダムが宗教的対立を越えて商業利益を追求する社会だったことが感じられる画面となっている。<桜田美津夫『物語オランダの歴史』2017 中公新書 p.77>