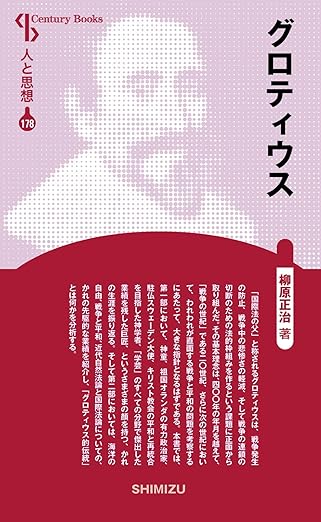グロティウス
17世紀前半、オランダ独立戦争期のオランダの法学者。三十年戦争などうち続く宗教戦争のさなかにあって、フランスに亡命したり、スウェーデンの外交官となるなど活躍しながら多くの著作を残した。主著はオランダの海洋進出の合法性を主張した『海洋自由論』(1609年)、中世以来のキリスト教的戦争論を継承しながら、自然法・国際法に基づく戦争の抑止と平和の維持を論じた『戦争と平和の法』(1625年)など。その著作によって、近代的自然法・国際法の父と評価されている。
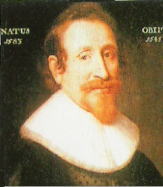
Hugo Grotius(1583-1645)
海洋自由論 そのころ1602年に設立されたオランダ東インド会社は、東インドでスペインに併合されたポルトガルと激しく衝突しており、26歳のグロティウスはその依頼を受けて1609年に『海洋自由論』を刊行して、海洋航行と交易の自由を自然法に基づいて論じ、注目を集めた。
戦争と平和の法 このような早熟の天才であったグロティウスだが、1618年、36歳の時、オランダのカルヴァン派内部の宗教対立から起こった政争に巻き込まれ、終身刑として投獄された。この年は、ドイツで三十年戦争(1618~1648)が始まった年であった。グロティウスは1621年に脱獄し、パリに亡命してルイ13世の保護を受けることになった。この年、フランス(ブルボン朝)はスペイン(ハプスブルク家)との戦争に踏み切り、三十年戦争に巻き込まれることとなった。戦争が長期化する中、1625年にグロティウスは亡命先のパリでルイ13世の諮問に答えて『戦争と平和の法』を書き、戦争の防止や緩和のためには、自然法の理念に基づいた国際法が必要であると提唱した。
その死後 その後、グロティウスはオランダに戻ることなく、スウェーデンの外交官としてパリで活躍した。オランダ独立戦争・三十年戦争は1630年代から講和に向かい国際会議が始り、グロティウスも講和交渉に加わることを望んだが、その機会はおとずれず、1645年に、スウェーデンからの帰途、ロストックで死去した。オランダの独立が国際的に承認されたのは、三十年戦争が終結した1648年の講和条約であるウェストファリア条約によってであった。<柳原正治『グロティウス』2000 清水書院 などによる>
近代自然法・国際法の父 グロティウスの業績は後の国際法の成立に大きな影響を与え、18世紀には『海洋自由論』の思想も合わせてグロティウスは「近代自然法・国際法の父」と言われている。ただし、最近ではその思想には多分に中世キリスト教の戦争観が残っているという学説が有力となり、否定的な見方が強まっている。グロティウスの思想は17世紀という段階のもので、18世紀後半のアメリカの独立、フランス革命という市民革命で明確になる国民国家としての主権国家体制、さらに産業革命後の資本主義の勃興に伴う殖民地の形成などをうけて始まる近代的な戦争が世界中で起こる時代のものではなかったという限界があった。それでも戦争を人間が起こすこと、国家間のルールが必要なこと、悲惨な殺戮や略奪を防止しなければならないことなどが初めて体系的に述べられたことの意義は大きい。
Episode 14歳で大学を卒業した神童グロティウス
グロティウスはオランダのライデン市の名門グロート家(オランダ語ではフロート)に生まれ、名前はフーゴーといった。たいへんな神童で、8歳の時ラテン語の詩を書き、11歳で当地の大学に入学した(*)。ギリシア語も学び、数学、哲学、法律の論文を書いて、14歳で大学を卒業。名前もラテン風にグロティウスと名乗った。15歳でオランダの首相の随員としてパリを訪れ、アンリ4世はその才能に驚嘆し、「オランダの奇蹟だ」といったという。16歳で弁護士として自立し、名声を博した。(*)もっとも当時のヨーロッパの大学への入学年齢は、現在よりはるかに若く、例えば1595年のライデン大学入学者150名のうち約三分の一は12歳から16歳までの少年たちであった。<柳原正治『前掲書』p.27>
オランダの宗教対立
グロティウスの巻き込まれた政争とは実質はカルヴァン派内の宗教対立であった。オランダはカルヴァン派が優勢であったが、カルヴァンの唱えた予定説を巡って厳格に解釈して一切を神の選択に委ねるという主流派(ホマルス派)と、緩やかに解釈して人間の自由意志を重視するアルミニウス派が対立するようになった。ホマルスもアルミニウスも共にライデン大学の教諭であり、純粋な信仰論争であったが、次第に政治的対立と結びついていった。各州の議会の中心勢力である都市貴族層の中にはアルミニウス派の影響力が強く各州の自由を主張したが、主流派は厳格なカルヴァン主義で連邦の宗教を統制しようとし、アルミニウス派の寛容はスペインとの妥協につながるとして反対した。主流派はオラニエ家第2代総督マウリッツと結んでついに1617年の連邦議会で教義の統一を図った。その結果はオランダ連邦7州の4対3で主流派が勝利を占めた。ホラント州はオルデンバルネフェルトを中心に、連邦は信仰まで統制すべきでないと反対した。グロティウスもそれに同調していた。1619年、総督マウリッツはアルミニウス派を裁判にかけ、オルデンバルネフェルトは死刑の判決によって処刑された。グロティウスはその時終身禁固の判決を受けマース川に浮かぶ小島のルフェスティン城に収監されてしまった。Episode グロティウスの脱獄と亡命
当時の受刑者は妻の同伴が許されていた。グロティウスの妻マリアは週に数度、川向こうの町に買い物に出ることができた。またグロティウスには研究に必要な書物が大きな長櫃に入れて届けられていた。マリアは、この長櫃を使って夫を脱獄させることを思いつき、夫が二時間も長櫃に閉じこもっていられるように練習させた。(引用)対岸のホルクム市が年に一度の縁日で賑わっていた1621年3月22日、計画は実行に移された。グロティウスのベッドは、まるで本人が横たわっているかのように盛り上げられ、彼の衣服がその上に置かれる。下着だけになったグロティウスが長櫃にもぐり込み、妻は運搬役の兵士たちをよぶ。荷物に違和感を覚えて不審がる兵士を、機転を利かせて煙に巻いたのは、長櫃に付き添った勇敢なお手伝いエルシェであった。<桜田美津夫『物語オランダの歴史』2017 中公新書 p.67>ホルテム市の知人宅で長櫃から出たグロティウスは、大工に変装して町を脱出、最終的にはパリに亡命した。グロティウスが脱獄に使ったという長櫃がアムステルダム国立美術館に置かれている。ところが同じくその時の長櫃だというのが当のルフェスティン城などの各地にいくつも展示されている。本物はそのいずれかなのか、またはすべてが偽物なのか。今ではわからなくなっているという。