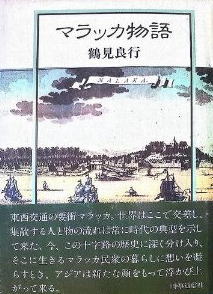スズ
東南アジアに産出する重要な金属資源。マレー半島、スマトラ島が主な産地となった。
スズ(錫)は金属元素の一つ(Sn)で、延性・展性に富み、錆びない特色があるので、食器や錫箔としてタバコや菓子の包装に用いられた。また鉄板にスズのメッキをしたものがブリキで生活用品や建材など多方面に使用される。なお、銅とスズの合金の青銅器が人類が最初に作った金属器である。青銅器時代はオリエントでは前3000年頃から始まり、前1000年頃には鉄器時代へと移行する。
錫は銅と合金にして青銅をつくるほかに、ハンダとしても使われる。原鉱は錫石として自然界に存在するが、西アジアではめったになく、高価であった。近年の研究では原産地はアフガニスタン・イスラーム共和国北部やタジキスタン共和国の山岳地帯ともいわれている。古代オリエントのアッシリアでは、これらの原産地から、イラン高原を横断し、アッシュールに運ばれていた。さらにアッシュール商人によってアナトリア(小アジア)に運ばれ、銀と交換されていた。前19~前18世紀の「マリ文書」(マリで発掘された楔形文字の記された粘土板)では錫は銀の10分の1の価格で、マリからさらに地中海岸のウガリト(現在のラス・シャムラ、フェニキア人の都市国家)などに運ばれた。<小林登志子『アッシリア全史』2024 中公新書 p.53,75-76>
マレー半島のスズはアヘンとともに増大した。スズ鉱山の華人労働者は低賃金で苦しむ中、アヘンで気を紛らわすしかなかったが、そのアヘンはイギリスが専売制度で利益を独占していた。アヘンが広がったのは中国だけではなかったし、またその利益を得たのはイギリスだけではなく、東インドにおけるオランダも同様であったことに注意する必要がある。<同 p.251-266>
古代オリエントのスズ(錫)
青銅器時代のオリエント世界では、青銅器の原材料となる銅、錫、および鉛の産地は限定されていた。そこで貴重な金属を求めて、アッシュール市の商人は活発な交易を行った。錫は銅と合金にして青銅をつくるほかに、ハンダとしても使われる。原鉱は錫石として自然界に存在するが、西アジアではめったになく、高価であった。近年の研究では原産地はアフガニスタン・イスラーム共和国北部やタジキスタン共和国の山岳地帯ともいわれている。古代オリエントのアッシリアでは、これらの原産地から、イラン高原を横断し、アッシュールに運ばれていた。さらにアッシュール商人によってアナトリア(小アジア)に運ばれ、銀と交換されていた。前19~前18世紀の「マリ文書」(マリで発掘された楔形文字の記された粘土板)では錫は銀の10分の1の価格で、マリからさらに地中海岸のウガリト(現在のラス・シャムラ、フェニキア人の都市国家)などに運ばれた。<小林登志子『アッシリア全史』2024 中公新書 p.53,75-76>
スズの近代史
(引用)19世紀中頃まで、スズの主な用途は、うすい鉄板にスズメッキをした食器だった。陶磁器が早くから普及した日本や中国と違って、欧米では、ブリキ皿が庶民の食器である。陶器はブルジョアの家庭や宮廷で使われたにすぎない。ところが、19世紀半ばになると、クリミア戦争、南北戦争に伴う缶詰め工業の発展、アメリカの西部開拓によるブリキ屋根材、石油缶の需要増大が起こり、スズ消費量が急増する。1825~75年の50年間に、イギリスのブリキ食器生産は、五倍に伸びている。ブリキ食器は、今日のプラスチック食器に当たるだろう。・・・(ヨーロッパのスズの産地であるイギリスの)コーンウォルの山スズも19世紀末、ようやく枯渇の時を迎えていた。こうして世界大の産業発展が、マラヤのスズ生産を促すことになる。<鶴見良行『マラッカ物語』1981 時事通信社 p.236>
マレー半島のスズ生産
マレー半島を初め、東南アジアのスズは鉱脈を掘るのではなく、風雨で崩されたスズが永い年月の間に河床に堆積した河スズだったので、河の流域ごとの地域が採掘権を持っていた。<同 p.195> イギリス領マラヤのスズ鉱山では華僑が、流入した華人労働者(苦力)から買い集める形が多かったが、オランダ領スマトラ島に属するバンカ島では政府直営のスズ鉱山会社が作られた。その結果、次第にスマトラ産スズの生産量が増大した。<同 p.237->マレー半島のスズはアヘンとともに増大した。スズ鉱山の華人労働者は低賃金で苦しむ中、アヘンで気を紛らわすしかなかったが、そのアヘンはイギリスが専売制度で利益を独占していた。アヘンが広がったのは中国だけではなかったし、またその利益を得たのはイギリスだけではなく、東インドにおけるオランダも同様であったことに注意する必要がある。<同 p.251-266>