サティ
インド社会に長く行われていた寡婦が夫に殉死する風習。寡婦殉死。イギリス植民地支配下で批判が強まり、ラーム=モーハン=ローイらの運動で1829年に禁止令が出された。
サティは寡婦殉死などと訳されるが本来は「貞節な妻」を意味した。ヒンドゥー社会に見られる風習で、夫が死んだとき、妻はそれに従って死ぬことが美徳とされ、人々に送られて生きたまま焼かれるという。これを見たイギリス人がインドの野蛮な風習「サティ」と紹介したため、寡婦殉死を意味することとなった。インド社会の民衆生活に深く根を下ろしていたヒンドゥー教では、女性の人格は基本的には認められておらず、結婚しても夫に従属し、離婚は認められず、その死後の再婚も認められなかった。そのようななかで寡婦が生きていくことが難しかったという現実があり、女性も夫に従って身を焼き滅ぼすのが美徳と考えたようである。このサティの習慣は近代まで続き、ようやく1829年に禁止令が出されたが、現在でも広いインドでサティが行われたことがニュースになることがあるという。
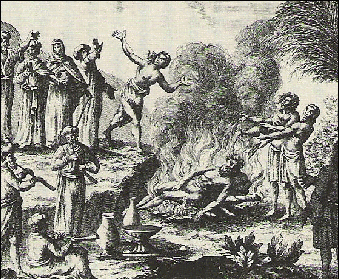
サティの風習 ベルニエ『ムガル帝国誌』二より
ギリシア人が伝えるインドの風習
ローマ帝政時代、アイリアノスがギリシアに伝わる話をギリシア語で書いた『ギリシア奇談集』にも「インド人の妻の殉死」の話が出ている。(引用)インドでは夫が死ぬと、その妻たちは夫を焼く火で焼死することを厭(いと)わない。死亡した男の妻たちは、そのことで互いに競い合い、籤(くじ)に当たった女が夫と共に焼かれるのである。<アイリアノス/松平千秋ら訳『ギリシア奇談集』岩波文庫 p.216>
ムガル帝国時代のサティ
この一種の殉死の習慣は、古くからあり、14世紀のイスラーム教徒のイブン=バットゥータの残した『三大陸周遊記』にも出てくる。南インドのヴィジャヤナガル王国では国王が死ぬと4~500人の後宮の女性が王の死体とともに荼毘に付されたという。ムガル帝国のアクバル帝は、たびたびサティ禁止令を出しているが、根絶出来なかった。また、17世紀半ばのアウラングゼーブ帝時代のムガル帝国を旅行し、その宮廷に仕えたフランス人ベルニエの記録『ムガル帝国誌』にも詳しく報告されている。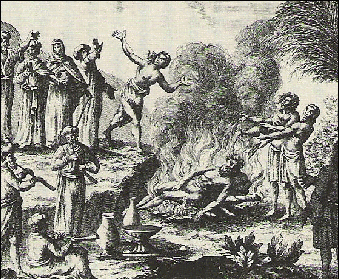
サティの風習 ベルニエ『ムガル帝国誌』二より
(引用)つまり、事実は、一から十まで言われている通りではありませんし、昔ほど多数が焼死しているのでもありません。現在統治しているイスラーム教徒達は、この野蛮な風習に敵対しており、できるかぎり防止しているからです。 とはいえ絶対的に反対しているわけではありません。というのも、反乱を恐れて、自分達よりずっと多数である偶像崇拝の徒(つまりヒンドゥー教徒)である人民に、自由な宗教行為を許しているからなのです。(中略)夫の死体と共に妻が焼死することに関して私が尋ねると、多くの人々は、彼女達のすることは夫に対するあふれんばかりの愛情によるものに他ならないと、私に納得させようとしました。(中略)本当のところは、これは妻達を夫にもっと隷属させ、夫の健康にとりわけ心を配らざるを得なくさせ、妻達が夫を毒殺するのを妨げるための、男達の策略以外のものではなかったのではありますが。<ベルニエ『ムガル帝国誌』二 2001 岩波書店 p.95-100>これによると、支配者であるイスラーム教徒は、サティを認めずやめさせようとたびたび禁令を出したが、ヒンドゥー教徒の反乱を恐れてあえて厳しく取り締まろうとしなかった、ということである。また寡婦も一族のために進んで火中に身を投じたという。ヒンドゥー教徒のアイデンティティの表現という側面があったらしい。右図は同書の挿絵である。
サティの禁止
19世紀に入って、イギリス殖民地支配のもとでインドの知識人のなかにもこのような風習を批判するものが現れ、ラーム=モーハン=ローイが中心となった運動によって1829年にイギリス植民地当局が禁止令を出した。しかしすぐにはなくならなかったという。Episode ガンディーの幼児婚
なお、インド社会には非人道的な風習として幼児殺害や幼児婚があった。これらは親の経済状態から子供が犠牲になることで、封建時代の日本にも見られたことである。ガンディーの自叙伝を読むと、ガンディーも13歳で結婚させられたということである。<ガンジー『ガンジー自伝』1921 中公文庫 セ.35~>出題 2010年 東大 第2問 問3 b
(アジア各地の独自の知の体系についての質問の一部)インドでは、ラーム=モーハン=ローイが、女性に対する非人道的なヒンドゥー教の風習を批判するパンフレットを刊行するなどして、近代主義の立場から宗教・社会改革運動を進めた。この風習を何というか答えなさい。解答 → サティ

