フス/フス派
15世紀のベーメンの宗教改革の先駆者。イギリスのウィクリフの聖書主義に感化され、カトリック教会を鋭く批判した。1414年、コンスタンツ公会議で異端とされ、翌年に火刑となった。その支持者はベーメンでフス戦争と言われる農民戦争を起こした。フス派は穏健派がその後も存続したが、ハプスブルク家のカトリック化の強制が進み、三十年戦争でプロテスタント軍が敗れたことで消滅した。
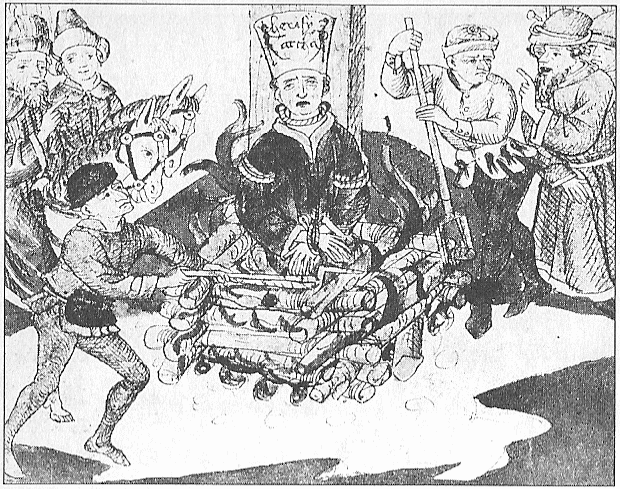
火刑にされるフス。
頭には悪魔を描いた帽子をかぶらされている。
ウィクリフの教説を継承
ヤン=フス Jan Hus 1370/71-1415 はプラハ大学で神学を学び、1398年から教授、1401年に哲学部長、1403年には学長となった。イギリスで教会を批判し、聖書による信仰を回復することを説いたウィクリフの教説を知ってその影響を受け、カトリック教会の世俗化を厳しく批判するようになり、1402年からチェコ語で説教をするようになった。イギリスのウィクリフの教説がベーメンに伝えられたのは、イギリスプランタジネット朝のリチャード2世が神聖ローマ皇帝カール4世(ドイツ王、ベーメン王を兼ねる)の娘を妃としたため、両地の関係ができ、プラハ大学の教授もオックスフォードで学ぶものがいたためである。
コンスタンツ宗教会議で異端とされる
フスの説教は、ベーメンの貴族や民衆に広く受け容れられ、影響力を持つようになった。1412年、ローマ教皇の贖宥状の発売を批判すると、ついに破門される。1414年に皇帝ジギスムントの召集したコンスタンツ公会議に召還されると、フスは自説を主張する機会と考えてそれに応じたが、審問では一切の弁明も許されず、一方的に危険な異端の扇動者であると断じられ、翌1415年7月6日、火刑に処せられた。 → 宗教裁判参考 火刑場のフス
1415年7月6日に行われたフスの火刑を、当時の目撃者の証言などを元にして再構成した著作からの引用しよう。(引用)フスの処刑はコンスタンツの市壁の外の、ライン河畔の草原で行われた。ここは中世的な世界観からすれば、市壁内のミクロコスモス(小宇宙)外の、マクロコスモス(大宇宙)の領域ということになる。ルートヴィヒ・フォン・バイエルン公を先頭にして、二千人の武装兵が警備し、貴族、司教、大司教を含めた群集が行列をつくった。処刑の際に兵士が動員されるのは、威嚇と民衆の暴動の防止対策である。市中引き回しの際に、フスは三匹の悪魔の絵が描かれた紙製のとんがり帽子をかぶせられた。帽子には「こいつは異端の親玉だ」とラテン語で書かれていた。
町を練り歩いていく途中、司教の宮殿の前ではフスの本が焼かれた。かれは残った灰の前でひざまずき、両手を上げ、天を見上げながら、詩編を唱えた。祈るフスの頭から悪魔の描かれた帽子が落ち、見張りがそれを頭にふたたびかぶせると、フスは笑った、司祭のウルリッヒ・ショラントが、異端を捨てて懺悔をする気があるなら「告解」(神に罪を告白して許しを請うこと)をせよと諭したが、フスは「そんな必要はありません。わたしは死に値する大罪を犯した者ではない」と拒否した。
刑吏は処刑場で、フスの手に鉄の枷をはめたが、それを見てフスは笑いながら、「われらを救い、至福をあたえたもうわが主イエスも重い鎖につながれた。それゆえ哀れで惨めな罪人であるわたしが、主の名において鎖を担うのを私は恥とは思っていない」といった。二台の荷車で運んできた麦わらと薪の束がかれの膝まで積まれ、フスは靴をはいたままの状態で、足を鉄の枷で支柱にくくられていた。
藁に火をつける前に、皇帝の使者フォン・パーペンハイムとバイエルン大公が、火刑を躊躇しているようにみえた刑吏たちに警告を与え、フスには信仰の誤りを撤回するようにいった。フスはそれに答え、天に向かって大きな声でこう叫んだ。
ああ神よ、あなたがわたしの証人です。偽りの証人によってわたしは罪に科せられましたが、罪とされるようなことは教えたことも説教したこともありません。わたしの説教や意見は、もっぱら人びとを罪から救うためになされたものなのです。わたしが聖書の言葉や解釈によって書き、教え、説教してきた福音は真実であり、それゆえ、今日、わたしは喜んで死ぬつもりです(J.R.グリグレヴィッチ『異端、魔女、審問官』)
フスの言葉を聞いたパーペンハイムとバイエルン大公は、手をたたいて処刑の合図を送った。ようやく刑吏は火をつけた。フスは大きな声で「神の子イエス・キリスト、われを哀れみたまえ!」と二度叫んだ。するとさっと風が立ち、炎と煙がかれを包んだ。しかしそのなかでかれの頭が揺れ、口が動いているのがみえた。
「フスの所有物は何ひとつ略取してはならぬ」と通達が出ていたけれども、バイエルン大公は、刑吏がフスのマントを手にしているのを見つけ、すぐさま火のなかへそれを投げ入れるよう命じた。マントがフスの聖遺物とされるのを避けるためである。同様に死体も念入りに焼かれ、灰は荷車に積まれてライン河に流された。しかしボヘミアからフスに随行していた人びとは、処刑場の土を掘り、それを一種の聖遺物として故郷に持ち帰った。<浜本隆志『拷問と処刑の西洋史』2024 講談社学術文庫(初刊 新潮選書 2007) p.40-42>
フス戦争 異端者から民族の英雄へ
フスの思想は、教会の誤りを正し、聖書に基づく信仰に戻ることに主眼があり、ローマ教皇の権威を否定したのでもなく、またウィクリフの化体説批判(聖餐の秘蹟を否定した)には同調していなかったので、急進的なものではなかったが、コンスタンツ公会議では危険思想の烙印を押されることとなった。フスの思想はむしろその処刑後、封建領主としての教会に苦しめられていた民衆の抑圧からの解放、またドイツ人に抑えられていたチェック人の自由を求める民族的自覚と結びつき、1419年、フス戦争(1419~36年)といわれる農民戦争(一揆)となって爆発する。フスの説教
(引用)フスの説教の中身は、残された原稿からほぼその全容を知ることが出来る。彼は聴衆に向かって説いた。現在の教会の悲惨な状態は、聖職者の不道徳に原因がある。その人が本当に聖職者といえるかどうかは、彼が本当に神の言葉を説いているかどうかで判断すべきであり、教皇や司教が彼を承認したかどうかは重要ではない。利益ばかり追い求め、教会で商売まがいの活動をしている司祭は、本当の司祭ではない。もったいぶった長たらしい祈りを唱えつつ、キリストを冒涜するようなことを平気でしでかすような修道士は、本当の修道士ではない。この世に生きる人々は、どのような身分であるかにかかわらず、神から与えられた職務を守って正しい生活を送り、悪がはびこらないよう十分に注意しなければならない。この世の終わりに皆が天国に行けるようにするには、それ以外に方法はないのだ、と。<薩摩秀登『物語チェコの歴史』2006 中公新書>
フス戦争後のフス派
フス戦争(1419~36年)は、フス派が急進派(タボル派)と穏健派に分裂し、皇帝が穏健派を取り込んで急進派と戦うという構図となり、最終的には急進派が敗れ、皇帝と穏健派の勝利となった。従ってフス派の穏健派はその後も信仰を認められた。 フス戦争後のベーメン(チェコ)では神聖ローマ皇帝によるカトリック教会保護に対して、フス派穏健派(ウトラキストという)もその信仰を認められて大きな勢力を保っていた。またフス派急進派の流れをくむ人々は「チェコ同胞団」を結成し、こちらはたびたび弾圧を受けたが、なおも存続していた。さらに、フスの火刑からほぼ百年経った1517年にルターによって宗教改革が始まると、ルター派のプロテスタントもチェコに進出してきた。ウトラキスト、チェコ同胞団、ルター派の非カトリック三派は、1575年には「チェコ人の信仰告白」を発表、神聖ローマ皇帝となったハプスブルク家のルドルフ2世もそれを承認した。三十年戦争
17世紀に入ると神聖ローマ帝国皇帝位にあるハプスブルク家は、このようなベーメンの状況を放置できないと感じ、イエズス会員を送り込むなど、強力なカトリック化を押しつけてきた。同時にチェコ語を公用語としているベーメン王国にドイツ人官吏を送り込み、ドイツ語化を進めようとした。皇帝側のベーメンに対するカトリックとドイツ語の強要は、チェコ人の反発を強めていった。ベーメン国王にプロテスタントに対する不寛容で知られたフェルディナントが指名されたことから対立は頂点に達し、1618年、プラハでベーメンの反乱が始まり、それをきっかけにドイツ全土をまきこむ三十年戦争となった。チェコのカトリック化の完成 ベーメンにおけるカトリックとプロテスタント両軍は、1620年、プラハ郊外のビーラー=ホラの戦いが決戦となった。戦いはプロテスタント軍の完敗に終わり、プロテスタント軍に参加したフス派系の信徒も多くが国外に逃亡せざるを得なかった。結果としてベーメン(チェコ)ではカトリック以外の信仰が禁止され、改宗を拒否した人々は国外に亡命し、さらに公用語がチェコ語からドイツ語に変えられた。このように三十年戦争の初期の段階で、チェコのプロテスタントとフス派が消滅し、ハプスブルク家支配のもとでカトリック化とドイツ化が決定的となるという大きな変化が生じた。以後、現在のチェコにいたるまで、ヨーロッパでのカトリック国として続くこととなる。
参考 フスの名誉回復
三十年戦争でフス派とプロテスタントの敗北に終わった後、チェコではカトリックが優勢となり、ヤン=フスの名も忘れられていった。長い忘却の期間の後、19世紀になってチェック人の民族運動(ベーメン民族運動)が活発になると、にわかにフスとその時代がチェック人の誇りとする歴史として意識されるようになった。スメタナの組曲『わが祖国』の5曲目もフス派の歌ったという“ターボル”という歌をモチーフに作曲されいる。また1915年7月6日にはフスの没後500年を記念したフスとフス派の群像の除幕式がプラハの旧市街ひろばで行われた。そして冷戦が終わった1990年にはローマ教皇ヨハネ=パウロ2世はプラハを訪れてフスの教会改革者としての再評価についてふれ、1999年にはヴァチカンで“フスに課せられた過酷な死と、その後に生じた紛争に対して、深い哀惜の意を表明する”との声明を読み上げた。フス裁判が誤りであったという断定は避けながら、フスは580余年を経て事実上の名誉回復をとげたと言うことができる。<薩摩秀登『物語チェコの歴史』2006 中公新書 p.99-102>