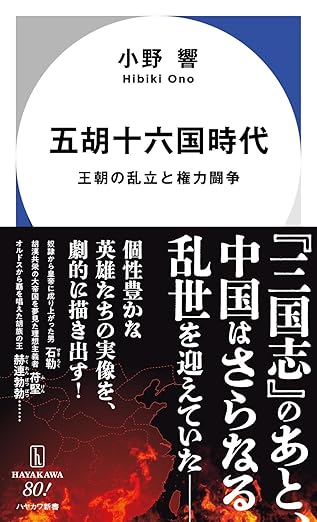五胡十六国
4~5世紀、中国の華北に興亡した北方民族(五胡)の建てた国々。304年、劉淵の漢から439年、北魏による統一までの135年間の華北をいう。
304年に匈奴の劉淵が漢(前趙)を建国してから、439年に北魏の太武帝が華北を統一するまでの、華北に興亡した五胡や漢民族の国々を総称して五胡十六国という。
まず、匈奴のリーダー劉淵は304年に自立して漢を称していたが、かろうじて西晋を支えていた東海王司馬越が311年に死去し華北の混乱が起きると、羯の石勒が晋を攻めると当時に、劉淵の子の劉聡は武将の劉曜を派遣して洛陽を占領し、略奪暴行の限りを尽くした。この永嘉の乱で、西晋は事実上滅亡し、司馬氏の一族は南方の建業(南京)に逃れ、東晋となる(316年)。
華北での五胡十六国の興亡は、4世紀から5世紀前半までの1世紀以上にわたっているが、大きく分ければ、376年に前秦の苻堅が一時的ながらほぼ華北を統一した時期までを前期とし、中国統一を目指した苻堅が、383年の淝水の戦いで東晋に敗れたことで、再び華北の各民族が分立してからを後期とすることができる。後期になるともっとも北辺にいて16国にも加えられていなかった鮮卑の拓跋氏の代国が急速に力をつけて、389年に魏王を称し、439年に華北を統一し、五胡十六国時代終わる。
また五胡の立てた国家といっても、各国の国家官僚として漢人が採用されており、征服王朝として漢民族を排除、支配したわけではない。
五胡の北方民族が華北の漢人社会と融合していった結果、彼らの生活習慣(騎馬の風習、椅子の生活、小麦が主食になるなど)の変化が起こり、それが現在の中国人の生活の基本につながっている。また、インドから中央ジアを経て入ってきた仏教が西域を経て五胡十六国のもとで保護(仏図澄・鳩摩羅什がその代表的な例)されたことも中国文化史を考える上で重要なことである。
注意 異民族君主の評価 五胡の君主たちを、異民族だから野蛮で無知であると想像するのは、中華思想による誤解である。すでに彼らは漢代から漢文化と接触し、その文化を身につけていた。例えば匈奴の劉淵は儒教の経典や『春秋左氏伝』などの歴史書、さらに『孫子』などの諸子百家の書物にも通じて居る。永嘉の乱で洛陽を破壊したと言われる劉曜は長安に宗廟や宮殿を修築し、多数の民を移住させて都市としての充実を図り、大学、小学を興して教育に意を用いている。彼は読書を好み、よく文章をなして草書や隷書に巧みであったという。こうした異民族君主の学識は、後の前秦の苻堅や、北魏の孝文帝にも受け継がれていく。<川本芳昭『中華の崩壊と拡大-魏晋南北朝』中国の歴史5 2005 講談社 2023再刊 講談社学術文庫 p.67>
※北魏の前身である「代国」は内モンゴルから起こって華北に進出したが、十六国に加えられていない。他に16国に加えられていない小国(西燕など)もある。なお、表の始祖は必ずしも初代皇帝ではない。地域はおよその勢力圏を示す。
※受験生諸君へ。もちろん十六国を暗記するなどまったく必要ない。4世紀~5世紀前半、華北で最初の匈奴の劉淵が漢を立てたことで始まり、五胡の16国が次々と興亡したことを抑えておけば良い。その間の重要な動きとしては、氐の前秦が苻堅の時、一時ほぼ華北を統一したが、383年の淝水の戦いで東晋に敗れ、それをきっかけに再び華北が分裂(五胡十六国時代の後半)となったことであろう。
太武帝の統一事業 北魏の第三代太武帝は、425年、北方の柔然を討ってから華北の諸国の征服活動に入った。426~7年、オルドスにあった赫連氏の夏国を攻めて平定、432~6年には遼西地方の馮氏(漢人)の北燕を攻撃して男女6000人の捕虜を平城に連行した。そして439年年に、太武帝は自ら大軍を率いて甘粛の北涼の征討に向かい、9月には5000人の官僚が降伏、20万人と倉庫の財宝を収容し、10月には涼州から3万余家を平城に移した。これをもって五胡十六国は終焉を迎え、華北は統一された、とされている。
439年の意味 この時現実にはまだ甘粛南部に後仇池という勢力(16国には入っていない)が残っており、その平定は3年後のことなので、華北統一とは言えない。439年を太武帝による華北統一、五胡十六国の終わりとするのは、『晋書』序文に、304年に匈奴の劉淵が漢を称してから136年で五胡十六国が終わったと書かれていて、北涼滅亡の439年がちょうど136年目にあたるからである。<松下憲一『中華を生んだ遊牧民-鮮卑拓跋の歴史』2023 講談社選書メチエ p.106-108>
西晋の混乱
晋(西晋)は中国の統一に成功したものの、290年に司馬炎(武帝)が死去すると、中国史上でもまれにみる大混乱時代に突入した。それは西晋の皇位継承の争いとなって現れ、八王の乱の内戦となり、勢力争いを続けた王たちは、それぞれ北方民族の騎馬部族を兵力として利用した。それが五胡と言われる北方民族が中華世界で活動する契機となった。まず、匈奴のリーダー劉淵は304年に自立して漢を称していたが、かろうじて西晋を支えていた東海王司馬越が311年に死去し華北の混乱が起きると、羯の石勒が晋を攻めると当時に、劉淵の子の劉聡は武将の劉曜を派遣して洛陽を占領し、略奪暴行の限りを尽くした。この永嘉の乱で、西晋は事実上滅亡し、司馬氏の一族は南方の建業(南京)に逃れ、東晋となる(316年)。
五胡と十六国の興亡
五胡とは、匈奴・鮮卑・羯・氐・羌の五つをいう。16国(下表参照)のなかには胡人ではなく漢人(漢族)の立てた国もある。華北での五胡十六国の興亡は、4世紀から5世紀前半までの1世紀以上にわたっているが、大きく分ければ、376年に前秦の苻堅が一時的ながらほぼ華北を統一した時期までを前期とし、中国統一を目指した苻堅が、383年の淝水の戦いで東晋に敗れたことで、再び華北の各民族が分立してからを後期とすることができる。後期になるともっとも北辺にいて16国にも加えられていなかった鮮卑の拓跋氏の代国が急速に力をつけて、389年に魏王を称し、439年に華北を統一し、五胡十六国時代終わる。
五胡十六国時代の中国
北方民族(胡人)が華北に国を建てたといっても、この時期に移住して征服活動をしたのではなく、ほとんどはそれ以前の漢代(前漢・後漢)・三国(華北の魏)・西晋を通じで移住し、漢人社会に溶け込みながら、騎馬兵力として漢人政権の傭兵化していた人々である。彼らが西晋の混乱を背景に政治的に自立したが、まだ統一的な権力になり得ず、互いに抗争した、というのが五胡十六国の分立の意味である。また五胡の立てた国家といっても、各国の国家官僚として漢人が採用されており、征服王朝として漢民族を排除、支配したわけではない。
五胡の北方民族が華北の漢人社会と融合していった結果、彼らの生活習慣(騎馬の風習、椅子の生活、小麦が主食になるなど)の変化が起こり、それが現在の中国人の生活の基本につながっている。また、インドから中央ジアを経て入ってきた仏教が西域を経て五胡十六国のもとで保護(仏図澄・鳩摩羅什がその代表的な例)されたことも中国文化史を考える上で重要なことである。
注意 異民族君主の評価 五胡の君主たちを、異民族だから野蛮で無知であると想像するのは、中華思想による誤解である。すでに彼らは漢代から漢文化と接触し、その文化を身につけていた。例えば匈奴の劉淵は儒教の経典や『春秋左氏伝』などの歴史書、さらに『孫子』などの諸子百家の書物にも通じて居る。永嘉の乱で洛陽を破壊したと言われる劉曜は長安に宗廟や宮殿を修築し、多数の民を移住させて都市としての充実を図り、大学、小学を興して教育に意を用いている。彼は読書を好み、よく文章をなして草書や隷書に巧みであったという。こうした異民族君主の学識は、後の前秦の苻堅や、北魏の孝文帝にも受け継がれていく。<川本芳昭『中華の崩壊と拡大-魏晋南北朝』中国の歴史5 2005 講談社 2023再刊 講談社学術文庫 p.67>
参考 ゲルマン民族の移動との類似性
中国で北方遊牧民の南下が活発となった4世紀~5世紀は、遠くヨーロッパではゲルマン民族の大移動が始まった時期と同じである。ユーラシア大陸の東西で同時に民族移動の波が起こったことは興味深い。また、ゲルマン民族がローマ帝国の傭兵としてその領内に移住していったのと同じように、五胡の北方民族も、東晋の八王の乱などで軍事力として用いられることによって中国内に移住していったことも同じような動きである。五胡十六国表
十六国を登場順に表にすると次のようになる。| 国号 | 始祖 | 種名 | 年代 | 地域 | |
| 1 | 漢(前趙) | 劉淵 | 匈奴 | 304~329 | 陝西 |
| 2 | 成漢 | 李雄 | 氐 | 304~347 | 四川 |
| 3 | 後趙 | 石勒 | 羯 | 319~350 | 山西・陝西 |
| 4 | 前燕 | 慕容皝 | 鮮卑 | 337~370 | 河北・山東 |
| 5 | 前涼 | 張重華 | 漢族 | 345~376 | 甘粛 |
| 6 | 前秦 | 苻洪 | 氐 | 351~394 | 陝西・山西 |
| 7 | 後燕 | 慕容垂 | 鮮卑 | 384~409 | 山東・河北 |
| 8 | 後秦 | 姚萇 | 羌 | 384~417 | 山西 |
| 9 | 西秦 | 乞伏乾帰 | 鮮卑 | 385~431 | 陝西 |
| 10 | 後涼 | 呂光 | 氐 | 386~403 | 甘粛 |
| 11 | 南涼 | 禿髪烏孤 | 鮮卑 | 397~414 | 甘粛 |
| 12 | 北涼 | 沮渠蒙遜 | 匈奴 | 397~439 | 甘粛 |
| 13 | 南燕 | 慕容徳 | 鮮卑 | 398~410 | 山東 |
| 14 | 西涼 | 李暠 | 漢族 | 400~420 | 甘粛 |
| 15 | 夏 | 赫連勃勃 | 匈奴 | 407~431 | 陝西・山西 |
| 16 | 北燕 | 馮跋 | 漢族 | 409~436 | 河北 |
※受験生諸君へ。もちろん十六国を暗記するなどまったく必要ない。4世紀~5世紀前半、華北で最初の匈奴の劉淵が漢を立てたことで始まり、五胡の16国が次々と興亡したことを抑えておけば良い。その間の重要な動きとしては、氐の前秦が苻堅の時、一時ほぼ華北を統一したが、383年の淝水の戦いで東晋に敗れ、それをきっかけに再び華北が分裂(五胡十六国時代の後半)となったことであろう。
五胡十六国の統一
代国→北魏の台頭 五胡十六国の分裂時代を終わらせたのは、十六国にあげられていない、北方の現在の内モンゴル自治区東部にあった鮮卑の拓跋部が遊牧部族連合を統合し、4世紀の初め西晋から代王の称号を与えられ、盛楽(現在のフフホト付近)を拠点に活動していた。後趙の石勒や前秦の苻堅が有力になると、それに服属していたが、淝水の戦いで前秦が弱体化したために台頭、拓跋珪は386年に国号を魏とし、398年には皇帝を称し、北魏の初代皇帝道武帝となった。太武帝の統一事業 北魏の第三代太武帝は、425年、北方の柔然を討ってから華北の諸国の征服活動に入った。426~7年、オルドスにあった赫連氏の夏国を攻めて平定、432~6年には遼西地方の馮氏(漢人)の北燕を攻撃して男女6000人の捕虜を平城に連行した。そして439年年に、太武帝は自ら大軍を率いて甘粛の北涼の征討に向かい、9月には5000人の官僚が降伏、20万人と倉庫の財宝を収容し、10月には涼州から3万余家を平城に移した。これをもって五胡十六国は終焉を迎え、華北は統一された、とされている。
439年の意味 この時現実にはまだ甘粛南部に後仇池という勢力(16国には入っていない)が残っており、その平定は3年後のことなので、華北統一とは言えない。439年を太武帝による華北統一、五胡十六国の終わりとするのは、『晋書』序文に、304年に匈奴の劉淵が漢を称してから136年で五胡十六国が終わったと書かれていて、北涼滅亡の439年がちょうど136年目にあたるからである。<松下憲一『中華を生んだ遊牧民-鮮卑拓跋の歴史』2023 講談社選書メチエ p.106-108>