カーター
アメリカ合衆国大統領。民主党。在職1977~1981年。人権外交をかかげ、パナマ運河返還、エジプト=イスラエルの和平などを実現したが、1979年のイラン革命でのアメリカ大使館人質事件では処理を誤った。同年末のソ連軍のアフガニスタン侵攻に対しては翌年のモスクワオリンピックをボイコットした。しかし「強いアメリカ」と小さな政府を掲げる共和党レーガンに敗れ、一期で終わった。退任後は元大統領の肩書きで北朝鮮、キューバなどを訪問して成果を上げ、2002年にノーベル平和賞を受賞した。
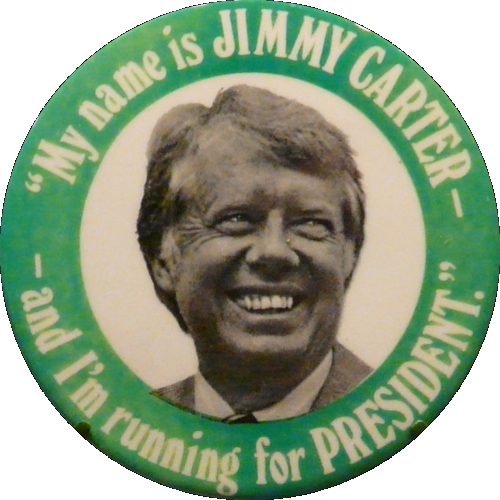
"My name is JIMMY CARTER and I'm running for PRESIDENT."
Jimmy Carter 1924-2024 アメリカ合衆国の民主党の政治家。南部のジョージア州知事。1976年の大統領選挙で、南部出身のリベラル派として、黒人と労働者層の支持で共和党のフォードを破り当選した。中央では無名だったので、立候補したときは Jimmy, Who? と言われた。
1977年1月20日、第39代アメリカ合衆国大統領に就任。内政課題のインフレでは減税策を採ったためかえって増進させ、減税率を引き下げたため、国民の信頼を失った。また1979年2月にイラン革命直面し、第2次石油危機が始まると、エネルギー政策の全面的見直しを提唱、アラブ原油依存体質の転換を図った。
しかしソ連との友好的な関係は同年のソ連軍のアフガニスタン侵攻によって崩れ、カーター政権はモスクワ・オリンピック参加を拒否して対抗し、SALTⅡ合意は破棄された。また同年、イラン革命が勃発、アメリカ大使館人質事件が発生してその解決に失敗し、80年の大統領選挙で共和党のレーガンに敗れ退陣した。 → アメリカの外交政策
退陣後は民主党政権下ではたびたび北朝鮮への特使として派遣され、人質事件の解決などにあたっている。
最後の手段としての人質救出作戦が1980年4月11日に決定された。バンス国務長官は軍事作戦は非現実的であり、強行すれば人質52人のうち何人かは処刑されるであろうと強く反対した。ブラウン国防長官、ジョーンズ統合参謀本部議長は賛成し、カーターは救出作戦を許可した。バンスは、たとえ成功しても辞任するとして辞表を提出した。 → 救出作戦の実際はアメリカ大使館人質事件の項を参照。
4月24日、作戦は強行された。しかし、大型ヘリが砂漠の風にあおられて墜落、さらに輸送機に接触して爆発し、作戦は失敗に終わった。バンス長官は予定通り辞任した。
1994年、北朝鮮が金日成のもとで核開発を進めているのではないか、という核疑惑が強まり、米朝関係が緊張した。クリントン大統領政権はカーターに北朝鮮訪問を要請、アメリカの大統領経験者として初めてカーターは北朝鮮入りした。カーター・金日成会談で北朝鮮は核開発凍結と査察の受け入れに合意し、同年の米朝枠組み合意につながった。北朝鮮の核開発はその後再開され、米朝間の緊張は続くこととなるが、カーターのつくったパイプは2010年、不法入国したアメリカ人の解放のために再び訪朝して、交渉の末いっしょに帰国することに成功している。
2002年、キューバを訪れてカストロ首相と会談した。1959年のキューバ革命後、アメリカ大統領経験者で初めてのキューバ入りとなり、関係改善の糸口をさぐった。これがオバマ政権下の2015年の国交回復につながった。これらの元大統領という肩書きを生かした外交努力が評価され、2002年にノーベル平和賞が授与された。
1月20日に大統領就任式に臨んだトランプは、カーターの業績であるパナマ運河のパナマへの返還を、カーターの名を上げなかったものの「愚かな贈り物」として否定し、取り返すことを表明した。カーターは数日の差でこのどんでん返しを聞くことなく、冥界に入った。
1977年1月20日、第39代アメリカ合衆国大統領に就任。内政課題のインフレでは減税策を採ったためかえって増進させ、減税率を引き下げたため、国民の信頼を失った。また1979年2月にイラン革命直面し、第2次石油危機が始まると、エネルギー政策の全面的見直しを提唱、アラブ原油依存体質の転換を図った。
Episode ジミー? フウー
(引用)カーターはジョージア州知事だったが全国的知名度は低く、マスコミも彼を田舎者扱いし、「ジミー、フウー?」(どのジミー?)というありさまだった。それだけに、「アウトサイダー」の自分は汚れたワシントンの中央政治に新風を吹き込むのだというカーターの主張は説得力があり、国民は、「私は決して皆さんに嘘をつきません」と言い切る彼を選んだ。
カーターを支持したのは出身地である南部諸州と黒人であり、黒人は97%が彼に投票した。カーターは就任式早々伝統を破り、式服ではなく仏の背広を着用し、議事堂からホワイトハウスまでの道のりをリムジンカーに乗らず、妻ロザリン、娘エイミーと手をつないで歩き、国民に身近な大統領であることをアピールした。・・・<有賀夏紀『アメリカの20世紀(下)』2002 中公新書 p.122>
カーター外交
その特質は「カーター外交」といわれる外交政策に現れている。まず人権擁護を柱にすえ「人権外交」を掲げ、1977年の新パナマ運河条約(運河建艦条約、1999年の返還で合意)の締結、1978年9月17日のエジプト=イスラエルの和平交渉の仲介(キャンプ=デーヴィッド合意)、1979年の米中国交正常化、ソ連とのSALT・Ⅱ合意などを実現させた。しかしソ連との友好的な関係は同年のソ連軍のアフガニスタン侵攻によって崩れ、カーター政権はモスクワ・オリンピック参加を拒否して対抗し、SALTⅡ合意は破棄された。また同年、イラン革命が勃発、アメリカ大使館人質事件が発生してその解決に失敗し、80年の大統領選挙で共和党のレーガンに敗れ退陣した。 → アメリカの外交政策
退陣後は民主党政権下ではたびたび北朝鮮への特使として派遣され、人質事件の解決などにあたっている。
イラン大使館人質事件
1979年、イラン大使館人質事件がおこると、テレビは連日大使館周辺のデモの映像を流し、人質事件が発生してから「今日で何日目」と連日報道した。「アメリカがこれまで、まったく相手にもしなかったような小国に、突然首根っこを押さえられたために、アメリカ人のフラストレーションは日一日高まった。」来年に予定されていた大統領選で再選を目指していたカーターは、自分の人気が急激に下がり、対抗馬のエドワード=ケネディに水をあけられたことに焦りを感じた。大統領は1カ月後の12月下旬から、ホワイトハウスの閣議室で毎週金曜日に朝食会を開き、関係閣僚、補佐官やスタッフが約50人集まり議論を重ねた。1979年12月のクリスマスにはソ連のアフガニスタン侵攻が始まったので、両方を検討することとなった。これとは別に国家安全保障会議(NSC)の常設下部機関で危機管理に当たる特別調整委員会がホワイトハウス地下の部屋で開かれ、こちらは大統領を除いてさらに徹底的に議論されていたが、決定は朝食会で行われた。まず首席補佐官ジョーダンが特使としてイランに派遣され、国王パフレヴィー2世独裁体制を支援したことを誤りと認め、遺憾の意を表したが、謝罪の言葉は使わなかったので、ホメイニ側に拒絶された。最後の手段としての人質救出作戦が1980年4月11日に決定された。バンス国務長官は軍事作戦は非現実的であり、強行すれば人質52人のうち何人かは処刑されるであろうと強く反対した。ブラウン国防長官、ジョーンズ統合参謀本部議長は賛成し、カーターは救出作戦を許可した。バンスは、たとえ成功しても辞任するとして辞表を提出した。 → 救出作戦の実際はアメリカ大使館人質事件の項を参照。
4月24日、作戦は強行された。しかし、大型ヘリが砂漠の風にあおられて墜落、さらに輸送機に接触して爆発し、作戦は失敗に終わった。バンス長官は予定通り辞任した。
(引用)バンスのような人がもっと多くいたら、この救出作戦は回避できたかもしれなかったという人もいるが、大統領の政治生命の維持が政策決定の重要な基準になり、また大統領自身の決断が、何より決定的力を持つアメリカ合衆国の政治制度の下で、これはなるべくしてなった救出作戦の決定だったと言えるだろう。<飯沼健真『アメリカ合衆国大統領』1988 講談社現代新書 p.135>
退任後、外交で活躍
カーターは在任中は特に大きな外向成果をあげることもなく、むしろ困難な舵取りを強いられて、イラン大使館人質事件に見られるような失敗がめだった。しかし、退任後は前・元大統領として、現職大統領にはできないような身軽さで世界を飛び回り、いくつかの成果を上げている。退任後に成果を上げた元大統領ということで珍しい存在だった。1994年、北朝鮮が金日成のもとで核開発を進めているのではないか、という核疑惑が強まり、米朝関係が緊張した。クリントン大統領政権はカーターに北朝鮮訪問を要請、アメリカの大統領経験者として初めてカーターは北朝鮮入りした。カーター・金日成会談で北朝鮮は核開発凍結と査察の受け入れに合意し、同年の米朝枠組み合意につながった。北朝鮮の核開発はその後再開され、米朝間の緊張は続くこととなるが、カーターのつくったパイプは2010年、不法入国したアメリカ人の解放のために再び訪朝して、交渉の末いっしょに帰国することに成功している。
2002年、キューバを訪れてカストロ首相と会談した。1959年のキューバ革命後、アメリカ大統領経験者で初めてのキューバ入りとなり、関係改善の糸口をさぐった。これがオバマ政権下の2015年の国交回復につながった。これらの元大統領という肩書きを生かした外交努力が評価され、2002年にノーベル平和賞が授与された。
NewS カーター元大統領 100歳で死去
2025年1月9日、ワシントン大聖堂で、昨年12月29日に亡くなったカーター大統領の葬儀が行われた。カーターは歴代大統領経験者で最も長命の100歳だった。葬儀には、1月20日の大統領就任式をひかえたトランプを始め、バイデン、オバマ、クリントン、G.W.ブッシュの歴代大統領が顔をそろえた。 → AFPbbニュース 2025/1/101月20日に大統領就任式に臨んだトランプは、カーターの業績であるパナマ運河のパナマへの返還を、カーターの名を上げなかったものの「愚かな贈り物」として否定し、取り返すことを表明した。カーターは数日の差でこのどんでん返しを聞くことなく、冥界に入った。


