三国時代(中国)
後漢滅亡後の中国に、220~280年、華北の魏・江南の呉・四川の蜀の三国が分立した時代。3~6世紀の長い魏晋南北朝時代という分裂期のはじまりとなった。
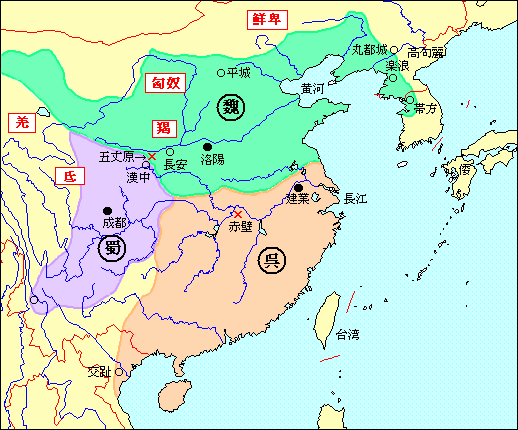
三国時代
220年、曹丕が後漢の献帝の禅譲を受けて魏を建国して皇帝となると、翌221年、劉備が成都で皇帝に即位(昭烈帝)して蜀を建国した。翌々年、孫権は呉王を称し、さらに229年に帝となった。一般に、曹丕が魏帝となった220年から実質的に三国鼎立の状態となったとして、三国時代としている。それ以後も三国の抗争が続き、263年、魏(実権は司馬炎に移っていた)が蜀を滅ぼすが、魏は265年に司馬炎に帝位を奪われて晋(西晋)に代わる。その晋が、280年に呉を滅ぼし、一時中国の統一を回復する。そこまでを三国時代という。この三国の歴史を次の晋の時に陳寿が叙述した正史が『三国志』である。 → 魏晋南北朝時代
三国の国力は対等だったのではない。土地・経済力・人口などの国力を総合すると、およそ、中原の魏が6、長江下流の呉が2、長江上流の蜀が1、の比率だったとされている。しかし、漢末の動乱で最も大きな損失を受けていたのが中原の魏であったこともあって、呉と蜀の分立が可能であった。
魏・呉・蜀の成立
189年に後漢の霊帝が死去してから、各地は群雄割拠という状態となり、漢王朝の統治の実質はなくなっていた。後漢の都洛陽は群雄の一人董卓によって支配され、それに対して後漢皇帝の親衛隊長だった袁紹らが攻撃を加えると、董卓は皇帝献帝を伴って長安に逃れた。そのとき、洛陽は董卓によって焼き払われ、漢の文物はほとんどが失われた。董卓が部下の呂布に殺されるという政変のなか、長安を脱した献帝は、東方に逃れ、曹操に保護された。その結果、後漢の皇帝を擁した曹操が有力となり、200年には袁紹を「官渡の戦い」で破り、華北の実権を握った。また、漢王朝の劉氏一族の血統を継ぐと自称した劉備は、始め曹操に協力したが、曹操が後漢の皇帝に取って代わろうとしていることを疑って決別し、関羽や張飛などの仲間と独自の勢力を築き、さらに207年には諸葛孔明を軍師として迎えた。長江流域の江南では、土豪の孫堅が力をつけ、一時は中央に進出、董卓の軍を破るなど有力となったが、若くして病死し、その子孫策が家臣に殺された後に弟の孫権が立ち、華北の曹操と劉備の争いの間に独立政権を作り上げた。
華北を抑えた曹操は、屯田制を実施するなど国土の回復に努めながら、全土の統一を目指し、南下を開始した。それに対して劉備の軍師諸葛孔明は江南の孫権と連合して曹操にあたる戦略を立て、208年の赤壁の戦いで曹操軍を迎え撃った。この決戦は呉軍の奇襲作戦で曹操軍の大敗となり、曹操の全国統一は頓挫し、その結果、曹操・劉備・孫権の三者が中国を分割支配する天下三分の状態が成立した。劉備は当初、拠点がなかったが、211年に長江上流の四川地方に入り、その地を支配した。
その間も、漢の献帝は依然として曹操の保護下にあり、曹操は216年には魏王に封じられることとなった。しかし220年、曹操が死んで代わって魏王となったその子曹丕はついに献帝に迫って退位させ、禅譲を受ける形にして皇帝文帝として即位し、魏王朝を開いた。こうして形式的にも後漢王朝は滅亡した。
三国の興亡
三国の中では、国力、軍事力の上では魏が圧倒的で、呉が次にあり、蜀は最も国力的には弱く、地方政権的な存在であった。それでも各国とも内部に豪族勢力を抱え、皇帝に権力が集中することはなかったため、いずれも中国全土を支配する力はなく、三分立体制が続いた。魏 魏は最も豊かな黄河流域(華北)を抑えて有力であり、屯田制によって荒廃した国土の復興にあたり、また九品中正による人材登用をはかるなど、法整備に努めたが、武将の司馬懿(仲達)が蜀の諸葛孔明との戦争でよく国を守ったことから実権をふるうようになり、その孫の司馬炎は265年に帝位を奪い、武帝として即位し晋(西晋)を建てる。
呉 呉は米作地帯の長江下流域を支配し、建業(現在の南京)を都とした。始め蜀と連合して魏にあたっていたが、曹操の働きかけを受けた孫権が魏と結ぶこととなり、蜀を攻めて関羽を攻め滅ぼすなど、三国の一角を維持していたが、司馬炎の晋によって280年に滅ぼされ、三国時代が終わる。呉の時代に江南の開発が始まり、さらにその勢力を中国の南方のベトナム方面に拡張した。
蜀 蜀は三国の中で最も国力も小さく、長江上流という地域にあって勢力を拡大することはできなかったが、劉備の死後は後継の劉禅を補佐した諸葛孔明の活躍で魏とはたびたび互角の戦いをした。諸葛孔明は蜀の背後を固めるため、南方の雲南地方にもしばしば兵を出し、その方面への漢人の進出の端緒となった。しかし、諸葛孔明が234年、最後の遠征の途次、五丈原で陣没すると、その後は次第に魏に圧迫され、263年、魏によって滅ぼされた。
