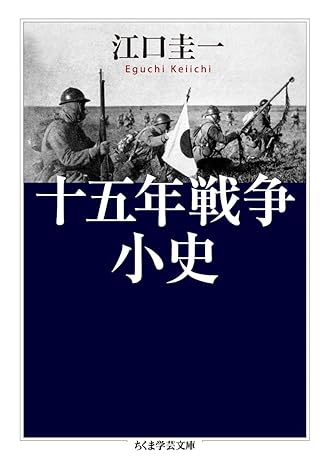満州事変
1931年9月、日本の関東軍が柳条湖事件を契機に中国軍との戦闘に突入、満州を占領した。翌年、満州国を建国。国際的非難の中で、国際連盟から脱退する。国内では軍国主義的傾向が強まり、五・一五事件で政党政治が終わりを告げる。次いで華北への侵略は日中関係をさらに悪化させ、1937年には全面的な日中戦争に突入した。満州事変は1945年まで続く、日中の十五年戦争の始まりとなった。
世界史の中の満州事変
第一次世界大戦後、国際連盟の設立(日本もその理事国であった)や、ワシントン会議、ロカルノ条約などの協調外交の積み重ねの中で、集団安全保障の理念は徐々に具体化されていった。その潮流には1929年に不戦条約を成立させると所までに達し、日本も一部保留しながら調印した。しかし、1929年10月に世界恐慌が始まると、急速に世界情勢は悪化し、ドイツ・イタリアのファシズムが台頭した。日本にもロンドン軍縮会議(1930年)への参加など国際協調も続いていたが、軍部台頭の圧力の間で日本外交は混迷の度を深めていった。そのような中で1931年に満州事変が起こった。世界恐慌とファッシズの台頭という世界情勢の中での満州事変という視点を忘れないようにしよう。また満州事変は、その後、満洲国建国・熱河作戦・華北分離工作・内モンゴル工作など、当時の軍の言葉で言えば「満蒙問題」として続き、1937年の盧溝橋事件をきっかけに日中戦争へと転化していく。さらに日中戦争は太平洋戦争の開始と共に第二次世界大戦への参戦という経過となり1945年の日本の敗戦まで続く戦争の時代の始まりだった。この時期の戦争を総称して十五年戦争とするのは、この満州事変の1931年を起点としている。
柳条湖事件
1931年9月18日、奉天郊外の柳条湖で南満州鉄道が爆破された。日本の関東軍は、それを中国国民軍に属する張学良軍の犯行であると断定し、鉄道防衛の目的と称して反撃し、軍事行動を拡大した。この柳条湖事件から開始された、宣戦布告なしの日中両軍の軍事衝突を満州事変といった。その真相は戦争中は伏せられていたが、戦後になって関東軍の謀略であることが明らかになった。 → 「事変」の意味については、支那事変を参照。この年には6月に中村大尉事件(関東軍の中村震太郎大尉が満州を調査旅行中、現地人に殺害された)や7月に万宝山事件(長春郊外で朝鮮人入植者と中国人が水利権を巡って争い衝突、日本軍が介入した)など緊迫した状況が続いていた。
<注意>高校世界史では、満州事変というと柳条湖事件だけと誤解される恐れがある。しかし関東軍はただちに軍事行動を拡大し、北満洲への出兵、さらに南の錦州への空爆・占領などを強行している。これらはいずれも若槻内閣の不拡大政策を無視して行われ、中国の反発だけで無く、国際連盟とアメリカなどの国際世論を強く刺激し、日本の国際的孤立を決定的にした。翌1932年1月、第1次上海事件を起こし、ついに戦火を中国本土に拡大することとなった。満州事変による中国東北部への支配権を確立するため同年3月満州国を建国。一方で熱河作戦を展開して支配権を河北に拡大、1933年5月の塘沽停戦協定で満州国を承認させた。ここまでの経緯を総合して満州事変として捉える必要がある。
満州全域への拡大
1931年9月18日に一斉に軍事行動を開始した関東軍は、約1万400の兵力を持って奉天、営口、安東、遼陽、長春など南満洲の主要都市を占領した。朝鮮軍は事前に関東軍と打ち合わせて、独断越境を実行し約4000を増援部隊として送った。若槻首相、幣原外相はただちに不拡大方針を決定、陸軍中央も関東軍にそれ以上の行動を認めないとして抑えにかかったが、関東軍はそれらに従わず、戦火を管轄外の北満州に拡大し、翌32年2月までにハルビンを占領した。自国の主権下にある満州で外国の軍隊の軍事行動が拡大されたことを、中国では「九・一八事変」ととらえ、攻撃に対して中国国民党政府で東三省の防備にあたっていた東北軍を指揮する張学良は当時病気療養のため北京に滞在しており、東北軍主力も北京周辺にあったので適切な対応が取れなかった。蔣介石は南京にいて東北を張学良にまかせており、北上の姿勢をとらなかった。関東軍はそれを予測して各要所に迅速に出兵し、一気に満州全域を占領した。
関東軍の意図
満州事変は、中央の日本政府や軍首脳の承認もなく、関東軍中枢の軍人によって計画され、実行された謀略であった。それを推進したのは関東軍参謀の石原莞爾中佐であったとされている。「満蒙(満州と内蒙古)」は日本の自給自足圏として生命線であり、また共産主義の浸透から朝鮮を守る必要があるという陸軍伝統の発想に加え、石原中佐ら関東軍参謀は世界恐慌による不況で満鉄の営業利益が悪化し、しかも張学良が満鉄と競合する新鉄道の建設を進めていることに危機感を持ち、満州を中国政府から分離させ、日本が直接統治すべきであると考え、そのためには政府の承認などの手続きによらず、謀略によって軍事行動を起こすしかない、と思っていた。石原莞爾の構想では、満州は独立させるのではなく日本が直接統治し、それは中国本土まで拡大してはならない、というものであった。なお、石原はソ連は第1次五カ年計画の途中でまだ極東に進出する余裕はないと判断、一方で日本が満州を支配することによって、将来のアメリカとの世界最終戦争に備えるという、妄想ともいえる戦略を構想していたという。日本政府の不拡大方針とその挫折
若槻礼次郎首相のもとで外相を務めていた幣原喜重郎は、関東軍の謀略であることを疑っていたが、自衛のためであるという軍の主張には反論できず、軍事行動は認めざるをえなかった。しかしそれ以上の拡大は認めないという不拡大方針を閣議決定とし、国際世論に配慮して中国側と撤兵を前提とした交渉を開始することとした。国際協調を基本とする幣原外交が配慮しなければならない国際世論とは、日本も加盟している九カ国条約と不戦条約に、日本自身が違反しているという非難であり、中国大陸に利権を持つアメリカ・イギリスの反応であった。帝国陸軍の中枢である参謀本部など軍首脳は出先の関東軍の行動を制御することが出来ず、また軍内部の強行派の勢力も強かったので、関東軍の行動を追認せざるを得なくなった。政府が不拡大方針を決定し撤兵を検討すると、南次郎陸軍大臣の辞任をちらつかせて若槻首相を揺さぶった。「軍部大臣現役武官制」であったため、軍が大臣を出さないとなると内閣を構成することができないからであった。
朝鮮軍の越境 事件勃発直後の9月21日、朝鮮軍司令官林銑十郎は混成第三九師団を越境させ、奉天に向かわせた。朝鮮の守備にあたる朝鮮軍が、国境である鴨緑江を越えて中国に入ることは、大元帥である天皇の命令(奉勅命令)を受け、議会の予算措置が必要であったが、そのような手続きを経ていない独断越境は重大な軍規違反であり、司令官は死刑という規則であった。しかし、軍の圧力で政府はすでに出動したという事実を認め、経費支出を承認した。林銑十郎は軍規違反を問われなかったどころか、“越境将軍”ともてはやされ、後には首相にまでなる人であるが、越境は独断ではなく、事前に詳しく関東軍と打ち合わせており、軍首脳の暗黙の了承があったものと思われる。
錦州爆撃 関東軍は10月8日に錦州に対する空爆を実行した。錦州は奉天と山海関の中間にあり、当時は奉天を追われた張学良が拠点としていた。関東軍は航空部隊を編成、石原莞爾参謀長が自ら成果を確認するため飛行機に乗り込み、爆撃を行った。アメリカのフーヴァー大統領はただちに抗議声明を発表した。それに対して日本は、錦州は匪賊(抗日ゲリラ)の拠点であるから爆撃した自衛措置であり、九カ国条約・不戦条約に違反していないと主張した。しかし、錦州爆撃は第一次世界大戦後、最初の都市爆撃であったことから、世界に衝撃を与え、10月24日に国際連盟理事会はただちに日本軍は撤兵することと決議案を討議した。理事国であった日本のみが反対し、13対1となったが、全会一致で決議する原則だったため国際連盟理事国決議には至らなかった。航空機による都市爆撃は、1937年、ドイツ軍によるゲルニカ爆撃が国際的非難を浴びたが、関東軍の錦州爆撃はそれよりも6年前のことだった。
チチハル占領 さらに1931年11月には北満州のチチハルまで戦線を広げた。チチハルは黒竜江省の省都で東清鉄道と交差する支線にあったが、南満州鉄道(本線)からは離れているので、関東軍の本来の防衛範囲を大きく逸脱する出兵であった。関東軍は張学良に協力している黒竜江省総司令馬占山軍を討伐することを目的に10月30日に北上を開始したが、厳寒の荒野で苦戦し、11月5日には馬占山軍に敗れている。11月19日にようやくチチハルに入城、若槻首相、幣原外相は馬占山討伐後ただちに撤退することを条件にその攻撃を認めていたが関東軍はそのまま占拠を続けた。
政党政治の苦難 民政党若槻礼次郎内閣(第2次)は議会制・政党政治の枠内で軍の独走を阻止しようとしていたが、国内では軍に呼応して強力な軍事独裁政権を作ろうという運動が露骨に行われていた。満州事変より前の3月には陸軍軍人橋本欣五郎らが結成した桜会が、若槻内閣を倒し宇垣一成大将を建てて軍部内閣を樹立しようとした計画が発覚するという三月事件が起こり、10月には桜会メンバーと大川周明の国家主義思想の影響を受けた軍人が、満州事変に呼応して政党内閣を暴力で倒す計画が発覚した10月事件、というクーデタ未遂事件が相次いだ。若槻内閣はこのような脅威にさらされ、軍部を押さえられず、また国際的な非難との間に立たされ、また閣内でも倒閣運動が起きる状況となり、12月11日に総辞職、政友会犬養毅内閣に代わった。その犬養内閣は軍とは比較的良好であったが、1932年になると超国家主義者の井上日召らのテロが相次ぎ(血盟団事件)、軍は新たに第1次上海事件を起こして華中に戦火を拡大、満州国の承認問題が難航する中で、海軍軍人らを主体としたクーデタである五・一五事件で首相が殺害され、戦前の日本の政党政治は終わりを告げる。
諸外国の動き
満州事変に対してアメリカは強く反発し、1932年1月、フーヴァー大統領は国務長官スティムソンの名で、日本の満州における軍事行動は九カ国条約(中国の主権尊重、機会均等、門戸開放の原則)と不戦条約に違反しているので承認できないという声明(スティムソン=ドクトリン)を発表した。しかし経済制裁などの実力行使は行わず、またイギリスも事態が満州に限られている間は黙認するという態度をとった。両国とも世界恐慌のさなかにあって、アジアに干渉する余裕がなかったことが背景にあった。中国政府(蔣介石)は共産党との内戦を優先する(安内攘外)ため、全面的な日本との戦争を避け、もっぱら日本軍の侵略行為を国際連盟規約違反であるとして国際連盟に提訴し、国際世論によって阻止することをめざした。国際連盟では日本も含む常任理事会で中国が提案した撤退勧告が可決されると、日本はなおも自衛行動であること、中国側には治安能力がないこと、などの理由で正当性を主張、調査団を派遣することを提案し、それが実行されることとなった。
ソヴィエト=ロシアでは1924年にレーニンは死んでいたが、1921年からネップ(新経済政策)が採用されて、経済を立て直し、翌年にはソ連邦が成立していた。この時期にソ連の承認が続き、日本とも1925年1月に日ソ基本条約が締結されていた。ついで1928年からスターリンによる第1次五カ年計画が開始され、満州には力をさけない状況になっていた。そのためスターリンは満州事変勃発に対しては中立不干渉を声明した。なおソ連はまだ国際連盟には加盟していない。
ワシントン体制の崩壊 満州事変で日本が公然と中国大陸への侵略を開始し、それをアメリカ・イギリスが阻止できなかった(しなかった)ことは、第一次世界大戦後のアジアの国際秩序とされていた、ワシントン会議(1921~22年)で成立した九カ国条約を柱とするワシントン体制が、事実上崩壊したことを意味している。それは、ヨーロッパにおけるロカルノ体制が、ヒトラーの登場によって破られていくのと時を同じくしており、ヴェルサイユ体制の両輪が崩れたことを意味していた。 問題は国際連盟を舞台とした交渉に委ねられることになったが、第一次世界大戦後に構築された集団安全保障の仕組みが、理事国という立場である日本が引きおこした行動を、アメリカとソ連が加盟していないという状況の下で、機能させることができるかが問われることとなった。
上海事変とその失敗
翌1932年1月、関東軍は北満州の中心地ハルビンを占領、同じ1932年1月、海軍を主体とした日本軍は中国本土で上海事変を起こし、戦火を拡大して中国に圧力を加えた。まさにこの1932年2月、国際連盟(すでにドイツは加盟し、理事国となっていたが、ヒトラー政権成立の前であった)は非加盟国のアメリカとソ連も参加してジュネーヴ軍縮会議を開催し、国際連盟は世界大戦の再発を防止すべく(最後の)努力をしていたのだった。日本の満州事変後の動きに国際的関心が強まっているなかで、上海事変を引き起こすという世界の動きから隔絶した日本の侵略行為は、世界的な理解を得られるはずはなかった。こうして中国本土への侵略は、中国軍の抵抗と国際世論の反発によって失敗し、石原莞爾らも満州の直接支配をあきらめ、陸軍首脳の意向を受けて満州に傀儡政権を樹立する策に転換し、満州国を建設して支配領域を確保する方向へと向かった。満州国の建設
関東軍首脳は当初は満州を直接統治下におくつもりであったが、国際情勢から行ってそれが困難と判断したか、事変開始直後に独立国家建設の方針に転換した。特務機関長土肥原大佐が動き、清朝の最後の皇帝であった溥儀を担ぎ出し、1932年3月に満州国を建設した(当初は溥儀は執政となった)。日本政府の犬養内閣は、満州国の承認をためらっていたが、5月に海軍軍人らによって首相が暗殺されるという五・一五事件が起きて政党政治が終わりを告げ、次の斎藤実内閣が軍部の圧力の下で9月、日満議定書を締結して満州国を承認、軍部の独断で始まった満州事変は国家によって追認された。多くの国民は関東軍の行為を、日露戦争で明治の日本人が血を流して獲得した満州の権益を不当な中国から守ったものとして歓迎した。日本の国際連盟脱退
日本政府は、満州国の建国は満州人の自主的な独立国家の建設であると主張したが、中国は不当な侵略行為であると提訴した。国際連盟はリットン調査団を現地に派遣するとともに双方の主張を聞いた上で報告書を提出した。報告書は柳条湖事件は関東軍の謀略であり、日本の主張である自衛行為であるとは認定できないというものであった。従って日本軍には満州からの撤退が勧告された。ただし満州での日本の一定の権益については認め、満州に自主的な国家が建設されることは容認していた。国際連盟に提出された報告書は、1933年2月の国際連盟総会で審議され、満州国の不承認と日本軍の撤退を42ヵ国の賛成、反対1(日本)、棄権1(シャム)で可決した。1933年3月、日本はそれを不服とする日本は国際連盟を脱退、孤立を深めていく。日中戦争への道
日本は満州国を傀儡国家として建設し、その資源を獲得するとともに多くの移民を送り込み、国内の経済不況を打開しようとした。しかし領土的欲望はとどまることを知らず、満州国に隣接する地域を含めた経済ブロック建設にむかった。熱河作戦 国際連盟での審議が終わっていない1933年2月、早くも関東軍は軍事行動を再開、満州国に隣接する熱河省に出兵、さらに万里の長城の山海関をこえて河北省に侵入し、北平(現在の北京)・天津に迫った。蔣介石は共産党との内戦を優先していたため、本格的な抗日戦を避け、1933年5月末に塘沽停戦協定を締結した。
塘沽停戦協定 この協定は停戦と同時に、中国政府は熱河省まで含めて満州国を承認し、日本軍は長城線まで退くとともに中国軍は河北省の大部分から撤兵する、つまり非武装地帯とするという内容であった。これによって満州事変は一応収束され、戦闘行為はなくなったが、日本はこの非武装地帯をさらに実質支配することをめざし、1935年には華北分離工作を進めて中国本土への侵略を進めることとなる。
盧溝橋事件 1931年の満州事変によって日本と中国は、宣戦布告無き戦争状態に入り、一旦停戦が成立したものの、日本軍の侵略行為はなお続いた。それに対して中国で抗日運動が激しくなる中、1937年に北平付近に駐留していた日本軍が軍事行動を起こして盧溝橋事件が勃発、全面的な日中戦争に突入する。さらに1941年には太平洋戦争に戦線が拡大、1945年の日本の敗北までの15年間にわたり戦争が続くことになるので、満州事変からのこれらの戦争を総称して十五年戦争という。
満州事件の歴史的意味
満州事変は、現地の関東軍の一部幕僚の独断で進められたという側面が強いが、それだけではなく国内の政府・軍中枢内部の同調者の動きがあって初めて可能であり、また天皇・政府・軍首脳が結果的に容認したこともが重要である。議会も政友会・憲政党のいずれも、全体的には「満蒙権益を守れ」という声が大勢だった。また、マスコミや世論も関東軍の行動をむしろ積極的に称賛する方が多かった。国民的な力で戦争への道を止めることはこの時点では困難だった。しかし、国際的な反応は、当事国である中国の提訴を受け、国際連盟の加盟国の多くは、日本の侵略行為と見ていた。その結果、国際連盟理事国であった日本がみずから脱退して国際的孤立への道を選び、次いでファシズム国家との提携に傾斜していく。国内では五・一五事件での犬養首相暗殺によって政党政治が終わり、軍部独裁体制へと向かうという重大な転換をもたらすこととなる。歯止めがなくなった軍国主義的路線は、1937年の日中戦争、さらに1941年の太平洋戦争へと続くこととなり、満州事変は「十五年戦争」のはじまりとなった。
日中の関係回復
満州事変から始まった日本と中国の不正常な関係は、1945年の太平洋戦争の日本での敗戦によってもすぐには解消されず、講和はできなかった。中国で国共内戦が再開され、1949年に中華人民共和国が成立、中華民国政府は台湾に逃れ、1950年6月、朝鮮戦争が勃発するという激動が続いたためもあって、国交回復はなされないままだった。ようやく1972年の田中角栄首相の訪中による日中国交正常化交渉の結果、同年に出された日中共同声明によってであった。従って日中の不幸な戦争状態は日中戦争を挟んで前後40年にわたっていたことになる。