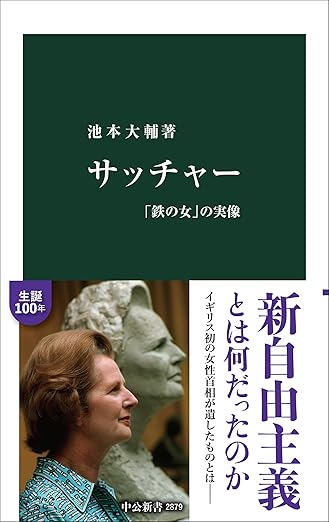サッチャー
1980年代の英首相(保守党)。イギリス経済を再建することを掲げ規制緩和、民営化、福祉政策、社会保障の削減など、新自由主義経済政策を推進した。外交ではフォークランド戦争、アイルランド問題では強硬姿勢を貫いた。

Margaret Hilda Thatcher
1925~2013
1979年~90年の11年間、イギリス首相を務めた女性の保守党政治家。地方都市の雑貨屋の娘(旧姓ロバーツ)という中間階級下層の出身であったが、自助努力をモットーとしたプロテスタントの一派メソジストの両親のもとで育ち、オックスフォードで化学を専攻、科学者の道を歩んでいた。就職に失敗し、政治に関心を向け、保守党集会でデニス=サッチャーと知り合って結婚、夫の支援で政治家を目指すようになり、弁護士の資格を取ると共に財政や税制を勉強、そこでハイエクやフリードマンの新自由主義経済学の影響を受けた。
1959年下院議員選挙に保守党から立って当選し、そこから中産階級の出身であること、何よりも女性であることという当時における強固なハンディキャップを克服するため、エスタブリッシュメント(既存の秩序)への果敢な挑戦を開始した。そして大方の予想を裏切り、政界で見事な立ち回りを見せ、保守党の最初の女性党首となり、さらに1979年にはイギリス史上初の首相となってイギリスを指導、また「鉄の女」the Iron Lady と言われた個性で1980年代という冷戦末期の世界の西側保守主義のリーダーの一人となった。現在では女性政治家は珍しくないが、当時は女性であることが新時代の旗手であるとの評価の重点であった。
また60~70年代は東西冷戦の真っ只中にあったが、ドイツのブラント首相の東方外交などによって緊張緩和(デタント)が始まっていた。ヒース内閣が1975年に東欧圏との融和をはかるヘルシンキ宣言に署名した際、サッチャーは保守派として強硬に反対した。このとき、東側からサッチャーに付けられたあだ名が「鉄の女」だった。つまり国際的反対派から、頭の固い女だ、と揶揄されたのだった。
サッチャーの登場は、男性優位と貴族社会の残滓というイギリスの伝統的価値観や、コンセンサス重視のイギリス政党政治の悪しき慣習に対する革新的で果敢な挑戦であったと同時に、政治的立場は社会主義と既得権益化している労働組合を敵視した保守主義の立場に立ち、冷戦時代が終わろうとしている国際環境の中で大英帝国の栄誉を守ることで大衆の期待に応えたものであった。
フォークランド紛争 そのなかで勃発したのが、1982年のフォークランド戦争だった。サッチャーは国内外の和平の動きをつぶし、強硬路線を撮り続け、この戦争に勝つことによって人気を回復することができた。
アイルランド問題 イギリスがかかえる最も深刻な問題はアイルランド問題であった。イギリスからの分離、アイルランドへの併合を求める北アイルランドのカトリック勢力はアイルランド共和国軍(IRA)による激しいテロをくり返し、北アイルランド紛争は混迷の度を深めていた。サッチャーは一貫してテロに対して厳しい姿勢で臨み、自らもテロの標的となって宿泊先のホテルを爆破されたこともあったが、対決姿勢を崩さなかった。
香港返還 強硬な姿勢を見せる一方、イギリスがかかえる歴史問題であった香港問題に関しては、1984年に中国の鄧小平と交渉、1997年の香港返還を約束、現実的な対応力も示した。
ヨーロッパ統合への関わり 当時のイギリスのもう一つの課題であったヨーロッパの統合の動きに対してはサッチャーは懐疑的な姿勢であった。その結果、西ドイツとフランスに主導権を取られているヨーロッパ連合(EU)とは一線を画し、2002年からの統一通貨ユーロに参加しないという判断となった。
サッチャー時代の終わり しかし、1989年、急速な動きで東西冷戦が終結し、ドイツ統一が実現するという動きはサッチャーの予想を覆す事態であり、イギリスの外交的な役割は低下した。そのような中、サッチャーは財政立て直しのために人頭税の導入をはかろうとしたが、それは国民から強い反対を受け、また保守党内からも長期政権の下で強権的な態度を取るようになった彼女に対する不満も鬱積していった。サッチャーは常に「コンセンサス」を求めるのは「なれ合い」に過ぎないとして嫌っていたが、政権末期には誰の意見も聞かず、側近の首も切ってしまうという行動が目立つようになり、孤立していった。ついに1990年11月、保守党党首を降り、同時に首相も退任した。その11年にわたる首相在任期間はイギリスの歴史の中で、20世紀最長であった。<近藤和彦『イギリス史10講』2013 岩波新書 p.292-296>
脱ケインズ政策 彼女は、早くからケインズ的な公共投資によって雇用を創出し財政出動によるコントロールを重視する経済政策を、社会主義計画経済であるとして否定し、社会保障や福祉政策の拡充による「大きな政府」が経済の発展を阻害すると考えていた。それに対して、できるだけ財政出費を抑え、資本主義本来の市場原理で自由競争を保障する必要があるという「新自由主義」(新古典派、または経済政策は財政によるより通貨の供給を通じて行うべきであるというマネタリズムの考え)の経済政策を採った。
社会保障の削減 サッチャー内閣の経済政策は正に新自由主義に基づいており、財政支出の中で大きな負担となっていた社会保障費の削減を強行し、さらに公共事業、教育予算などを次々と削減、抑制し、一方で規制緩和を推進した。それは、自分の力で生きよ、という美名のもとに弱者を斬り捨てていく結果となった。社会保障の削減で特に標的とされたのが、公的年金制度で、サッチャーはその廃止と、私的年金への転換をはかった。
サッチャリズム このような「小さな政府」や「民営化」などをキーワードとした政策は「サッチャリズム」と言われ、それ以後の各国の保守政党の模範とされ、アメリカのレーガン大統領、日本の中曽根内閣などがそれを継承した。また21世初頭の日本で郵政民営化を進めた小泉内閣もその系譜上にある。<サッチャーについては、森嶋通夫『サッチャー時代のイギリス』1988 岩波新書などを参照>
年金制度改悪の失敗 サッチャー政権の失政として人頭税の導入と並んで個人年金制度の導入失敗が挙げられている。
ブレア労働党政権からブレクジットへ サッチャー後は保守党メジャー内閣が後継となったが、サッチャー時代の反動から脱新自由主義の動きが高まり、民営化の行き過ぎや社会福祉切り捨てへの批判が強まった。それをうけて1997年の総選挙では労働党が圧勝し、ブレア内閣が成立した。ブレアはサッチャー路線を全面的な否定はせず、第三の道を提唱し、イギリス経済の立て直しを図ることとなる。
あれだけ激しかった北アイルランド紛争もサッチャー時代が終わったことで平穏化し、ヨーロッパ連合(EU)との関係も修復された。しかし、ブレアは外交ではサッチャーのような自己主張をせず、イラク戦争ではアメリカに引きずられ、大きな禍根を残すこととなった。さらに冷戦終結後の世界に拡がった、統合よりは分離へ、という動きがイギリス及び、EU懐疑派が台頭、2016年の国民投票でついに分離派が多数を占め、2020年2月1日にイギリスのEU離脱が正式に決まり、BREXIT(ブレクジット)という変動へと突入した。
問題文(前略)第二次世界大戦以降も、イギリスではその時々の経済的、社会的状況に鑑みて、年金制度を含めた福祉制度に対して様々な改革が行われた。次の資料は、20世紀に国営企業の民営化を推し進めた首相が、社会保障費などにかかわる福祉制度の改革を行った後に、インタビューに答えた時のものである。
資料
首相の名 あ アトリー い サッチャー
改革の内容 X 「ゆりかごから墓場まで」と言われた福祉制度を充実させた。
Y 貧民を救済するための救貧法を制定した。
Z 「小さな政府」を実現すべく、社会保障費を見直した。
蛇足 このサッチャーの発言には、国民に対し国家の保護を当てにするのではなく自力で生きよ、というその本音がストレードに現れている。個人が自立し、家族による保護があれば、国家の社会保障費の出費は抑えられるという目算である。国民よ、生活保護や年金に頼らずに、自力で生きていけ、というわけだ。社会など存在しない、個人が生きているだけだ、というそのことばは、日本でも「公助・共助」よりも「自助」だ、という政府の宣伝の中に生きている。
また日本では2000年代に入ってから、さかんに生活保護バッシングや、少子高齢化対策という名目での年金削減が進んでいる。この動きのルーツはサッチャーによる社会保障制度「改革」であり、またその背後には新自由主義の経済思想があった。「改革」というよりはっきりと「後退」というべき施策であり、しかも本家のイギリスではサッチャー後のブレア政権などで行き過ぎた「弱者切り捨て」だったとしてサッチャリズムは修正が図られているのに、日本の政府は1980年代のサッチャー改革を30年遅れでやろうとしている。
筆の滑りが止まらないので書くが、サッチャーがいう「社会なんかない、あるのは家族だ」という発言が、旧来型の家族を理想として、男女平等・夫婦別姓の否定、ましてや同性婚などもってのほかで生産性がない、という発言としてぶりかえされている。「権利を主張するより義務を果たせ」という声は、労働組合や社会運動に対しても向けられている。背景はイギリス病からの脱却がテーマとされていた1980年代のイギリスと、現在の中国や韓国に追い抜かれ長期経済低迷の中にある日本とが共通するのかもしれないが、強烈な劇薬をあえて国民の飲ませようとしたサッチャーが曲がりなりにも国民に(フォークランド紛争でのナショナリズム受けするパフォーマンスで)支持されていたことのに対して、30年という一周遅れの日本では、新自由主義も貫徹できず、政治も経済もギクシャクとしていて時代に合わなくなっていると言えるのではないだろうか。
「世界史の窓」は政治的に偏向していると時々非難されますが、サッチャーを取り上げるのにそれを「改革」だといって持ち上げるのが政治的中立だとは思えません。新春の能登半島地震、羽田空港の衝突事故で目が覚めたところで、共通テストでこの問題を見て、考えさせられたのはサッチャーのやったことは「改革」と評価されるのだろうか?ということです。現代の諸問題と切り離すことのでる歴史なんてありませんね、受験生の皆さんはどう思いますか。<2024/1/27記>
1959年下院議員選挙に保守党から立って当選し、そこから中産階級の出身であること、何よりも女性であることという当時における強固なハンディキャップを克服するため、エスタブリッシュメント(既存の秩序)への果敢な挑戦を開始した。そして大方の予想を裏切り、政界で見事な立ち回りを見せ、保守党の最初の女性党首となり、さらに1979年にはイギリス史上初の首相となってイギリスを指導、また「鉄の女」the Iron Lady と言われた個性で1980年代という冷戦末期の世界の西側保守主義のリーダーの一人となった。現在では女性政治家は珍しくないが、当時は女性であることが新時代の旗手であるとの評価の重点であった。
サッチャー登場まで
イギリスは戦後の労働党政権の下で採られた重要産業国有化と社会保障制度を柱とした福祉国家政策によって財政難が続き、1960~70年代のイギリスが「イギリス病」に陥ったと見られ、さらにオイル=ショックに見舞われていた。1970年に成立した保守党ヒース内閣は有効な手を打つことができず、労働組合のストが相次ぎ、特に1978年末~79年初めは公共部門のストで国民生活の困窮と混迷が続いた。ヒース内閣の教育相に抜擢されたサッチャーは、思い切った教育予算のカット(例えば学校給食でのミルク提供の廃止など)などで一目おかれるようになり、1975年に保守党党首に推され、イギリス最初の女性党首となった。保守党の有力政治家も当初は単に繋ぎとしてしか考えていなかったようだ。また60~70年代は東西冷戦の真っ只中にあったが、ドイツのブラント首相の東方外交などによって緊張緩和(デタント)が始まっていた。ヒース内閣が1975年に東欧圏との融和をはかるヘルシンキ宣言に署名した際、サッチャーは保守派として強硬に反対した。このとき、東側からサッチャーに付けられたあだ名が「鉄の女」だった。つまり国際的反対派から、頭の固い女だ、と揶揄されたのだった。
サッチャーの登場は、男性優位と貴族社会の残滓というイギリスの伝統的価値観や、コンセンサス重視のイギリス政党政治の悪しき慣習に対する革新的で果敢な挑戦であったと同時に、政治的立場は社会主義と既得権益化している労働組合を敵視した保守主義の立場に立ち、冷戦時代が終わろうとしている国際環境の中で大英帝国の栄誉を守ることで大衆の期待に応えたものであった。
サッチャー時代
小さな政府 1979年5月の総選挙でサッチャー党首の保守党が勝利し、5月4日、初の女性首相が誕生した。誰もが2,3年しかもたないだろうと予測していたが、サッチャー内閣は積極的な施策を次々と実行に移していった。まず「小さい政府」を実現すると言う公約を守り、財政難の解消のためとして公共事業の削減と民営化(規制緩和)を進め、福祉事業や社会保障を次々と削減し、抵抗する労働党とその支持母体の労働組合を既得権にしがみついているだけとして攻撃した。その強硬な姿勢は保守層だけでなく大衆に支持され、イギリス経済の回復に大きな期待がかけられた。しかし、目にみえた経済回復は訪れず、かえって競争が激化する中、労働者の解雇、賃金カットが続き、中下層の生活不安が募ってきて、80年代に入ると急速に人気が落ちていった。フォークランド紛争 そのなかで勃発したのが、1982年のフォークランド戦争だった。サッチャーは国内外の和平の動きをつぶし、強硬路線を撮り続け、この戦争に勝つことによって人気を回復することができた。
アイルランド問題 イギリスがかかえる最も深刻な問題はアイルランド問題であった。イギリスからの分離、アイルランドへの併合を求める北アイルランドのカトリック勢力はアイルランド共和国軍(IRA)による激しいテロをくり返し、北アイルランド紛争は混迷の度を深めていた。サッチャーは一貫してテロに対して厳しい姿勢で臨み、自らもテロの標的となって宿泊先のホテルを爆破されたこともあったが、対決姿勢を崩さなかった。
香港返還 強硬な姿勢を見せる一方、イギリスがかかえる歴史問題であった香港問題に関しては、1984年に中国の鄧小平と交渉、1997年の香港返還を約束、現実的な対応力も示した。
ヨーロッパ統合への関わり 当時のイギリスのもう一つの課題であったヨーロッパの統合の動きに対してはサッチャーは懐疑的な姿勢であった。その結果、西ドイツとフランスに主導権を取られているヨーロッパ連合(EU)とは一線を画し、2002年からの統一通貨ユーロに参加しないという判断となった。
サッチャー時代の終わり しかし、1989年、急速な動きで東西冷戦が終結し、ドイツ統一が実現するという動きはサッチャーの予想を覆す事態であり、イギリスの外交的な役割は低下した。そのような中、サッチャーは財政立て直しのために人頭税の導入をはかろうとしたが、それは国民から強い反対を受け、また保守党内からも長期政権の下で強権的な態度を取るようになった彼女に対する不満も鬱積していった。サッチャーは常に「コンセンサス」を求めるのは「なれ合い」に過ぎないとして嫌っていたが、政権末期には誰の意見も聞かず、側近の首も切ってしまうという行動が目立つようになり、孤立していった。ついに1990年11月、保守党党首を降り、同時に首相も退任した。その11年にわたる首相在任期間はイギリスの歴史の中で、20世紀最長であった。<近藤和彦『イギリス史10講』2013 岩波新書 p.292-296>
新自由主義 その内政
内政においてはまず、1970年代に国有化された四部門(鉄道、炭坑、発送電、鉄鋼)と電信電話、社会保険、医療、さらに教育の大部分と住宅の相当部分民営化(privatize)した。脱ケインズ政策 彼女は、早くからケインズ的な公共投資によって雇用を創出し財政出動によるコントロールを重視する経済政策を、社会主義計画経済であるとして否定し、社会保障や福祉政策の拡充による「大きな政府」が経済の発展を阻害すると考えていた。それに対して、できるだけ財政出費を抑え、資本主義本来の市場原理で自由競争を保障する必要があるという「新自由主義」(新古典派、または経済政策は財政によるより通貨の供給を通じて行うべきであるというマネタリズムの考え)の経済政策を採った。
社会保障の削減 サッチャー内閣の経済政策は正に新自由主義に基づいており、財政支出の中で大きな負担となっていた社会保障費の削減を強行し、さらに公共事業、教育予算などを次々と削減、抑制し、一方で規制緩和を推進した。それは、自分の力で生きよ、という美名のもとに弱者を斬り捨てていく結果となった。社会保障の削減で特に標的とされたのが、公的年金制度で、サッチャーはその廃止と、私的年金への転換をはかった。
サッチャリズム このような「小さな政府」や「民営化」などをキーワードとした政策は「サッチャリズム」と言われ、それ以後の各国の保守政党の模範とされ、アメリカのレーガン大統領、日本の中曽根内閣などがそれを継承した。また21世初頭の日本で郵政民営化を進めた小泉内閣もその系譜上にある。<サッチャーについては、森嶋通夫『サッチャー時代のイギリス』1988 岩波新書などを参照>
年金制度改悪の失敗 サッチャー政権の失政として人頭税の導入と並んで個人年金制度の導入失敗が挙げられている。
(引用)サッチャー政権が創設しようとした個人年金制度は、公的年金制度に代替させようとして、加入者に大きな損害を与え大失敗した政策である。推進したのは保険社会保障省である。この制度に対しては、野党・労働党が問題点を繰り返し指摘していた。だが、保険社会保障省はこれをイデオロギー的反対とみなし、真剣に検討することを怠った。貿易産業省も、本来、年金商品の不適正販売という問題は関係するはずであった。しかし、担当閣僚同士がライバル関係にあったこともあり、保険社会保障省が貿易産業省を巻き込んで積極的に協議することはなかった。<高安健将『議院内閣制―変貌する英国モデル』2018 中公新書 p.185>
大英帝国への回帰 その外政
彼女は「ヴィクトリア女王の時代に帰れ」というスローガンを掲げ、大英帝国の栄光の復活を訴え、ヨーロッパ統合には批判的であった。1980年のモスクワ=オリンピックでは前年のソ連のアフガニスタン侵攻に抗議してボイコットを呼びかけ、1982年のアルゼンチンとのフォークランド戦争では精鋭部隊を南大西洋まで派遣して島々を奪回して「国益を守った」として大衆的な人気を回復した。またイギリスの「喉に刺さったトゲ」であるアイルランド問題については、IRAのテロに屈しないという姿勢をくずさなかった。しかし、香港返還では現実的な対応を見せて中国側に妥協し、外交に一貫性がないと一部で批判された。なお当時、南アフリカ共和国では黒人に対するアパルトヘイト政策に対する闘いが強まっていたが、サッチャーはたびたびアパルトヘイトを擁護する発言をして国際的に批判されることもあった。そこにサッチャー外交の体質が現れていると言える。Episode 日本軍に爆撃されてハワイを手放しましたか?
映画『サッチャー鉄の女の涙』を見ていたら、こんなシーンがあった。フォークランド戦争の時、イギリスに軍事行動を思いとどまらせようしたレーガン大統領は特使の国務大臣へイグを派遣、サッチャーを訪問したヘイグが、フォークランドのような遠く離れた島が攻撃されたからといって反撃するのはやりすぎでは、と意見をしたのに対し、サッチャーは「ハワイが日本軍に攻撃されたとき、アメリカは遠い島だからといってハワイの人たちを見捨てましたか?」と逆に質問し、ヘイグを黙らせた。ハワイとフォークランドでは本国から離れていることは同じだが、全く別で比べられないと思うが、サッチャーはヘイグの痛いところを突いたものだ。映画にはなかったが、サッチャーは「大英帝国の一部なら、どんな遠くとも軍を出します」というのが本音だったのだろう。Episode 「鉄の女」のもう一つのニックネーム
サッチャーを「男勝り」と言う表現はジェンダー差別であり許されない。「鉄の女」というのは広く流布した彼女のニックネームだった。なお彼女にはもう一つニックネームがあって、それは「ティナ」(Tina)。これは、彼女が議会答弁で、いつも、There Is No Alternative.(選択の余地はない)と答えたからだそうだ。曲がり角だった1979年
イギリスでサッチャーが首相に就任した1979年は、記憶にとどめておくべき年となった。イギリスがケインズ流の社会民主主義から新自由主義に転換したことは、その後資本主義先進国で追随する動きが続出し、世界経済にも大きな影響を及ぼしていった。この年、世界では、2月のイラン革命からイスラーム圏の激動が始まり、中国では前年に始まった鄧小平の改革開放の動きはこの年に本格化し、明確に資本主義経済の導入が始まった。一方ソ連では12月にアフガニスタン侵攻を強行し、それはソ連崩壊への引き金となったばかりでなく、イスラーム過激派が力を持ち始めるきっかけとなった。それらが10年後の冷戦の終結に収斂し、21世紀の地域紛争とテロの時代へとつながっていく。このように1979年を21世紀の始まりとみる見方も出されている。<クリスチャン=カリル/北川和子訳『すべては1979年から始まった』2015 草思社>サッチャ-後のイギリス
サッチャーは国内改革を強引に押し進め、フォークランド紛争でも戦争を辞さない決断を行って「鉄の女」というあだ名と共に人気が高まったが、その手法には根強い反対もあった。とくに、ドイツが統一によって戦前のような大国となることに懐疑的であったことから欧州統合の動きに対して反対し、国際的には孤立の傾向を強めていった。また経済を立て直したと評価されたものの、格差の拡大と共に社会不安が広がり、最後には財政不安を解消する手段として人頭税を打ち出したために、国民的な支持も失っていった。1990年、保守党党首を辞任し、首相の座も退いてサッチャー時代は終わった。退任後も上院議員として政治に関わったが、2008年、記憶障害の症状(認知症であろう)が進んでいることを公表、2013年に脳溢血で死去した。ブレア労働党政権からブレクジットへ サッチャー後は保守党メジャー内閣が後継となったが、サッチャー時代の反動から脱新自由主義の動きが高まり、民営化の行き過ぎや社会福祉切り捨てへの批判が強まった。それをうけて1997年の総選挙では労働党が圧勝し、ブレア内閣が成立した。ブレアはサッチャー路線を全面的な否定はせず、第三の道を提唱し、イギリス経済の立て直しを図ることとなる。
あれだけ激しかった北アイルランド紛争もサッチャー時代が終わったことで平穏化し、ヨーロッパ連合(EU)との関係も修復された。しかし、ブレアは外交ではサッチャーのような自己主張をせず、イラク戦争ではアメリカに引きずられ、大きな禍根を残すこととなった。さらに冷戦終結後の世界に拡がった、統合よりは分離へ、という動きがイギリス及び、EU懐疑派が台頭、2016年の国民投票でついに分離派が多数を占め、2020年2月1日にイギリスのEU離脱が正式に決まり、BREXIT(ブレクジット)という変動へと突入した。
出題 2024年共通テストでサッチャー登場
2024年1月13日の大学入試共通テスト「世界史B」第1問(抜粋)で次のような出題があった。問題文(前略)第二次世界大戦以降も、イギリスではその時々の経済的、社会的状況に鑑みて、年金制度を含めた福祉制度に対して様々な改革が行われた。次の資料は、20世紀に国営企業の民営化を推し進めた首相が、社会保障費などにかかわる福祉制度の改革を行った後に、インタビューに答えた時のものである。
資料
あまりにも多くの子どもや大人たちが、自分たちの問題を社会に転嫁しています。でも社会とは誰のことを指すのでしょうか。社会などというものは存在しないのです。存在するのは、個々の男と女ですし、家族です。そして、最初に人々が自分たちの面倒を見ようとしない限りは、どんな政府だって何もできはしないのです。自分で自分の世話をするのは私たちの義務です。それから、自分たちの隣人の面倒見ようとするのも同じように義務です。最初に義務を果たさないならば、権利などというものは存在しないのです。
問9 前の文章を参考にしつつ、インダビューで資料のように答えた首相の名あ・いと、その人物が行った改革の内容として推測できることについて述べた文X~Zとの組合せとして正しいものを選べ。首相の名 あ アトリー い サッチャー
改革の内容 X 「ゆりかごから墓場まで」と言われた福祉制度を充実させた。
Y 貧民を救済するための救貧法を制定した。
Z 「小さな政府」を実現すべく、社会保障費を見直した。
答え
首相の名 い 改革の内容 Z
蛇足 このサッチャーの発言には、国民に対し国家の保護を当てにするのではなく自力で生きよ、というその本音がストレードに現れている。個人が自立し、家族による保護があれば、国家の社会保障費の出費は抑えられるという目算である。国民よ、生活保護や年金に頼らずに、自力で生きていけ、というわけだ。社会など存在しない、個人が生きているだけだ、というそのことばは、日本でも「公助・共助」よりも「自助」だ、という政府の宣伝の中に生きている。
また日本では2000年代に入ってから、さかんに生活保護バッシングや、少子高齢化対策という名目での年金削減が進んでいる。この動きのルーツはサッチャーによる社会保障制度「改革」であり、またその背後には新自由主義の経済思想があった。「改革」というよりはっきりと「後退」というべき施策であり、しかも本家のイギリスではサッチャー後のブレア政権などで行き過ぎた「弱者切り捨て」だったとしてサッチャリズムは修正が図られているのに、日本の政府は1980年代のサッチャー改革を30年遅れでやろうとしている。
筆の滑りが止まらないので書くが、サッチャーがいう「社会なんかない、あるのは家族だ」という発言が、旧来型の家族を理想として、男女平等・夫婦別姓の否定、ましてや同性婚などもってのほかで生産性がない、という発言としてぶりかえされている。「権利を主張するより義務を果たせ」という声は、労働組合や社会運動に対しても向けられている。背景はイギリス病からの脱却がテーマとされていた1980年代のイギリスと、現在の中国や韓国に追い抜かれ長期経済低迷の中にある日本とが共通するのかもしれないが、強烈な劇薬をあえて国民の飲ませようとしたサッチャーが曲がりなりにも国民に(フォークランド紛争でのナショナリズム受けするパフォーマンスで)支持されていたことのに対して、30年という一周遅れの日本では、新自由主義も貫徹できず、政治も経済もギクシャクとしていて時代に合わなくなっていると言えるのではないだろうか。
「世界史の窓」は政治的に偏向していると時々非難されますが、サッチャーを取り上げるのにそれを「改革」だといって持ち上げるのが政治的中立だとは思えません。新春の能登半島地震、羽田空港の衝突事故で目が覚めたところで、共通テストでこの問題を見て、考えさせられたのはサッチャーのやったことは「改革」と評価されるのだろうか?ということです。現代の諸問題と切り離すことのでる歴史なんてありませんね、受験生の皆さんはどう思いますか。<2024/1/27記>