建艦競争(イギリスとドイツの)
19世紀末から20世紀初頭、ドイツとイギリスが軍艦の建造を競った海軍軍備拡張競争。ドイツは世界政策を掲げるヴィルヘルム2世のもと、ティルピッツが主導して1898年の第1次、1900年の第2次艦隊法で海軍増強を図った。それまで世界の海軍国として優位を保っていたイギリスは重大な挑戦と受け止めて、対抗する海軍軍拡を開始した。1905年に大型戦艦の建造に着手して競争はエスカレート、第一次世界大戦まで続いた。帝国主義の時代における列強の軍備拡張競争の最も典型的な例と言える。
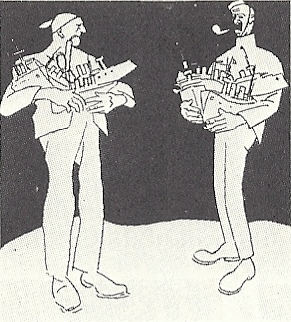
建艦競争
ドイツ帝国はヴィルヘルム2世の世界政策のもとで海軍大臣ティルピッツが主導し、イギリスに対抗するため海軍増強策を立案、1898年3月に帝国議会で第1次の艦隊法を制定して6年間の長期にわたる軍艦その他の建造をみとめさせ、さらに1900年6月に第二次艦隊法で軍艦建造計画を倍増させた。事実、ドイツ艦隊は、アジアでの中国分割、モロッコ事件、アフリカ植民地獲得、太平洋への進出など、活動領域を拡大していった。
それに対して、世界最大の海軍力を誇り、海外各地の植民地支配を展開していたイギリスは、重大な挑戦と受け止め、海軍力の増強に力を入れ、ドイツの世界政策を阻止しようとする動きを強めた。両国はその後それぞれの国力、工業力を挙げてて艦隊建造を競った。1905年にはイギリスはドレッドノート級といわれる大型戦艦の建造を開始、ドイツもそれに対抗して潜水艦の建造を開始、建艦競争は歯止めなく進行した。二国間の競争がそれぞれの経済負担が増大したため、たびたび両間の調停が試みられたがいずれも失敗し、第一次世界大戦へと突入した。
第1次艦隊法 ヴィルヘルム2世は1897年4月の演説で「世界のいたるところで、われわれはドイツの市民を保護しなければならず、またいたるところでドイツの名誉を守らなければならない」と揚言し、そのための制海権の重要性を強調した。同年6月にティルピッツが海軍大臣に就任、それまで陸軍に対して手薄だったドイツ海軍の建設に着手した。同年11月、ドイツ人宣教師が山東省で殺害されると直ちに艦隊を派遣して膠州湾を占領した。ヴィルヘルム2世はこの事件を捉え、ただちに海軍力の増強の必要を強調して、ティルピッツに7年計画の海軍増強案を作成させ、帝国議会に上程した。その骨子は戦艦7隻、大型巡洋艦2隻、小型巡洋艦17隻を建造するというもので、保守党、国民自由党と中央党(一部を除く)が賛成、反対する政党もあったがわずかな修正を加えただけで、1898年3月に賛成多数で可決・成立した。この第一次艦隊法は規模はまだ小さかったが、長期間の建艦事業が継続できるようになったことが重要で、ヴィルヘルム2世は9月に「ドイツの将来は海上にあり」と高らかに叫んだ。
第2次艦隊法 1898年の中国分割、ファショダ事件、米西戦争に続き、1899年には南アフリカ戦争、義和団事件が勃発して国際危機が高まる中で、ヴィルヘルム2世は海軍力のさらなる強化に乗り出し、1900年6月、ティルピッツ海相に第2次建艦法を帝国議会に上程させた。これは戦艦38隻,大型巡洋艦14隻、小型巡洋艦38隻という、第1次に倍増する大軍拡であったが、議会ではほとんど反対がなく、6月に通過・公布された。その後もティルピッツは艦隊法に修正を加え「世界最強の海軍」をめざした。この年、4月には中国で義和団事件が起こり、ドイツ人外交官が殺害されると、8月には8カ国連合軍が北京に入城、ドイツ軍も参加してた。こうしてドイツの世界政策は現実のものとなっていった。
ドイツの「結集政策」 それでは議会はなぜ大きな財政負担が想定される艦隊法に合意したのだろうか。当時議会の与党の保守党はエルベ川以東の大土地所有者ユンカーが支持基盤であったから、地主の利益とは無関係な建艦政策には批判的だった。建艦政策推進の中核的政党の国民自由党はラインラント、ヴェストファーレン、シュレジェン(の北部)などの重工業を代表する政党で、造船・鉄工業・機械・石炭・火薬の増産そのものに期待し、帝国党もドイツの世界強国かを支持した。以上三つの与党に対して、野党の社会民主党は社会主義者鎮圧法が廃止されて以降、急成長していた。中央党はカトリックという宗教的基盤があり、プロテスタントのプロイセン勢に反発していた。当時の議会では与党三党では過半数を取れない状況だったが、まず与党を結束させる必要があり、そこで編み出されたのが「結集政策」であった。
艦隊法の議会通過 結集政策とは地主に対しては農業関税率を引き上げを約束し(それによって国内農業を保護するという保護主義)、一方の工業家には海軍軍拡で利益を保証する(つまり工業製品を輸出でなく国内の軍備に充てる)というもので、大土地保有者と重工業資本家を結集しようとしたのだった。社会民主党と自由主義政党は反対を明確にしていたので、キャスティングボートを握ったのは中央党であった。1897年11月、中国山東省でドイツ人カトリック宣教師が殺害された事件の直後に政府が海軍力増強をめざす第一次艦隊法を上程すると、中央党のバイエルン派が反対しただけで、他が賛成に回り、翌98年3月28日に賛成212,反対139で可決された。社会民主党と中央党の一部、いくつかの自由主義小政党の反対は押し切られた。<義井博『ヴィルヘルム2世と第一次世界大戦』2018 清水書院 p.60-61>
ドイツ帝国のジレンマ 大地主層(ユンカー)のために保護関税施策によって小麦輸入にはトンあたり3.5マルクから5.5マルクに引き上げられ、「ドイツ国民は高いパンを食べなければならなくなった」。そしてこの穀物関税収入引き上げによって軍艦建造の費用は調達され、それが重工業資本家を富ませることになった。
一方ドイツは、バルカン方面ではオーストリアとともにロシアの南下と敵対しており、次第に英独の二国間競争という形態ではなく、英仏露の三国協商と独墺を軸とした三国同盟の軍事同盟間の対立へと転換し、1914年の第一次世界大戦勃発へと向かった。
それに対して、世界最大の海軍力を誇り、海外各地の植民地支配を展開していたイギリスは、重大な挑戦と受け止め、海軍力の増強に力を入れ、ドイツの世界政策を阻止しようとする動きを強めた。両国はその後それぞれの国力、工業力を挙げてて艦隊建造を競った。1905年にはイギリスはドレッドノート級といわれる大型戦艦の建造を開始、ドイツもそれに対抗して潜水艦の建造を開始、建艦競争は歯止めなく進行した。二国間の競争がそれぞれの経済負担が増大したため、たびたび両間の調停が試みられたがいずれも失敗し、第一次世界大戦へと突入した。
ドイツの外交政策転換
ドイツは19世紀後半に普仏戦争の勝利を契機としてドイツ帝国を成立させ、ビスマルクの主導のもと、工業化を達成するとともに軍国主義態勢を作り上げ、19世紀末の帝国主義時代には世界の強国の一つとされるに至った。その背景には第二次産業革命が急速に進行したことが挙げられる。しかしビスマルク外交は勢力均衡論に基づき、列強のバランスを重視するものであり、また植民地獲得ではイギリス、フランスに後れを取っていた。1888年に皇帝となったヴィルヘルム2世は、1890年にビスマルクを辞任させ、ドイツの対外政策を大きく転換させた。ドイツの艦隊法制定
ウィルヘルム2世のドイツは1898年に第1次の艦隊法を制定、戦艦、巡洋艦を含む艦隊計画を実施に移した。さらに、1901年の第2次の建艦法で、艦隊建造予算は単年度ではなく数年にわたる予算として決定し、議会の抵抗を抑えた。海軍拡張計画は主として海軍大臣のティルピッツによって立案、推進された。第1次艦隊法 ヴィルヘルム2世は1897年4月の演説で「世界のいたるところで、われわれはドイツの市民を保護しなければならず、またいたるところでドイツの名誉を守らなければならない」と揚言し、そのための制海権の重要性を強調した。同年6月にティルピッツが海軍大臣に就任、それまで陸軍に対して手薄だったドイツ海軍の建設に着手した。同年11月、ドイツ人宣教師が山東省で殺害されると直ちに艦隊を派遣して膠州湾を占領した。ヴィルヘルム2世はこの事件を捉え、ただちに海軍力の増強の必要を強調して、ティルピッツに7年計画の海軍増強案を作成させ、帝国議会に上程した。その骨子は戦艦7隻、大型巡洋艦2隻、小型巡洋艦17隻を建造するというもので、保守党、国民自由党と中央党(一部を除く)が賛成、反対する政党もあったがわずかな修正を加えただけで、1898年3月に賛成多数で可決・成立した。この第一次艦隊法は規模はまだ小さかったが、長期間の建艦事業が継続できるようになったことが重要で、ヴィルヘルム2世は9月に「ドイツの将来は海上にあり」と高らかに叫んだ。
第2次艦隊法 1898年の中国分割、ファショダ事件、米西戦争に続き、1899年には南アフリカ戦争、義和団事件が勃発して国際危機が高まる中で、ヴィルヘルム2世は海軍力のさらなる強化に乗り出し、1900年6月、ティルピッツ海相に第2次建艦法を帝国議会に上程させた。これは戦艦38隻,大型巡洋艦14隻、小型巡洋艦38隻という、第1次に倍増する大軍拡であったが、議会ではほとんど反対がなく、6月に通過・公布された。その後もティルピッツは艦隊法に修正を加え「世界最強の海軍」をめざした。この年、4月には中国で義和団事件が起こり、ドイツ人外交官が殺害されると、8月には8カ国連合軍が北京に入城、ドイツ軍も参加してた。こうしてドイツの世界政策は現実のものとなっていった。
イギリスの海軍増強
ドイツの海軍大拡張は当然イギリスを刺激し、海軍増強に乗り出した。1905年にドレッドノート級(弩級)戦艦の建造に着手すると、ドイツも計画を拡大、さらに1908年には毎年4隻の戦艦建造を計画した。それに対してイギリスは「二国標準主義」を唱え、ドイツの4隻に対して8隻建造する計画を立てた。こうして両国の建艦競争は果てしなくくり返される様相を呈し、次第に両国の財政負担を圧迫していった。参考 イギリスの「二国標準主義」
イギリスの「二国標準主義」とはドイツの2倍の戦艦を建造する、という意味ではなく、それ以前からイギリス海軍の基本方針でとして海軍力世界第一位の優位を保つには、海軍力第二位と第三位の二国の合計海軍力を上まわっている必要があるという思想のことを言う。19世紀末までは第二位がフランス、第三位がロシアだったが、フランス海軍は伸び悩み、ロシア海軍が日露戦争で敗れたことにより、情勢は大きく変化し、1905年からは第二位がアメリカ、第三位がドイツとなった。イギリスはそれぞれ相手を仮想敵国の対象とするようになった。ここからイギリスはドイツの海軍力の増大を抑える必要があると意識し、建艦競争が本格的にスタートする。<この項、代ゼミ教材センター越田氏のご教示による>Episode “超弩級”の意味
最近はあまり聞かれないが、以前は良く“超弩級の大作”とか“超弩級のスペクタクル”などと映画の宣伝によく使われていた。この“超弩級”とは、弩級を超えるという意味で、弩級とはイギリスの戦艦ドレッドノート号クラスのこと。超ド級と書いてもよい。ドレッドノート Dreadnought とは「恐れを知らない」という意味で、ドレッドノート号は1906年に建造された排水量17900トンで30センチ砲10門を備えていた(広辞苑)。それを超える大型戦艦を超弩級といったわけで、建艦競争時代の言葉として日本でも大正年間からよく使われた。しかしその後、大艦巨砲時代に突入すると、各国の戦艦は殆ど「超弩級」となった。第二次世界大戦期には日本海軍の戦艦「大和」(排水量64000トン)や「武蔵」(排水量65000トン)が建造されたが、その頃には航空機の発達で無用の長物になってしまった。ティルピッツの「危険」理論
帝国主義の全地球的な拡大によって、海軍力が世界の強国としての地位を得る条件であると考えられるようになり、各国が海軍の強大化を競ったが、そのなかでも特に急激な艦隊の建設を推進したのがドイツであり、それを提唱したのが海軍大臣ティルピッツであった。ティルピッツは、他国がドイツ海軍と戦う場合に、それによって危険にさらされることを覚悟しなければならない程度にドイツ海軍を強化するという理論(?)をたて、それは「危険」理論といわれた。このティルピッツの理論は、ドイツの世界政策をささえるものでもあった。<岡部建彦『二つの世界大戦』世界の歴史20 1978 講談社 p.15>建艦競争を支えたドイツの国家体制
この途方もない建艦競争はどのようにして可能だったのだろうか。またその財政的裏付けはあったのだろうか。まずドイツ帝国(第二帝国)の特異な国家体制を知る必要がある。ドイツではドイツ皇帝の権限が強大で、帝国議会は成年男子普通選挙によって議員が選出される当時のヨーロッパの中では最も進んていたが、実態は議会の権能は弱かった(議院内閣制ではなかった)。それでもドイツの軍拡は皇帝の勅令ではなく、議会の合意の上で進められたことは重要である。ドイツの「結集政策」 それでは議会はなぜ大きな財政負担が想定される艦隊法に合意したのだろうか。当時議会の与党の保守党はエルベ川以東の大土地所有者ユンカーが支持基盤であったから、地主の利益とは無関係な建艦政策には批判的だった。建艦政策推進の中核的政党の国民自由党はラインラント、ヴェストファーレン、シュレジェン(の北部)などの重工業を代表する政党で、造船・鉄工業・機械・石炭・火薬の増産そのものに期待し、帝国党もドイツの世界強国かを支持した。以上三つの与党に対して、野党の社会民主党は社会主義者鎮圧法が廃止されて以降、急成長していた。中央党はカトリックという宗教的基盤があり、プロテスタントのプロイセン勢に反発していた。当時の議会では与党三党では過半数を取れない状況だったが、まず与党を結束させる必要があり、そこで編み出されたのが「結集政策」であった。
艦隊法の議会通過 結集政策とは地主に対しては農業関税率を引き上げを約束し(それによって国内農業を保護するという保護主義)、一方の工業家には海軍軍拡で利益を保証する(つまり工業製品を輸出でなく国内の軍備に充てる)というもので、大土地保有者と重工業資本家を結集しようとしたのだった。社会民主党と自由主義政党は反対を明確にしていたので、キャスティングボートを握ったのは中央党であった。1897年11月、中国山東省でドイツ人カトリック宣教師が殺害された事件の直後に政府が海軍力増強をめざす第一次艦隊法を上程すると、中央党のバイエルン派が反対しただけで、他が賛成に回り、翌98年3月28日に賛成212,反対139で可決された。社会民主党と中央党の一部、いくつかの自由主義小政党の反対は押し切られた。<義井博『ヴィルヘルム2世と第一次世界大戦』2018 清水書院 p.60-61>
ドイツ帝国のジレンマ 大地主層(ユンカー)のために保護関税施策によって小麦輸入にはトンあたり3.5マルクから5.5マルクに引き上げられ、「ドイツ国民は高いパンを食べなければならなくなった」。そしてこの穀物関税収入引き上げによって軍艦建造の費用は調達され、それが重工業資本家を富ませることになった。
(引用)たしかに、結集政策によって、ドイツ帝国の支配階級であるユンカーと重工業資本家とは利益を保証された。だがしかし、それに目を奪われているあいだに、この政策の裏面にひそむ危険を抜本的に検討しなかったことこが、ドイツ帝国を一路破滅へのコースに追い込む結果を招いた。というのは、農産物関税はロシアとの友情を、また海軍拡張がイギリスとの友情のために、ともに決定的にマイナスの要因となることを看過していたからである。結集計画はこの点に致命的な欠陥がひそんでいたのであり、ドイツは第一次世界大戦の敗戦と革命による支配階級の崩壊にいたるまでこのジレンマから脱出できなかったが、それはドイツ帝国の国家構造に根ざす自己矛盾であったといえよう。<義井博『ヴィルヘルム2世と第一次世界大戦』2018 清水書院 p.65>
建艦競争から世界大戦へ
イギリス・ドイツの二国間軍拡はこうして展開されたが、その一方でイギリスは単独でのドイツ包囲は困難と判断してフランスとの提携を重視するようになり、1904年に英仏協商を成立させた。またドイツの3B政策は、イギリスの3C政策との対立、二度にわたるモロッコ事件などでイギリス・フランスの提携は強まり、1913年には英仏海軍協定を締結、イギリス海軍は主力を北海に置き、フランス海軍は地中海に置くことで合意し、ドイツ海軍に備えることとした。一方ドイツは、バルカン方面ではオーストリアとともにロシアの南下と敵対しており、次第に英独の二国間競争という形態ではなく、英仏露の三国協商と独墺を軸とした三国同盟の軍事同盟間の対立へと転換し、1914年の第一次世界大戦勃発へと向かった。
海軍軍縮「海軍休日」へ
大戦後、ヴェルサイユ条約によってドイツの軍備制限は大幅に実施され、ドイツは海軍力をほぼ失った。代わってイギリスに対抗できる海軍力を持ったのはアメリカ合衆国であり、それとともに日本であった。日本は日露戦争で勝利し、第一次世界大戦では被害を受けることなく軍備拡張の機会を得て新たな海軍大国として登場した。世界大戦後の国際協調の気運が高まる中で、平和維持のためには列強と言われた国々が歩調を合わせて軍備拡張路線を放棄する必要が認識されるようになり、特に海外領土獲得手段としての海軍力の制限が課題となったが、そこでの制限の対象となったのは日本の海軍力であった。国際協調の最初の成果は、1921年からのワシントン会議によって翌1922年にワシントン海軍軍備制限条約が締結された事に現れた。これは主力艦を対象としたものであったが、その締結によって新規の戦艦建造はできないことになったので建艦競争の時代は終わり、海軍休日(建艦休日)といわれる時代となった。しかし、海軍力はイギリスとアメリカの優位が固定されたため、日本海軍には強い不満が残るものであった。繰り返された軍拡競争
第一次世界大戦前のイギリスとドイツの建艦競争と同じような軍拡競争は、第二次世界大戦後の冷戦時代に米ソの核兵器開発競争として再現された。しかしこの競争は、アメリカ・ソ連ともにその経済や社会を行き詰まらせることになり、両者は中距離核戦力全廃条約で「おたがいにやめましょ」方式でその制限に同意せざるを得なくなった。核戦争防止協定も成立している。しかし、ワシントン海軍軍縮条約がイギリス・アメリカの優位を維持するために妥協したものであったのと同じように、核不拡散条約(NPT)は核保有国を固定化するという妥協の道を選んだ。こう見てくると、軍縮協定は当事者だけでなく「みんなでやめましょ」方式でなければ意味がないというのが歴史の教訓であるようだ。
