科挙
中国の隋に始まり、唐で発展し、宋で変質しながら、元での一時的停止を挟み、明・清まで継承された官吏登用制度。中国の各王朝の皇帝政治を支える官僚を実力試験方式で選抜するもので、儒学の学識を基礎にした作文や詩文の能力が重視された。清朝末期の1905年に廃止された。なお、朝鮮・ベトナムなど周辺諸王朝でも実施された。
科挙の概略 中国では官吏選任は選挙といわれ、漢の武帝の時の郷挙里選で最初の整備が行われた。その後、三国時代の魏で九品中正制が始まったが、門閥貴族による高級官僚独占の弊害が生じ、有効な人材登用には至らなかった。そこで隋の文帝(楊堅)は九品中正制を廃止して、587年に学科試験による官吏登用制度を始めた。その制度が「科目による選挙」という意味で「科挙」と言われるようになった唐の時代であるが、実質的には隋の文帝に始まるとしてよい。
科挙制度は実質的には唐で整備された。その試験内容として儒学の経典が課せられ、儒学・儒教は官吏の必須の教学となったため、知識層に深く浸透し、また詩文の能力も重視されたことから、漢詩の創作が競われることとなり、唐詩の最盛期をもたらした。
その後、宋(北宋)に科挙制度は整備され、最終試験に殿試が設けられるなど、皇帝専制政治を支える官僚の登用法として完成した。宋代では科挙合格者は上級官僚として士大夫とよばれ、支配層となると同時に文化の担い手として存在した。
次のモンゴル人による征服王朝である元では一時停止されたが、その末期には復活し、次の明でも大規模に行われようになった。清朝は女真(満洲人)が中国を支配した国家であったが、科挙制は明代を継承して続けられ、清末には科挙によって登用された漢人官僚が重要な役割を果たした。明・清では科挙の前に学校試が組み込まれるという改革があった程度でその基本システムは変更されなかった。19世紀になるとアヘン戦争、太平天国の乱という激動を経て中国社会の改革が求められるようになったが、科挙制度は維持され、ようやく、清末の改革のひとつとして1905年に廃止されるまで続いた。
科挙制はヨーロッパにも知られるようになると、フランスの啓蒙思想家ヴォルテールは、科挙のシステムを高く評価している。たしかに一つの官吏登用システムが6世紀から20世紀まで(中断はありながら)続いたことは他に例を見ない。
なお、科挙の受験資格は男性だけであったが、清末の太平天国では、1853年に一度だけ女性のための科挙(女科)が実施された。これはまったく例外的なものである。
さらに科挙は、隋・唐に律令制度とともに周辺諸地域の国家で採用された。朝鮮半島では高麗が958年に科挙を導入、次の朝鮮王朝(李朝)でも継承され、この間、科挙合格者の家系は両班として支配階層を形成していった。ベトナムでは李朝の時、1075年に科挙が導入されている。このように科挙制は長期にわたって継承され、アジアの周辺諸国にも影響を及ぼした制度であった。ただし、日本では律令制度や儒教の理念は受容したが、科挙は導入されなかった。
「科挙」については、主として清代のことをとりあつかった本であるが、<宮崎市定『科挙』-中国の試験地獄- 1963 中公新書・中公文庫>がおもしろい。様々な不正受験(カンニングや替え玉受験など)の話などを知ることが出来る。
(1)隋・唐の科挙制
三国時代の魏の九品中正制に替わる官吏登用制として、隋で学科による選抜が始まった。それが唐で制度と整備され、特に則天武后の頃から官僚制度をささえるシステムとして出来上がった。
隋の選挙制
魏に始まる九品中正制は、地方の豪族層を貴族階級として固定化させ、門閥貴族を生み出した。中国を統一した隋の文帝(楊堅)は、世襲的な貴族の優先権を一切認めず、中央と地方の官僚を門閥にとらわれずに人材を登用することを目指し、試験による官吏登用制度を採用した。官吏登用は一般に「推挙された者を選抜する」意味で「選挙」と云われていたが、ここに初めて試験を導入したのが隋であった。「科挙」とは科目による選挙を略した言葉で、唐代に使われるようになるが、その始まりは隋の文帝の587年としてよい。ただ隋代では毎年の合格者は数名程度にすぎなかった。制度として完成するのは唐代を経て10世紀の宋代である。唐の科挙制
唐は隋の制度を継承し「科挙」といわれるようになったが、当初はそれほど重視されたわけではなく、また官僚もすべてが科挙で選ばれたわけではなかった。貴族(魏晋南北朝時代以来の門閥貴族)には蔭位の制があって、科挙を受けなくとも父親の官位で子どもが一定の高位につくことができ、そのような官僚を任子と言われていた。始めは任子が優勢で科挙で選ばれた進士はそれを補う形だった。このように唐の前半までは貴族(門閥貴族)社会であったといえる。唐の科挙制の充実
唐の中期頃まではこのような状況であったが、則天武后の政治では旧来の貴族が排除されて科挙合格者が重用されることがあり、一旦それは元に戻ったが、安史の乱後の唐朝後期には科挙合格者の官僚が次第に力をつけるようになってきた。門閥派(任子出身者)と科挙派(科挙合格者)はそれぞれ党派をつくるようになった。特に科挙合格者は、試験官と合格者、あるいは同期合格者などの間で朋党を結成する傾向が強く、9世紀前半には皇帝をそっちのけにして両派の党争(門閥派の李徳裕と科挙派の牛僧孺の対立なので「牛李の争」という)が約40年にわたって続き、政治が混乱した<宮崎市定『大唐帝国-中国の中世-』 1968 中公文庫 p.392>。科挙の実際
科挙を受けるものはまず、地方の国子監が管轄する国子学以下の国立学校で学ぶ必要があったが、まもなく国子学は有名無実化し、地方官の推薦を受けたもの(郷貢)が受験するようになった。科目には秀才科、明経科、進士科などがあった。秀才科は時事問題についての小論文、明経科は経書の解釈が問われ、進士科は詩賦(詩文)の能力を問われるものであった。明経科の経書の解釈にあっては、はじめは様々な解釈が行われていて基準がなかったため、太宗は孔穎達に命じて『五経正義』を編纂させ、基準とした。三科の中ではじめは秀才科が重視されたが、次第に行われなくなり、その名は科挙試験受験資格者を意味するようになった。明経科と進士科が残ったが特に進士科が官吏の登竜門とされて人気があり、競争率は明経科が10倍程度、進士科は百倍と言われた。官吏は科挙の合格者から選ばれるのを原則としたが、高級官吏の子供には一定の官位に任官するという蔭位の制があり、有利であったので、完全な試験による人材登用制度とは言い切れない面もあった。科挙は厳密に言えば官吏資格試験であり、省試といわれる本試験の実施事務は尚書省の礼部が管轄(736年より)していた。実際に官吏になるためには吏部の行う吏部試によって任用されなければならなかった。(2)宋の科挙制
唐末から五代にかけての騒乱で貴族層が没落、宋の太祖趙匡胤は皇帝専制体制を支える官吏選抜法として、科挙の最終試験に殿試を加えるなどの改革を行い、科挙制を完成させた。
貴族の没落と科挙の変質
五代の争乱の中で荘園を失った貴族は没落し、宋の時代にはまったく没落して、皇帝独裁政治の確立と共にそれを支える士大夫(地主、知識人層)が科挙合格者として官僚層を形成することとなる。宋の太祖趙匡胤の時に殿試が加えられるなど、科挙制度の整備によってそれが完成され、以後は元では一時停止されたが明で復活し、清朝まで官僚登用制度として継続、清末期の1905年に科挙は廃止されるまで続いた。宋代の科挙制度の完成
科挙が、誰でも受験でき(といってももちろん男性だけだが)、公平で客観的な官吏登用制度としての形態を整えたのは宋の時代であった。宋(北宋)の科挙制の特徴をまとめると次の4点である。<平田茂樹『科挙と官僚制』世界史リブレット9 p.10>- それまでの諸科を廃止し、進士科に一本化したこと。(王安石の改革)
- 最終試験として殿試を設置(太祖趙匡胤のとき)し、州試(解試)→省試→殿試の三段階選抜方式が完成したこと。
- 試験内容が経義(経書の解釈)・詩賦(作詩)・論策(論文)の三分野となったこと。
- 厳格な試験体制の整備(不正防止の徹底)がなされたこと。
Episode 五〇歳で進士なるのは若い方
科挙に合格すること=進士になること、は「至難中の至難な業」と言われ、今度こそ、とがんばって試験勉強に明け暮れるうちに、歳月はいつとなく流れ去り、始めは紅顔の美少年であった者も、いつの間にか十年二十年と年月がたち、やがて五十、六十の老人になってしまう。唐代の諺(ことわざ)にすでに、「五十少進士」(五十歳で進士になるのは若い方)というのがあった。宋代には老年で進士となった人を「五十年前二十三」といって嘲笑した。<宮崎市定『科挙』-中国の試験地獄- 1963 中公新書・中公文庫>(3)元での科挙の停止
モンゴルのフビライが中国を支配して立てた元朝ではモンゴル人が支配層を占めたため、科挙は実施されなくなった。しかし、元末の1313年には復活した。
元の科挙 停止と復活
モンゴル人の征服王朝である元王朝ではモンゴル人の優位のもとで、科挙は実施されていなかった。1276年の南宋の滅亡とともに中国の長い伝統であった科挙はいったん中断されることとなった。科挙が行われなくなったため、宋以来の士大夫(地主層出身で知識人として官僚となった人々)は没落した。しかし、元は次第に漢文化に傾斜していったため、仁宗のときの1313年に初めて科挙を実施、その後も何回かは実施された。ただし、漢人で合格者(進士)となるものはごく少数であった。完全な科挙の復活は次の明代を待たなければならない。 → 元の文化Episode 九儒十丐
きゅうじゅじっかい、と読む。元王朝で科挙が中止されたため、儒者の地位が低くなったことを示す言葉。儒は儒者のこと、丐(かい)は乞食のことで、儒者は下から二番目の低いランクであるという意味である。なお、十段階のランクとは「官-吏-僧-道-医-工-匠-娼-儒-丐」というものであるが、官(上級職)と吏(一般官吏)は科挙が再開されてもモンゴル人や色目人が多かった。僧侶と道士の地位が比較的高いことも注目される。ただしこのことばは、儒者たちが、自分たちがモンゴル人にいかに貶められていたかという境遇を過度に強調するために使われたという見方もあり、現在は実態に合っていなかったとされている。(4)明・清の科挙制
漢民族の王朝支配を回復した明は、強大な皇帝権力を支える官僚制のシステムの一環として科挙制を実施した。官吏の統治理念として朱子学が重視され、科挙もそれに基づいて実施された。次の清朝は女真(満洲人)が中国を征服して建てた王朝であったが、官僚制度とそれを支えた科挙制はそのまま継承した。清朝末期の1905年に最終的に廃止された。
明代の科挙制
科挙は元代に一時停止されたが、元末の1313年に再開された。それ以降は、南宋の朱子が大成した宋学(朱子学)の知識がおもに問われるようになり、四書の理解と暗記が必須となった。明代で継承された科挙でも朱子学が基準とされ、永楽帝はそのために、『四書大全』と『五経大全』を編纂させた。科挙(高級官僚試験)の最も重要な進士試験を最高成績で合格したものは翰林院の学士となり、皇帝の顧問として詔勅の起草などにあたる、もっとも名誉ある官職であった。翰林院学士は最も名誉ある役職とされた。唐・宋では首席合格者だけが選ばれたが、明の太祖洪武帝は二位、三位の者も翰林院に入れて充実させ、さらにその中から内閣大学士を選出した。なお、元・明・清の科挙では、地方での予備試験(唐の郷貢、宋の解試=州試)を郷試(その合格者が挙人)、都での礼部の試験(唐の貢挙、宋の省試)を会試(その合格者が進士)と言うようになった。
明代の科挙の実際
明代においても科挙は、その開放性に最大の特徴があった。奴婢や俳優など賎民とされた者や前科のあるものを除き、受験資格はほぼすべての男子に開かれていた。しかし、実際に家庭環境によって差があり、長期の「受験勉強」ができるのは富裕者の子弟に限られていた。その点では「身の丈に合った」者しか合格できなかったといえる。科挙受験をめざす子供は5,6歳ごろから教師につき、経典の読み方・暗記や、やさしい対句の作り方から始めて、経典の解釈や八股文と呼ばれる科挙用の文体の作り方を習う。経典というのは、まず必修が四書、すなわち『大学』『中庸』『論語』『孟子』であり、テキストは普通朱子の注釈書が使われる。それがすむと五経であるが、これは科挙試験では『易経』『書経』『詩経』『礼記』『春秋』のなかから選択できる。八股文というのは、明代から用いられるようになった科挙試験特有の文章の書き方で、長さは普通400字から500字程度だが、そのなかに4つの対句(1対を二股と数える)を含まなくてはいけないことから、八股文という。<岸本美緒他『明清と李朝の時代』1998 世界の歴史12 p.84>
Episode 丸暗記だけではなかった科挙の試験
(引用)出題の仕方は、たとえば必修の四書題の例でいうと、四書のなかからある一部分が出題され、受験者はその部分(四書などは完全に暗記しているので、どんな断片的な出され方でももとの文章全体がわかる)の趣旨を、作者(『論語』なら孔子)の語気で述べる。すなわち、ここでは受験者が聖人の意図をどの程度自分のものとして体得しているかが問われるのである。科挙の受験勉強というとたんなる暗記学問と思われるかもしれないが、暗記は前提であって、基本的にはこうした「小論文」形式である。<岸本美緒他『同上書』p.85>
清朝の科挙
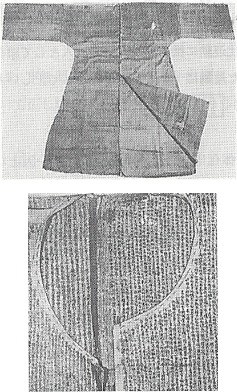
科挙で不正行為に使われた
下着とその拡大図
2002年センターテスト世界史A
参考 曾国藩のケース 清末に漢人官僚として活躍した曾国藩を例として見てみよう。曾国藩の祖父は湖南省湘郷県の山深い農村で農地の開墾に成功して地主となった富農ではあったが、学問がなく科挙を受験できなかったことを悔い、息子には早くから勉学を督励した。その息子は28歳の時、自ら科挙を目指すとともに家塾を開き、幼いわが子曾国藩の才能に期待した。曾国藩は4歳で四書五経の暗唱をはじめ、5歳で漢字を覚えた。8歳から父の家塾に入り翌年には五経を読破し、いよいよ科挙の受験勉強に入った。この年齢での受験準備開始は決して早くはない。 科挙の地域予備試験である童試に受かると生員といい、科挙の本試験受験資格が得られる。生員となるのは当時の中国の人口4億のわずか0.3%の130万人に満たず、さらに三年に一度、省ごとに行われる郷試に合格するのは生員の1割、10万人に過ぎない。
曾国藩の父は17回目の受験で1832年にようやく童試に合格、生員となって郷紳といわれる地域エリートとして認められたが、すでに43歳になっていた。ところが翌年、息子の曾国藩は童試に合格、父と肩を並べた。さらに曾国藩はなんと翌年の郷試に合格、24歳で父を抜いてしまった。郷試に合格すると挙人という学位が授与される。彼はさらに翌1854年、中央で行われる会試の合格を目指して上京。しかし会試に一回で合格することはまずない。やはり落第した曾国藩は北京の同郷施設である長沙会館に滞在して受験勉強を続ける。通常なら会試は三年に一度だが、翌年ラッキーなことに皇太后の還暦を祝う「恩科」が実施された。しかし合格はかなわず、やむなく故郷に戻る。上京する旅費は自弁だから、帰りの旅費は県知事から百両を借り、服まで質に入れた。二年後の会試も借金して旅費を作り上京、三度目の受験で合格した。
会試に合格すると進士と言われ、そのまま天子道光帝が宮中で主催する殿試に臨む。殿試には落第はなく、ランクを決めるもので、トップ三人は天子直属の学問所・秘書室の翰林院に入る。第二位グループは約80人、残りが第三位クループで約100人、曾国藩はその第42位だった。翰林院に入ることが将来の高官位を約束されることになる。第二、第三グループから有用な人材を見つけるという目的で再試験が行われる。それを「朝考」というが、曾国藩はそこで三位以内に入り翰林院に入ることが出来た。三年間の研修を経て卒業試験に合格すれば、何年間かの地方官職まわりの後に大臣クラスの地位につくことが見えてくる。ときに28歳、曾国藩が意気揚々と故郷に帰ると大宴会が待っている。彼を見込んで借金に応じた人たちはそれ以上の見返りが見込めるからだ。筆マメな曾国藩は借金と出費を克明に記録しているという。<岡本隆司『曾国藩』2022 岩波新書 p.22-35>
以上は清朝末期に科挙の難関突破に成功して政府高官となった曾国藩のケース、その曾国藩が立ちむかったのが太平天国であった。
科挙と太平天国 清末の1851年から64年まで、大反乱となった太平天国を率いた洪秀全は科挙の不合格者で、落第してからキリスト教の影響を受けて自らキリストの弟と称して一つの国家機構を作り上げた。その太平天国でも科挙が行われているが、中国史で初めて女性を受験者とする科挙が行われたことが注目される(定着はしなかった)。
また清末に日清戦争に敗れ、列強による中国分割が進む中、科挙の会試のために上京していた康有為が皇帝に直接上書して改革を提言するという前代未聞のことが起こり、彼が登用されて1898年4月に戊戌の変法が始まった。そのなかでは科挙の形態や設問の内容も時代にあったものに改訂されるなどの手直しが行われた。しかし、戊戌の政変で康有為ら改革派が排除されたため、科挙の改革も頓挫した。
科挙の廃止
1900年に義和団事件が起こり、列強によって鎮圧された後、西欧文明への関心を高めた西太后らは、光緒新政でようやく立憲体制への転換を表明したが、その際、1904年を最後として、翌1905年9月2日に科挙の廃止に踏み切った。科挙が廃止されたことは、中国の伝統的な価値観である儒教の世界観を柱とした政治や文化のありかたの転換を意味し、西欧を範とした科学的、合理的な世界観に基づく法観念や知識が官吏に求められることになった。そのため、北京などに官吏養成のための学校が設立され、中央官吏への道は海外留学経験、特に日本への留学が重視されるようになり、日本への留学生が増加した。そのような若い知識人の中から、1915年に刊行された『新青年』を舞台として文学革命が始まり、胡適や魯迅などの白話文学とともに儒教批判が展開される。
(5)朝鮮の科挙制
高麗は唐から律令制を学んで統治に取り入れ、科挙も実施した。次の朝鮮王朝でも科挙を独自発達させた。高麗、朝鮮を通じて科挙合格者となった家系は両班といわれる支配階層を形成した。
高麗と朝鮮王朝の科挙
朝鮮では高麗時代の958年以来、官吏登用制度としての科挙が定期的に実施されていた。しかし、高麗時代には高級官僚は蔭位の制によって高官の子弟から官吏が登用されていたので、科挙の比重は低かった。朝鮮王朝(李朝)を開いた李成桂は、1392年の即位の年に科挙の実施を宣言し、翌年に李朝最初の科挙が実施された。その後次第に制度が整備されて、1894年(日清戦争の年)に廃止されるまで、500年にわたって実施された。科挙には、文官を選抜する文科、武官を選抜する武科、専門技術者を選抜する雑科の三科があったが、文科が最も重視された。文科は三年に一度、地方ごとの郷試、都での会試、王の臨席のもとでの殿試の三段階で実施され、殿試合格者定員は33名と決まっていた。朝鮮王朝の科挙の特徴 明・清の科挙と較べて、朝鮮の科挙の特色の一つは、合格者が特定の少数家門に独占されていたことが挙げられる。李朝時代を通じ、300名以上の文科合格者を出した同族集団は5つ存在した。また、中国に較べて人口比で合格者が約5倍ほど多かった。これは朝鮮の科挙が3年に一度の式年文科だけでなく国王の即位や世嗣の誕生などを名目に臨時に実施されることが多かったためと思われる。朝鮮の科挙の合格は、同族集団にとって出自の由緒正しさを示す重要な要素となり、代々、科挙合格者を出す家系が「両班」といわれるようになった、と考えられる。<宮嶋博史他『明清と李朝の時代』1998 世界の歴史12 p.99-106>
特に15世紀末になると、地方の両班で科挙に合格して中央で活動するようになり、改革を志向した人々は士林といわれ、たびたび保守派から厳しい弾圧(士禍)を受けた。17世紀には士林の間に党派が形成され、激しい党争を繰り返すようになる。
