アイルランド
アイルランド GoogleMap
アイルランドは大ブリテン島の西側にある大きな島。長くイングランドの支配を受け、18世紀以降、自治要求がたかまり、イギリスにとっての「アイルランド問題」が深刻化し、独立戦争の過程で1920年に北アイルランドはイギリス領、南部にはアイルランド自由国が分離した。北アイルランドが分離したアイルランド自由国は自治か完全独立かで内紛が続き、国号も1937年のエールを経て、1949年にアイルランド共和国となった。北アイルランドはイギリスの一部として続くが、プロテスタント住民によるカトリック教徒差別から対立が激化し、北アイルランド紛争が長期化した。
- (1)ケルト文化とカトリック化
- (2)イングランドとの関係
- (3)クロムウェルの征服と植民地化
- (4)イングランドへの併合
- (5)アイルランド自由国の独立
- (6)エール
- (7)アイルランド共和国
関連ページ
アイルランドの歴史 概略
イングランドからの侵攻 1171年にはイングランドのプランタジネット朝ヘンリ2世の支配が及び、封建制が導入された。さらにヘンリ8世以降、イギリスの宗教革命によって生まれたプロテスタントが移住するようになり、カトリック住民との宗教的対立が始まった。特にピューリタン革命の時期の1649年にクロムウェルによる征服が行われ、アイルランドの植民地化が始まった。名誉革命の時にはウィリアム3世が侵攻してカトリック勢力を破り、プロテスタント支配が確定した。
イギリスによる併合 フランス革命の影響などでアイルランドに民族運動が起きると、イギリスは1801年にアイルランドを併合して国号を「大ブリテン及びアイルランド連合王国」とした。19世紀には自由主義の影響を受けてカトリック教徒による自治の要求が強まり、アイルランド問題はイギリスにとって最大の課題となった。1829年にはオコンネルの活動でカトリック教徒解放法が成立したが、1845年から深刻なジャガイモ飢饉に襲われ、多くのアイルランド人がアメリカ新大陸などに移民していった。1870年代にはアイルランド国民党の運動によってアイルランド土地法が制定され、小作人の権利の向上が図られたが、要求は次に自治権の獲得に向いていった。自由党グラッドストン政府はアイルランド自治法案をたびたび議会に諮ったが上院の拒否で不成立が続いた。
自治法から分断法へ ようやく20世紀に入ってアイルランド自治法が成立したが、第一次世界大戦によって実施が延期された。それに不満な独立派が1916年にイースター蜂起といわれる武装蜂起を行い、それは鎮圧されたが、それ以降、シン=フェイン党を中心とする独立運動が激化し、1919年にアイルランド共和国の独立を宣言し、アイルランド共和国軍(IRA)による戦闘を開始した。このイギリス=アイルランド戦争が長期化する中、1920年、イギリスのロイド=ジョージ内閣はアイルランド統治法(分断法とも言う)を制定、北アイルランドはイギリス領とし、それ以外に高度な自治権を与えて自治領とすることを決定、アイルランドは分断されることとなった。1921年、イギリス=アイルランド条約が締結されて戦闘は終わり、シン=フェイン党は自治領となることを認め、翌1922年1月、26州がアイルランド自由国として独立したが、完全なイギリスからの分離を主張するグループとの間で内戦へと転化していった。イギリスは「大ブリテン及び北アイルランド連合王国」と称し、北アイルランドはその一部となった。
アイルランド自由国から共和国へ アイルランド自由国では内戦が収束した後、主導権を握ったデ=ヴァレラは、1937年に君主制を否定し、国号をアイルランド語によるエールに変更した。第二次世界大戦ではエールは中立を守り、戦後の1949年にイギリス連邦から離脱すると共に国号を正式にアイルランド共和国とした。こうしてイギリスとの関係をすべて断って完全な主権国家となったアイルランド共和国は、貧困と農業主体の遅れを克服するために工業化を進め、次第に経済成長を実現させ、軍事同盟であるNATOには加盟せず、ヨーロッパの経済統合には同調して1973年にECに加盟した。
北アイルランドの苦悩 同じアイルランドでありながら、北アイルランド(アルスター地方)はイギリス領としてとどまり、議会と政府を持つ地方自治は認められたが、その実権はプロテスタントのユニオニスト(イギリスとの一体化を強めることを主張)が握り、少数派のカトリック教徒をイギリスからの分離を目指す危険な存在として厳しく差別、弾圧する態勢を敷いていた。それに対してカトリック側は宗教の自由など人権や政治・経済活動の平等を求めて抵抗し、またその中には民族主義を掲げ、イギリスからの分離とアイルランド共和国への併合を主張するナショナリスト、あるいいはイギリスの君主制を否定するリパブリカンなどは過激な実力行使を展開し、両勢力の流血を伴う衝突は1920~30年に繰り返された。
北アイルランド紛争、解決へ この北アイルランド紛争は、第二次世界大戦後の1970年~80年代に世界的な公民権運動の影響や各地の民族運動の激化の影響を受けてさらに活発となり、分裂のため勢力が衰えていたシン=フェイン党とIRAも勢力を盛り返し、北アイルランドだけでなくロンドンなどでも盛んに爆弾テロを実行、それに対してプロテスタント側もカトリック教徒を襲撃し、各地で双方による悲惨な殺戮が続いた。イギリスは警察や軍隊の力で鎮圧に当たったが、カトリック側への取り締まりが苛酷であったため反発を買い、かえって事態を悪化させた。ようやく90年代に入り、東西冷戦の終焉、ヨーロッパ経済統合の進展などの情勢の変化の中で和平の動きが高まり、1989年に講和が実現、曲がりなりにも武装も解除され、平和が実現した。
アイルランド(1) ケルト文化とカトリック化
ケルト文化
アイルランドには旧石器時代の遺跡もあるが、前4000年ごろには農耕・牧畜が行われるようになっていた。その島に鉄器文明をもたらしたケルト人は、前5世紀ごろ、大陸から渡来したらしい。彼らはドルイドという司祭を中心とした独自の文化をもつ部族社会を形成した。ローマ人がアイルランドのケルト人をゲール人と呼んだが、直接支配を及ぼすことはなかった。その後もアイルランドの先住民族をゲール人、その言語をゲール語と呼んでいる。カトリック教会による布教
聖パトリックの布教 アイルランドはカトリック信仰が根強く、現在でもイングランドの新教徒(国教会)とは対立している。アイルランドに正統派カトリック教会のキリスト教を伝えたのは、5世紀初頭から中頃、聖パトリックによってであった。聖パトリックはなかば伝説的な人物で正確なところは判らないが、ブリテン島西部で生まれ、奴隷としてアイルランドに連れ去られ、羊の番をしながら6年間を過ごし、脱走してブリテン島に帰ったという。しかしその後、今度は自らの意思でアイルランドに神の福音を伝えるために渡り、北東部のアーマーを中心に布教活動を続け、ローマ教会からアイルランドの司教として認められたという。聖パトリックは今でもアイルランドの守護聖人とされ、彼を偲ぶ3月17日はセント・パトリック・デーといわれ、現在もアイルランドの国民的祝日とされている。アイルランドの修道院 5世紀末に聖パトリックの弟子の一人、コーマックが修道院長となり、それ以後2世紀にわたってアーマー教会の長は修道院長と司教を兼ねることとなった。西ヨーロッパのキリスト教国のなかでアイルランドは修道院が教会を支配した唯一の国となった。その後もアイルランドでは独自の修道院文化が発達し、古典の筆写や研究が盛んに行われた。またアイルランドには、各地に独特の円環をもつ石造の十字架が多く残されているのも修道院文化の遺物である。<波多野裕造『物語アイルランドの歴史』1994 中公新書 18-24>
アイルランド(2) イングランドとの関係
ヴァイキングの襲来
アイルランドは、ブリテン島と違い、ローマの支配も直接は及ばず、ゲルマン民族の大移動期の侵入も受けなかった。そのため独自のケルト文化が維持されたといえる。しかし、9~11世紀にはしばしばヴァイキングと言われたノルマン人の侵攻を受け、一時はダブリンにノルマン人の支配が成立したが、彼らは沿岸部を一時的に支配して交易を行ったが、領域的な支配は行われず、イングランドと異なりノルマン人の王朝が永続することはなかった。アングロ=サクソン人の移住
12世紀後半、イングランド及びウェールズから、アングロ=サクソン人がアイルランドに移住するようになった。彼らは先住民のケルト系ゲール人の土地を奪い、次第に領主化していったが、大小の領主が分立する状態となった。有力領主の一人のマクマローはレンスター地方の王を名のったが周辺諸侯との争いによって追放され、イングランド王プランタジネット朝初代のヘンリ2世に救援を求めた。1169年、ヘンリ2世は家臣のストロングボウを派遣した。(引用)このストロングボウとノルマンの騎士の襲来が、現在に至るまで800年以上にわたるアイルランドと英国との政治的紛争の始まりであった。1171年にはヘンリ2世自身がアイルランドにやってきた。彼らはヨーロッパの封建制度や新しい法体系などをもたらした。<鈴木良平『アイルランド問題とは何か』2000 丸善ライブラリー p.151>ヘンリ2世はアイランドの主権を主張してアングロ=サクソン系の領主の土地を安堵し、臣従させた。ヘンリ2世の後のジョン王もアイルランドへの宗主権を主張し、ダブリンに官吏を置いて支配した。アングロ=ノルマン系の領主は土着し、12~13世紀はアイルランドのイギリス化が進んだが、14世紀にはゲール系勢力の巻き返しも始まった。イギリス王権の弱体化もあって、アイルランドは、アングロ=ノルマン系の支配地域とゲール人勢力の支配する地域が拮抗する状態となった。つまり、イングランドの勢力はアイルランドを完全に支配することはできないでいた。特に百年戦争とバラ戦争が続く中、イングランドの王権はアイルランドに及ばなくなり、貴族は代官を置いて所領を支配、現地ではアングロ系、ゲール系のいずれにも有力な氏族が成長した。
ヘンリ8世のアイルランド支配
イギリス王は形式的にはアイルランド太守としてローマ教皇からアイルランドの支配をまかされているという建前であったが、宗教改革を断行してローマ教皇と関係を断ったヘンリ8世は1541年、みずからをアイルランド国王とすることを、アイルランド議会で承認させた。こうして形の上でアイルランドは独立した国であるがイングランドと同じテューダー朝の国王の支配を受けるという、同君連合の形態となり、それとともにイングランドから盛んに移民が行われた。しかし、アイルランドには国教会はなかなか浸透せず、宗教面ではカトリックが依然として有力なまま続いていた。北アイルランドの宗教対立の始まり ヘンリ8世はそれまでのアイルランド支配を改め、国王として直接統治するためダブリンに出先の行政府を置いた。さらにイギリス宗教改革をアイルランドに持ち込み、多くのプロテスタントを移住させた。その施策はエリザベス1世にも継承され、1584年は北アイルランド(アルスター地方)の北西部のデリーにロンドンの富裕な商人が多数移住させたので、ロンドンデリーと言われるようになった。このようなイギリス政府の強引な移住者政策は、その後、大きな禍根を残すこととなった。ヘンリ8世時代以前の移住者は Old English といわれたが、彼らはカトリックであった。ところがヘンリ8世時代以降の移住者 New English はプロテスタントであった。プロテスタントは次々と移住し、やがてアイルアンド全島ではカトリックが多数であるが、北アイルランドではプロテスタントが多数派になり、カトリック教徒は少数派として迫害されるようになった。<鈴木良平『同上書』 p.152,>
アイルランド(3) クロムウェルの征服と植民地化
ピューリタン革命の主導権を握ったクロムウェルは王党派=カトリックの討伐を口実に1649年、アイルランドを征服し、実質的植民地化を行った。さらにアイルランドのカトリック教徒と結んで再起を図ったジェームズ2世が1690年にウイリアム3世のプロテスタント軍に敗れ、アイルランドの植民地化が決定的になった。
クロムウェルは、1649年夏、カトリック教徒が多く王党派の拠点となっているとしてアイルランドを征服した。6月15日、議会はクロムウェルをアイルランド総督に任命。アイルランドでは国王軍のオーモンド公がカトリック軍と同盟、反議会の活動を展開していた。クロムウェルは8月13日にブリストルを出航、15日ダブリンに上陸し、12000名の新着の部隊と先任の5000名の部隊を合流させ、9月ドローエダ、10月ウェックスフォードなどを攻略、その間ミル-マウントの虐殺、寺院の焼き討ち、婦女子の乗ったボートを沈めるなど残虐行為を行った。クロムウェルはそれを「神のみちびき」と議会に報告している。50年5月26日「クロムウェルの恨み」を残し帰国した。その後、アイルランドでは、イギリスからの独立運動が激しく展開されることとなる。<浜林正夫『イギリス市民革命史』P.199-201>
ウィリアム3世のアイルランド征服
1688年、カトリック復興をもくろむ国王ジェームズ2世に反発した議会が、プロテスタントの擁護者としてオランダ総督(事実上のオランダ国王ともいえる)オラニエ公ウィレム3世を迎え入れ、ジェームズはフランスに亡命した。これが名誉革命である。オランダ軍とともに上陸してイギリス(厳密にはイングランド)国王となったウィリアム3世を、カトリック勢力の強いアイルランドでは国王とは認めなかった。この情勢を見てジェームズはアイルランドに赴き、反ウィリアム勢力を結集して挙兵した。イギリス国王となったウィリアム3世はオランダ軍を率いてアイルランドに出兵し、1690年7月のボイン川の戦いでジェームズとカトリック軍を破った。ウィリアム3世のプロテスタント軍はその後もアイルランド各地を転戦してカトリック勢力を蹂躙した。これは、1171年のヘンリ2世の時に始まり、クロムウェルの時に本格化したイングランドのアイルランド征服(植民地化)が完成したことを意味している。これ以後、プロテスタントによるアイルランド支配が進み、カトリック地主の土地は取り上げられて、差別されていく。Episode 「野鴨の逃亡」
1690年、ボイン川の戦いでジェームズ2世の軍は敗れたが、アイルランドのカトリック兵士はイギリス軍に投降することなくフランスなどのヨーロッパ各国に逃亡し、その地の軍隊に加入した。彼らの逃亡は「野鴨の逃亡」といわれ、その数は約5万人とも言われる。彼らはアイルランド兵の精鋭であり、彼らの流出はアイルランドにとっては痛手であったが、フランス軍に加わった彼らは隙あればいつでも故国アイルランドに攻め込んでイギリス支配を覆そうと考えていた。それをイギリスは恐れ、とりわけナポレオン戦争の時はフランス軍にアイルランド人兵士が加わることを恐れ、海岸のあちこちに砦を築いた。実際にアイルランド西部の港キンセールにはナポレオン戦争の時にフランス兵が襲来して捕らえられ、彼らが幽閉された城が「フランス人の牢屋」として未だに残っている。<鈴木良平『アイルランド問題とは何か』2000 丸善ライブラリー p.159-160>アイルランド(4) イングランドへの併合
イングランドは島民の反抗を抑えるために直接統治に乗り出し、1801年にアイルランド併合を実行、大ブリテンおよびアイルランド連合王国が成立、アイルランドは実質的にイギリスの一部となり支配が強化された。差別されたカトリック教徒の中に自治を求める運動が始まり、アイルランド問題の深刻化するなかで、1845年にジャガイモ飢饉が起こり、多くのアイルランド人がアメリカ大陸に移民として逃れた。19世紀後半にはアイルランド独立を目指す武装闘争が開始された。
カトリック抑圧とイングランドによる併合
18世紀には一連の「カトリック処罰法」が制定されアイルランドのカトリック教徒は徹底的に無力化された。アイルランド語は使用できず、その文化・伝統は否定され、カトリック教徒は大学に行けず、医者にも弁護士にもなれなかった。土地も所有できず小作人として暮らすしか無かった。カトリック農民は5ポンド以上の価値のある馬を所有することも出来なかった。18世紀後半にはアメリカ合衆国の独立、フランス革命の影響を受けて、アイルランドでも独立運動が始まった。1791年、ウルフ=トーンが「統一アイルランド人協会」(ユナイテッド・アイリッシュメン)を組織し、1798年に挙兵したがイギリス官憲によって捕らえられ、自決した。その時約3万人が死んだと言われる。イギリス政府は独立運動を抑えるためにアイルランドの併合に動き、1800年に合同法を成立させ、1801年1月1日にアイルランド併合を実行し、それによって正式国号は大ブリテンおよびアイルランド連合王国となった。併合は統合ととらえられ、むしろカトリック教会上層はこれによってイギリスと対等になれると考えて賛成し、プロテスタント勢力は植民地時代の特権が失われるとして反対した。 → 19世紀以降のアイルランド問題
アイルランド問題
その結果、イギリスでは審査法によってカトリック教徒は公職に就くことができなかったため、アイルランドの多くのカトリック教徒は差別され、イギリスの支配に対する不満が強くなり、19世紀にはアイルランド独立運動はアイルランド問題としてイギリス本国でも深刻に受け止められるようになった。イギリス本国は18世紀から19世紀にかけて産業革命を展開し、工業化・海外植民地獲得によって大英帝国といわれる繁栄期を迎えたが、アイルランドは北部のベルファーストなどのアルスター地方を除き、産業革命に取り残されて依然として農業国にとどまり、本国人の地主の下で小作人の貧困が進んでいた。しかもナポレオン戦争終結後、イギリスに大量の穀物が輸入されるようになると、食肉需要が高まり、アイルランドに土地を持つ地主(不在地主)は農地を牧場にするため小作料を引き上げ、農民の追い出しにかかった。土地を離れたくない農民は高い小作料を我慢し、その分安価な食糧としてジャガイモに依存しなければならなくなっていった。
ジャガイモ飢饉 そんな中で、1845年9月にジャガイモ飢饉といわれる大飢饉が発生、1849年ごろまで続いてアイルランド農民に大きな犠牲が出た。これは天候不順とともにジャガイモの疫病の蔓延という自然災害であるが、要因としてイギリスの穀倉とされたアイルランドの農民がジャガイモ単作に過度に依存するようになっていたことが挙げられる。またイギリス本国はちょうど保護貿易から自由貿易に転換する時期であり、保守党ピール内閣は1846年、このジャガイモ飢饉を理由に穀物法の廃止に踏み切ったが、続く自由党政権は自由主義経済の自由放任主義の原則に忠実だったあまり、この飢饉と農村の貧困に対する政策を積極的に行おうとしなかったところに原因がある。
飢饉と移民による人口の減少 1845~51年の間に100万~150万人が飢えと病気で死に、100万人がアメリカやカナダに移民として逃れて、さらに次の5年間にも100万にもの人がアイルランドを離れた。アイルランドの人口停滞は続き、1990年現在でアイルランドの人口は350万にすぎず、一方、アメリカには4300万、全世界では7千万のアイルランド系の人が住んでいるといわれる。
民族主義の武装闘争、始まる ジャガイモ飢饉による人口減少とともに、それを契機として、特に土地問題での不満が強まり、自治の獲得ともに要求を掲げた民族主義(ナショナリズム)が高揚することとなった。1848年には青年アイルランド党がイギリスとの分離を掲げて武装蜂起、その後も、フィニアンと名乗る秘密組織が武装蜂起した。これらの運動はいずれも鎮圧されたが、19世紀の民族主義、自由主義を求めるヨーロッパにおける1848年革命と同様の運動が、イギリス領のアイルランドでも起こっていることが注目される。
グラッドストン
アイルランドの小作人の解放を求める運動は、1870年代にさらに活発化し、アイルランド国民党やアイルランド土地同盟が結成されてイギリス議会でも活動が展開されるようになった。イギリス政府はこの間、アヘン戦争、インドの反乱、アメリカ南北戦争、クリミア戦争など植民地経営と外交問題で大きな課題を抱えていたためアイルランド問題は軽視されていたが、ようやくグラッドストン自由党内閣はアイルランド問題に正面から取り組みを開始した。まずグラッドストンは、1870年、「アイルランド土地法」を制定し、問題の解決をはかったが農民の不満は解消できなかった。イギリス人地主と小作人の対立は次第に激化し、1880年にはアイルランド各地で「土地戦争」(1880~83年)といわれる衝突事件がおこったが、運動が過激化すると弾圧も強化され、次第に運動は退潮した。アイルランド自治法案の否決
イギリス議会での選挙法の改正は、議会の構成を変化させ、1884年の第3次選挙法改正では都市労働者層に選挙権が拡張された結果、アイルランド国民党が議席を伸ばした。時のグラッドストンは国民党の支持を得るため、1886年にアイルランド自治法案を議会に提出した。しかし、この第1次をはじめ、以後3次にわたって提案したが、下院は通過しても、上院(貴族院)で阻まれ、成立しなかった。こうしてイギリス帝国のお膝元での紛争は「のどに刺さったトゲ」といわれ、次の20世紀のアイルランド問題はさらに激しくなっていく。
アイルランド(5) アイルランド自由国の独立
第一次世界大戦中の1916年、アイルランド独立を掲げたイースター蜂起が起こるも弾圧された。その後に急速に支持を集めたシン=フェイン党が選挙で勝利し、アイルランド共和国の独立を宣言したが、それを認めないイギリスとの間で1919年からのイギリス=アイルランド戦争となった。1920年にイギリスのロイド=ジョージ内閣はアイルランド統治法(分断法)を制定、北アイルランド6州をイギリス領として一定の自治を与え、それ以外の26州にはイギリス帝国を構成する自治国として実質的独立を認めるとした。翌1921年、イギリス=アイルランド条約で講和し、26州はアイルランド自由国として独立したが、運動の中心であったシン=フェイン党は分裂し、こんどは内戦となった。
イースター蜂起
アイルランド問題が大きく動いたのは第一次世界大戦をきっかけとしていた。大戦勃発直後の1914年9月にイギリス議会でようやくアイルランド自治法が成立したが、第一次世界大戦が勃発したという理由で実施が延期されることなった。アイルランドでは延期に反発した急進派が1916年2月の復活祭の日に武装蜂起(イースター蜂起)し、ダブリンで激しい市街戦となったが、イギリス政府は軍隊を派遣して鎮圧した。その際、派遣軍は蜂起首謀者パトリック=ピアスなど16人を逮捕して裁判にもかけずに処刑、他にも多数を処刑したことで、非難が高まった。この蜂起は、アイルランド自由主義同盟(IRB)という急進派が起こしたもので、すでに1905年に結成されていたアイルランドの民族運動組織であるシン=フェイン党は、組織としてはこの蜂起に加わっていなかったが、この蜂起でのイギリス政府の過剰な弾圧はアイルランド人の憎しみを買い、独立を訴えるシン=フェイン党への支持が高まった。
1918年に総選挙の結果、アイルランド独立を主張するシン=フェイン党が民衆の支持を受けて大勝した。イースター蜂起に加わって生き残ったデ=ヴァレラらはロンドンの本国の議会に出席することを拒否し、1919年にダブリンに独自のアイルランド共和国議会を開設して、独立宣言を発した。大統領はデ=ヴァレラが就任、シン=フェイン党を創立したアーサー=グリフィス、IRBの軍事部門アイルランド義勇軍(後のIRA)を率いるマイケル=コリンズらも閣僚となった。
イギリス=アイルランド戦争
イギリス本国のロイド=ジョージ内閣はそれを認めず、シン=フェイン党の解散を命じ、党員を逮捕、弾圧を強めたため、1919年4月以降、シン=フェイン党はゲリラ闘争、テロを開始、アイルランド独立戦争(イギリス=アイルランド戦争)が始まった。アイルランド側はマイケル=コリンズが義勇兵を募り、アイルランド共和国軍=IRAを組織した。ロイド=ジョージはその一方、妥協を図るべく、1920年にアイルランド統治法(分断法、分離法とも言われる)を公布したが、それは北アイルランド(アルスター地方)と南アイルランドを分離し、それぞれに程度の違う自治権を与えるというものだった。この提案を北アイルランドは受け入れたものの、シン=フェイン党は拒否、それをうけてイギリス政府は本格的な弾圧に乗り出し、軍隊を派遣した。この世界大戦からの復員兵からなる軍隊はその制服から「ブラック・アンド・タンズ」と言われ、かつてのクロムウェルのアイルランド侵略を思い出させる残虐行為を行い、アイルランド民衆の強い憎しみを生むこととなった。
アイルランド自由国の成立
イギリス=アイルランド戦争は長期化し、アイルランド民衆は戦いに疲弊、イギリス国内や国際世論も次第に戦争反対に傾いたため、1921年4月、両軍は停戦に合意、交渉に入った。交渉はロイド=ジョージ挙国一致内閣の提示した北部分離案を軸に進められた。それはプロテスタントの多い北アイルランド(アルスター地方)を、カトリックの多いアイルランドから分離させた上で、残りの南アイルランドを自治領とすることを認める、というものであった。予備交渉を行った大統領デ=ヴァレラからロンドンでの最終交渉を任されたグリフィスやマイケル=コリンズは、「共和国」としての独立という本来の目的は達することは出来ないが、戦争を停止し、将来の共和国独立の第一歩とするためには妥協が必要と判断し、1921年12月6日にイギリス=アイルランド条約に調印、アイルランド自由国が成立することとなった。
なぜ「自由国」になったか
この時イギリスにも承認されて成立したのは「アイルランド自由国 Irish Free State」であり、シン=フェイン党がかねて称していた「アイルランド共和国 Irish Republic」ではなかった。イギリスがアイルランド側と交渉する際に最もこだわったのがこの国名問題だったようだが、これもロイド=ジョージが巧妙にデ=ヴァレラを説得した結果だったという。(引用)ロイド=ジョージはデ=ヴァレラから republic のアイルランド語訳には poblacht と saorstat があり、後者を直訳すれば free state にもなるとの説明を引き出した。ロイド=ジョージは自らもウェールズ人である点を、アイルランド人のデ=ヴァレラにアピールし、独立アイルランドの国号には英語ではなくアイルランド語を用いるよう誘導した。そこで saorstat を国号とすることで両者が妥協したことにより、その英訳はアイルランド自由国となり、結果的にロイド=ジョージはアイルランドの国号から republic を排除することに成功したのである。<森ありさ『アイルランド独立運動史 シン・フェイン、IRA、農地紛争』 1999 論創社 p.198>
シン=フェイン党の分裂
この案を巡ってシン=フェイン党は分裂した。条約交渉に当たったコリンズ、グリフィスらは分離・自治領を受け入れることを主張、それに対してデ=ヴァレラらはあくまでアイルランド全島の完全独立と大英帝国からの分離(王政の否定)を主張した。アイルランド議会で条約は賛成64,反対57の7票差で承認され、国民投票でも条約承認派が上まわったので、条約は批准された。1922年1月16日、グリフィス、コリンズらを核として正式に発足したアイルランド自由国とは、独自の議会と政府をもつが、あくまでイギリス帝国の一部の自治領=ドミニオンのひとつであり、カナダやニュージーランド、オーストラリアなどと同じくイギリス国王に忠誠を誓い、その代理の総督が統治するというものだった。北アイルランドはアイルランド自由国には加わらず、イギリス本国の一部として残った。
アイルランド自由国政府に対して分離したデ=ヴァレラら完全独立を主張する急進派はゲリラによる武装闘争を開始、内戦となった。この内戦で自由国政府軍を率いたマイケル=コリンズは殺害され、その他かつての独立の闘士同士が殺し合う、悲惨な戦いとなった。<このあたりの経緯は、映画『マイケル=コリンズ』に詳しく描かれていて参考になる>
マイケル=コリンズの葛藤
映画『マイケル=コリンズ』で詳しく描かれたように、マイケル=コリンズにとってはイギリスとの妥協は苦渋の選択であり、アイルランド自由国についても全面的な賛成ではなかった。自らアイルランド義勇軍を指導しイギリスとの戦いの先頭に立っていた彼は、調印やむなしとしながらも、調印直後には「自らの処刑執行令状にサインをした」心境だったと、共和国の実現を一時的にも放棄せざるを得なかったことの無念を語っている。<森ありさ『同上書』 p.112>それではコリンズは「アイルランド自由国」のどこに希望を見出したのであろうか。自治領に留まったことで依然としてイギリス総督が存在し、イギリス国王に忠誠を誓わなければならないことは屈辱であるが、それよりも議会と政府を持ち、イギリス軍は撤退しアイルランド共和国軍を国防軍とする実質的な国家となることを選んだのだった。そして自治領としてのカナダをモデルとして、アイルランドが独自にアメリカ合衆国に大使を送り、イギリスと対等な形でヴェルサイユ条約に調印し、アイルランドの同意がなければイギリスが外国との条約を締結することが出来ず、交戦に先立っては相談を受ける権利が与えられる“可能性”がある、と考えた。このような見通しでコリンズは、“とりあえず”条約に同意するという妥協を選んだのだった。<森ありさ『同上書』 p.114>
自治領から実質的な独立国へ
アイルランド自由国は独自の二院制の議会と政府を認められたもののあくまで自治領(ドミニオン)であり、イギリス国王に忠誠を誓い、国王代理の総督が駐在するというイギリス帝国の一部であった。自由国政府はコリンズの目指したカナダと同じような国際的な地位を獲得しながら、外交、貿易などでの実質的支配権を確立しようと努力した。北部分離と自治領であることを認める多数派は統一アイルランド党(フィン=ゲイル)として与党となりコスグレーヴ首相はイギリスと妥協しながら実質的な独立を実現すべく、まず工業の育成・振興に努め国力の充実を図った。1923年には国際連盟にも加盟した。
ウェストミンスター憲章
イギリス帝国の自治領のありかたも、コリンズが想定したように次第に変化してきた。アイルランドの追求した戦略であるイギリス自治領=ドミニオンとしてのイギリス帝国内の地位を向上させることが、その努力によって実現に向かったのだ。1931年にイギリスがウェストミンスター憲章を制定し、各自治領は本国と同じ権利を持ってイギリス連邦を構成することとなり、アイルランド自由国もそれを構成する独立国としてイギリスと対等な国家となった。しかし、イギリス連邦というイギリス国王を国家元首としていることには変化はなく、完全な共和政国家とは言えず、名実ともに独立した国民国家として共和政と言えるようになるには、なおも課題は残った。アイルランド(6) エール/アイレ/エーレ
1932年にアイルランドの政権を握ったデ=ヴァレラが、1937年に憲法を制定し、主権国家としての独立を達成し、アイルランドの独自性を強めて国名をゲール語でエールとした。しかしイギリス連邦には残留した。
世界恐慌の影響がおよぶ
野党の立場となったデ=ヴァレラは、完全な独立、つまり共和政国家となることをめざし、アイルランド共和党(フィアナ=フェイル)を結成した。デ=ヴァレラはその後もイギリス本国とアイルランド自由国政府に抵抗を続けたが、次第に穏健な姿勢を採るようになった。この情勢を大きく転換させたのは、1929年に始まった世界恐慌がアイルランドにも及んだことだった。その影響が1930年代に強まり、経済が行き詰まることによって統一アイルランド党政権の支持が下がり、共和党のデ=ヴァレラへの支持が高まったのだ。デ=ヴァレラ政権
アイルランド自由国でおこなわれた1932年の選挙において、デ=ヴァレラの率いるアイルランド共和党が大勝した。1916年以来の小作農、貧農の支持の高かったデ=ヴァレラは、世界恐慌対策として農民の救済を約束し、アイルランドが自治領となって以来、農民がイギリス政府に納めることになっていた土地購入代金の納入を一方的に中止した。イギリスは報復としてアイルランドの家畜、農作物への輸入関税を引き上げたが、デ=ヴァレラは保護政策をとって国内工業育成につとめ、経済的自立の努力を続けた。この関税戦争は粘り強い交渉で最終的に解決、実質的な独立への足場を固めた。新憲法で国号変更
1937年、新憲法が制定された。それはデ=ヴァレラがかねてから主張していた、真の独立を確立することを実現したものであり、自ら「主権をもった独立・民主国家」であると規定し、国名をエール(アイレ)と称し、従来のイギリス国王の代理としての総督を廃止し、国民の代表として国民が選出する大統領を置いた。またその国土は北アイルランドを含むと定めた。新憲法は1938年発効して大統領にはプロテスタントの学者ハイドが選出された。エールという国号 エール Eire はアイレまたはエーレとも表記し、ゲール語(アイルランドの固有の言語)でアイルランドのことを意味する。従って国名を改めたわけではなく、憲法でも英語表記ではアイルランドとするとされていた。
イギリスは、エールがイギリス国王の王冠への忠誠を廃止を決めたことは事実上イギリス連邦から脱退することを意味するので強く反発した。しかし、そのころヨーロッパではナチス=ドイツ、イタリアというファシズム国家の台頭があり、戦争の危機が迫っていたため、イギリスもアイルランドの独立を認めざるを得なかった。
第二次世界大戦での中立 デ=ヴァレラ首相の率いるエールは、第二次世界大戦が勃発しても中立の堅持と他国への軍事基地の提供をしないことを声明し、大戦中それを遵守した。イギリス・アメリカからは強い参戦の要求があったが、一貫して中立を守った。デ=ヴァレラの中立策はナチス=ドイツが勝利した場合に備えていたとも言われ、第二次世界大戦後にはイギリス・アメリカからその姿勢を非難された。ただし、イギリスがドイツ軍による空爆で生産の低下が深刻になると、穀物・畜産品を輸出し、労働力を提供して支援を行い、またフランスが敗北してドイツ軍の侵攻が予想されると、志願兵を募って備えていることも事実である。しかし、全面的な参戦はついに行わず、海外への派兵も行わなかった。
アイルランド(7) アイルランド共和国
1949年、イギリス連邦から正式に脱退し、国号をアイルランド共和国として独立した主権国家となった。北部のアルスターを除くカトリック地域を統治するが、その併合を求めるIRAのテロ行為が頻繁に起こるようになり、紛糾が続いた。現在もNATOには加盟していないが、EUに加盟し、北アイルランド紛争も鎮静化している。
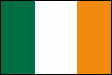
アイルランド国旗:緑はカトリック、オレンジはプロテスタント、白は両者の和解と友愛を象徴する。
アイルランド憲法上は北アイルランドも含めてのアイルランドであると規定していたが、事実上、北アイルランドは依然としてイギリス領にとどまっていた。それでも、北アイルランドを除くアイルランド26州が共和国となったことは、13世紀から続いたイギリスのアイルランド全島支配が終わったことと、イギリスとは異なるケルト人を主体とし、カトリックが多数を占める国民国家が成立したことを意味していた。
また、アイルランド共和国となってイギリス連邦から脱退したことにより外交も従来のイギリス国王名ではなく、共和国大統領を元首とし、諸外国との使節の交換も独自に行うようになった。
なお、アイルランド共和国は、第二次世界大戦中の中立政策を戦後も維持し、集団的自衛権を掲げるNATOにも加盟せず独自路線をとった。
北アイルランド紛争の激化
イギリス領として留まっていた北アイルランドでは地方議会と政府のもとで一定の自治が認められ、多数を占めるプロテスタント勢力は、アイルランドへの併合を拒否し、あくまでイギリスとの統一された状態の維持を主張し、彼らはユニオニストといわれていた。1920~30年代にはユニオニストが北アイルランドの議会と政権を独占し、イギリス政府の支援を受けながら、少数派であるカトリック信者(人種的にもイギリス人ではなくケルト系だと意識された)に対する迫害、差別的な処置、言動を続けていた。カトリック側のテロによる反抗に対してプロテスタント側が報復するという対立が続いた。第二次世界大戦後の1960年代になり、アメリカの黒人などによる公民権運動が盛んになるとその影響を受け、北アイルランドのカトリック信者の間でも平等な権利と自由を求める運動が強まっていった。その中心となったのが勢力を盛り返したIRAであり、彼らは1969年8月に武装闘争の再開を宣言、テロ攻勢を開始した。これが、70年~80年代に激しくなった北アイルランド紛争であった。
IRAのテロ活動を取り締まるイギリス当局の弾圧も強まりたびたびテロとそれに対する報復が行われ、世界を震撼させる事態が続いた。特に80年代にはサッチャー政権の下で厳しい取り締まりが行われ、IRAによる首相暗殺失敗などもあり紛争はエスカレートしていった。紛争は民族的・宗教的対立の面が強かったが、その背景には、北アイルランドのプロテスタントとカトリックの間の経済的格差などの社会問題もあった。
EC加盟とEUの恩恵 1973年にはアイルランドとイギリスは同時にヨーロッパ共同体(EC)に加盟した(拡大EC。現在のEU)。ECはその後EUとなって経済統合が進み、1990年代にはアイルランド経済は急速な成長を見せている。それは貧乏国だったアイルランドが、EUからの多額の援助金が得られたという理由があり、アイルランドはEU諸国の中で、加盟の恩恵を最も強く受けた国でもあった。アイルランドと北アイルランドの境界も自由に行き来できるようになったので、北アイルランド紛争も事実上意味が無くなり、イギリスとの関係も改善されることとなった。
北アイルランド紛争の現在
イギリスの労働党ブレア政権の下で和平交渉が進み、1998年4月10日に「北アイルランド和平合意」が成立してIRAも武装解除に応じることとなり、平和が実現した。こうしてかつてはアイルランドと言えば、零細な農民による農業生産が主で工業化が遅れていること、慢性的な財政不安が続いたこと、などの課題を抱えているといわれたが、現在では北アイルランドの格差も縮まっている。ところが、2016年、イギリスのEU離脱が国民投票で可決されると、アイルランドはEU残留を表明したので、北アイルランドとの境界は再び関税業務のため自由な行き来が出来ないことになり、実際の離脱交渉に当たって最大の懸案事項となった。イギリスのEU離脱は難航したものの、2020年12月末に大筋で合意、国境での入管手続きなどは復活することとなったが、自由貿易協定の締結などで歩み寄りができ、当面の合意無き離脱は回避された。





