フランスの歴史
フランス GoogleMap
- (1) ガリア・ガロ=ローマ・フランク王国
- (2)カペー朝・ヴァロア朝
- (3)主権国家・ブルボン朝の成立
- (4)ブルボン朝絶対王政
- (5)フランス革命とナポレオン
- (6)復古王政・七月王政・第二共和政
- (7)第二帝政・第三共和政
- (8)フランスの帝国主義
- (9)第一次世界大戦
- (10)ファシズムと人民戦線
- (11)第二次世界大戦
- (12)戦後と第四共和政
- (13)第五共和政とド=ゴールの時代
- (14)コアビタシオンと揺れるヨーロッパ統合
フランス(1) ガリア、ガロ=ローマ、フランク王国
ガリアからガロ=ローマへ
ローマ時代にガリアと言われ、カエサルによって征服され属州となる。4世紀以降ゲルマン人の侵入を受け、その中のフランク人が優勢となりフランク王国を建設、ローマ=カトリックに改宗。カール大帝のもとで封建国家として発展。9世紀に三つに分裂、その中の西フランクがフランス王国のもとになる。10世紀にカペー朝が成立した。
現在のフランスの地は、ローマ時代にはケルト人が居住し、ガリアと言われていた。前1世紀にカエサルがガリア遠征を行って征服し、その属州となってから、ローマ文化が浸透した。この時代をガロ=ローマ時代と言っており、現在でもローマ時代の水道や円形競技場は南フランスを中心に遺跡として残っており、また属州(プロヴィンキア)であったことはプロヴァンスという地名に残っている。属州ガリアの中心都市であった交通の要衝ルテティアは後にパリとして発展する。フランク王国
4世紀ごろからライン川の東側にいたゲルマン人の各部族が大移動を開始、いくつかの部族がこの地に侵攻し、防ぎきれなくなったローマ帝国の支配は後退して、ほぼ西北部にフランク王国、東南部にブルグンド王国(後にブルゴーニュ地方となる)が支配、西南部にはイベリア半島の西ゴート王国が勢力を伸ばすという三分化された。そのうち481年にメロヴィング朝のフランク王国を建国したクローヴィスが、496年にカトリックに改宗してローマ教会との関係を深め、ローマ人の官僚を登用して国家体制を整備し、ほぼ後のフランスの領域を支配した。フランク王国は534年にはブルグンド王国を滅ぼしてガリアを統一した。さらにイスラームのヨーロッパ侵入を宮宰のカール=マルテルが732年にトゥール・ポワティエ間の戦いで撃退し、その子ピピンがカロリング朝を開いた。ピピンの子のカール大帝はその周辺に領土を広げ、800年にカールの戴冠によってローマ皇帝の称号を得、ローマ教会の保護者であり、西ヨーロッパの支配者としての地位を確立した。
西フランク王国
フランク王国が843年のヴェルダン条約で三つに分裂した事によって生まれた西フランクが、フランス国家へと継承されることとなる。西フランク王国は870年のメルセン条約で中部フランクの西半分を領土に加えたが、そのころから第2次民族移動の時期に入り、ノルマン人(いわゆるヴァイキング)が西ヨーロッパ各地の海岸に侵攻してきた。911年にはロロの率いるノルマン人が北西の海岸に定住してさらに、パリを脅かすようになると、国王シャルル3世はロロにたいし、キリスト教に改宗することを条件にノルマンディー公国の支配権を認めた。フランス(2) カペー朝・ヴァロア朝
11世紀ごろから農業生産力が高まり、十字軍時代に商業が復活して封建社会が変質するとともに封建領主層が没落し、カペー朝の王権が強化される。フィリップ4世はローマ教皇と争い優位に立った。ヴァロワ朝への継承をめぐってイギリス王家との百年戦争が展開されたが、この14~15世紀にわたる戦争の長期化で、封建領主の没落が決定的になり、ヴァロワ朝のもとで絶対王政が成立する。
カペー朝の成立
987年にカロリング朝の王家が断絶し、パリ伯ユーグ=カペーが王位を各地の豪族に押されて王に選出され、カペー朝が創始された。このときから、「フランス」と称するようになる。カペー朝の王位は世襲されたが、王権は周辺の諸侯に押されて、強くはなかった。カペー家の他にノルマンディー公やアンジュー伯、ブルゴーニュ公などの有力諸侯が分権的な力を振るっており、またローマ教皇もフランス王よりも強大な力を有していた。イギリス国王であるノルマン朝ウィリアムやプランタジネット朝ヘンリ2世はフランス国内にも領地をもち、形式的にはフランス王の臣下であるが、カペー家より力があるという状態が12世紀の十字軍時代の初めまで続いた。封建社会の変質
しかし、三圃制農業の普及などによる生産力の向上は、十字軍運動を一つの契機として遠隔地貿易が盛んになるという変化をもたらした。フランス国内では、北イタリア諸都市と、フランドルの毛織物地帯を結びつけるシャンパーニュ地方に定期市が開かれ、その西に位置してセーヌ川の水運で結ばれたパリの経済も発展した。貨幣経済の発展は次第に封建社会の基盤である荘園制を変質させて行き、封建領主層は次第に力を失っていったが、反比例して王権は強化された。カペー朝の王権強化 そのような変化を背景として、13~14世紀にはカペー朝の王権の強化がすすみ、フィリップ2世の時に基礎が築かれ、1214年にはブーヴィーヌの戦いでイギリスのジョン王を破り、フランス内のイギリス王領はギエンヌ地方のみとなった。フィリップ2世の時に始まった、南フランスの異端アルビジョワ派に対するアルビジョワ十字軍は、次のルイ9世の時、1229年に終わり、フランス王権は南フランスにまで及んだ。
ローマ教皇との抗争 フィリップ4世は国内の教会領に課税しようとしてローマ教皇とも争い、1302年にフランス最初の身分制議会である三部会を開催してその支持を取りつけ、1303年、アナーニ事件でボニファティウス8世を幽閉し、憤死させた。1309年からはフランス人のローマ教皇クレメンス5世を強制的に南フランスのアヴィニヨンに移し、「教皇のバビロン捕囚」を強行した。
ヴァロワ朝へ
カペー朝フィリップ4世以降は短命な国王が続き、1328年、シャルル4世を最後に断絶、三部会は国王に国王のいとこにあたるヴァロワ家のフィリップ6世を選んだ。こうしてヴァロワ朝が始まったが、それに対してフィリップ4世の娘イサベルを母としていたイギリスのプランタジネット朝エドワード3世がフランス王家王位継承権を主張し、両者は百年戦争へと突入する。百年戦争
ヴァロワ朝フランスとプランタジネット朝イギリスの間の百年戦争(1339年~1453年)は、フランドル地方やアキテーヌをめぐる両家の争いという側面もあり、戦闘はすべてフランス領内で行われた。戦争の長期化に伴い、封建社会の矛盾も深くなり、1348年には黒死病の流行、1358年にはジャックリーの乱という農民反乱などが頻発した。そのために封建領主層は没落し、かわってヴァロワ朝の王権が強化され、絶対王政の基盤が築かれた。百年戦争を終結させたシャルル7世は王権の確立に努め、財政の整備・国王軍の創設などを行い、絶対王政への道を開いた。ジャンヌ=ダルク 百年戦争の過程で突如現れたオルレアンの少女ジャンヌ=ダルクは、フランスを勝利に導きながらイギリス軍に捕らえられて魔女として処刑された。ジャンヌはイギリス軍に蹂躙されていたフランスを救った救国の英雄としてフランス人の心をとらえ、フランスの国民統合の象徴として民族国家成立に大きな影響を与えた。
フランス(3) 主権国家・ブルボン朝の成立
フランソワ1世はヨーロッパの覇権をハプスブルク家カール5世と争う。16世紀に宗教改革の波がフランスにも及び、カルヴァン派が勢力を強め、宗教対立からユグノー戦争に突入。その宗教戦争を克服したブルボン朝のもとで主権国家フランスの絶対王政の全盛期となる。
主権国家の形成
ヴァロワ朝シャルル8世は、分裂するイタリアに介入し、1494年にナポリに遠征、長期にわたるイタリア戦争を開始した。さらに次のフランソワ1世は神聖ローマ皇帝の位をハプスブルク家のカール5世と争って敗れ、1521年に再びイタリア戦争の戦端を開いた。イタリア戦争はフランソワ1世、カール5世の死後、1559年のカトー=カンブレジ条約で講和となったが、この戦争の過程でフランスは政治体制、軍事体制を整え、主権国家を成立させた。ユグノー戦争 ヴァロワ朝のもとで王権は強化されたが、同じころ、宗教改革の嵐がフランスにも波及した。フランス人のカルヴァンはジュネーヴで改革を進めたが、その信仰はカルヴァン派としてフランスにも広がり、彼らはユグノーと言われるようになった。国王を初めとするカトリック派も根強く、ヴァロワ朝末期は深刻な宗教戦争であるユグノー戦争が1562年に始まった。その過程で、1572年には旧教徒による新教徒に対するサンバルテルミの虐殺のような凄惨な事件も起こった。ユグノー戦争は最も深刻なキリスト教新旧両派の宗教戦争であるとともに王権を巡る封建勢力の抗争でもあり、旧教国スペインと新教国イギリス・オランダ双方からの介入もあって長期化し、1598年に終結するまで36年を要した。この戦争を経て、フランスは強力な王権のもとで統治される絶対王政の段階へと移行する。
ブルボン朝の成立
ユグノー戦争中の1589年、アンリ3世が暗殺されたため、ブルボン家の新教徒アンリが即位してアンリ4世となり、ブルボン朝が成立した。しかし新教徒の王を認めない旧教徒は反発を強め、なおも内乱は続いた。そのような中、国家統一を優先したアンリ4世は1593年に自ら旧教に改宗し、さらに1598年にナントの王令を発して新教を認めてユグノー戦争を終結させた。こうしてフランスの宗教内乱を克服したブルボン朝のもとで、絶対王政が発展していくこととなる。リシュリューとマザラン 17世紀前半、ルイ13世の時の1624年、宰相となったリシュリューは王権の強化に努め、1635年からはハプスブルク家との対抗上、ドイツの三十年戦争に介入し、さらにルイ14世の幼少期の宰相マザランによって、中央集権化、官僚制や税制、軍制の整備が進められ、絶対王政が展開される基盤がつくられた。
この間、従来の貴族が帯剣貴族(武家貴族。騎士としての世襲の貴族)と言われたのに対して、高等法院などの上級官僚に登用されて新たに貴族に加わった人びとを法服貴族と言うようになった。
フロンドの乱 王権強化が進められることによって既得権を失っていった貴族たちは1648年に高等法院の貴族が反乱を起こし、1650年には貴族層に広がり、農民にも同調する動きがあったが、1653年までにはすべての反乱は鎮圧された。この貴族を中心とした反王権の反乱をフロンドの乱といっている。反乱側は組織的統制を欠き、マザランの動かす政府を倒すことはできず、これらの貴族の反乱が鎮圧されたことによって、ルイ14世の絶対王政は全盛期をむかえることとなる。
フランス(4) ブルボン朝絶対王政
17世紀後半のルイ14世は、コルベールの重商主義で国富を増やし、オランダ・ドイツ諸侯領を侵略。さらにイギリスと激しい植民地戦争をつづける。やがて国家財政を破綻に向かわせ、旧体制の危機となる。
ルイ14世 絶対王政全盛期
17世紀末から18世紀初頭のルイ14世の親政時代はフランス絶対王政の全盛期であった。財務長官コルベールによる重商主義政策によって産業の保護、インドやアメリカ大陸への植民地経営が進められた。またカトリック体制を強化するためにナントの王令を廃止したが、その結果、新教徒が国外に脱出し、産業の発展には阻害要因となった。ルイ14世の時代は南ネーデルラント継承戦争・オランダ侵略戦争・ファルツ戦争という侵略戦争を展開して、領土をライン流域まで拡大した。国際的にはイギリス・オランダ・オーストリア(ハプスブルク家)と対立して孤立したが、強大な絶対王政のもとで中央集権化を推し進め、豊かな国力を背景とした強力な軍隊を有して戦いを有利に進めた。北アメリカ大陸での植民地拡大も積極的に進め、カナダを王領地に編入し、ルイジアナを獲得した。インドにおいてもフランス東インド会社の拠点としてポンディシェリ・シャンデルナゴルが設けられ、イギリス東インド会社と激しく競い合った。
またその繁栄を象徴するヴェルサイユ宮殿が造営され、宮中を中心に豪華なバロック様式が開花した。しかし18世紀に入り、スペイン継承戦争では自らの孫をスペイン国王にすることはできたものの、アメリカ植民地でのイギリスとの英仏植民地戦争ではアン女王戦争では敗れ、ユトレヒト条約では領土の拡張もできず、かげりが見え始めた。 1715年9月、ルイ14世は死去、王位継承者の曾孫ルイ15世はわずか5歳だったので、オルレアン公が摂政となった。
ルイ15世 絶対王政の衰退
ルイ15世は1723年から親政を開始した。その統治期間はヨーロッパの主権国家間の争いに加わり、オーストリア継承戦争、七年戦争を戦い、その間、イギリスとのアメリカ大陸でのジョージ王戦争・フレンチ=インディアン戦争、インドでのカーナティック戦争・プラッシーの戦いと激しい植民地戦争を展開した。イギリスとの戦争はフランスの不利のまま推移し、1763年、パリ条約でいったん終結した。それによってフランスは、カナダとミシシッピ以東のルイジアナなどを失い、インドでも主導権をイギリスに奪われることとなった。また、この先代から続いたヨーロッパ大陸と植民地での第2次百年戦争は国家財政に大きな負担となり、絶対王政が揺らいでいく。
啓蒙思想の展開
宮中ではバロック様式に代わりロココ様式が流行し、貴族文化が洗練されていったが、思想界では啓蒙思想が新しい地平を切り開き始めた。モンテスキュー・ヴォルテール・ルソー・ディドロらの百科全書派などが活躍を始め、かれらの封建社会批判は、次のフランス革命を準備していくこととなる。ロココ美術の流行
ルイ15世の時代のヴェルサイユ宮殿では、華やかな宮廷文化が開花した。ルイ14世時代の文化はゴチック文化と言われ、豪快で華麗な建築や美術が愛好されたが、18世紀に入るとルイ15世の宮廷を中心に、より洗練された、優雅で軽妙なロココ様式と言われる様式の室内装飾が好まれるようになり、それは絵画にもあらわれ、広く時代の特徴となっていった。この宮廷文化の中心となったのが、ルイ15世の公式愛妾であったポンパドゥール夫人であり、その保護のもとで画家ブーシェらが活躍した。フランス(5) フランス革命とナポレオン
18世紀末~19世紀初頭、アンシャンレジームの矛盾の深化からフランス革命勃発へ。第一共和政からナポレオンの第一帝政へ。
ルイ16世 アンシャンレジームの矛盾が深化
ルイ16世の治下では1775年からアメリカ独立戦争が始まり、当初は様子を見ていたが、結局1778年、フランスは参戦したために、その財政負担は大きくなった。ルイ14世・15世と続いた対外戦争による負債はさらに増加し、それに加えて宮廷内では王妃マリ=アントワネットらの奢侈による出費がさらに財政を脅かしていた。ルイ16世は重農主義者のテュルゴー、さらに銀行家のネッケルに財政改革を行わせ、彼らは特権身分である第一身分(聖職者)や第二身分(貴族)に対する課税の必要を主張した。しかし、それらの改革案は貴族の反対に遭い、ルイ16世も改革に踏み切ることができなかった。その頃フランス社会は、少数の特権身分が土地の大部分を領有し、農民の多くは封建的な地代の負担や、地主への小作料の負担に苦しみ、折からの天候不順による凶作もあって、都市民、農村のいずれも、アンシャン=レジーム(旧制度)に対する不満を強めていった。フランス革命
1789年5月、フランス・ブルボン朝のルイ16世は、財政難を回避するために三部会を開催した。しかし第三身分代表は、国民の代表機関として独自に国民議会を開催、憲法の制定まで解散しないことを誓った。ルイ16世がそれを認めず、武力で解散させようという動きを見せたことからパリ市民が反発、1789年7月14日にバスティーユ牢獄を襲撃してフランス革命が勃発した。全国の農村でも暴動が起き、それをうけて1789年8月4日夜、国民議会は封建的特権の廃止と人権宣言を決議した。これがフランス革命の最初の成果であるが、この段階では革命は開明的な貴族層に主導され、立憲君主政をめざすものであった。国民議会は立憲君主政を柱とする1791年憲法を成立させた。ところがルイ16世はそれを受け容れず、1791年6月、国外逃亡を図ったため、国王に対する非難が高まる。さらに、外国の革命干渉軍が迫る中、1792年8月10日に8月10日事件でパリのサンキュロットを主力とした革命派民衆がテュイルリー宮殿を襲撃して国王を幽閉、一気に立憲王政派は排除され、男子普通選挙による国民公会が成立した。第一共和政 1792~1804年
1792年9月20日、ヴァルミーの戦いでフランス軍がプロイセン・オーストリア連合軍を破り、革命軍の勝利がパリに伝えられた翌9月21日、国民公会が召集され、王政の廃止を決議、翌9月22日からフランス最初の共和政体制である第一共和政が成立、「フランス共和国第1年」と称することになった。国民公会では、上層ブルジョワジーの立場から穏健な共和政を維持することを主張するジロンド派と、小ブルジョワ、都市下層民の立場に立って革命の推進を図るロベスピエールらの山岳派が対立するなか、山岳派の主導で1793年1月21日、前国王ルイ16世は処刑された。これに対し、イギリス首相ピットが提唱し第1回対仏大同盟が結成され、革命への干渉が強められた。ジロンド派と山岳派の対立は、サンキュロットが再び蜂起して1793年6月、議会からジロンド派を追放したことによって決着し、山岳派が公安委員会を抑えて革命を主導し、そのころからジャコバン派といわれるようになった。
ジャコバン派独裁のもとで、1793年6月24日に1793年憲法が制定され(実施はされず)、さらに1793年7月には封建地代の無償廃止が実現して社会改革が進められた。また、最高価格令・徴兵制・革命暦などの革命的諸政策がうちだされた。このような革命の急進化は国内の反革命各派の動きを強め、1793年3月からフランス西部の農村地帯では王党派やカトリック勢力と結んだ農民反乱であるヴァンデーの反乱が起こり、革命政府は全力をあげて12月頃までにその鎮圧に成功したが、多数の犠牲者が出た。しかし左派のエベールらは理性を崇拝する祭典を開催し、すべての宗教を否定して人間理性のみを崇拝することを強制しようとした。
一方でジャコバン派内部にロベスピエールの急進的な姿勢に批判的な右派も生まれていたが、ロベスピエールはエベール等の急進左派と共にそれらの分派を排除して1794年4月には独裁権力を握り、1794年6月8日には最高存在の祭典を挙行した。ロベスピエールは反対派を次々とギロチンにかけ、恐怖政治を展開した。
しかし、情勢は革命当初から大きく変化し、封建地代の廃止など社会改革が進んだ結果、一定の財産を得た農民層や小市民層が保守化し、革命の急進化を恐れるようになった。革命政府内にも革命のこれ以上の進展を食い止め、安定を求める勢力が現れ、彼らは密かに急進派の一掃を企て、1794年7月のテルミドールのクーデタで議場からロベスピエールと急進派のジャコバン派を排除することに成功した。
翌1795年成立した1795年憲法によって、総裁政府が成立したが、左右からの揺さぶりが続き、イタリア遠征などで軍事的成功を収めたナポレオンが、1799年11月、ブリュメール18日のクーデタによって統領政府を成立させ、自ら第一統領となって実権を握った。
ナポレオンのローマ教皇との和解であるコンコルダート、イギリスとの和平であるアミアンの和約、それにフランス銀行の設立とナポレオン法典(フランス民法典)の制定はいずれも皇帝になる前の事績である。
第一帝政 1804~1814年
軍事的成功と内政での実績をもとに、ナポレオンは1802年に終身統領となり、1804年に国民投票によって即位し、ナポレオン1世となった。これによって第一共和政は終わり、第一帝政となった。国家の安定と対外戦争での利益を求めるブルジョワジー、土地所有者となった中小農民のいずれも共和制よりもナポレオンの帝政を選んだ。1804年5月、ノートルダム大聖堂に戴冠式を挙行し、1814年4月まで皇帝支配の時期が続く。その間、ナポレオン戦争が全ヨーロッパの範囲で展開された。それはナポレオンの野心によって行われた戦争であったが、周辺の諸国の民衆にとっては自由と平等をもたらす解放戦争であり、絶対王政を維持していた君主にとってはその存在の根底的な危機であった。しかし、やがて民衆にとってもナポレオン帝国に組み込まれて自由が抑圧される結果となっていく。抑圧された征服地の民衆がナポレオンに対して最初に抵抗したのがスペインの反乱であった。そのゲリラ戦にナポレオンは苦しむことになり、そこからナポレオンのヨーロッパ支配が崩れていく。ナポレオン帝国の崩壊 ナポレオンのフランスにとって、最大の敵はイギリスであった。イギリスはまさに産業革命を展開しており、議会政治のもとでブルジョワジーが自由な経済活動を行うことを基盤とした資本主義国として成長しつつあった。フランスは工業力ではイギリスに大きな後れをとっていた。ナポレオンはイギリス経済に打撃を与えようと大陸封鎖令を出したが、それはかえってイギリス工業製品がヨーロッパに入ってこなくなり、また穀物や原料をイギリスに輸出できないという点で大陸諸国にとって大きな痛手であった。そのため大陸封鎖令は効果がなく、ロシアのように公然と離反する国が現れた。それに対するロシア遠征は失敗に終わり、その敗北とともに急速にナポレオン帝国の崩壊が始まり、ロシア・プロイセン・オートリア連合軍とのライプツィヒの戦いに敗れてパリを占領されたことによって、1814年、ナポレオンは退位した。
ナポレオンは翌年エルバ島から一旦パリに戻り、皇帝に復帰するので百日天下(1815年3月~6月)もナポレオンの第一帝政に入るが、それも1815年6月、ワーテルローの戦いで敗れて終わりを告げた。フランスはルイ18世のブルボン朝が復活して「復古王政」の時期となり、ヨーロッパはウィーン体制の反動期に入る。
フランス(6) 復古王政・七月王政・第二共和政
19世紀前半のフランスは、ウィーン体制下の復古王政と七月王政が続く。この間、産業革命が進行した。1848年の二月革命により第二共和政となるが、ナポレオン3世が実権を握って第二帝政が成立した。
復古王政
ナポレオン第1帝政に続くフランスの政体で、1814~1830年まで。ナポレオン1世の第一帝政が1814年にその退位で終わった後(1815年に一時ナポレオン1世の帝政が百日天下として復活するが)、フランスで復活したブルボン朝のルイ18世・シャルル10世の支配時代を「復古王政」という。またルイ18世のもとでは、タレーランが正統主義を掲げてウィーン会議に参加し国際的立場を維持したが、ウィーン議定書では国土はフランス革命前に戻され、イギリス・ロシア・オーストリア・プロイセンの四国同盟によって監視されることとなった。このウィーン体制のもとで、賠償金も払い終わった1818年には、五国同盟に加えられてヨーロッパの強国として復活した。上層ブルジョワジーの形成 復古王政のもとでフランスでも革命で亡命していた貴族(亡命貴族=エミグレ)が帰国して復権した。国王と貴族たちは革命前のアンシャン=レジームの復活を策したが、市民意識は定着していたので、所有権の不可侵や法の下の平等などの革命の成果は保障されていた。1824年に即位した弟のシャルル10世は、より反動的な政治を行ったが、それでもこの頃から、産業資本家や金融業者が成長し、上層ブルジョワジーを形成するようになり、彼らは古い王政と貴族支配に対する反発を強めていた。シャルル10世が不満をそらそうと1830年6月にアルジェリア出兵を強行すると、かえって反発が高まり、上層ブルジョワジーが国王を追放し、オルレアン家のルイ=フィリップを王位に就けるという七月革命が起きる。
七月王政
1830年7月に七月革命によって、国王ルイ=フィリップのもとでの立憲君主政の政体が成立した。この「七月王政」は、1848年の二月革命まで続くことになる。ブルジョワに支えられた王政 七月王政の政治体制は1830年の憲法に基づく、立憲君主政。議会は制限選挙制によって有産者が多数を占め、上層ブルジョアジーが支配権力を握った。そこで、ルイ=フィリップを市民王、七月王政をブルジョア王政などといわれたこともあった。
産業革命と植民地獲得 この七月王政の18年間はフランスの産業革命時代となり、機械化が進み鉄道の建設が始まった。また1830年に始まるアルジェリア出兵による植民地化をさらに進め、またエジプト=トルコ戦争でのムハンマド=アリーへの支援など、東方問題への介入を強めた。
普通選挙制要求の高まり 一方、産業革命の進行に伴い、都市の中産階級と労働者階級も形成され、彼らは普通選挙などの改革を要求して選挙法改正運動を展開した。上層ブルジョアジー政権である国王ルイ=フィリップとギゾー内閣への批判を強め、政府の集会禁止に対して各地で改革宴会を開催し、気勢を上げるようになった。
第二共和政
フランスの二月革命によって成立した1848年~1852年の共和政体。フランス革命時の第一共和政(1792年9月~1804年5月)に次ぐ共和政。正式には11月の共和国憲法制定からであろうが、一般的に2月の七月王政崩壊後の臨時政府も含めて第二共和政としている。 → 1848年革命二月革命 1848年2月、七月王政のギゾー内閣が、改革宴会の開催を禁止したことに反発したパリ市民が抗議行動を始めると衛兵が発砲して死者が出たため、市民は各所にバリケードを築き、王宮を襲撃した。あっけなく国王ルイ=フィリップは亡命し七月王政が倒れた。フランスではここから年末にルイ=ナポレオンが大統領に選出されるまで一年にわたる激しい政変が続き、またベルリンやオーストリアの三月革命に飛び火し、全ヨーロッパで諸国民の春といわれる民族運動の昂揚によってウィーン体制が崩壊するという激動の始まりとなった。
臨時政府の動揺 二月革命の臨時政府には当初、ラマルティーヌなどの穏健なブルジョワ共和派と、ジャコバン派とも言われた急進的な共和主義者がおり、さらに労働者を基盤に社会主義の実現をめざすルイ=ブランらも含まれていた。しかし、臨時政府は革命を推進したパリの大衆の動きに常に左右され、一方では地方農村を基盤とする保守派である王党派(これにもブルボン王家を正統とする派やオルレアン家を支持する派などがあり、また絶対王政の復活を策する過激な王党派から立憲王政体制に妥協的な穏健な王党派までさまざまだった)も活動を続けており、臨時政府の統治は安定しなかった。
4月の選挙 臨時政府のもとでは、ルイ=ブランなどの主張により労働者を救済するための国立作業場の設置など、積極的な改革が進められた。しかし、政権内部にはブルジョワの立場と労働者の立場の違いが次第に明らかになり、また政府が公共事業のために課税を強化したことに対して農村の自営農層が不満をもつようになった。そのような経済不安が続くなか、1848年4月、憲法制定のための四月普通選挙が、21歳以上の男子の普通選挙によって行われた。この結果、穏健ブルジョワ共和派が多数を占め、また王党派も票を増やしたが、急進共和派と社会主義者など労働者の代表は少数にとどまった。この結果を受けたブルジョワ共和派は、労働者の保護よりも、産業や農業の保護、教会との協力を強めることに舵を切り、社会主義勢力の排除を図ることとなった。
六月蜂起 1848年6月、ブルジョワ勢力が主導権を握った臨時政府が国立作業場の廃止に踏み切ると、反発した労働者の蜂起を政府軍が鎮圧するという六月蜂起の事件がおこった。それを力で抑えきったブルジョワ共和派は軍人のカヴェニャックを担いで政治を安定させようとした。一方では、労働者の六月蜂起に危機感を強めた反共和政の右派は正統王朝派・オルレアン派にカトリックの勢力も加わって同盟し秩序党を結成し議会で勢力を増大させていった。 → 第二共和政の動揺
ルイ=ナポレオンの大統領当選 11月に制定された第二共和政憲法は人民主権、三権分立、大統領制を採用し、男子普通選挙を定め、その規定に従って1848年12月に大統領選挙が行われた。そこで大方の予想を裏切りルイ=ナポレオンが当選し、1848年12月15日、フランス大統領に就任した。
ルイ=ナポレオンは、ナポレオンの甥であることが、フランスの大衆にかつての栄光を回復する希望を与え、革命と蜂起で疲れていた国内に安定を与えると考えられたものと思われる。ルイ=ナポレオンは共和派を排除し右派のメンバーからなる内閣を発足させ、「共和政主義者なき共和政」といわれた権力をにぎった。翌年5月に立法議会選挙が行われると、右派の秩序党が53%で過半数を占め、穏健共和派は12%と惨敗、左派(この時は急進共和派と社会主義者が合同し山岳党―モンタニャールと称した)は35%と健闘し、議会は中道派が壊滅し、左右両極化が進む結果となった。
ルイ=ナポレオンは議会内には基盤がなく、直接的な国民の支持が必要だったので、カトリック勢力の支持を受けていたため、1849年にはフランス軍をイタリアに派遣してローマ共和国を倒し、教皇ピウス9世のローマ帰還を実現した。
議会では多数派となった右派の秩序党は、大統領ルイ=ナポレオンを無視する形で、集会の禁止、出版印刷税の復活、ストライキの禁止、カトリック教会が初等学校教育を行うことを可能にするファルー法の制定、選挙法の改悪(選挙資格の定住条件を6ヶ月から3年に増やすなど)など、反動的な立法を次々に議決した。このような議会に対して民衆が離反していくのを見ながら、ルイ=ナポレオンは機会を待っていた。
ルイ=ナポレオンのクーデタ 1851年12月2日、ルイ=ナポレオンは1851年のクーデタによって議会を解散させ、秩序党のティエールなど中心人物を逮捕した。年末の12月21日に国民投票を実施、投票率83%、賛成92%という圧倒的支持でクーデタは承認され、一気に共和政の息の根を止めた。翌1852年12月2日にはナポレオン3世として即位して第二共和政は終わり、第二帝政へと移行する。
フランス(7) 第二帝政から第三共和政へ
ナポレオン3世の第二帝政の時期、産業革命が進行、対外戦争・植民地獲得戦争を展開した。しかし1870年、普仏戦争に敗れ、パリ=コミューンを経て第三共和政となる。
第二帝政
1852年から70年までの22年間のナポレオン3世による統治時代のフランスを第二帝政いう。ナポレオン3世は叔父であるナポレオン1世の権威を背景にした大衆的な支持を力に、議会を形骸化し、軍隊と官僚を駆使して独裁的な政治を行った。その政策は、産業革命の進行に伴う産業資本家の成長をはかり、自由貿易政策に転換したこと、同時に産業資本家の利益の拡大を図り、国民的人気を得るために盛んに対外的な膨張政策をとった。そのような政治のあり方はボナパルティズムといわれることもあった。権威帝政から自由帝政へ 50年代に権威帝政といわれる独裁的な体制を作りあげたナポレオン3世は、自らが自由貿易主義者であったところから、1860年に皇帝大権で英仏通商条約を締結し、それまでの保護貿易体制を改め、関税を大幅に下げてイギリス工業製品の受け入れに踏み切った。その結果、企業の淘汰、資本の独占化がすすみ、技術革新・交通・通信の整備、銀行の成長、労働力の都市への移動などが進み、フランスの産業革命の完成期を迎えた。そのアピールのため、ナポレオン三世は、パリ万国博覧会を1855年と1867年の二度開催した。同時にそれは産業資本家の企業活動の自由の要求、労働者の権利要求、さらに社会全般の言論の自由などの要求が強まることを意味している。
ナポレオン3世は60年代に議会の一定の権限拡大、労働団結権の承認、一定の言論の自由、政治犯の釈放などで答え、その時期を自ら「自由帝政」と称した。本来両立しない自由と帝政を併存させるためには「偉大な皇帝」による恩恵としての自由でなければならず、皇帝の権威を創り出すために行われたのが「積極的外交」であった。
人気取りの外交政策 「人気取り」のために膨張的な外交政策をとったが、それは常に危険な冒険を伴っていた。クリミア戦争にはじまり、アロー戦争とインドシナ出兵では植民地や勢力圏の拡大に成功したが、メキシコ出兵は失敗に終わり、外交政策でのつまずきが始まった。
普仏戦争の敗北
プロイセン王国のビスマルクの挑発を受けて始まった1870年の普仏戦争では1870年9月のスダンの戦いでナポレオン3世自身が捕虜となったため退位に追い込まれ、第二帝政は終わりを告げた。1871年1月、パリに迫ったプロイセン軍はヴェルサイユ宮殿でドイツ帝国のヴィルヘルム1世の戴冠式を挙行し、フランスは大きな屈辱を味わうこととなった。さらに臨時政府のティエールは賠償金を支払い、アルザス・ロレーヌ(厳密にはその一部)をドイツに割譲して戦争を終結した。ナポレオン時代の報復に成功した形のドイツのビスマルクは、これ以後フランスの再起を押さえ込むための外交をヨーロッパで展開していく。第三共和政
フランスの第二帝政に代わる政体で、一般に1870年9月4日に共和政を宣言し国防臨時政府が成立してから、1940年までの約70年にわたる政体を第三共和政という。1875年1月に第三共和政憲法が制定されているため、第三共和政の開始時期については、1870年とするものと、1875年とするものとがあって混乱しているので注意すること。 → 第三共和政の項を参照臨時政府とパリ=コミューン 1870年9月から71年2月までは国防臨時政府が、71年2月からはティエールを首班とする臨時政府が対外的にもフランスを代表したが、国内には王政復古や帝政の復活を目指す勢力も根強く残っており、安定しなかった。また、臨時政府がプロイセンに降服したことに対して、パリの市民・労働者が反発して徹底抗戦を掲げ、パリから臨時政府軍を追いだして1871年3月28日にパリ=コミューン成立を宣言した。パリ=コミューンは労働者が権力を握った最初の社会主義政権としての国家権力であったが、ブルジョワ勢力に支持されたティエールの臨時政府軍によって5月に鎮圧された。ティエールは共和政を掲げて8月に大統領となったが、議会内の保守派・王党派によって失脚させられ、王党派のマクマオンが大統領となった。ようやく1875年に議会は第三共和政憲法を可決し、フランスの政体は共和政であることが確定した。
第三共和政の時代のフランスは、資本主義が急速に成長し、帝国主義段階を迎えていく時期に当たるが、ブルジョワ共和政政府に対して労働者の増大を背景にした社会主義者や労働組合運動などの左派の活動と、ブルボン王家の復活やボナパルティズムを支持する小農民などの勢力も政府を揺るがし、この左右両派からの攻勢によって政情は不安定であった。
フランス(8) 共和政と帝国主義
1875年、第三共和政憲法が制定されたが、左右両派からの攻勢が続いて不安定であった。この間資本主義の発展が続き、帝国主義の段階に入り、列強間の対立抗争が激化、第一次世界大戦に突入する。
共和政の危機
第三共和政の下で、普仏戦争敗北からの国力の回復、国際社会への復帰を目指し、1880年代までに大資本と結んだ共和派による政治がほぼ確立した。しかし、普仏戦争で失ったアルザス・ロレーヌ地方の奪回など、対独強硬論を唱える右派と軍部の台頭、一方の労働組合主義(サンディカリズム)の台頭、フランス社会党の進出という労働運動、社会主義勢力の成長もあって、共和政は左右双方からの攻撃を受けて常に動揺した。また政党政治も未成熟で、小党が乱立して安定せず、議員の汚職事件などの腐敗もあって権威を失い、19世紀末には大きな危機に陥った。そのような中で共和政を否定して軍部独裁政権の樹立をめざすクーデタ事件である1889年のブーランジェ事件が起こった。1889年 ブーランジェ事件の年 ドイツに対する復讐戦争を煽り、人気を集めた軍人が、王党派やナポレオン崇拝者などの支援を受けて共和国政府を倒そうとしたクーデタ事件であったが、首謀者自身が実行をためらったために失敗に終わった。この1889年はフランス革命から100年目に当たっており、記念してパリ万国博が開催され、その目玉としてエッフェル塔が建設された。共和政を倒そうというクーデタが失敗したことで、パリ万博は共和政の祭典として盛り上がり、エッフェル塔はフランスの産業発展の象徴となったが、それはブルジョワ共和政の勝利の象徴でもあった。一方のパリ万国博は、世界各地のフランス領植民地の展示が中心で、フランスが帝国主義段階に入ろうとしていることの象徴でもあった。
ドレフュス事件 しかし第三共和政の危機はその後も続いた。1892~3年にはパナマ運河会社の再建をめぐる汚職事件であるパナマ事件で多くの政治家・ユダヤ人財界人が贈収賄で逮捕された。これは第三共和制の危機であると共に、くすぶっていた反ユダヤ主義が勢いつく契機となり、それが1894年に始まったドレフュス事件で表面化し、フランスはドレフュスを擁護する派とそれを攻撃する派とに二分され、激しい議論が交わされた。反ドレフュス派は参謀本部を中心とした軍部とカトリック教会、王党派などの保守派がユダヤ人に対する敵視で一体化した勢力であり、その包囲網によって裁判ではユダヤ人将校のドレフュスがドイツのスパイと断定されたが、文学者ゾラなどの活動によってやがて証拠の改ざんなどが明らかになり、ようやく1906年に無罪が確定したという事件であったが、それによって最大の共和政の危機は回避され、カトリック教会と教育の分離などの政教分離の原則が確認されるなど、民主主義の前進にもつながった。
政党の結成 ドレフュス事件の危機の中で結成されたブルジョワ政党の急進社会党(社会主義政党ではなく、急進的な共和主義者の政党)と社会主義政党のフランス社会党の二つの共和勢力が、第三共和制の議会を主導するようになった。これらのブルジョワ共和主義者と社会主義者は、軍部とカトリック教会という国家主義・保守主義の力を抑えるため、1905年に政教分離法を成立させた。これによってナポレオンのコンコルダート(政教和議)は否定され、国家と宗教の分離、個人の信仰の自由という原則(ライシテ)が確立した。
フランスの帝国主義
共和政が維持される一方、この時期はフランスの工業力も発展し、帝国主義の段階に入り、19世紀末から20世紀初めにかけてアフリカ分割に加わってモロッコからサハラを横断してジブチに至るアフリカ横断政策をとり、アフリカ縦断政策をとるイギリスと対立を深めた。両国は1898年に上ナイルのスーダンでのファショダ事件で衝突の危機となったが、フランスはイギリスに妥協してスーダンから撤退し、コンゴの一部を得たにとどまった。しかしアフリカでは1830年にアルジェリアを植民地化、1881年にはチュニジアを保護国化し、つづいて1912年にはモロッコ保護国化を行った。チュニジア侵出ではイタリアと対立、モロッコ侵出ではドイツと対立してモロッコ事件が起きるなど、利害対立が鮮明になった。
また、すでに東南アジアでは1884年に清仏戦争で苦戦しながらベトナムに対する清の宗主権を排除し、1899年にはラオスを保護国化し、フランス領インドシナ連邦の殖民地を拡大した。また日清戦争後、ロシア・ドイツとともに三国干渉を行って日本に遼東半島を還付させ、清の弱体化につけ込み、1898年の中国分割では広州湾を租借し、鉄道敷設権などを得た。
帝国主義列強の勢力均衡策
フランスは、普仏戦争の敗北以来、外交的には常にドイツを仮想敵国としていた。1870~80年代にはドイツ帝国のビルマルク外交によって孤立を余儀なくされたが、90年代にドイツの世界政策との対立が明確になると、イギリス・ロシアとの提携を深めていった。イギリスとはファショダ事件で衝突を回避した後、1904年に英仏協商を成立させ、フランスのモロッコでの、イギリスのエジプトでの権益を相互に承認した。ロシアは早く1890年にドイツが再保障条約の延長を拒否したことを受けてフランスに接近、両者は1894年までの間に露仏同盟を締結した。これによってフランス・イギリス・ロシアは三国協商を形成することになり、ドイツ・オーストリア・イタリアの三国同盟の脅威に対抗することとなった。このような列強間の秘密軍事同盟によって勢力均衡を図るのが当時の「外交戦略」の基本姿勢であったが、結局、平和を維持することはできなかった。フランス(9) 第一次世界大戦
第一次世界大戦ではドイツに攻め込まれたが塹壕戦で耐え、連合国としての勝利を勝ち取る。1919年、ヴェルサイユ条約で領土拡張。ドイツに対する過酷な姿勢を取る。20年代には国際協調路線を取る。
第一次世界大戦への参戦
1914年6月、バルカンでサライエヴォ事件が起き、情勢が緊迫し、「七月の危機」が高まる最中、フランスの大統領ポワンカレは7月20日~23日にペテルブルクを訪問、露仏同盟を最終的に強化した。その7月23日にオーストリアがセルビアに対して最後通牒を発し、25日のセルビアが回答、28日にオーストリアが宣戦布告して第一次世界大戦が開始された。翌日、ロシアはセルビアを支援してオーストリアに宣戦し、ドイツは三国同盟を守ってオーストリア側で参戦、フランスはイギリスとともに三国協商の規定に従ってロシアを支援し、参戦した。こうして第一次世界大戦が勃発した。フランスは、開戦当初はドイツ軍の速攻によって攻め込まれたが、マルヌの戦いで食い止めてからは塹壕戦に突入して戦線が停滞した。総力戦に突入し、消耗が続いたが、アメリカ合衆国の参戦によって協商側がようやく勝利した。
ヴェルサイユ体制
勝利国となったフランスはパリ講和会議において、クレマンソーが対独強硬姿勢を主張、それが容れられる形でヴェルサイユ条約は、敗戦国ドイツに対する苛酷な要求を含んでいた。フランスはまずアルザス・ロレーヌを回復し、巨額の賠償金を認めさせ、さらにラインラントの非武装、ドイツの軍備制限など将来にわたる安全保障を実現しようとした。しかしこの過酷な要求はドイツ内部における反ヴェルサイユ体制という感情を生み、結果として安全保障とはならずナチス=ドイツを台頭させ、フランスは大きな犠牲をはらうこととなった。国際協調
フランスは国際連盟の常任理事国として、大戦後の国際平和に大国としての役割を担うこととなった。しかし、対独強硬姿勢は改めず、1923年1月にはベルギーとともにルール占領を強行し、ドイツに賠償金の支払いを迫った。ドイツ賠償問題は最大の課題であり、なおも緊張が続いたが、ドイツのシュトレーゼマン政権が履行政策(賠償金支払いを実行すること)に転じたため歩み寄りが実現し、1925年にロカルノ条約を締結し、フランスはドイツとの国境地帯での地域的集団安全保障体制を実現した。賠償問題もアメリカ資本の支援がドーズ案、ヤング案で実現して解決の方向性が見いだされ、国際協調の時代が実現した。この間、ジュネーヴ海軍軍縮会議に参加し、1928年、フランス外相ブリアンはアメリカのケロッグと協力して不戦条約の締結に成功したが、これらの国際協調の動きは、翌1929年の世界恐慌で崩れ去ってしまう。フランス(10) ファシズムの台頭と人民戦線
第一次世界大戦後も第三共和政の政情不安が続くとともに、30年代以降世界恐慌とファシズムの脅威にさらされ、1936年に人民戦線ブルム内閣が成立した。しかし、ブルム内閣は不況対策に失敗、スペイン戦争の対応をめぐる内部対立から38年4月に退陣した。
世界恐慌の影響
フランスは重工業の発展はアメリカ・ドイツに比べて進んでいなかったので、世界恐慌の影響は比較的遅かった。それでも農業不況が先行する形で30年代には深刻な不況に落ち込んでいった。列強がそれぞれ通貨の平価を切り下げ、植民地や勢力圏を囲い込むブロック経済体制を取るようになると、フランスは金本位制を維持するオランダ、ベルギー、スイスと金ブロック(フラン=ブロック)を構成してイギリス・アメリカと対抗しようとし、また植民地であるアルジェリア・インドシナなどの経営に力を入れるようになった。ファシズムの台頭
すでに隣国イタリアではムッソリーニのファシスタ党が権力を握っていたが、1933年にはドイツでヒトラー政権が成立、フランスはファシズム勢力に直接脅かされる情勢となった。特にドイツは公然とヴェルサイユ体制打破を掲げ、再軍備を強行してフランス侵攻を準備する形勢となった。また国内でも第三共和政下の政党政治が汚職や経済の無策から混乱し、労働組合のストライキが多発、不安を抱くブルジョワジーの中に共産主義に対する恐怖と議会政治に対する失望が広がり、その隙間にファシズム勢力が台頭してきた。人民戦線
それまでフランス社会党とフランス共産党は同じ社会主義政党でありながら、前者は議会制民主主義に則り暴力革命を否定し、反ソ連の立場に立ち、後者はコミンテルンのフランス支部として革命を目指し、社会党など社会民主主義をブルジョワ的な階級敵と見ていたので、激しい非難合戦を展開していた。そのため傘下の労働運動も二つに分裂、対立していた。30年代に入り、ファシズムの台頭という新たな情勢に対し、次第に両者の対立を克服して統一戦線をつくる必要があるという意識が強まり、1933年2月の政府の汚職事件を口実とした右翼の騒擾事件(スタヴィスキー事件)を契機に左翼の幅広い共同行動が始まった。共産党のトレーズは、ブルジョワ政党である急進社会党(ドレフュス事件の時にクレマンソーが結成した、急進的な共和主義政党。基盤は中間的な市民層で、戦間期に政権を担当した。)に対しても働きかけ、1935年7月14日には三党の共催による「パンと平和と自由」を求める大集会を全国で開催し、フランス人民戦線を成立させた。この動きを見たソ連のスターリンは35年5月仏ソ相互援助条約の締結に応じ、さらに7月25日、コミンテルン第7回大会は反ファシズム人民戦線戦術をとることを各国共産党に指示した。1936年1月に、社会党・共産党・急進社会党などの人民戦線綱領が作られ、総選挙の結果、人民戦線派が勝利して、1936年6月に社会党のレオン=ブルムが首相となって組閣し、フランス人民戦線が成立した。
ブルム内閣の挫折
そのころ、人民戦線の成立で勢いついた労働組合は、工場占拠などの激しいストライキを展開していた。ブルム内閣は人民戦線綱領に基づき、週40時間労働制や有給休暇制度の創設など労働者の待遇改善を実現、労働者の要求に応えた。当初の数ヶ月は改革が進んだが、次第に資本家・ブルジョワ勢力は国際競争力の低下を恐れて不安を強めていった。ついにその意を受けた閣内の急進社会党閣僚が、金兌換を停止するとともに、フランの金平価を28%切り下げ、金の輸出禁止に踏み切った。そのため労働者の収入は低下し、今度は労働者の不満が高まった。このような経済政策での閣内不一致でブルム内閣が動揺していたところに、スペイン内戦支援問題が起こった。スペイン共和国ではこの年1月にすでに人民戦線政府が成立していたが、同時に軍部の反乱が勃発、内戦が始まっていた。7月、モロッコからドイツとイタリアの軍事支援を受けたフランコ将軍が本土に侵攻してくると、共和国政府はイギリス、フランスなどに支援を要請した。ブルムと共産党はただちに支援を決定したが、スペインでの革命の波及とソ連の影響力の強まることに不安を抱く急進社会党や社会党右派が強く反対し、この問題でも閣内不一致に陥った。またイギリスも不干渉で同調するようフランスに要請したため、ブルムは結局スペイン支援をあきらめる。この二つの問題で立ち往生したブルム内閣は、37年6月総辞職、その後も形式的な人民戦線内閣のもとで混乱が続き、ブルムが復帰したが、それも38年4月に退陣し、人民戦線は終焉した。
フランス(11) 第二次世界大戦
ダラディエ内閣はヒトラードイツに対する宥和政策をとったが、その膨張を抑えることができず、第二次世界大戦が開始されると1940年5月ドイツ軍に侵攻され、国土の大半を占領され、ヴィシーに対独協力内閣が成立。国内のレジスタンスとともにド=ゴールの亡命政権が抵抗を指導、1944年8月にパリを解放した。
宥和政策
ヒトラーは仏ソ相互援助条約をロカルノ条約違反であると非難し、ドイツの脱退を宣言した。スペイン内戦ではイギリス・フランスの不干渉政策を尻目にムッソリーニのイタリアとともに積極的にフランコ反乱軍を支援、ゲルニカ空爆などを含む直接介入を行い、共和国軍とそれを支援するソ連軍、国際義勇兵との間で、一種の世界戦争の「予行演習」を行い、1939年までにほぼ共和国を圧倒し、フランコ独裁政権の成立をもたらした。自信を深めたヒトラーは次いでチェコスロバキアのズデーテン地方の割譲を要求、それを受けて38年に開催されたミュンヘン会談では、フランスの急進社会党ダラディエ内閣はイギリスのネヴィル=チェンバレンとともにヒトラーに対する宥和政策をとってズデーテン地方の割譲を承認、反ファシズムの旗印を取り下げた。しかし、ヒトラーの領土的野心を抑えることはできなかった。
第二次世界大戦
1939年9月、ヒトラーがポーランドに侵攻して第二次世界大戦が開始されると、ポーランドとの攻守同盟を結んでいたフランスはドイツに対して宣戦布告した。しかし、ヒトラーがポーランド軍を次々と撃破し、ワルシャワに迫るという情勢になっても、フランス軍はポーランドに支援軍を送ることもせず、西部戦線でドイツに攻勢をかけてポーランドを救うこともしなかった。この段階に至ってもなお、ヒトラーはポーランドを奪えば侵略をやめ、停戦に応じるであろうという甘い予測、宥和政策の継続があったのであろうが、このことはフランス国民にとっても「奇妙な戦争」、つまり宣戦布告したにもかかわらず戦争をしないという、状態であった。しかしこの観測が誤りであったことはポーランドをソ連と分割し終えたヒトラーが、1940年に矛先を西部戦線に向けたことでただちに明らかになった。1940年5月10日、ドイツの侵攻が始まると、わずか1ヶ月後の6月14日にパリ陥落、6月22日に休戦協定を結んでフランスは降伏した。フランスは占領地区、併合地区、自由地区の三つに分割され、1940年7月11日にペタンを国家主席とするヴィシー政府が成立した。ヴィシー政府は大統領制と議会を廃止し、ここに第三共和政は終りを告げた。
ヴィシー政府とレジスタンス
ヴィシー政府はイギリスを除いて各国に承認されたが、ドイツに協力することによってフランスの存続を図ろうとした。ペタンは84歳の元帥で第一次世界大戦の英雄であったが保守以外にこれといった政治理念はなく、人民戦線に反対した人々やファシスト、反共主義者、カトリック教徒など雑多な集まりに過ぎなかった。政策も建前は国民革命を表明したが、カトリックの宗教教育を復活させるなど復古的なものにとどまった。それよりもまず「ユダヤ人狩り」を行うなどナチス=ドイツに迎合する面が強く、また占領区の男性はドイツの労働力の不足を補うものとして動員された。占領と同時にフランス各地でナチスドイツに対するレジスタンス(抵抗運動)が始まり、自然に組織化されていった。最も組織的にレジスタンスを展開したのはフランス共産党で、ドイツ軍人などに対するテロや後方攪乱を盛んに行った。また国外に亡命した軍人の中でド=ゴールが自由フランス政府を1940年6月、ロンドンで組織、BBC放送を通じてフランス国内のレジスタンスを呼びかけた。1943年6月3日には「フランス国民解放委員会」が亡命政府として成立、レジスタンスを組織的に指導するとともに、戦後の枠組みの構築を開始した。
フランスの解放
1944年6月6日、連合軍がノルマンディー上陸作戦を敢行、8月25日にパリが解放された。9月9日にド=ゴールがパリに帰還し、臨時政府首相として国家再建に当たることとなったが、まず対独協力者に対する裁判が行われ、ペタン以下が死刑判決を受けた。ペタンは後に無期禁固に減刑されたが、元外相のラヴァルらヴィシー政府幹部は処刑され、他に正規の裁判なしに約5000人が報復として殺害されたという。フランス(12) 戦後のフランスと第四共和政
第二次世界大戦でドイツが敗北し、フランスは解放される。総選挙を実施しド=ゴールを首相とする社共を含む連立政権が成立、1946年10月第四共和政が成立した。その後政情不安が続く中、インドシナ、アルジェリアの植民地独立戦争が激化し、1958年にド=ゴールが首相復帰、憲法を改正して第五共和政となる。
戦後の臨時政府
戦後の政治の主導権をめぐってドイツと戦ったレジスタンスの内部に、共和派と共産党の対立が激しくなる中、ド=ゴールは共産党勢力が力を付けることを警戒し、臨時政府の首相となることを承認し、1945年11月に憲法制定国民議会で満場一致で臨時政府首相に指名された。臨時政府は経済再建と憲法制定に取り組んだが、ド=ゴールは最大の勢力となった共産党と対立したため、1946年1月、辞任した。その後に実施された総選挙(フランスで始めて婦人参政権を行使)では、共産党、人民共和派(MRP、キリスト教系保守中道政党で反共を掲げる)、社会党が大きく議席を伸ばし、共産党・社会党を含む3党連立内閣が成立した。
第四共和政
1946年10月に新憲法が成立、47年1月に施行されて第四共和政が成立、第三共和政の政権不安定を反省して内閣の権限強化が図られたが、なおも小党分立が続いて不安定であった。 フランス第四共和政は1946年10月から1958年までの12年間の短い間であったが、その第四共和制憲法のポイントは次のようにまとめられる。- 議会 立法権は第一院の国民議会のみが持ち、第二院の共和国評議会は諮問機関とされた。
- 大統領 国民議会と共和国評議会の両院合同会議で選出され、任期7年であるが、その権限は第三共和政よりも小さく、対外的に国を代表するほか、実質的な権限は無かった。
- 内閣 第三共和政下での政治の不安定を反省し、内閣の権限は強化され、総理大臣(首相)は大統領によって指名されるが議会の絶対過半数の信任が必要で、閣僚を任免する権限が認められた。
不安定な政体
その後もフランスの内閣は連立せざるを得ず、戦中のレジスタンスでの協力意識が薄れるにつれ、閣僚間の対立が始まり、常に不安定であった。そのため戦後復興の課題が一向に解決されず、国民の不満は高まっていった。臨時政府首相を辞任したド=ゴールは政界から引退したが、共産党の勢力拡大を恐れ、右派の結集を図って「フランス人民連合」(RPF)を結成し、その党首となって政界に復帰し、第四共和政に反対して大統領権限の強化を実現し、強いフランスの再生を主張して、支持を集めた。
この間、1950年に外相のシューマンが提唱したヨーロッパ石炭鉄鋼共同体(ECSC)が発足し、ヨーロッパの統合への動きではフランスは主導的な役割を担った。
しかし、内政での不安定に加え、フランス植民地の遺産であるインドシナとアルジェリアで、戦後の民族意識の高まりとともに独立運動が開始された。インドシナ戦争とアルジェリア戦争に対しては、国内の共産党、社会党などの独立容認の意見と、軍部や保守派など海外領土維持の主張がするどく対立し混乱が続いた。
植民地の喪失
インドシナ戦争では1954年5月7日にディエンビエンフーの戦いに敗れ、ジュネーヴ会議の結果、ジュネーヴ休戦協定を締結、ベトナム共和国の独立を承認し、フランス領インドシナ連邦は解体した。アルジェリアでは民族解放戦線(FLN)が1954年11月に武装蜂起し、アルジェリア戦争が始まり、第四共和政政府は独立承認に傾いたが、植民地の入植者と軍が反発、58年に本国政府に対して反乱を起こした。 → アルジェリア問題
フランス(13) 第五共和政とド=ゴールの時代
1958年、ド=ゴールは首相として第五共和制憲法を成立させ、自ら権限を強化した大統領に選出された。その後10年にわたって権力を握り、アメリカに追随しない独自外交と経済復興に成果をもたらした。しかし長期政権化は、社会のひずみを強くし、1968年に学生ら青年層の反発が強まり、翌69年に辞任に追い込まれた。
ド=ゴールの再登場 第五共和政
このような内外の困難に対応できない第四共和政政府に対し、国民は議会の議論より強いリーダーシップを望むようになった。そのため、1958年に政権は崩壊、保守派の支持するド=ゴールが首相に復活、さらに大統領権限を強化した第五共和政憲法を提案、1958年10月の国民投票で承認され、第五共和政に移行した。第五共和政の規定による1958年12月の大統領選挙でド=ゴールが当選すると、一転して保守派を抑えてアルジェリアの独立を承認して問題を解決し、国民の圧倒的な支持を背景に69年までド=ゴール時代が続く。
ド=ゴールの外交
フランス経済はマーシャル=プランによって復興することが出来たが、ド=ゴール時代にはアメリカへの依存を脱却し、次第に独自色を強めていく。特に外交政策では、ド=ゴールはアメリカ及びイギリスに対抗して、独自のド=ゴール外交を展開し、「フランスの栄光」の再現を目指した。その姿勢は1960年2月の核実験の強行・1966年7月1日にNATO軍事機構脱退・イギリスのヨーロッパ経済共同体(EEC)への加盟反対・中華人民共和国の承認などに明確に現れている。五月危機
ド=ゴール政権はその後、10年あまり続いたが、初期の圧倒的な国民の支持も長期政権に対する批判が次第に出てきて、1968年5月の世界的な学生運動の盛り上がりの中でフランスでも起こった五月危機によってその権威が揺らぎ、翌年ついに辞任した。フランス(14) コアビタシオンと揺れるヨーロッパ統合
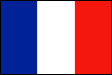
80~90年代、左派のミッテラン、右派のシラク大統領の時代には、第五共和制憲法の規定の下、大統領と首相が異なる政党に属する保革共存という事態が続いた。ヨーロッパ統合についても反対派が台頭、黄信号が点っている。
フランス国旗として有名な三色旗はフランス革命の中で1794年にラ=ファイエットが考案し、革命のシンボルとして用いられるようになった。国民公会が正式な国旗として定め、ナポレオン時代に定着した。王政復古期に一時使われなかったが、七月革命の時に国旗として復帰し、現在はフランス国旗と言えばこの三色旗を意味する。自由・平等・博愛を意味するというのは、こじつけ的なところがあるらしい。
現代のフランス
第一次世界大戦、第二次世界大戦という二度にわたる隣国ドイツの侵略を受けながら、戦後は経済の復興に成功し、第四共和政(1946~1958)を経て、現在は第五共和政(1958~)という政体をとっている。戦後は、国際連合の安保理の常任理事国としてその主要メンバーとなり、冷戦下の米ソ二大勢力に対抗すべく、ヨーロッパ統合の先頭にたち、国際政治にも大きな発言力を有してきた。インドシナやアルジェリア、アフリカのフランス領など、かつては植民地大国であったが、いずれもその独立を抑えることはできず、1960年代前半までで独立を容認した。現在は、増大した移民を抱え、経済の停滞からは右派が台頭し、またヨーロッパ統合に対しても懐疑的な声が国内に強まり、大きく変容している。左派ミッテラン政権の登場
ド=ゴール退陣後の大統領選挙は、ド=ゴール主義を継承するか、脱却するかが問われることとなり、ポンピドゥー(1969~74)はド=ゴール主義を継承し、ジスカールデスタン(1974~81)は脱ド=ゴールをかかげた。しかしいずれも保守派政権であり、その経済政策は,ドイツや日本に後れをとって低迷したため、国民は変化を求めるようになっていった。そのような時期の1981年の大統領選挙では、フランス社会党を率いたミッテランが、それまで対立していたフランス共産党との協力関係を築くことに成功し、当選を果たした。左派が政権に加わったのは、1948年の社会党(SFIO)・人民共和派(MRP)・急進社会党(Radicaux)などによる中道左派連立内閣以来、33年ぶりあった。第五共和政第4代大統領となったミッテランは、公共投資の増加、国有化の推進による雇用の拡大、最低賃金の引き上げや社会保障の拡充による購買力の向上をめざすという、社会民主主義政策を実行した。これは、イギリスのサッチャーやアメリカのレーガンなどの新自由主義がとった「小さな政府」とまったく異なる対照的な政治として注目された。しかし、目先の景気の回復には結びつかず、1986年総選挙では社会党は敗北した。
コアビタシオン
1986年の総選挙敗れても、大統領は議院内閣制ではないので、ミッテランは大統領にとどまった。しかし議会では多数派となった保守派から首相を選ばざるを得なくなり、シラクを指名した。こうしてフランス第五共和政憲法の規定により、大統領が左派、首相が右派という、保革共存の政体が成立、これをコアビタシオンといった。コアビタシオンの下では、ほぼ、外交は大統領、内政は首相という棲み分けを行い、バランスがとられることとなった。しかし、大統領と首相が基本的政治姿勢で対立することがしばしば起き、シラクも間もなく辞任した。ミッテランは個人的な人気が高く、大統領選挙で再び勝利して大統領を二期目も務めたが、首相はやはり保守派のバランデュールを指名せざるを得ず、コアビタシオンが続いた。ミッテランの長期政権が国民の支持を失い、1995年にシラクが大統領となったが、1997年には首相には社会党のジョスパンが指名され、コアビタシオンが続いた。サルコジ大統領
1995年から2期12年を務めたシラクに代わり、2007年にサルコジ大統領が大統領に選出された。サルコジはシラクの後継者として指名され、議会多数派の保守中道連合の支持を受けていたが、2007年大統領選挙では社会党の女性候補との間の決選投票でようやく選出されるという辛勝であった。2005年秋の学生と外国人労働者の騒擾事件を厳しく弾圧したときの内務大臣で暴動を起こした若者を「社会のクズ」と呼んで非難されたが、かえってその強硬路線がフランスの栄光を望む保守層の人気を集めた。しかしサルコジ自身はハンガリー系の移民の子で、少年時代に両親が離婚、中学生の時は留年を経験するという屈辱からはい上がり、弁護士資格を取って政治家になった苦労人であったことから人気が高かった。現在のフランスでは、2005年5月の国民投票で批准できなかったEU憲法条約の再批准問題とともに、依然として高い失業率と経済格差、増え続ける移民問題もかかえていた。サルコジ大統領は従来のフランスのアメリカとは一線を画していた外交路線を親米路線に転換する傾向があり、また内政ではフランス伝統の平等主義をすて、新自由主義的な競争原理、市場原理の導入を強めた。2009年4月4日には、ドゴール大統領の時のNATO脱退以来、43年ぶりにNATO軍事部門へ完全復帰した。
参考 フランスの地域語の復活
かつてフランスは地域語が堂々と使われる多言語国家であったが、フランス革命で革命理念をフランス語で広めるため、1794年には「地域語・方言の抹殺」を目標に、フランス語言語教育が行われた。公立学校でフランス語教育が義務化され、19世紀末に初等教育が無償化され急速に普及し、学校で地域語を話すとお仕置きされていた。第二次世界大戦後の51年に政策の転換が図られ、地域語を学校で教えられるようになり、81年のミッテラン政権でその流れが進められた。保守派の抵抗もあって92年の憲法改正では「共和国の言語はフランス語である」と明記された。しかしヨーロッパ統合のなかで、ヨーロッパの多言語主義がとられるようになって、フランスでも地域語の復権がはかられ、2008年7月の憲法改正で地域語は「フランスの遺産」と明記されることとなった。代表的な地域語にはアルザス語、オクシタン語(南部地域)、ブルトン語(ブルターニュ)、コルシカ語、バスク語などがある。<朝日新聞 2008年12月26日記事>社会党オランド大統領
2012年4月の大統領選挙でサルコジは、社会党のオランドに決選投票の末に敗北し、フランスはミッテラン時代以来の革新政権に戻った。オランド政権は、社会党政権として雇用の回復や女性の参画などが期待されたが、経済政策では景気浮揚を狙って富裕層に対する課税を後退させるなどの政策が効果を上げず、景気後退が続いて人気が低落した。2014年にはサルコジを大統領選挙の時の収賄容疑で逮捕し、人気挽回を図ったのではないかと注目されている。イスラーム教徒との軋轢 2015年1月7日、イスラーム過激派による諷刺新聞シャルリー=エブド社襲撃事件が起こった。ムハンマドを諷刺した絵を掲載したことに反発したイスラーム教徒がその編集部を襲撃したもので、背景には政教分離(ライシテ)を原則とするフランス社会でのイスラーム信者の不満があったが、フランス人はライシテの原則と言論の自由を叫んでテロリストを非難した。すると今度は2015年11月13日にパリ同時多発テロが起き、一般市民に犠牲者130人がでて、オランド大統領もテロとの戦争を宣言する事態となった。これらの事件は政教分離(ライシテ)を国是とする現代フランスに大きな衝撃と深い分断を持ち込んだ。<伊達聖伸『ライシテから読む現代フランス』2018 岩波新書>
2017年大統領選挙
2017年の大統領選挙はオランドが自らあまりの人気の無さから出馬を断念、左右両派から有力候補が5人出馬、経済政策と共に移民問題、そしてライシテの原則に対する姿勢が問われる選挙となった。結果は決選投票となり、オランド政権下で経済・産業・デジタル大臣を務めた39歳のマクロンと、右翼の国民戦線ルペン(戦後フランスの代表的国家主義者ルペンの娘)の間で争われ、マクロンが勝利した。従来の中道左派(社会党)・中道右派(共和党)のいずれにも飽き足らなく感じていた国民が、中道現実路線の若手政治家に期待したのだった。またこの大統領選挙は、第五共和政で続いていた、保革の二大政党の候補者のいずれかが当選するという結果にならず、初めて2大政党以外の候補者が当選した。また国民が直接選挙で大統領を選ぶようになった1965年以降でも初めてのことだ。これはフランス政治の保革対立(厳密に言えば中道左派と中道右派)という伝統的な対立構図が崩れたことを示している。
Episode 24歳年上のファーストレディ
マクロンの39歳での就任は、1848年に40歳で大統領に選出されたルイ=ナポレオン(後のナポレオン3世)を越える、史上最年少であった。またマクロンは、高校生の時に国語の教師で既婚だったブリジットと恋に落ち、転校させられたりしながら、24歳の年の差を超えて結婚したことが話題となった。
マクロン大統領
マクロンは国立行政学院卒業のエリートとして財務省に入り、その後ロスチャイルド銀行に入って投資家として成功した。その若さと行動力を期待され、オランド大統領のもとでヴァルス内閣の経済・産業・デジタル大臣に就任した。一時は社会党に属したが、それに縛られない規制緩和や財政拡大路線をとったので閣内でも批判されるようになり、独自の政党「前進!」を結成し、中道改革路線を明確にした。大統領就任後、党名を「共和国前進」に改称し、与党として総選挙でも勝利し、若さも相俟って人気も高まった。黄色いベスト運動 しかしマクロン政権の「改革路線」は既存の労働組合や貧困層からは強く反発された。2018年11月からガソリン燃料税引き上げを図ったところ、トラック運転手による抗議活動から「黄色いベスト運動」といわれた激しいデモが起こり、一時は暴動に発展した。それに対してマクロンは柔軟な姿勢を見せ、燃料税引き上げを断念、広範な国民との対話を重ね、2019年4月には低所得者などへの所得税削減と年金の増額を約束した。一時は退陣も近いかと思われたが、反マクロン運動はその後沈静化した。
外交ではEU維持を掲げイギリスのEU離脱やトランプの「アメリカ第一」主義には抵抗する姿勢を明らかにし、トランプのイラン核合意離脱には強く反対している。一方では移民制限や徴兵制の復活案など、保守派ウケする対策も打ち出している。右派、EU懐疑派も依然として根強く、若い大統領がフランスの舵取りをどのように行うのか、注目されている。<2019/8/26記>
NewS ノートルダム大聖堂の火災
2019年4月15日未明、パリのノートルダム大聖堂で火災が発生、尖塔が焼け落ち、内部も大部分が焼失するという災害が起こった。世界遺産でもあり、フランスのカトリック信仰の中心であって、パリの歴史や文学の舞台ともなった大聖堂の火災はフランスだけでなく世界中の人々を悲しませた。原因は修復工事中の失火と見られている。マクロン大統領はただちに大聖堂の復活を支援することを表明した。