タイ(シャム)
現在のタイの地に、13世紀以降、タイ人が北方から移住し、スコータイ朝、アユタヤ朝などが興亡した。一時ビルマ人に支配された時期もあったが、18世紀のラタナコーシン朝はラオス、カンボジアを属国とし、領土を拡げた。19世紀には植民地化の危機があったが、イギリス・フランスの緩衝地帯となったため独立を維持した。長くシャムと称していたが、1932年の立憲革命後、39年からタイに変更した。第二次世界大戦では日本との関係を深め枢軸国側に加わった。戦後は経済を復興させたが、クーデタが相次ぎ、経済危機もあって政治的な苦難が続いている。
タイ GoogleMap
現在のタイ国の地域に最初に現れた国家は、モン人のドゥヴァーラヴァティ王国であった(タイ人の国家ではないので、通常はタイの王朝には加えない)。すでに上座部仏教を取り入れたこの国はチャオプラヤ川上流に栄えていたが、東のクメール人の侵攻を受けて衰えた。
クメール人のアンコール朝は12世紀に最盛期となり、現在のタイ領域のモン人などを支配する大国となり、アンコール=ワットを造営して栄えたが、かわって13世紀から中国南部の雲南地方にいたタイ人が南下を開始し、「タイ族の大いなる沸騰」といわれる活動を開始して国家を建設していく。
注意 シャムとタイ タイ人は中国史料では暹(セン)として現れ、14世紀ごろからシャムと言われるようになり、自らも国号を「シャム」としていた。現在の国号としてのタイは、ごく新しく、1939年に変更しものである。従ってそれ以前は「シャム」とすべきであるが、ここでは便宜的に一貫性をもたせるため「タイ」と表記している。
タイ(1) タイ人国家の変遷
13世紀以降のタイ人の歴史の中で、次のような国家が興亡した。スコータイ朝:タイ人がクメール王国から自立して立てた最初の国家がスコータイ朝で、1240年頃(1257年頃とする説もある)、チャオプラヤ川上流のスコータイを中心に、クメール人に代わって建国した。第3代のラームカムヘーン王の時の1283年、タイ文字を作り、上座部仏教を保護した。
アユタヤ朝:1351年にチャオプラヤ川中流のアユタヤを中心にアユタヤ朝が出現し、スコータイ朝を併せ、ビルマやカンボジアとも争い、1431年にはカンボジアのアンコール朝の都アンコールを占領して領土を広げた。このころのタイ人の国家はシャムといった。1569年には西のビルマのタウングー朝に侵攻され、15年間その支配を受けたが、16世紀末には独立を回復し、逆にビルマに侵攻した。アユタヤ王朝はチャオプラヤ川から海上に出て、交易でも栄えた港市国家ということができ、17世紀にはポルトガルやオランダ、中国商人と並んで日本人の活動も及んできて、日本町が作られ、山田長政などが活躍した。1767年、ビルマのコンバウン朝の侵入によってアユタヤが破壊され、アユタヤ朝は滅亡した。
北部の王朝:なお、13、14世紀頃には、チャオプラヤ支流のビン川流域でビルマに近いチェンマイにはランナー王国(「百万の田」の意味)、ラオスには同じタイ系のラオ人のランサン王国(「百万頭の象」の意味)があった。いずれもタイ人系の国家であるが、タイの歴史の中では傍系に置かれている。いずれも16世紀にビルマのタウングー朝の支配下に入った。
トンブリー朝:1768年、地方政権の一つであったトンブリー朝のタークシンが立って、ビルマ人を撃退し、独立を回復した。タークシン王はカンボジアに進出し、アンコール=ワットのあるシュムリアップなどを併合した。しかし、王は仏教勢力を抑圧する余りに奇行が多くなり、部下のチャクリが王位を奪ってラタナコーシン朝が成立した。
ラタナコーシン朝:1782年、チャクリがラーマ1世としてラタナコーシン朝(チャクリ朝、バンコク朝とも言う)を建国し、都バンコクを中心としてやはり交易と農業で栄え、北部のランナー王国や南部マレー半島のイスラーム勢力を次第に統合して、その領土(属国支配も含めて)は現在のタイの倍ほどの広さとなり、ラオスやカンボジア、マレーシア(北部)にも及んでいた。
タイ(2) ラタナコーシン朝のシャム
19世紀以降のタイ(ラタナコーシン朝シャム)は、周辺でのイギリス・フランスの侵略が進む中、1855年にボウリング条約で開国した。イギリス・フランスがタイを緩衝地域として直接対決を避けたため、領土は縮小させながら独立を維持した。
イギリスは1819年にシンガポールを獲得、マレー半島方面からタイの勢力圏を脅かし、さらに1824年に始まり、三次に及んだイギリス=ビルマ戦争でビルマを植民地化し、フランスは1858年のインドシナ出兵をはじめとして、ベトナム・カンボジア・ラオスに及ぶフランス領インドシナ連邦(1887年)を形成していった。
このようにタイは東西からのイギリスとフランスの勢力による圧迫に苦しむこととなった。まずイギリスは自由貿易を求めて、1825年、タイに特使バーネイをバンコクに派遣し、ラーマ3世に迫り、イギリス商人のバンコクでの商業活動を認めさせた。このバーネイ条約は不平等なものではなかったが、イギリス=ビルマ戦争の最中に結ばれたタイにとって最初の外国との条約であり、本格的な開国への第一歩となった。
タイの開国
1855年、ラーマ4世はイギリスとの通商条約であるボウリング条約を締結、さらに同様な不平等条約を欧米諸国と結び自由貿易を受け入れた。同時に外国人顧問を多数受け入れ、近代化を図った。次の19世紀後半、ラーマ5世(チュラロンコン大王)は巧みな外交でイギリスとフランスを操り、両者が牽制し合ったこともあって、タイは勢力圏を大幅に割譲せざるを得なかった<注>ものの、東南アジアで唯一、植民地化の危機を脱し、独立を維持することができた。<注> タイが英仏に領地を割譲したため領土が半分になった、といわれることがあるが、それは誇張した言い方で、必ずしも正確とはいえない。この時失ったのは、タイの本来の領土ではなく、宗主権を有して勢力圏としていた部分である。正確には「領土の喪失」ではなく「宗主権などの間接的な支配権、勢力圏の喪失」と言うべきことである。 → ボウリング条約の項を参照。
タイのカンボジア・ラオス宗主権喪失
ラーマ4世からラーマ5世の時代、19世紀後半はビルマを併合したイギリスと、ベトナム・カンボジアなどフランス領インドシナを獲得したフランスが、双方からタイに迫り、その主権も脅かされた時期であった。タイはカンボジアを保護国とし宗主権を有していたが、フランスのナポレオン3世はカンボジア王に迫って1863年にカンボジア保護国化を認めさせた。その際はカンボジアの北西部、バッタンバン、シュムリアップ(アンコール=ワットなどが含まれる地方)などはタイの宗主権が残された。
その後、フランス(第三共和政)はフランス人官僚殺害に対する抗議という名目で、1893年7月13日、チャオプラヤ川河口のパークナームから軍艦をさかのぼらせ、タイの砲台と交戦し、バンコクのフランス領事館前に停泊して港を封鎖し、メコン川左岸(東岸)のタイが宗主権を有していた現在のラオスの割譲を迫った。パークナームでは両軍が衝突しタイ側に20人の死者が出た(パークナーム事件)。やむなくラーマ5世は1893年10月3日、フランスの要求をのみ、賠償金の支払い、メコン東岸のラオスの宗主権などの放棄を受け入れた。これは日清戦争の前年であり、日本が清の朝鮮に対する宗主権を放棄させたことと時を同じくしている。またフランスはその10年前の1884年、清仏戦争で清を破り、清のベトナムに対する宗主権を放棄させている。
タイが植民地化しなかった事情
イギリスが1886年にビルマ全土を植民地化して、タイへの進出の姿勢を見せ始める一方で、フランスはメコン左岸とカンボジアにとどまらず、メコン右岸(西岸)への進出を露骨に開始した。こうしてタイは東西から帝国主義による植民地分割の危機が迫ったが、この二国は直接的な対決を回避し、1896年、タイのチャオプラヤ川流域を両国の緩衝地域とすることで合意し、英仏宣言をだした。これによってタイは英仏間の「緩衝国」となったため、独立を維持することができたが、その要因としてはタイの置かれた地政学的な位置によること以外にも、それを導いたラタナコーシン朝のラーマ5世の巧みな外交力もあげることができる。アフリカにおける英仏対立 しかし、イギリスとフランスがタイを緩衝国とすることで直接対決を避けた理由は、タイの側に要因があったのではない。当時両国はアフリカにおいて、イギリスが縦断政策、フランスが横断政策をとり、スーダン付近でにらみあっていた。しかし、両者は全面的な対立を避け、勢力圏を分割することで共存を図る姿勢をとっており、それが1898年9月19日のファショダ事件になって現れる。東南アジア方面でも角を突き合わせた両国は、一定の植民地を確保した上で、妥協の道として選んだのが、この「緩衝国」宣言であった。18世紀に繰り広げたアメリカ大陸とインドにおける英仏植民地戦争(第2次百年戦争)が、アメリカ独立革命・フランス革命の要因となったことを両国が意識したのかもしれない。それよりも共倒れを避けようとする帝国主義国独特の自己保存欲が働いたのであろう。
英仏協商 両国の妥協は、さらに1904年の英仏協商によって明確になった。これはエジプトとモロッコをそれぞれが勢力圏とすることを認めたのが主眼であったが、同時にタイにおいては独立国と認めながら、チャオプラヤ川の西部と西南部はイギリス、東部と東南部はフランスの勢力圏とすることを承認し合ったものである。このようにタイが英仏の緩衝地域という役割を果たしたことによって英仏両国の直接侵攻はこれ以上進むことはなかった。またラーマ5世は、近代化に当たり、欧米各国から顧問を招いたが、特定の国から多くなるとその力が強くなるので、その数のバランスをとるなどの工夫をした。
不平等条約の改正と領土縮小
フランスはパークナーム事件後に南部の港チャンタブリーを占領、それをテコにタイと交渉を続け、チャンタブリーの返還の代償にルアンプラバン対岸などを割譲させた。フランスはそのころ、アジア系保護民をタイ領内に送り込み、彼らについてもフランスが領主裁判権をもつと主張して不法行為を繰り返させるという手段でタイを混乱させていたので、不平等条約の治外法権(領事裁判権)撤廃はタイにとって切実な要求となっていた。フランスとの間に入ったアメリカ人顧問の仲介で、1907年に保護民に対する領事裁判権を廃止することとの交換で、タイはカンボジア北西部のバッタンバン、シェムリアップなどの宗主権を放棄し、フランスに割譲した。これでカンボジア全域がフランスの保護国となった。1909年には同じくアメリカ人顧問の仲介によってイギリスと交渉し、イギリスが割譲を要求していたマレー半島の4州(クダー、ペルリス、クランタン、トレンガヌ)を譲渡する代わりに、領事裁判権の撤廃を認めさせた。この1909年の割譲によって、現在のタイの領域が確定した。タイのナショナル・ヒストリーではこれまでに割譲で失った領土は、現在の国土面積51.3万平方㎞にほぼ匹敵すると言われているが、これまでの「失地」の大半はかつての属国、つまり朝貢関係にあった地方政権であり、タイがこの広大な領域すべてを直接支配していたわけではない。それでもこの「失地」は屈辱的な歴史として語られており、後に「失地」回復運動の対象となっていく。<柿崎一郎『物語タイの歴史』2007 中公新書 p.133-134>
第一次世界大戦参戦と不平等条約改正
第一次世界大戦が勃発すると、タイは当初は中立を宣言したが、ワチラーウット王(ラーマ6世)は途中から条約改正の好機と捉え、参戦した。1917年7月、ドイツ、オーストリア=ハンガリーに宣戦布告、飛行部隊と自動車輸送部隊をヨーロッパ戦線に派遣した。このとき赤、青、白の三色旗を国旗と定めた。パリ講和会議には戦勝国として参加し、不平等条約改正(関税自主権の回復と領主裁判権の完全撤廃)をアメリカ、イギリス、フランスなどに求めた。民族間の平等を掲げるウィルソン大統領のアメリカは翌年に新条約を結んで関税自主権回復を認め、治外法権についてはタイの法典完成後5年後に実現することで合意した。イギリス、フランスとの交渉は難航し、イギリスは関税自主権の回復に反対、綿製品などの関税は今後10年間は5%以内に抑える条件付きでようやく合意した。フランスとはバンコクからの鉄道をカンボジア国境まで延伸すること、メコン川の国境を見直し、川中の島をすべてフランス領とすることなどを合意し、結局不平等条約改正作業は1927年までかかった。<柿崎『同上書』 p.140-141>タイ(3) 立憲君主政となり、国号をタイに変更
第一次世界大戦後の1932年にピブンらに指導された立憲革命が起こり、立憲君主政となる。ピブン政権は1939年に国号をシャムからタイに変更し、国民の国家意識の高揚を図った。
立憲革命
ラタナコーシン朝のタイ(シャム)は第一次世界大戦後では戦勝国に加わり、国際的地位が上がったが、一方国内では国王による絶対王政の政治を立憲政治に改めるべきであるという知識人や軍部の一部が現れてきて、大きな岐路に立たされた。フランス留学中にパリで秘密結社人民党を結成した軍人のピブン(ピブーン)や官僚のプリーディーらが帰国後、1929年の世界恐慌で疲弊したタイで立憲王政を樹立することを目指し、1932年6月に立憲革命を実行、国王ラーマ7世もそれを受け入れ、タイは立憲国家となった。国号をシャムからタイに変更
立憲革命後も人民党の内部対立などから政府が安定しない状況が続いたが、1938年に首相となったピブンは、世界情勢が厳しくなる中、近代的主権国家の樹立を目ざし、またタイ人の国家である自覚を国民に求めるため、1939年10月3日に国号をシャムからタイに変更した。Episode タイの大国主義
1939年6月24日に立憲革命記念日に際し、ピブン首相は総理府布告をもって、それまで用いられていた国名を「シャム」Siam から「タイ」Thailand に改めた。タイ人はタイ語の thai が「奴隷」に対して「自由」を意味すると主張しているが、語源的には語頭に無気音をもつもう一つの民族名 tai に近い。知識人の中にはこの変更は国境外にいる「タイ族」をも勢力に含めようというピブンの覇権主義にほかならないとして、タイを使用するのを拒否する少数派もいる。<『タイの事典』同朋舎 p.191 石井米雄>※そういえば、タイ映画『少年義勇兵』には、少年兵を前に指揮官がタイに変更した意義を演説する場面がありました。この映画は、ピブン時代のタイで組織された少年義勇兵が日本軍と戦うという映画です。
タイ(4) 第二次世界大戦 日本との同盟関係
第二次世界大戦ではタイは当初は日本に協力の姿勢を見せカンボジアに侵攻した。しかし、太平洋戦争が始まるとビルマ・マレーの英領をめざした日本はタイに侵攻した。ピブン首相は日本と同盟関係を結び英米に宣戦布告した。それ以後微妙な立場に立たされる。
日本軍の侵攻と同盟
1941年7月、日本軍が南部仏印に進駐し、連合国側は日本に対する経済制裁の強化を打ち出すと、両陣営に挟まれたタイに危機が迫った。ピブンは中立を声明、世界に「平和を訴える」放送を行い、バンコクを無防備都市とすると宣言した。日本軍の侵攻を防ぐねらいであった。ところが、1941年12月8日、日本軍が真珠湾攻撃を行い、太平洋戦争が始まったその日に、日本軍はタイ南部のチュンポンなどに上陸、現地の軍と警察が防戦した。このとき、動員されていた少年義勇兵も戦争に参加した。この戦闘ではタイ側に138人、日本側に141人の戦死者が出ている。しかし、ピブンは直ちに停戦を命じ、軍政を行わずタイの独立と主権を尊重する替わりに日本軍の通過を認めた。続いて「日本・タイ同盟条約」を締結し同盟国となった。
枢軸側に参戦
1942年1月にはイギリス軍がバンコクを空爆、日本はビルマ侵攻を本格化させ、ピブン政権も英米に宣戦布告し、タイは枢軸国で参戦する形となった。ピブン政権は満州国承認、汪兆銘政権承認など日本寄りの姿勢を強め、1943年7月には日本の東条英機首相とのバンコク会談で、日本のビルマ侵攻に協力するかわりに、ビルマの一部とマレー半島の一部をタイ領に編入するという共同声明を発表した。ピブンの大東亜会議不参加 ただし、同1943年11月の東京で開催された大東亜会議にはピブン自身は出席せず、代理を参加させた。ピブンは当初、ヨーロッパではドイツ、アジアでは日本が勝利するだろうと判断し、日本に全面的な協力をしたが、戦局が変化するに伴い、次第に態度を変化させた。また泰緬鉄道の建設など、軍需物資の徴発や輸送での過度な負担を強いられたことに日本に対する不信を募らせていた。輸出の大幅な減少、石油その他の物資不足からタイ経済は大きな犠牲を強いられ、日本は「大東亜共栄圏」を標榜したがタイ民衆の現実からは「共貧圏」であることが露呈した。それらを背景にピブーンの「日本離れ」が急速に進んだものと思われる。一方、海外のタイ人の中に反日組織として「自由タイ」が結成された。<柿崎一郎『物語タイの歴史』2007 中公新書 p.177-178>
抗日運動とピブンの失脚
この間、日本はビルマ侵攻の準備を進め、タイとビルマを結ぶ泰緬鉄道建設を開始、東南アジア諸地域から集めた捕虜を使役し、多数の犠牲者を出した。タイ国会ではピブンの親日政策を批判するプリーディー(かつてパリ留学中にピブンとともに人民党を立ち上げた一人)などが自由タイと連携し、1943年夏から抗日運動を開始、インドのイギリス軍や重慶の国民政府と連絡を取り始めた。1944年7月にはピブンの首都移転案が国会で否決され、ピブンは辞任した。プリーディーらは武装蜂起を計画したが、それを実行する前の1945年8月15日、日本軍が降伏した。イギリスはタイを敗戦国として扱おうとしたが、アメリカはフランスと同様に扱い、タイの宣戦布告を不問とし、その戦争責任は問われないことになった。しかし、ピブンら対日協力者は戦犯として拘束された。<『タイの事典』p.197 市川健次郎>Episode タイの『少年義勇兵』
第二次世界大戦中、タイ軍と日本軍が交戦したことはあまり知られていない。しかし、1941年12月8日、日本軍は中立を宣言していたタイに突如上陸した。ビルマへの侵攻に備えた軍事行動であった。このとき、上陸地点のチュンポンで日本軍と対戦したタイ軍の中に、少年義勇兵がいた。彼らは急きょ集められた14歳から17歳の少年たちであった。この事実を掘り起こして映画にしたのが、2000年にユッタナー=ムクダーサニット監督の『少年義勇兵』。戦争に直面した少年たちをみずみずしく描いた佳作である。チュンポンで暮らしていた日本人も重要な役割で描かれている。戦闘場面に出てくる日本兵は服装など実際とは違うようだが、アジアの人々にとって日本軍の侵攻がどのように思われていたのかを考えさせる作品である。現在、DVDで見ることが出来る。タイ(5) 戦後のタイ
第二次世界大戦後、アメリカの反共軍事体制に組み込まれる。国内政治では不安定な状態が続き、クーデターによる軍政が続き、民主化は遅れた。
戦後のタイ
タイは太平洋戦争では、ピブン政権が日本と同盟関係を結び、英米に宣戦布告をした国であったが、そのときのピブン政権に対して反日路線を主張したグループ(自由タイ)がアメリカに協力したことから、枢軸国としての責任をとらされることなく、戦後はアメリカの支援で経済復興を進めることができた。領土返還を条件に国連加盟 戦後のフランスのド=ゴール政権は、戦中のヴィシー政権がタイ領として認めたカンボジア北西部の返還を求めたが、タイが拒否したため紛糾した。1946年5月フランス軍がタイ領に侵攻したため、タイは国際連合に加盟して安全保障理事会に提訴しようと考えたが、フランスはタイの国連加盟に拒否権を発動する構えを見せた。タイは国際社会への復帰を優先して結局「失地」をフランスに引き渡すことを了承したので戦闘は終わり、同年12月、タイは敗戦国では最初に国際連合加盟を認められた。これによってピブンの「大タイ主義」で拡張した領土はすべて返還され、タイは1907年に策定された領域に戻った。
ピブンの復権と失脚
1946年5月には首相となったプリーディーのもとで議会制民主主義、複数政党制を認めた民主的な憲法が作られたが、プリーディー内閣が左派に傾斜していることを不安視されて辞任し、政治的混乱が続くと、陸軍は1947年にクーデタで内閣を倒した。対日協力者として捕らえられていたピブンは、国軍司令官に任命されて復活し、1948年4月に軍によって政権に復帰した。復帰後のピブンは、東西冷戦が深刻になる中、親米反共路線をとり、1954年9月には東南アジア条約機構(SEATO)に加わり、東南アジア共産化の脅威と戦うアメリカのパートナーとなった。ただし、かつて立憲革命を指導したピブンは、国内政治では西欧型の議会制政党政治を定着させようとし、政党活動を自由にし経済政策でも民間企業の保護を主眼とした。しかし、ピブン自身の金銭選挙に対する非難が強まり、1957年にサリット将軍を中心としたクーデタが起こり、ピブン政権は倒れた。サリットの開発独裁
1958年10月、再びクーデタを起こし、翌年2月首相の座に着いたサリットは憲法と議会を停止し、国王を「父」、国民を「子」と位置づける「タイ式民主主義」を掲げて政党政治の混乱と共産勢力の台頭を抑え、一方で外国資本を積極的に導入して「開発」(タイ語でパッタナー)を推進し、開発独裁を展開した。サリットは1963年12月に病気で死去したが、その後に現れたタノーム政権(首相タノームと副首相プラパートによる政権なのでタノーム・プラパート政権ともいわれた)も軍を背景として議会政治を抑え、開発を進めるという開発独裁の形態をとった。また、たびたびクーデタが起こっており、そのたびに国王が調整するという、独自の立憲君主政が機能している。ASEANの発足
1960年代後半からインドシナ半島のベトナム戦争の時期のタノーム=プラパート政権は、ベトナム・ラオス・カンボジアの共産勢力に対する最前線となったことによって、1967年に共産勢力に対する共同防衛組織として東南アジア諸国連合(ASEAN)を発足させた。タイの他、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールの外相がバンコクに集まり、「バンコク宣言」を発表して発足したASEANは、当初は東南アジアの共産化を協同して阻止する反共軍事同盟の性格が強かった。開発独裁への反発と反日運動
内政では憲法は効力を失い、開発独裁を旗印とした権威主義的な体制のもとで、首相の大権で事が決まるというむしろ相対的に安定した長期政権が続いた。しかし、70年代には都市と農村の格差、貧富の差の拡大など開発独裁の矛盾が表面化してきた。その矛盾は、まず日本の一方的な経済進出に対する反発として表面化し、1972年に反日運動が起こった。タイ全国学生センターが中心となって、日本商品不買運動が始まり、日本大使館やタイで最初のデパートであった大丸へデモが仕掛けられた。それは対日貿易赤字の拡大に対する抗議であったが、矛先は日本に向けられているものの、「開発独裁」によって日本の企業の進出や日本商品の氾濫を許したタノーム政権に対する抗議が本質だった。血の日曜日 運動の拡大を恐れた政府が、ビラを配っていた学生を逮捕したことに対し、抗議する学生や市民40万人がタマサート大学に集まってデモを開始したところ、1973年10月14日に軍・警察が発砲し死者77人、負傷者444人がでる惨事となった。同日夕方、プミポン国王はタノーム首相を退陣させて沈静化をはかり、タノームら政府首脳は国外に逃亡した。この10月14日事件は「血の日曜日」とも言われ、大きな犠牲を払って、タイが開発独裁・権威主義から脱し、民主化への歩みを開始したことを意味していた。学生運動の盛り上がりは、世界的なベトナム戦争反対運動と連携していた。翌1974年1月には新憲法が公布され、同時に政党活動の自由も認められた。その翌年には総選挙が実施された。しかし、その後のタイ政治は、小政党の乱立と腐敗などが続き、それに対してたびたびタイ軍事クーデタを行うということが暫くくりかえされることとなる。
タイ(6) 現代。国土と民族。政治と経済。
現代のタイ王国の概要
国土
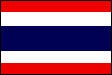 現在のタイ王国はインドシナ半島の中央部に位置し、チャオプラヤ川の流域全域とマレー半島中部を占める。東はラオスとカンボジア、西はミャンマー(ビルマ)、南はマレーシアに接する。国土はチャオプラヤ川流域には平野が多く、古くから米その他の農業が盛ん。その東側は国境のメコン側までなだらかな高原が続く。首都はラタナコーシン朝初代のラーマ1世以来、チャオプラヤ川河口のバンコクに置かれている。
現在のタイ王国はインドシナ半島の中央部に位置し、チャオプラヤ川の流域全域とマレー半島中部を占める。東はラオスとカンボジア、西はミャンマー(ビルマ)、南はマレーシアに接する。国土はチャオプラヤ川流域には平野が多く、古くから米その他の農業が盛ん。その東側は国境のメコン側までなだらかな高原が続く。首都はラタナコーシン朝初代のラーマ1世以来、チャオプラヤ川河口のバンコクに置かれている。タイの国旗 中央の紺色は国王、その外側の白は宗教、赤は民族を象徴する。1917年、ラーマ6世の時制定された。
民族と宗教
タイ人はタイのほかにラオスやカンボジア、ミャンマー北部、中国南西部にも存在している。シナ=チベット語族に属し、最初からこの地にいたのではなく、11~13世紀頃、中国南西部からチャオプラヤ川流域に移動してきたと考えられている。文化的にはインド文化の影響が強く、ビルマなどと同じく上座部仏教が盛んであり、現代においても寺院・僧侶は崇拝されており、建国の理念の一つとされている。なお、南部のマレー半島はイスラーム教徒が多く、彼らの中には過激な分離運動を行っているものもある。70~90年代の政治と経済
政治はラタナコーシン朝の王をいただく立憲君主政。憲法と議会があり選挙も実施されているが、時として軍部クーデタが起きることが多い。1970年代後半にはベトナム反戦運動の影響もあって民主化運動が強まると、保守層と右派の反発も起こって政治的対立が激しくなった。 → タイ軍事クーデター1970年代、ベトナム戦争終結後に東南アジアでは比較的安定した経済成長をとげていったが、それを支えたのが戦後の高度経済成長を遂げた日本市場であった。同時にタイでは日本企業の進出も多く、「日本の工場」などとも言われるようになり、反日感情が表面化した場合もあった。70年代後半にベトナム戦争が終結し、インドシナ3国も次第に社会主義経済からの脱却を図るようになったため、東南アジア諸国連合(ASEAN)も反共軍事同盟という性格は薄まり、地域的経済協力機構へと転換して行き、その中でタイは常に先導的役割を果たした。
プレーム政権 1976年10月、左派の学生と右派の衝突で、学生らに多くの死者が出た10月6日事件を機に軍部クーデタが起こり、その後も不安定な政治情勢が続いたが、1980年代は軍人出身のプレームが、国王を利用しながら調整型の政治を行って対共産党などの左翼運動を押さえ、NIEsに次ぐ経済成長に成功し、一定の安定を実現した。その中で選挙による議会と文民首相の選出の要求が高まり、1988年に総選挙が行われるとプレームは敗れたため退陣した。
チャーチャーイ政権 代わった文民首相のタイ民族党・チャーチャーイ首相は、ソ連のペレストロイカ、中国の改革開放、ベトナムのドイモイなどが進み、東南アジアの国際社会が安定したことを受け、「インドシナを戦場から市場へ」と提唱し、タイ経済の成長を図ったが、経済成長優先の金権体質が次第に非難されるようになった。内閣が国民的支持を失ったとみた軍は、1991年2月にクーデタを決行してチャーチャーイ内閣は倒れた。しかし政治的混乱が続く中、スチンダー陸軍司令官が首相に就任すると、国民の反発が激しくなった。
5月の流血事件 1992年5月、スチンダーの軍政に反対する市民集会にむけて軍が発砲、死者40人、負傷者600人という惨劇が起こった。このとき、事態収拾に乗り出したプミポン国王がスチンダーを辞任させると、国王が軍部クーデタ後の混乱を調整する機能を持つというタイ独特の政治形態が典型的に現れた。その後、タイ民主党やタイ民族党などの政党指導者による文民内閣が続き、政治的混乱の一方でASEANによる経済協力も軌道に乗り、タイ経済は異常なほど急成長を遂げた。
アジア経済危機の震源地
1980年代からの工業化が著しいが、NIEs諸国に比べ、米などの農作物の比重が大きいのが特徴で、アグリビジネスといわれるエビの養殖(日本への輸出向け)などが急速に発展した。ASEAN諸国やNIEs諸国、日本との貿易を基盤に輸出産業を増産させ、規制緩和と金融自由化によって外国からの資金を積極的に受け入れることによって農業国から工業国への転換を遂げた。政治の不安定もいざとなれば軍と国王が抑えるということも欧米の投資家による投資を呼び込む理由となり、世界的な規模の投資家がタイに出資するようになった。有り余る資本は土地などに投機されて、瞬く間に実体経済からかけ離れたバブル状態になっていった。1992年のクーデタ後に登場した政党政治は、そのようなグローバル経済の動向に振り回されながら、適切な対応を怠る中、1996年頃から輸出が頭打ちとなり、金融機関の経営が行き詰まり、1997年になると外国資本が引き揚げ、為替相場でのバーツ売りが始まった。こうして1997年7月2日、タイの通貨バーツの対ドル交換比率が暴落した。この為替相場の暴落は、マレーシア・韓国・インドネシアなどのアジア各国の通貨にも広がった。これがアジア通貨危機であり、タイはその震源地となったのだった。IMF融資による危機脱却 タイはやむなく国際通貨基金(IMF)の緊急支援を要請、IMFは支援の条件として緊縮財政による収支の改善を求めた。それに従って緊縮財政に転じたため国内の不況はさらに悪化し、経済危機に陥った。バーツの価値が半減したため輸入品価格が高騰して、消費は落ち込み、企業は収益を上げることができず倒産と従業員の解雇が相次いだ。
時のチャワリット首相(軍人出身で新希望党党首)は責任を取って辞任、代わった文民のチュアン政権はIMFの示したシナリオによって経済再建に着手、不良債権の処理などの金融改革を行い、雇用を確保するための公共投資を日本の資金援助などで実施、危機からの脱却を図った。経済成長率は大幅に下がったが、翌年になるとバーツ切り下げによって輸出競争力が回復したため、1999年には経済のV字回復を実現した。しかし、雇用の回復は遅れ、株価の低迷が続いたため、国民はより強力な経済政策を推進するリーダーを求めるようになった。課題であった憲法制定も、経済危機の混乱を克服するために合意が成立し、1997年9月に国会で採択された。これはタイ最初の民主的憲法であったが、新憲法に基づいた総選挙は2001年まで延期された。
21世紀のタイ
2001年の総選挙で第1党となったのはタイ愛国党を率いるタクシンであった。チェンマイの裕福な中国系一族の出身で警察官僚となり、実業家に転進してからは人脈を生かして通信事業などの新分野に進出して成功を収め、政治家に転身した人物であった。タクシンは経済危機の後遺症からの脱却を望む大衆に訴えるため、わかりやすい政策として経済成長と貧困対策を両立させるタクシノミクスともいわれる路線を打ち出し、特に農村部と貧困層に支持が広がったため、選挙で圧勝した。タクシン政権 タクシンの狙いどおり、タイ経済は一定の復興を実現し、1992年から始まったメコン川流域の広域経済圏としてのメコン圏構想でのタイの先進的役割も増大し、東南アジアに広くタイ経済の版図が広がった。タクシンはシンガポールのリー=クアンユーやマレーシアのマハティールらの成功に倣いながら、一種のポピュリズム政治家として、国家の財政を一企業のようなトップダウンで運営する手法によって、グローバル化に対応し規制緩和や自由化を進めたが、次第にその利益が一族や政権に近い企業に流れる仕組みが明らかになって行き、特に都市部の中間層はタクシンのポピュリズムを「バラマキ」と批判して反発が生まれていった。
2006年の軍部クーデタ こうした国内の分断による矛盾は、2006年にタクシンの一族企業のインサイダー取引が暴露されたことから一気に噴きだした。タクシンは批判をかわすため議会を解散、国民の審判を受けるためとして総選挙に打って出ると、選挙では勝てないとみた反タクシン派は総選挙をボイコットする戦術を採った。野党不在の選挙で勝利を収めたが、国王は憲法裁判所に判断を委ねたところ、選挙結果は違憲であり無効との結論が出たため、事態は膠着状態に陥った。その状況を見た軍幹部は、2006年9月19日、政権側に混乱の原因があるとして軍事クーデタを実行してタクシン政権を倒した。国王プミポンもクーデタを支持したことで、タイはまたまた民主的な手続きではなく「軍のクーデタ→国王の調停」という方式で政治を転換させた。
続く政治的混乱 タクシンは海外から帰国できない状態が続いているが、その後も国内では農村を基盤としたタクシン支持派(赤シャツ派)と都市中間層を基盤とした反タクシン派(黄シャツ派)の激しい対立が続き、2009~10年には両派の衝突でバンコクがマヒ状態となる混乱が起こった。一時はタクシンの妹インラックが首相に選ばれたが、反タクシン派はタイ愛国党の非合法化を働きかけ、最高裁が愛国党の解散を命じる判決を出すなど巻き返しが図られた。またまた2014年に軍部クーデタでタクシン派政権が倒れ、プラユット将軍による軍事政権が成立、憲法と議会が停止されるという事態となった。軍政権が人権や報道の自由を制限する態勢を強めると、学生を先頭にした民主化運動が起き、政情不安が深刻となったが、2016年に国王プミポン(ラーマ9世)が死去し、国王による調整という従来のタイ式の問題解決プロセスが取れなくなっており、タイがどのような方向に向いていくのかが注目されている。




