ポルトガル/ポルトガル王国/ポルトガル共和国
イゲリア半島の南西部に位置し、スペインと共にレコンキスタの過程で建国したキリスト教国。15世紀末からの大航海時代に他のヨーロッパ諸国に先駆けて海外進出を開始し、アフリカやアジア、南米大陸に広大な植民地を築く。日本にも商館を設け、関係が深い。16世紀末からは衰退が始まり、植民地は次々と独立、植民地大国としての地位は失った。
おポルトガル GoogleMap
イベリア南西部に1143年、ポルトガル王国が成立。キリスト教をかかげ、13世紀までにレコンキスタを完了。15世紀初めにはヨーロッパ各国に先駆けて海外進出を開始、大航海時代の先駆けとなった。ポルトガル船はアフリカ南岸からインド洋を経て東回りでアジアに通商圏を広げ、ブラジル、アフリカ各地、インドや中国に植民地と貿易拠点を設け、スペインと世界を二分して支配する海洋帝国として繁栄した。日本にも1543年種子島に来航、平戸に商館を設けて南蛮貿易を行った。
しかし、16世紀後半になると、イギリス・オランダが台頭し、インドや東南アジアの主導権を奪われ、さらに1580~1640年はスペインに併合された。独立回復後はイギリスへの経済的従属をつづけながら、アンゴラなどのアフリカとブラジルにまたがる植民地を経営した。特にブラジル経営は黒人奴隷を使役して大きな利益を得た。
フランス革命後に実権を握り、1804年に皇帝となったナポレオンは1806年に大陸封鎖令を発し、イギリスの孤立化を図った。ポルトガルに対してもイギリスとの貿易の禁止を命じたが、ポルトガルが拒否したため、1807年11月、軍を派遣してリスボンを制圧した。このナポレオンによるポルトガル征服に対してポルトガル王室はイギリスの支援でブラジルに逃れたが、民衆はナポレオン軍に対する抵抗を続けた。ナポレオン失脚後、国内でも1820年に立憲王政に移行し、ポルトガル王室はようやくリスボンに戻るが、この混乱の中からブラジルの独立を許したため、ポルトガルの植民地大国としての繁栄は終わった。
19世紀末から20世紀に帝国主義列強のアフリカ分割が進む中、ポルトガルのアフリカ植民地経営も危機に直面した。そのような中で、1910年に立憲王政が倒されて第一共和制となった。
この共和制は第一次世界大戦などで財政難に陥って混乱し、1936年にサラザールの独裁政権が成立、第二次世界大戦で中立を守ったため戦後も体制を維持した。ようやく1960年代からアフリカ植民地で独立運動が激化、その鎮圧に苦慮するうちに国内でも反独裁、反植民地の声が高まっていった。
1974年のポルトガル革命で40年以上に渡ったサラザール独裁体制を倒して第二共和政となり、国内政治の民主化が実現したが、同時にインド・アフリカの植民地が次々と消滅し、海外領土をほぼすべて失い、かつての植民地帝国の姿は完全に過去のものとなった。
またポルトガルの民主化は、同じように独裁政治が続いていた隣国スペインのフランコ体制の動揺に影響を与えた。ポルトガルは、現在はヨーロッパ共同体(EU)の一員となっているが、恒常的な経済不振、財政難に困難な国政運営が続いている。
- (1)国家の形成
- (2)大航海時代
- (3)アジア・アフリカ進出
- (4)植民地帝国の推移
- (5)植民地帝国の変質
- (6)第一共和政とサラザール体制
- (7)ポルトガル革命と民主化
ポルトガル(1) 国家の形成
5世紀、イベリア半島にゲルマン民族の移動がおよび、半島北西部にその一部のスエヴィ人が411年には王国をつくり、さらに585年には西ゴート王国に征服された。711年、西ゴート王国の内紛に乗じて半島にイスラーム勢力が侵入し、わずか数年で半島の大部分を支配下におき、ポルトガルの地でもその支配が長く続くこととなった。
ポルトガル王国の建国
レコンキスタの過程でイベリア半島中央部に生まれたキリスト教国カスティリャ王国は、イスラームの支配を次第に排除してゆき、ポルトガル北部もその支配下に入った。ドーロ川以北の地はポルトゥカーレ(現在のポルト市)といわれていたが、カスティリャ王に従っていたフランスのボルゴーニャ(ブルゴーニュ)出身の騎士エンリケがポルトゥカーレ伯として入り、その南のドーロ川以南のコインブラ伯とあわせて治めるようになった。これがひとつのまとまりとしてのポルトガルの範囲(南部はまだイスラーム支配下にある)の成立である。エンリケの子のアフォンソ=エンリケスは自ら王を名乗り、カスティリャ王と戦って、1143年にローマ教皇の仲介によって和平条約を結び、カスティリャ王国から分離しポルトガル王国を建国した。1179年、エンリケスは教皇アレクサンドル3世から正式に国王として認められ、アフォンソ1世と称した(これ以後をポルトガルではボルゴーニャ朝と言っている)。ポルトガル・レコンキスタの完了 ポルトガル王国は権力基盤を強化拡大するためカトリック教会・修道院を保護し、同時にレコンキスタを推進した。1147年にはおりから南下していたイギリスの十字軍艦隊との共同作戦によりリスボン攻略に成功、テージョ川以南に進出した。さらにテンプル騎士団などの支援のもとでレコンキスタを進め、一進一退が続いたが、1212年、ポルトガル王アフォンソ2世はカスティリャ王と共にラス=ナバス=デル=トロサの戦いでイスラーム軍に大勝し、これを機にイスラーム勢力は後退し、1249年にアフォンス3世は南端のシルヴェスとファロを征服し、レコンキスタを完了した。
ヨーロッパ最古の国境画定 1297年、ポルトガルのディニス国王はカスティリャ王国とのアルカニーゼス条約を結んで両国の国境を画定した。この国境線は現在のポルトガルとスペインの国境線として続いており、今日まで続くヨーロッパで最も古い国境線である。<金七紀男『ポルトガル史』彩流社 p.49>
ポルトガル語 ポルトガル語はスペイン語と同じラテン語から派生したロマンス語系の言語。イベリア半島北西部に駐屯していたローマ軍団の兵士たちが話していた俗ラテン語から生まれた。帝政末期の5世紀から西ゴート時代の8世紀にかけて、「ガリシア・ポルトガル語」に転化し、現在のポルトガル語とスペインのガリシア地方で話されているガリシア語の共通の祖語となった。レコンキスタの進行と共に南に向かい、11,12世紀にルジタニア・モサレベ語と接触してガリシア語との違いが明確になってポルトガル語が生まれたと考えられている。13~14世紀には公式の文書はラテン語からポルトガル語で表記されるようになった。<『同上書』 p.63>
なお、ポルトガル語は現在でもブラジルでは公用語として広く使われている。アフリカの旧ポルトガル領であるアンゴラなどでも公用語とされているが、実際に使用する人は少数になっている。
ポルトガル(2) 大航海時代
15世紀にポルトガルは海洋進出を開始、アフリカ西岸を南下し、黒人貿易などに乗り出した。その結果、1488年に喜望峰に到達し、大航海時代の先鞭をつけた。

リスボンの港の「発見のモニュメント」。先頭に立つのがエンリケ王子。山川出版社『スペイン・ポルトガル史』口絵より
1383年、親カスティーリャ派の国王が即位すると農民反乱が各地で起こり、介入したカスティリャ軍がペストのために撤退すると、コインブラで国会(コルテス)を開催した中小貴族と都市ブルジョワジーは、王位継承者に前国王の遺児アヴィス騎士団長ジョアン1世を選出した。こうして、ポルトガルは中小貴族と産業ブルジョアジーに支えられるアヴィス朝の時代となる。
海外進出の開始
15世紀初め、ポルトガルのアヴィス朝ジョアン1世は、アフリカ西岸進出を開始、大航海時代に先鞭をつけ、まず、1415年にジブラルタルの入口にあたるモロッコのセウタを攻略した。エンリケ航海王子 ついでその子のエンリケ王子が主導して、1431年にアゾレス諸島に到達、さらにアフリカ西海岸地帯に進出し1441年にはリオ=デ=オロでアフリカの黒人を奴隷とするために捕らえた。ついで1445年にはヴェルデ岬に至った。ポルトガルはアフリカ西岸のギニア地方で金と黒人奴隷を獲得して利益を上げると、スペイン王国の進出に先手を打って、1455年にローマ教皇からキリスト教の布教を大義名分として、すでに「発見」され、さらに将来「発見」されるであろう非キリスト教世界における征服と貿易の独占権、異教徒の奴隷化を認めるローマ教皇教書を獲得した。
国王ジョアン2世 次にジョアン2世は、1482年にはアフリカ西岸のギニア湾に面したエルミナ(現在のガーナ)に要塞を建設し、金・黒人奴隷・胡椒(ギニアショウガ)・象牙などの獲得拠点とした。このころから明確にアフリカ南端への到達と、インド洋への進出をめざすようになり、バルトロメウ=ディアスを派遣し、1488年に喜望峰に到達した。
スペインとの世界分割
一方、スペインが派遣したコロンブスが1492年に西回りでインドに到達したことを主張していたので、ポルトガルとスペインは勢力圏の調整を行い、1493年に教皇子午線(教皇境界線)が設定され、その東をポルトガル、西をスペインが領有することが認められた。それに不満なポルトガルは翌1494年、直接交渉してトルデシリャス条約を結び、境界線を西にずらした。これが西欧諸国による植民地分界線の最初であった。その結果、アフリカ大陸とアジアはポルトガルの勢力圏とされただけでなく、後に発見されたブラジルがポルトガル領とされる根拠となった。ジョアン2世は1495年に死去、次のマヌエル1世(在位1495~1521)の時代にポルトガルの海外発展は最高潮に達した。ポルトガルの派遣したヴァスコ=ダ=ガマが1498年にカリカットに到達して、インド航路が開かれ、1510年にはゴアを占領してインド、東南アジア進出の拠点とし香辛料貿易を展開した。また、1500年にはカブラルが新大陸のトルデシリャス境界線東側に到達して、ポルトガル領ブラジルとして領有した。こうしてポルトガルの植民地帝国としての基礎が築かれ首都リスボンにはアフリカからの黒人奴隷・インドからの香辛料・ブラジルからの砂糖などがもたらされ、16世紀には世界経済の中心地として繁栄した。
ポルトガルの進出の理由
15世紀前半のポルトガルは、人口は110万と推定されるにすぎない小国であった。そのような小国ポルトガルが、ヨーロッパ諸国の中で最初に海外に進出した(またそれができた)理由を現代の経済史家ウォーラーステインは次のように説明している。「初期のポルトガル人探検・航海者の目的は、海上ルートによる金の探索(北アフリカの中継業者を出し抜いて直接スダンの金を獲得すること)であった。金と並んで香辛料も目的であったが、長期的な目的となったのは小麦・砂糖・魚肉・木材・衣料などの基礎商品の獲得である。過剰人口のはけ口説や宗教的情熱説は根拠が薄く、一種の「口実」である。ポルトガルが真っ先に対外進出ができた理由は、
- 大西洋岸にあり、アフリカに隣接しているという地理的条件、
- すでに遠距離貿易の経験を持っていたこと、
- 資本の調達が容易であったこと(ジェノヴァ人がヴェネツィアに対抗するため、ポルトガルに投資しており、リスボンで活躍していた商人の多くはジェノヴァ人であった)、
- 他国が内乱に明け暮れていたのにポルトガルだけは平和を享受し、企業家が繁栄しうる環境があったこと、
ポルトガル(3) アジア・アフリカへの進出
15世紀末~16世紀 ポルトガルは盛んにアジアに進出、インドに拠点を設け、中国・日本にも進出した。また東西アフリカ海岸に拠点を設け奴隷貿易とアジア貿易の拠点とした。
ポルトガル人来航の頃のインドの状況
ポルトガルのヴァスコ=ダ=ガマの指揮する船団が、カリカットに来航したのは1498年。インドにムガル帝国が成立するより以前のことであり、当時インドには統一的政権は存在せず、とくに南インドにはヴィジャヤナガル王国(ヒンドゥー教国)やバフマン王国(イスラーム教国)などが対立している状態であった。またポルトガル進出以前のカリカットは、アラビアやエジプトからのムスリム商人が来航し、アラビア海はマムルーク朝の制海権のもとにおかれていた。また、15世紀の前半には明の鄭和艦隊がカリカットに来て、さらにアラビア海に進出していた。中国商人の活動は明が海禁政策をとったため衰えるが、アラビア海からベンガル湾を経て東南アジアに至る海域で、ヨーロッパ商人が進出するより遙か以前から、ムスリム商人・中国商人による活発な交易が行われていたことはしっかり認識しておく必要がある。インドでの覇権
ポルトガルはインドとの香辛料貿易からイスラーム勢力を排除して、その利益を独占しようとして海軍を派遣し、活動拠点を建設する必要を感じた。その任務のために常駐統括者として総督(インド副王)が1505年におかれた。初代のアルメイダは1509年にはディウ沖の海戦でマムルーク朝エジプトの海軍を破って紅海・アラビア海の制海権を握った。第2代のアルブケルケは、1510年にゴアを武力で占領して拠点とした。ゴアはアジアにおける最初のヨーロッパ諸国による植民地となり、実に1961年にインドに返還されるまでポルトガル領であった。西アジア・東南アジアへの進出
ついで1510年にはスリランカ(セイロン島)を征服、1511年にはマラッカ王国を滅ぼし、1515年にはペルシア湾入り口のホルムズ島を占領した(ホルムズ島は1622年、サファヴィー朝のアッバース1世によって奪回される)。1521年には香料諸島としれ知られるモルッカ諸島に城塞を建設、同年西回りでやってきたスペインと激しく争い、翌1522年にはテルナテのスルタンから香辛料の独占権を得ている。両国は1529年のサラゴサ条約でアジアにおける両国の境界線を取り決めて、それによってポルトガルはモルッカ諸島を勢力下に置いた。モルッカ諸島の南方、スンダ列島の東端のティモール島にも進出したが、その地は間もなくオランダと争うこととなってほぼ東西で折半し、その東半分を東ティモールとして支配した。香辛料貿易
ポルトガル人の香辛料貿易はインドの土侯たちに火器などを代償としてカリカットなどマラバール産の胡椒を手に入れ、さらにマラッカから運ばれた丁子などの香辛料をゴアに集積し、インド航路でモザンビークなどを経由して喜望峰を回り、リスボンに持ち帰った。それは、従来のアラビア商人やエジプト商人から買うよりはきわめて安価に大量に得られる取引であった。商品はリスボンに運ばれてからアントウェルペンやロンドンに運ばれたので、リスボンにはドイツのフッガー家などのヨーロッパ各地から商人が集まり、彼らはポルトガルの国家事業である船団に出資し、利益を得た。今もリスボン港の付近から胡椒や陶磁器を満載したまま沈んだ沈没船が引き上げられることがある。中国・日本への進出
その勢力は明王朝の統治する中国に及び、1517年には広州で通商を開始、1557年ごろまでには広州に近いマカオに居住するようになった。一方、1543年ポルトガル商人の乗った中国人のジャンク船が種子島に漂着してから日本との接触も始まり、1550年には平戸に商館を設置し、九州の諸大名との通商を行うようになった。これは日本では南蛮貿易といわれ、ポルトガル商人は中国産の生糸を独占して安く買い取り、日本で高く売りつけて利益を上げたほか、宣教師を通じて鉄砲や火薬を大名に売りつけ、大名の中にはキリスト教を受け容れてキリシタン大名となるものも現れた。ポルトガルのアフリカ植民地支配
ヨーロッパ人のアフリカ大陸侵出の口火を切ったのが黒人奴隷貿易 ポルトガルはスペイン王国の進出に先手を打って、1455年にローマ教皇からキリスト教の布教を大義名分として、すでに「発見」され、さらに将来「発見」されるであろう非キリスト教世界における征服と貿易の独占権を認める教書を獲得した。それによってポルトガルはアフリカ西岸のギニア地方での金と黒人奴隷で大きな利益を上げ、1482年にはその拠点としてジョアン2世が現在のガーナの地にエルミナ要塞を建設した。さらに現在のナイジェリアの海岸のベニン王国に商館を置いた。またダホメ王国とも交易を行った。ギニア湾上に浮かぶサン=トメ島にはアジアからもたらされたサトウキビを栽培しアフリカからの黒人を奴隷として使役する砂糖生産の農園つまり砂糖プランテーションの原型を作った。またポルトガルはサン=トメ島を奴隷貿易の中継基地として黒人奴隷の輸出を開始した。
ポルトガルの奴隷貿易 15世紀から16世紀前まで黒人奴隷貿易はポルトガルが独占していた。1550年代末には王室財政の収入の中で約3000万レアイスで、金貿易に匹敵するほどの重要になっていた。ポルトガルのリスボンに運ばれた奴隷のほとんどはヨーロッパ内で使役され、まだ新大陸へ供給されていなかった。
コンゴからアンゴラへ 1485年からポルトガル人はコンゴ川(ポルトガル人はザイール川と名付けた)を遡りコンゴ王国と接触した。ポルトガルは宣教師を送り込み、コンゴ王国のキリスト教化を図った。コンゴ王国はポルトガルの影響下でキリスト教化が進んだが、植民地支配のもくろみは阻まれ、その矛先は南のアンゴラに向かっていった。
インド航路 1492年、スペイン王が派遣したコロンブスが西回りで新大陸に到達したことから、スペインとポルトガルは1494年にトルデシリャス条約で世界分割協定を行い、ポルトガルは東半球の支配権を得て、東廻り航路でインドに到達することを急いだ。すでに1488年にバルトロメウ=ディアスがアフリカ最南端の喜望峰に到達していたが、ついに1498年にヴァスコ=ダ=ガマ船団がアフリカ南端を回航してインド洋に入り、カリカットに到達してインド航路を開拓した。それに伴ってインドへの寄港地、補給地として重要性を増したアフリカの東海岸への拠点建設が急がれることとなった。
アフリカ東海岸に進出 16世紀に入るとインド副王となったアルメイダは、アフリカ東岸のソファラ、キルワ、モンバサを次々と攻略し要塞を建設、さらに1507年にはモザンビークを占領した。こうしてアラビア海においてイスラーム商人を駆逐し、1509年のディウ沖の海戦でマムルーク朝海軍を破り、制海権を獲得した。ソファラを拠点としてザンベジ川流域の内陸に侵出し、モノモタパ国から金・象牙などを得る交易を行い、一時はその領土化を狙ったがそれには失敗した。後にポルトガル領東インドはモザンビークを中心に建設された。
15世紀から始まったポルトガルの黒人奴隷貿易は19世紀半ばまで続いた。当初、その支配は奴隷貿易とアジア貿易の帆船の寄港地としての港市に限定されていたが、その維持は困難でケープ植民地は放棄された。またモンバサは1698年にオマーンのイスラーム政権の軍に攻撃されて陥落した。またギニア湾岸のベニン王国はオランダ、次いでイギリスが進出したため放棄した。ダホメ王国にはフランスが進出したためポルトガルは後退した。
ポルトガル植民地帝国の形成
16世紀末から17世紀にかけて、オランダとイギリスがインド洋貿易に進出し、インドではイギリスの、東南アジアではオランダの覇権が出来上がると、ポルトガルはアジア貿易から後退せざるを得なくなった。それに代わって、アフリカ内陸の植民地化に努めるようになり、西海岸のアンゴラ、ギニアビサウ、東海岸にモザンビークがポルトガル領となり、ブラジルとともにポルトガルの植民地帝国としての富の源泉となった。その他、アフリカ沖のヴェルデ岬諸島と、ギニア湾のサン=トメ島とプリンシペ島などもポルトガル領であった。ブラジルの領有 ブラジルは1500年にポルトガルの航海者カブラルが偶然に到達し、その地がトルデシリャス条約で定められた東西分割線でポルトガル領とされた東側に入っていたことから、その領土に組み込まれた。ポルトガルはブラジルにサトウキビ栽培を導入し砂糖の生産に特化させ、多くの砂糖プランテーションを建設し、労働力としてアフリカからの黒人奴隷を導入した。ブラジルの砂糖は16~17世紀のポルトガル(および1580~1640年にポルトガルを併合したスペイン)の経済を支えた。ところが1693年にブラジルで金鉱が発見され砂糖に代わる重要産業となり、植民地としての重要さをさらに増すこととなった。金の採掘量が減少しはじめると、それに代わって18世紀末から19世紀にはコーヒーが新たに導入され、コーヒープランテーションがポルトガルに大きな富をもたらした。その労働力として黒人奴隷の需要は1822年のブラジル独立後まで続き、ブラジルにおける奴隷解放は1888年まで遅れることとなった。
ヨーロッパ最西端の小国ポルトガルは、こうしてアフリカ大陸と南米大陸に大西洋をまたいで植民地をもつこととなり、「植民地帝国」あるいは「大西洋帝国」と呼ばれるようになった。 → ポルトガル植民地の拡大
ポルトガル(4) 植民地帝国の推移
1580年にスペインと合同王国となり、また海外領土の多くをオランダとイギリスに奪われて、急速に衰退した。1640年に独立を回復、ブラガンサ朝ポルトガル王国となり、絶対王政を敷いた。イギリスとの経済的結びつきを強めながら、アフリカとブラジルの大西洋にまたがる植民地は維持した。
スペインによる併合(同君連合)
ポルトガルのセバスチャン国王はモロッコ遠征を企てたが、1578年、イスラーム教徒のサード朝との戦いで戦死、次の王エンリケは老人で1年後に死去、これにによってアヴィス朝が断絶した。それを受けて1580年に、スペイン国王フェリペ2世がポルトガル王位の継承権を主張した。父のカルロス1世がポルトガルのセバスチャン王の叔母の間に生まれたのがフェリペ2世だったからである。ポルトガルの身分制議会コルテスもそれを承認して、スペインによるポルトガル併合が行われた。スペイン王フェリペ2世はポルトガル王としてはフェリペ1世として両国王を兼ねた。これは同君連合の形式を取り、ポルトガルは国家として消滅したわけではなく、国会(コルテス)、官僚・軍隊などを独自に持っていた。しかし、これによってスペイン国王はポルトガルの海外領土もふくめて「太陽の沈むことのない帝国」を支配することとなった。スペインとの同君連合を認めた理由 1580年、ポルトガル議会がスペインとの同君連合を受け入れたのは、経済的にも有利だという判断があったからと考えられている。同君連合となったことで、ポルトガルとスペインの国境関税は廃止され、ポルトガルの商人たちは合法的にスペイン領に進出して大きな利益を得ることができるようになった。両国の国境線をまたぐ人やモノの移動が活発になっただけでなく、「トルデシリャス条約」で分割されていた新大陸南米のブラジルでも、境界線を越えて西側のスペイン領アマゾンに打って出る好機を得た。<丸山浩明『アマゾン500年』2023 岩波新書 p.28>
アマゾン川流域への進出 トルデシリャス条約の西側のアマゾン川流域は1541年にスペイン人が太平洋側からアンデスを越え、上流から河口まで下ることに成功していたが、同君連合となった頃はほとんど手を出すことができないでいた。同君連合がもたらしたアマゾン進出の好機を最大限に利用したポルトガルは、17世紀に入ると盛んに探検と入植を開始した。1637~39年、ペドロ・ティシェイラを隊長とした探検隊はアマゾン河口からさかのぼり、ペルー副王領のキトまで到着した。それをきっかけに、ポルトガル人は同君連合であるスペイン領アマゾン流域への入植地をひろげていった。<丸山『前掲書』p.36>
アジアでのポルトガルの後退
しかし、1640年に独立を回復するまでの約60年間のスペインへの併合期間にポルトガルのインド洋・東インド諸島でのかつての繁栄は失われた。1600年にはモルッカ諸島、1609年にはスリランカ(セイロン島)をいずれもネーデルラント(オランダ)船に奪取され、1622年にはホルムズをイギリスとサファヴィー朝アッバース1世の連合軍に奪われた。また、17世紀には東アジアでもさかんにポルトガル船を襲撃するようになったオランダ商船は、1609年には日本の平戸に商館を設けてポルトガルと競合するようになった。またイギリスも17世紀から東アジアにも進出、同じく平戸に商館を設けた。日本の鎖国 新教国であったオランダとイギリスは、旧教国ポルトガル・スペインがキリスト教布教を通じて植民地化を策謀していると盛んに訴えたので、江戸幕府は次第にキリスト教の禁止に傾き、ついに鎖国に踏み切って1639年にポルトガル人は来航禁止となった。マカオのポルトガル政庁と商人は日本に使節を送り、貿易の再開を懇請したが、幕府は拒否し、使節団を捕らえて処刑してしまった。このとき、江戸幕府はポルトガルの報復攻撃を恐れて西国の大名に警備を命じたが、ポルトガルにはその力はなく、日本との貿易が再開されることはなかった。さらに1641年にはマラッカをオランダに占領された。
この一連の動きは、ポルトガルがスペインに併合された結果、アフリカ海岸からインド洋、南シナ海、東シナ海におよぶ広大な海域を管轄しなければならなくなったところに無理が生じたということであろう。これらの海域の間隙をついてオランダ、イギリスの商船が進出すると、ポルトガル商船はその餌食とならざるを得なかった。
Episode 国王は生きている
1580年以来、スペインに併合されていたポルトガルでは、形式的には同君連合であったが、次第に内包される不満も高まっていった。ポルトガルではスペインとの併合のきっかけとなった1578年の国王セバスチャンのモロッコでの戦死は、遺体が見つからないことから次第に「国王は死んでおらず、必ず生還してスペインの軛(くびき)からポルトガルを解放してくれる」というセバスチャニズモ(いわばメシア待望論)が台頭し、17世紀にはポルトガル人の心を捉えて反スペイン暴動まで起きるようになった。<丸山浩明『アマゾン500年』2023 岩波新書 p.36>ポルトガルの独立回復
ポルトガルのスペインからの独立運動は、ブラガンサ家を中心に結束した勢力によって、1640年に勝利を収め、同君連合を解消した。その背景には、この年、三十年戦争の終わりにさしかかり、フランスがスペインのカタルーニャに進攻、それに呼応してカタルーニャの農民反乱が起こったことがあげられる。苦境に立ったスペイン政府(カスティーリヤ=マドリード政府)はポルトガルに出兵を要求してきた。ブラガンサ朝の始まり 1640年12月1日、ポルトガルの貴族ら40人からなる集団がリスボンの王宮を襲撃し副王マルガリータ女王を逮捕、かわってポルトガルの名門ブラガンサ公のジョアン4世をポルトガル国王として立てた。この宮廷革命は民衆の支持ではなく、カタルーニャの反乱やフランスのリシュリューの支援があって可能だった。こうしてポルトガルは、スペインから独立を達成、これ以降はブラガンサ家の国王が継承するブラガンサ朝となり、1910年まで継続する。独立再開後のポルトガルは、スペインとの対立とブラジル、アジアでのオランダとの抗争もあったので、イギリスとの提携を求めざるを得ず、1652年にはクロムウェルとの間で同盟関係を結び、イギリス商人の経済活動に特権を与えている。
イギリス経済との結びつき イギリスとの密接な関係は王政復古期にも続き、ジョアン4世の娘カタリーナ(英語読みキャサリン)はチャールズ2世の妃となった。このときキャサリンはタンジールとボンベイの領有権に加え、大量の砂糖を持参金にした。さらにこのとき、ポルトガルからイギリスの宮廷に茶を飲む習慣が伝わったという。
1686年にはイギリスの仲介でスペインとの平和条約が成立、スペインがポルトガルの独立を承認した。さらに1701年にスペイン継承戦争が起こると、ポルトガルはイギリスとの同盟関係からフランス・スペインと戦った。その背景にはポルトガル産のワインのイギリスへの輸出が増大し、ポルトガル経済を支えていたことがあげられる。両国は1703年にはメシュエン条約を締結してポルトガル産ワインの関税を引き下げる代わりにイギリスの毛織物の輸入を解禁した。
ポルトガル植民地の拡大
ポルトガルは1580~1640年の間はスペインに併合され、17世紀にはオランダ、イギリスに押されて後退し、独立を回復した後の17世紀後半にも、植民地支配は後退して行き、1664年にはインドのコチンを失った。アジアにおけるポルトガル領は、インドのゴア、インドネシアの東ティモール、中国ではマカオ(1887年に正式にポルトガル領となる)などのみとなった。アフリカでは、西岸のアンゴラとギニアビサウ、東岸のモザンビークの植民地支配を維持した。 → アフリカ植民地支配の動向しかし、南米大陸の広大なブラジルでは、1693年に金鉱が発見され、それまでの砂糖に代わって金が植民地の主産物となり、ポルトガル経済を支えることとなった。ブラジルで不足する労働力として、ポルトガル人奴隷商人はアフリカ植民地からさかんに黒人奴隷を輸入した。さらに1701年に起こったスペイン継承戦争では、イギリスと同盟してフランス・スペインと戦い、スペインからアマゾン川両岸とラ=プラタ川東岸を獲得した。拡張したブラジル植民地でさらに金鉱とダイヤモンドが発見され、ブラガンサ朝ポルトガル王国は繁栄の時期を迎える。
ポルトガル(5) 植民地帝国の変質
ポルトガルは17世紀後半から、オランダ、イギリスに押され、アジア貿易の拠点を失っていったが、南米大陸のブラジル、アフリカ大陸東岸などの広大な植民地は維持した。1807年のナポレオンの進攻を機に、ポルトガルは立憲君主国に移行するとともに、ブラジルの独立を認め、大きく変貌した。小国ポルトガルはなおもアフリカとアジアに植民地を維持しながら、停滞を余儀なくされていった。
18世紀前半の黄金時代
ジョアン5世(在位1706~50)は「ブラジル金の威力をもって文字通りポルトガル近世の黄金期を現出した」と言われている。ジョアン5世はフランス国王ルイ14世を見習って絶対君主としてふるまい、リスボンに歌劇場を開設したり、王立歴史学アカデミーを創設するなど啓蒙君主としてもふるまった。ジョアン5世は、1750年のスペインとのマドリード条約で、ラ=プラタ川東岸を与える代わりにトルデシリャス条約の分界線を遥かに超えた西側のアマゾン川流域を獲得した。両国の紛争はその後も続いたが、1777年に最終的な和平が成立し、ポルトガルの領土は、現在のブラジルの範囲と同じ範囲で確定した。これによってスペインとポルトガルという二大強国による世界分割であったトルデシリャス条約はようやく効力を失った。ブラジルの金はどこへ? ブラジルからの金をもとにポルトガルは大量の金貨を鋳造したが、その使い道は王宮や教会の造営に回された。この時期はポルトガルのバロック時代であり、豪壮な建築物が多数見られるが、それらはブラジルからの金をもとに造営されたのだった。また当時、ポルトガルのワイン輸出に対しイギリス産の毛織物を輸入していたが、国内の繊維産業が未発達であったことによって一方的な輸入超過となっていたため、金貨はイギリスに流れて行った。ポルトガルで金貨を蓄え、国内産業を育成するという措置は執られず、かえってイギリスはここで得た金貨を資本として蓄積し、18世紀中頃に産業革命というテイクオフを可能にしたのだった。
大地震と改革失敗
1755年11月1日、リスボンは大地震に襲われ、大火災と津波によって1万5千人が犠牲となり、首都は壊滅した。この時の死者は6~10万に上り、市民の3分の2にあたっていたという数字も上げられている。このリスボン大地震は、大航海時代のポルトガルの繁栄の完全な終わりを告げるものとなった。この大災害からの復興を指導したのが下層貴族出身のポンバル侯爵であった。国王から全権を委ねられた侯爵は辣腕を振るい、まったく新しい都市計画でリスボンを復興させ、その勢いで強権的な上からの改革を行った。絶対王政の体制をめざしながら、1759年、イエズス会や異端審問所などの守旧勢力を次々と追放、解散させ、一方でイギリスとの交易による経済成長を図った。しかし、ポンバル侯爵の専制的な手腕は国王との対立をもたらし、1777年に失脚、ポルトガルの改革も途絶え、再び低迷に陥った。そのようなポルトガルを覚醒させる出来事は、ピレネー山脈の北からやって来た。
ナポレオンのポルトガル征服
ポルトガルは一貫してイギリスとの同盟関係を維持しそれとの交易で潤っていたが、フランス革命でブルボン王朝が倒れ、次いで登場したナポレオンは革命の理念を全ヨーロッパに拡散するとともに、その支配をも及ぼそうとし、イベリア半島にも進出、ポルトガルの隣国スペインを支配下においた。ヨーロッパ大陸で唯一その支配の及んでいなかったポルトガルに対し、1806年、大陸封鎖令を発し、イギリスとの断絶を強く迫った。ポルトガル政府がそれを拒否すると1807年11月、ついにナポレオンのポルトガル征服が開始された。スペインもまたナポレオンに協力し、フランス・スペイン連合軍がジュノー将軍に率いられて侵攻してきた。ポルトガル王室(ブラガンサ朝)は抵抗の意図がなく、1万人を超える随員を従えてブラジルに避難し、リオ=デ=ジャネイロに首都を移してしまった。独立の回復 1808年、スペインの民衆がナポレオンに抵抗して蜂起したスペイン独立戦争に刺激され、ポルトガル北部の都市の民衆が決起し、イギリスのウェリントン将軍の支援を受け、ナポレオン軍を破った(イギリスでは「半島戦争」と言っている)。1811年までにフランス軍を撤退させ、ポルトガルは独立を回復したが、イギリス軍の駐屯が続き、事実上のイギリス支配となった。ポルトガル王室は本国に戻らず、ウィーン会議が始まってもブラジルに留まり、1815年にポルトガル=ブラジル=アルガルヴェ連合王国と称した。
ポルトガルの自由主義革命
ポルトガル国民は国王から見放され、イギリスの支配を受けているという現状に反発を強め、1820年1月にスペイン立憲革命に呼応する形でポルトガルでも自由主義者が反乱を起こした。反乱は全土に広がり、9月に臨時政府が成立した。イギリスの駐屯軍司令官はブラジルに渡って、国王に帰還を要請したが、国王は帰還を拒否し、さらに司令官のポルトガルへの再入国を拒絶した。司令官は、ポルトガル政治に復帰することなく、イギリスに戻った。 。立憲君主政へ 臨時政府は12月、間接選挙を実施し、1821年1月、立憲議会(コルテス)を召集し、立憲君主政をとる憲法草案を作成した。ブラジルにいた国王ジョアン6世はようやく同年7月リスボンに戻り、憲法草案に忠誠を誓い、翌1822年9月、憲法が正式に発布された。この「1822年憲法」はポルトガル最初の近代憲法として国民主権・三権分立・直接選挙・一院制などを定め、異端審問官の廃止、出版の自由などを認めた画期的なものであったが、ブラジルの独立と自由は認めず、植民地支配を継続させるものであった。それに対して、ブラジルでは不満が強まった。
ブラジルの独立 ブラジルでは本国からの分離運動が強まった。地主や軍人、官僚を主体とした自由主義穏健派は、急進的な共和制が実現することを恐れ、ブラジルに残っていた摂政ペドロ(ジョアン6世の長男)をかつぎだし、1822年9月7日に独立を宣言、ペドロ1世を皇帝とする「ブラジル帝国」として独立した。
こうしてナポレオンの侵入を契機としてポルトガルのブラガンサ朝絶対王政は崩壊し、ポルトガルは立憲君主政国家となるとともに、ブラジルという最大の植民地を失うこととなった。これは植民地帝国としてのポルトガルは終わりを告げたことを示しており、ポルトガルは19世紀以降はヨーロッパでもっとも貧しい国の一つになってしまった。アフリカにおける植民地はなおも存続していたが、その植民地経営も効率が悪く、その没落を食い止められなかった。
アフリカ植民地支配の動向
1822年にブラジルは独立したが、アフリカ植民地はさらに維持され、黒人奴隷貿易が行われていた。奴隷制度に対する批判がイギリスで強まると、その圧力を受けて、1842年にポルトガルは海外領の奴隷貿易を全面的に廃止した。ブラジルでは1888年まで奴隷制が残っていたが、これによって奴隷貿易は実質的に終わりを告げた。19世紀末になると、列強によるアフリカ分割が激しくなる。列強は1884~85年に、ドイツのビルマルクの調停により、アフリカに関するベルリン会議を開催、ポルトガルはヨーロッパ最初の植民地所有国として広範囲な「歴史的所有権」を主張したが、会議の結果は「実効的支配」の原則に従い、西岸のアンゴラとギニアビサウ、東岸のモザンビークに限定された。
ポルトガル政府は大西洋岸のアンゴラとインド洋岸のモザンビークを結ぶアフリカ横断地域を支配しようと、たびたび探検隊を派遣、さらに現在のザンビアとジンバブエなどにも出兵したが、その利害は、南アフリカからカイロをめざすセシル=ローズ主導のアフリカ縦断政策を採るイギリスと真っ向から衝突した。1890年、イギリスは突如ポルトガルに最後通牒を突きつけポルトガル軍の撤退を要求、ポルトガルはその圧力に屈して撤退した。ポルトガルが撤退した地に後に建設されたのがローデシアである。
ポルトガルの植民地はイギリスとの抗争に敗れたが、その後も長く続き、第二次世界大戦後のアフリカ諸国の独立の動きの中で植民地支配の矛盾はさらに深まってゆき、ようやく1974年の本国の民主化によって実現することになる。ポルトガルはアフリカに最初に植民地を持った国であったが、その殖民地が最後に独立するという皮肉な結果となった。
ポルトガル(6) 第一共和政とサラザール体制
1910年、王政が倒され共和政となったが政党間の争いが続いて安定せず、第一次世界大戦後に経済の行き詰まりを打破することに成功したサラザールが、1932年に独裁体制を成立させた。サラザール独裁体制は第二次世界大戦後、その死後カエターノに継承された。この間、アフリカ植民地は依然として維持された。
王政の崩壊と第一共和政成立
ポルトガルの帝国主義諸国との植民地競争のなかで、アフリカ植民地の維持に苦慮しながらなんとか維持していたが、国内ではブラガンサ朝立憲君主政は財産による制限選挙であったため、農村の有力者(スペインにおけるカシケと同じ存在)が占める王党派が実権を握り、国民的意識の形成と産業の近代化は遅れていた。そのような中、次第に共和政がポルトガルの発展に繋がると自覚するブルジョワジーは共和党を結成し、さらに小市民層の中にはカルボナリ党と称する急進共和派も生まれた。国王の指名する政府が植民地政策で失敗(1890年、イギリスの最後通牒を受諾)したことで、反王制運動が盛んになっていった。国王暗殺事件 国王ドン=カルロスは反王政運動を抑えるため内閣の独裁を認め、政治犯を植民地送りにする法律を制定すると、コインブラ大学の学生ストに始まり、リスボンなどでストライキがひろがり、騒然とする中、1908年2月1日国王と王太子が共に共和党員によって暗殺された。王党派政府は分裂し、8月の総選挙は都市部で共和党が躍進した。
1910年革命 1910年10月4日、リスボンで共和派が反乱を起こした。一旦は政府軍に鎮圧されかかったが、海軍が革命陣営に加わって王宮を砲撃すると、国王マヌエル2世はおびえて逃亡し、ジブラルタルをへてイギリスに亡命した。こうして1640年からのブラガンサ朝王政は終焉となり、共和派の歴史学者テオフィロ=ブラガを臨時大統領とする共和制国家(第一共和政)が発足した。
第一共和政 第一共和政では貴族制度は廃止され、21歳以上の普通選挙制となり、ストライキ権も認められた。政権は軍人・官僚・医師・弁護士といった都市の上層中産階級を基盤とした共和党が握った。1911年8月には共和国憲法が制定され、三権分立・任期四年の大統領制・二院制の直接選挙などが規定された。しかし共和党は内部の権力闘争によって分裂、さらに労働争議が多発してストライキが続き、ストライキを弾圧する共和派政府に対する支持は失われた。
第一次世界大戦 1914年、第一次世界大戦が勃発すると世論は親英派と親独派に分かれ、政党間の争いもあって混乱したが、1915年5月に親英派の民主党が権力を握り、ドイツに宣戦した。アフリカ植民地へのドイツの進攻を阻止するためであった。参戦と共にアフリカ、フランスに20万に上る兵士を派遣し、ポルトガルの国力を大きく弱体化させた。大戦末期から戦後にかけて、1917年には軍の一部によるクーデタ事件、1919年には王党派の王政復古の宣言、1921年には政府の首相の暗殺(流血の夜)といった不穏な事件が続き、次第に軍人の政治参画が多くなっていった。一方、戦中戦後の財政難はさらに深刻になり、負債が増大し、経済不況が長びいてストライキがさらに頻発した。
軍事政権の出現 1910年以来、16年間で45の内閣が交替した第一共和政の不安定な政治に失望した人々は、強力な政権の出現を欲するようになった。そのようなとき、1926年5月28日に大戦の英雄ゴメス=ダ=コスタ将軍がブラガで革命宣言を発し、リスボンに進軍、6月19日に政権を奪った。軍はクーデタに成功するとまもなくコスタ将軍を追放して、軍代表としてカルモナ将軍を選び、秩序を回復する名目で議会の解散、新聞の検閲復活などを実施、反発した共和派の反乱を鎮圧し、28年に直接選挙で大統領に選出されて軍部独裁政権を樹立した。その政府の財政担当に登用されたのがコインブラ大学教授サラザールであった。
サラザール独裁体制
サラザールは蔵相として増税と厳しい歳出削減によって財政黒字を実現し、さらに1929年に始まる世界恐慌もポルトガルへの影響は比較的少ないなか、大規模な公共事業で失業者の増大を防ぎ、経済を再建して「救世主」とみなされるようになった。サラザールは自己の支持基盤として「国民同盟」を発足させ、軍部を抑えた上で、1932年7月に首相の座についた。「新国家」体制 サラザールは1933年、「新国家」(エスタド=ノヴォ)体制の憲法を国民投票にかけて成立させた。表面は国民投票で選ばれる大統領制をとる共和制憲法であるが、立法権の力は弱く、行政府の首相に権限が集中していた。また特色として「組合主義」(コルポラティズモ)という経営者と労働者の宥和を掲げ、各種組合の代表者が組合議会を構成して立法府に参与できる点であった。これは、同時期に登場したイタリアのムッソリーニやスペインのプリモ=デ=リベラのファシズムに影響されたものであった。
第二次世界大戦 1936年にはサラザールは首相・蔵相・外相・陸海軍相を兼ねる独裁体制を作り上げた。同年、スペイン内戦が始まると、フランコ軍側に義勇兵を派遣し、ファシズム国家間の連携を図り、1939年、第二次世界大戦が始まるとただちに中立を宣言した。フランコ政権と同じく、当初は独・伊の枢軸側に好意的であったが、戦局が連合国側に傾くと43年にはイギリスと秘密条約を締結しアゾレス諸島の基地の使用を認め、アメリカ合衆国に対しても42年から日本軍に占領されている東ティモール奪回の支援を条件に基地の使用を認めた。このような連合国(特にイギリス)に対する協力姿勢が、ファシズム国家でありながら戦後においても国際社会で生き残れた理由であった。
戦後のサラザール体制 1932年に成立したサラザール政権は、隣国スペインのフランコ体制と同じく、第二次世界大戦後にも温存された。それは東西冷戦が深刻になる中、その反共産主義の姿勢が、アメリカなど西側陣営の一員として認められたからであった。しかし、サラザール体制のもとで言論の自由や民主化は抑えられ、人権抑圧、腐敗が進み、経済も停滞してヨーロッパでもっとも遅れた国家となっていた。その植民地として続いたアフリカでも貧困と圧政が続いた。
NATOへの加盟 第二次世界大戦後の国際政治では、結成当初から北大西洋条約機構(NATO)の一員として西側の軍事機構に組み込まれている。これは、大西洋上のアゾレス諸島を領有していたことの戦略的意味が大きい。サラザール独裁体制が続いており、自由と民主主義を掲げる西欧諸国の中には独裁政治への批判は強く、当時はポルトガルはNATOの恥部といわれたが、東西冷戦という状況の中で独裁政治も暗黙のうちに認められることとなった。しかしフランコ独裁政権下のスペインと同じく、ポルトガルは閉ざされた国としてその実情を知られることは少なかった。 → NATOの加盟国
植民地支配の矛盾
経済的にはアンゴラ、モザンビーク、ギニアビサウのアフリカ植民地支配に依存し、フランス領やイギリス領のアフリカ諸国の独立にもかかわらずポルトガル領は独立が認められなかった。1961年からポルトガル領でも独立運動が始まると、ポルトガル軍は植民地維持のため厳しい弾圧を行い、闘争は泥沼化し、次第に国内に疲弊感が強まった。前年の1960年はアフリカの年と言われるアフリカ諸国の独立が続き、国連総会も植民地の独立を促す決議がなされ、ポルトガルのアジア支配の拠点であったゴアに対してインドが実力を行使して接収し、ポルトガルはそれを認めざるを得なかった。
独立が最も遅れたポルトガル領アフリカ植民地 1960年の「アフリカの年」以降もアフリカ諸国の独立が相次ぎ、イギリス・フランス・ドイツなどの植民地は次々と独立していった。しかしその中で、ポルトガル領とベルギー領の独立はなかなか進まなかった。ポルトガル領は、西アフリカ海岸(大西洋沿岸)のギニアビサウとアンゴラ、東岸のモザンビークなどであったが、これらの植民地が70年代まで続いた理由は次のようなことがあげられている。
- ポルトガルによる軍事支配が行われたこと。独裁政権のもと、国内と同じような軍事支配が行われ、国家予算の約4割が軍事費に充てられた。
- 隣国の南アフリカ、ローデシアのイギリス系白人国家がポルトガルによる支配を支援したこと。また、利害関係の深いイギリス、アメリカがポルトガルを支持した。ポルトガル軍は植民地戦争でベトナム戦争での米軍と同じナパーム弾を使用した。
- ポルトガル農村の貧困のため、特に第二次世界大戦後、アフリカ植民地への移民が急増した。例えばアンゴラのポルトガル人は1940年に4万4千人(人口の1.2%)だったのが、70年には29万(同5.1%)に増加した。
しかし、1960年代のアフリカの民族運動はポルトガル領をも揺るがすこととなった。1961年からアンゴラなどで独立運動が始まり、それが本国のサラザールの独裁体制を動揺させ、その死後の1974年に植民地・本国同時革命が起こって独裁体制が倒されるとともに、植民地の独立も実現させることとなる。
ポルトガル(7) ポルトガル革命と民主化
1974年クーデターによって独裁政権が倒され、民主化が始まった。当初は軍主導で社会主義路線をあゆんだが破綻し、76年に民政に移管した。1986年にEUに加盟したが、経済的立ち後れが続いている。
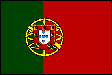
現代史では、1910年に王政を廃止してポルトガル共和国となったが、この第一共和政は安定せず、1932年代にサラザールの独裁体制によるファシズム国家となった。しかしサラザール体制は第二次世界大戦で中立を守ったことから戦後も生き残ることができ、戦後は東西冷戦の中でNATOに加わったことなどで独裁体制を維持した。この間、アフリカなどの海外植民地がポルトガル経済を支えたが、次第に矛盾が深化し、1960年代以降は本国政府は激しい独立運動に悩まされることとなった。
1974年 ポルトガル革命
1968年にサラザールは引退したが、後継者カエターノの独裁体制が続いた。反体制を唱えるスピノラ将軍ら国軍運動(MAF)が始まり、1974年4月25日、クーデタに成功、ほぼ無血で独裁体制は倒され、新政権は植民地の放棄を表明した。カーネーション革命といわれたこのポルトガルの政変は次のような経過で起こった。国軍運動 独裁政治打倒の原動力となったのは大尉クラスの軍人によって組織された国軍運動(MAF)であった。軍の大尉クラスは中下層市民出身者が多く、軍内部での昇進で差別されていただけでなく、アフリカや東ティモールの植民地での戦いの最前線に送られていた。彼らの中に植民地戦争の正当性への疑問が次第に強まり、1973年に「大尉運動」グループが組織され、カエターノ政権に抗して植民地戦争の即時停戦、植民地の独立を主張していた野党勢力と手を結ぶようになった。彼らは政権に近い軍上層部のスピノラ将軍に対しては不信感を持っていたが、74年2月、スピノラ将軍が植民地戦争の平和的解決を提唱し『ポルトガルとその将来』を発表、カエターノ首相と決別を明確にしたので、スピノラらをかつぐクーデターに同意した。3月5日、陸海空三軍の代表は「大尉運動」を「国軍運動」に再編し、スピノラ将軍を革命の指導者として推すことを決定した。
カーネーション革命 1974年4月25日午前零時25分、ラジオから流れた反戦歌「グランドラ、ヴィラ・モレナ」を合図にリスボン北東に駐屯する機械化部隊が行動を開始、放送局を占拠して4時20分にクーデタ布告を放送した。民衆は続々と反乱軍のもとに集まり国軍運動支持を表明した。トマス大統領とカエターノ首相は官邸を軍に包囲され、午後5時半、スピノラ将軍に全権を移譲し、48年に及ぶ独裁体制は終わった。国軍運動は救国軍事評議会を結成し、三週間以内の文民大統領選挙、一年以内の憲法制定議会選挙、秘密警察・事前検閲の廃止、政治犯の釈放など国内の民主化を即刻実施した。サラザール体制下で亡命を余儀なくされていた社会党、共産党などの指導者も急きょ帰国し、臨時政府への参加の意志を明らかにした。5月1日、半世紀ぶりに開催されたメーデーには民衆は兵士の銃口にカーネーションの花をさして「リスボンの春」を謳歌した。
革命後のポルトガル
1974年のポルトガル革命によって半世紀近くにわたったサラザール・カエターノ独裁体制(エスタド=ノヴォ)は崩壊、また500年にわたった植民地帝国も終わりを告げた。スピノラを臨時大統領とする暫定政府が発足したが、民主化の方向と主導権をめぐってスピノラと国軍運動との間に対立が生じた。特にそれまで抑えられていた労働者の賃上げ闘争が一気に過熱し各地でストライキが続発する中、国軍運動が左派と結んで主導権を握った。スピノラは左派の排除を狙って再度クーデタを企てたが失敗し、同年9月30日に辞任した。その後国軍左派による軍政が敷かれ、産業国有化や農地改革などの改革が強行されたが、政権内部も社会党・共産党の対立が生じ、1975年4月に1929年以来、実に46年ぶりに行われた選挙の結果、社会党が第一党となり、穏健路線が支持された。その後も党派の路線闘争が続く中、カトリック教会(国民の80%がカトリック信者)が反共産党の姿勢を強めたため国軍運動から左派が排除され、主導権を失った。こうして軍主導の民主化が政治の混乱と経済の悪化を招いたため、76年に完全に民政に移管して総選挙が行われた。その結果、穏健な改革路線を採る社会党が第一党となりソアレス内閣が成立し、本格的な民主化が進められることとなった。
植民地の放棄と独立
植民地独立も簡単ではなかった。スピノラ将軍は実質的支配継続を狙い、経済圏構想と独立の可否を住民投票で決めることを提唱したが、植民地側は完全即時独立を主張し、交渉は拒否された。それをうけて国軍運動が主導権を握る国家評議会は、海外領土をポルトガルの不可分な部分であるという憲法第一条を廃棄して、まず1974年9月10日にギニアビサウが独立、75年6月25日にモザンビークが独立した。石油やダイヤモンド、鉄などの資源の豊富なアンゴラは白人入植者が最も多かったので交渉は難航したが、9月のスピノラ大統領の退陣により、10月22日に独立を承認した。しかしアンゴラの解放勢力は「アンゴラ解放人民運動」(MPLA)、「アンゴラ完全独立民族同盟」(UNITA)、「アンゴラ解放民族戦線」(FNLA)の三派に分かれて抗争していたため、内戦が続いた。ようやく75年三組織が暫定政権を持ち回ることで合意が成立し、11月11日に独立が決定した。サン=トメ島とプリンシペ島はサン・トメ=プリンシペとして独立、ヴェルデ岬諸島はカーボ=ヴェルデとして、75年7月までに独立した。独立したモザンビークとアンゴラの二国は、ただちに隣接するローデシアと南アフリカ共和国の白人政権から激しい軍事介入を受け、内戦は1990年代初めまで続くという苦難の道を歩むこととなる。東南アジアに残ったポルトガル領の東ティモールでは、独立派が1975年に独立を宣言したが、インドネシアへの併合を主張する勢力も多く、1975年12月にインドネシアのスハルト政権が軍事介入し、76年7月に併合を強行した。その後は東ティモールのインドネシアからの独立戦争が戦われる(2002年に独立達成)。また中国の一部であるマカオに対しては、1976年に大幅な自治を認め、1999年12月に中国へのマカオ返還が実現した。
なお、1996年には、ポルトガル語を公用語とする旧植民地諸国をふくめて、「ポルトガル語諸国共同体」を結成している。旧宗主国ポルトガル以外に、ブラジル、アンゴラ、ギニアビサウ、モザンビーク、カーボ=ヴェルデ、赤道ギニア、サントメ=プリンシペ、東ティモールが加盟している。
EUとポルトガル
ヨーロッパの統合の動きには政治上の独裁体制や経済停滞が続いたために遅れたが、1986年にスペインと共にヨーロッパ共同体(EC)に加盟した。そのままヨーロッパ連合(EU)の一員となり、1999年にはユーロも導入しているが、ユーロ圏ではその経済力の不足がドイツなどの先進国から警戒され、2011年の欧州債務危機に際してはEUおよびIMF(国際通貨基金)の金融支援を要請した。その年発足した社会民主党内閣は金融支援の条件としての緊縮政策を実施した。しかし、賃金引き下げ、労働時間延長、社会保障費切り下げなどは国民生活を直撃し、経済成長がストップしたため、2015年の総選挙で社会民主党が敗北、反緊縮政策を主張する社会党が少数与党となり、共産党、左翼ブロック、緑の党が閣外協力する体制となった。反緊縮路線が成功するかどうか、現在注目されている。