スペイン/イスパニア
イベリア半島のポルトガルを除く部分を支配する大国。この地はローマの属州ヒスパニア(ラテン語読み)とされたことから、現地の言葉でエスパーニャ(スペイン語読み)となり、日本ではイスパニアといわれ、現在では英語読みであるスペインと言われるようになった。
この項は、以下のスペイン王国成立以降を扱うので、それ以前についてはイベリア半島などを参照して下さい。スペイン王国の歴史を段階的にまとめると次のようになる。
- (1)スペイン王国の成立とレコンキスタ
- (2)スペイン帝国 16世紀の全盛期
- (3) 16世紀後半 衰退始まる
- (4) アジア進出の状況
- (5) 中南米植民地の支配
- (6)ナポレオンの支配と独立戦争
- (7)19世紀スペインの苦悩
- (8)米西戦争の敗北
- (9)第1次世界大戦とスペイン
- (10) 第二共和政とスペイン戦争
- (11) フランコ独裁体制
- (12)スペインの民主化と現代
Amazon Music 永遠のフラメンコギター ベストライブ フラメンコギターと言えば天才パコ・デ・ルシアですよね。
スペイン(1) スペイン王国の成立とレコンキスタ
1479年、アラゴン王国とカスティリヤ王国が合同してスペイン王国が成立。レコンキスタ(国土回復運動)を推進し、1492年にグラナダのナスル朝を滅ぼして完了した。同年、スペイン王国の派遣したコロンブスが新大陸に到達した。
スペイン王国(両君王国)の成立
レコンキスタを推し進めたキリスト教国カスティリャ王国とアラゴン王国が1479年に合同しスペイン王国(イスパニア王国)が成立した。その年、アラゴン王国の王子フェルナンドが即位し、その妻(1469年に結婚)イサベル女王のカスティリャ王国と合同してスペイン王国となった。「イサベルとフェルナンドは同権」の王として二人で統治した(スペイン王としてはイサベル2世・フェルナンド5世と称した)。このふたりには、1496年にローマ教皇アレクサンデル6世(スペインのボルジア家出身)から「カトリック両王」の称号が贈られた。レコンキスタの完了
1492年1月には、イスラームの最後の拠点グラナダを陥落させ、8世紀以来続いたレコンキスタを完成した。同1492年10月、スペインの派遣したコロンブス艦隊が大西洋を横断、西インド諸島に到達した。またイベリア半島には多くのユダヤ人が居住していたが、同1492年3月31日に、両王の名で、ユダヤ教徒追放令を出し、キリスト教に改宗したユダヤ人(コンベルソ)以外のユダヤ教教徒を追放しており、スペインにとっての重大な転換点となった年であった。 → 1492年という年世界分割の始まり
大航海時代の先鞭を付けたポルトガルに対して、スペインの派遣したコロンブス艦隊が西回りでインドに到達したかも知れないというニュースは、大きな脅威であった。早くも両国は植民地分界線の交渉をローマ教皇アレクサンデル6世の斡旋によって行い、1493年に教皇子午線の東をポルトガル、西をスペインが領有することとした。翌1494年、両国は直接交渉してトルデシリャス条約を結び、境界線を西にずらした。こうして早くも15世紀末にはポルトガルとスペインによる世界分割が行われた。コロンブス自身はこの島々をインドの一部と考えたが、その後のアメリゴ=ヴェスプッチの探検で新大陸であることが判明した。こうしてトルデシリャス条約の境界線の西側に広大な世界が広がっていることが判明し、焦点は西回りでアジアに到達できるかどうかに移っていった。
イタリア戦争での勝利
1494年、フランスのシャルル8世がイタリアに侵入してイタリア戦争が始まると、フェルナンドはローマ教皇アレクサンデル6世、神聖ローマ皇帝ハプスブルク家のマクシミリアン1世、ヴェネツィア、フィレンツェなどと同盟を結んでフランス軍を撤退させることに成功した。さらにフェルナンド5世は1504年にナポリ王国の併合に成功した。主権国家の形成
カトリック両王のもと、スペインは国家機構の整備、中央集権化を進め、国民統合と領土拡張に成功して主権国家の形成にむかい、絶対王政を成立させた。またカトリック教国としての統一性を強化するため、国内のユダヤ人やイスラーム教徒は国外追放した。スペイン王国では、聖職者、貴族、都市の代表からなる身分制議会であるコルテス(現在のスペインの国会もコルテスという)が開催されていたが、絶対王政が確立するとその機能を失う。スペイン(2) スペイン帝国 16世紀の全盛期
1519、カルロス1世が神聖ローマ皇帝となり、ヨーロッパの領土と新大陸の植民地を支配する大帝国となる。新大陸の富を独占し、未曾有の繁栄期を迎えたが、イタリア戦争、宗教改革、オスマン帝国の侵攻などの問題も起こった。
ハプスブルク家の支配
スペインの統合を成立させたフェルナンドとイサベルは、二人の間の娘のファナ(後に精神を病んだので狂女といわれた)を神聖ローマ帝国皇帝のハプスブルク家、マクシミリアン1世の皇太子フィリップ(スペイン名フェリペ)と結婚させた。このあいだに生まれたカルロスはすでにブルゴーニュ公(ネーデルラントを含む)を相続していたが、1516年、さらにスペイン王位を継承してカルロス1世(在位1516~56年)となり、ここにハプスブルク家がオーストリアとブルゴーニュ、そしてスペインを支配するハプスブルク帝国が成立した。カルロス1世=カール5世 1516年、17歳でスペイン王なったカルロスは、父の所領ブルゴーニュで育ったのでスペイン語は話せなかったという。そのカルロスはさらに1519年、対立候補のフランスのフランソワ1世を破って神聖ローマ皇帝に選出され、カール5世となった。その領土はスペインのみならず、ブルゴーニュ、ネーデルラント、ドイツ、オーストリア、南イタリアにひろがっており、さらに当時展開されていた大航海時代の中で、アメリカ新大陸が加わることとなる。
スペイン王の神聖ローマ皇帝就任の意味 スペイン王カルロス1世が神聖ローマ皇帝カール5世となった結果、彼のもとに「アラゴンとそのイタリアおよび地中海の権益、カスティーリャとその最初に征服した植民地、ブルゴーニュ=フランドル王家、オーストリア、そして最後に神聖ローマ帝国などが集約された。」このことは歴史的にはどのような意味をもっているのだろうか。ピエール=ヴィラールの『スペイン史』では次のように端的に指摘している。
(引用)これらの歴史的事実がスペインの将来にとってどういう価値を持つかという点を取り上げるだけでいいだろう。ひとつは、スペインの政治が神聖ローマ帝国の理念と結びついたことであり、もうひとつは、スペインの力が分散され、スペインが経済的に破綻したことである。<ピエール=ヴィラール/藤田一成訳『スペイン史』1992 白水社 文庫クセジュ p.39>
カルロス1世統治下の海外発展
1494年のトルデシリャス条約により、ポルトガルは東廻り航路でアジアに向かい、スペインは西回り航路の開拓をめざした。最大の焦点はアメリカ大陸を迂回できる航路の発見であったが、カルロス1世がカール5世として神聖ローマ皇帝となった1519年、彼が派遣したマゼラン船団がマゼラン海峡を発見、太平洋を横断し、フィリピンに到達し、西回りでのアジア到達に成功した。マゼラン自身は現地で死んだが、部下の艦隊は香料諸島と言われたモルッカ諸島を経て、インド洋を横断、1522年に帰国し、はじめて世界周航を成功させた。これを契機としてスペインはアメリカ大陸に広大な新領土を持つと共に、アジアとの交易に乗り出し、植民地帝国・海洋帝国として歩み始めた。アメリカ新大陸には、黄金などの資源が期待されたので、スペインは次々と征服者(コンキスタドール)を派遣し、それに従って多くの入植者が渡っていった。コルテスはメキシコに遠征してアステカ帝国を滅ぼし、ピサロはアンデス山脈山中のインカ帝国を征服、その結果、アメリカ大陸はブラジルを除き、ほぼスペイン領となった。こうして、大航海時代のスペインは、貿易港セビリャに新大陸からの銀がもたらされ、空前の繁栄の時代を迎える。
宗教改革・ウィーン包囲
15世紀末のヨーロッパは、オーストリア・ネーデルラント・スペインなどを領有するハプスブルク家と、ヴァロア朝フランスの対立・抗争を軸として国際政治が展開された。フランスのイタリア侵入から始まったイタリア戦争(狭義、1521~44年)は、関係した諸国の絶対王政のもとでの国民統合、領土概念などを成立させ、主権国家体制に移行させていった。一方、1517年にはドイツでルターの宗教改革が始まってキリスト教の旧教と新教の対立という宗教戦争の側面が強くなり、さらに1529年にはオスマン帝国のスレイマン1世によるウィーン包囲が大きな脅威となっていた。カール5世の時代は大航海時代の栄光と同時に、イタリア戦争、宗教改革、オスマン帝国の脅威という危機の時代でもあったことを忘れてはならない。「胡椒と霊魂」 この間、スペインは大航海時代の繁栄のもと、強固なカトリック信仰が守られていた。その中から宗教改革に伴うカトリック教会の危機を強く意識したスペインの青年、イグナティウス=ロヨラ・フランシスコ=ザビエルらは、1534年年にパリでイエズス会を結成し、1540年にはローマ教皇の公認を得て、海外布教に積極的に乗り出した。その運動は「胡椒と霊魂」といわれるようにスペインの海外進出と深く結びついていた。
スペイン(3) 16世紀後半 衰退始まる
16世紀後半、スペイン帝国はフェリペ2世のもとで全盛期となるが、イギリスとの戦争、オランダの独立などが続き、国家財政の破綻を招き、17世紀に急速に衰退する。
「太陽の沈まぬ国」
このフェリペ2世時代(1556~98)にスペイン王国は全盛期を迎えた。1561年に宮廷をマドリードに定め、63年からエル・エスコリアルに修道院兼王宮を建設した(84年に完成)。1571年にはレパントの海戦でオスマン帝国海軍に挑戦してそれを破り、この勝利で無敵艦隊と称されるようになったスペインの海軍は、プレヴェザの海戦以来失っていた制海権を回復した。同年、アジアではマニラ市を建設してフィリピン植民地支配を強化した。さらに1580年にはポルトガル王国の王朝断絶を契機にその王位を継承してポルトガル併合を実行した。其の結果、スペインの領土はポルトガル領の植民地も獲得、新大陸からアジアに至る地球を一周して分布し、「太陽の沈まぬ国」といわれる広大なものとなった。
しかし、関係が悪化したイギリスは、エリザベス1世ものとで海外進出を活発化させ、同時にスペイン領であるネーデルラントでは新教徒の間にスペインのカトリック強制に対する反発から独立の機運がたかまり、1581年に独立を宣言、オランダ独立戦争が開始された。1588年にはスペインの誇る無敵艦隊がオランダ独立を支援するイギリス海軍とのアルマダ戦争(海戦)に敗れるという事態となった。
フェリペ2世の破産宣言
カルロス1世(カール5世)からフェリペ2世に至る16世紀のスペインは、特にアメリカ大陸の銀などの資源を独占して、広大な領土をもつ大帝国であった。またフェリペ2世は、マドリッド郊外にエスコリアル宮殿を建設(1563~84年)するなど、その宮廷は構成を極め、文化が花開いていた。しかし、実際にはフランスとのイタリア戦争、オスマン帝国とのレパントの海戦、オランダの独立戦争、イギリスとの戦争という戦争が続いており、その戦費は大きくスペイン財政を圧迫していた。その戦費捻出のため、フッガー家をはじめとする富豪から借金していたので、アメリカ新大陸からもたらされる銀は多くがその返済に充てられ、スペインに蓄えられることはなかった。早くも1557年に、フェリペ2世は最初の破産宣告(国庫支払い停止宣言)を行い、債務をその額の5%の年金支払いとする長期公債に切り替えている。その後も支払い停止措置は、60年、75年、96年と繰り返された。フェリペ2世はこの財政危機を課税強化で乗り切ろうとし、依然繁栄していた新大陸との交易に対する課税を増やした。しかし、新大陸との交易は、産銀量の減少もあってふるわなくなり、フェリペ2世没後の1609年にはオランダが実質的独立したことによって、商工業の中心が北ネーデルラントに移ったこと、また17世紀にはイギリス・オランダが台頭したことによって、スペインは衰退を余儀なくさせた。(引用)黄金でおおわれていると思われていたスペインの王は、貧困ゆえに身動きがとれなくなり、1557年に破産した。世界的な覇権を目指す考え方は、間違いなく時流には合わなかった。純粋に国家中心の政治の時代が到来したのである。<ピエール=ヴィラール/藤田一成訳『スペイン史』1992 白水社 文庫クセジュ p.40>
17世紀のスペインの衰退
17世紀には急速が衰退が進んだが、その一因は1618年に始まった三十年戦争に介入したことにある。それ以前のカルロス1世の時代のイタリア戦争でも財政が破綻していたが、オランダ独立戦争は1581年から続き、1609年には事実上の独立を認めざるを得なくなっていた。またこのころにはアメリカ新大陸の金銀の産出が減少し始めたため、さらに国家財政の危機が大きくなっていた。それにもかかわらず三十年戦争が起きると、旧教徒の応援のため、またフランスとの対抗のために、国王フェリペ4世は出兵した。政治の実権を握っていた宰相オリバレスは、それまでカスティーリャだけが負担していた戦費を、スペインの他の地域に課すようにしたが、それに反発したカタルーニャの反乱(1640年、カタルーニャ(カタロニア)地方で起こった農民反乱。収穫人戦争ともいう。)が起き、さらにポルトガルもスペインから分離運動が起こって、同年独立を回復した。また、三十年戦争ではフランス軍とのラクロワの戦いに敗北し、大きな痛手を被った。その講和条約として1648年に成立したウェストファリア条約では、ついにオランダの独立を承認し、かつてスペインの富の源泉であったオランダはこれで完全にその手を離れ、スペインの没落は決定的となった。その後、スペイン=ハプスブルク家の断絶によってフランスのルイ14世が介入し、1701年スペイン継承戦争(~14年)が勃発、その結果ブルボン朝がスペインを支配することとなる。スペイン衰退の原因
スペインは16世紀末から17世紀を通じて急速に衰え、大国の地位を失っていった。その要因はさまざまなことが考えられるが、毛織物業以外の産業資本の停滞を招いた次の二点を指摘することが出来る。- 新大陸から得た銀は宮廷の奢侈に浪費され産業育成などに回されなかったこと。
- 本国以外の産業や植民地の資源に依存し、国内産業の基盤が作られなかったこと。
- 封建社会のもとで土地の大部分は貴族・教会が所有し、免税の特権が与えられていたこと。
- 商業を担っていたユダヤ人とイスラーム教徒(ムーア人)を宗教的に迫害し、追放したこと。
- 海外領土からの銀は国庫に入らず貴族と投機業者の手によってヨーロッパに流失したこと。
- 国内取引に対する重税が国内産業の発展を阻害したこと。
- 海外との取引の実際の利益の多くが、イギリスとオランダの密輸業者に握られていたこと。
スペイン(4) アジア進出の状況
1571年にマニラを建設し、フィリピンを植民地支配。太平洋を横断するガレオン貿易を展開した。日本とも交易を行ったが、江戸幕府の鎖国政策で後退した。
しかし、本来の目的のインド到達は、東廻りでの1498年のバスコ=ダ=ガマのカリカット到達によってポルトガルに先を越されてしまった。両王は、発見地をなおもインドの一部だと言い張るコロンブスを見限り(1500年、コロンブス逮捕、本国送還)、新たに探検隊を派遣して西回りでアジアに抜けることのできる「海峡」を発見することにつとめた。
それは、次のカルロス1世(つまりカール5世)が派遣したマゼラン船団がマゼラン海峡を発見、太平洋を横断して1521年にフィリピンに到達したことによって成功した。しかしめざす香料諸島、モルッカにはすでにポルトガルが東回りで到達しており、両国の抗争が発生した。
カール5世は、フランスとヨーロッパの覇権を争っていたのでポルトガルとの対立を長引かせるわけにはいかず、また当時の航海技術では太平洋を西から東に戻ることが困難であったため、1529年にサラゴサ条約を締結してモルッカ諸島の支配権をポルトガルに譲渡した。
その後、太平洋を往復する航路が開発され、1571年にはフィリピンにマニラ市を建設して、メキシコのアカプルコとの太平洋をまたぐガレオン貿易を行った。スペインは
スペインと日本
日本とスペインの関係は、1549年のザビエルが鹿児島に上陸したときに始まる。その後も多くのスペイン人宣教師が来日し、カトリックの布教にあたった。九州のキリシタン大名は天正遣欧使節として少年たちを西廻りのスペイン経由でローマ教皇に派遣した。しかし、スペインの日本との交易は遅れ、1584年にようやく平戸に商館を設けて交易を開始した。スペインは日本に対しては交易よりもキリスト教の布教に力を入れる傾向があった。また、豊臣秀吉は1587年にバテレン追放令を出してキリスト教の布教禁止に転換していたが、1596年にスペイン船のサン=フェリペ号が土佐沖に漂着したとき、乗組員がキリスト教布教をスペインの世界征服のためであると誇張してのべたためにキリスト教取り締まりを強化することとなった。また豊臣秀吉はフィリピンのルソン島征服を一時計画したためにスペインとの関係は悪化した。
Episode 太平洋を初めて横断した日本人
日本の鎖国
その後、仙台藩主伊達政宗は徳川家康の許可を得て1613年、遣欧使節として支倉常長を派遣した。支倉常長は同じく太平洋を渡りメキシコを経由して大西洋を横断し、スペインに行き、さらにローマ教皇に謁見した。しかし日本はキリスト教禁教の原則を改めなかったので通商は開けず、20年に帰国した。1616年に家康が死去してから、江戸幕府は急速にキリスト教全面禁止と貿易統制策(いわゆる鎖国)に踏み切り、1624年にはスペイン領のルソン(フィリピン)が宣教師の拠点となっているとして、スペインとの国交を断った。スペイン(5) 中南米植民地の支配
コロンブスの新大陸到達以来、16世紀にスペインは西インド諸島、南北アメリカに進出、現地の文明を亡ぼしながら植民地を拡げ、南米のブラジル、西アジア諸島の幾つかの島をのぞく広大なスペイン植民地を形成した。
16世紀、征服者(コンキスタドーレス)によってインディオの文明は破壊され、その上に成立したスペイン植民地支配は、エンコミエンダ制というカトリックの布教と結びついたインディオに対する苛酷な労働を強制して展開された。1545年に発見されたポトシ銀山などでの莫大な銀の資源もスペインに独占され、インディオの強制労働によって経営された。それによって急激なインディオ人口の減少がもたらされると、スペインはアシエンダ制という大土地所有制を採用するようになり、また西インド諸島などではアフリカからもたらされた黒人奴隷を労働力として砂糖やタバコなどを生産するプランテーションが始まった。スペイン人入植者に黒人奴隷を供給し、その生産品を買い付けてヨーロッパにもたらす三角貿易は、17世紀からはオランダ商人が進出し、次いで18世紀からはイギリスが主役となった。
スペインの植民地統治
スペインは「インディアス」と呼んだ新大陸植民地をヌエバ=エスパーニャ(ほぼ北米)とペルー副王(スペイン国王の代理)に分けて支配し、重要地点にアウディエンシアという司法・行政機関を置いた。また植民地統治の上で、カトリック教会とその教区司祭が重要な役割を果たした。植民地社会には、入植者である白人には本国生まれのスペイン人と、現地生まれのスペイン人(クリオーリョ)の違いがあり、現地のインディオは次第にその人格は認められ身分上は自由人扱いであったが、現実には経済的に貧しく、また白人とインディオの混血であるメスティーソが実質的にその上に存在した。また奴隷として連れてこられた黒人も多く、また白人と黒人の混血であるムラートも増えてきた。ラテンアメリカはこの複雑な人種的身分制社会として続くが、権力を握っている本国人に対するクリオーリョの不満を中核として、身分差別に苦しむメスティーソ、インディオ、黒人らの中から独立運動の主体が育っていく。スペイン(6) ナポレオンの支配と独立戦争
1808年、ナポレオン軍に征服されたが民衆が蜂起しスペイン独立戦争始まる。ナポレオン没落後、ブルボン朝が復活。この間、ラテンアメリカのスペイン領が次々と独立する。
18世紀のスペイン
スペイン継承戦争(1701~14年)によって成立したスペイン=ブルボン朝の支配のもとで、18世紀スペインはかつてのような繁栄は遠のき、封建制度と教会の支配が根強く残存し、他のヨーロッパの諸国のような産業や政治の面での近代化への歩みは起こらなかった。それでも農業の安定とアメリカ大陸との交易は人口増加をもたらし、スペインでも徐々に資本の蓄積と工業化が進み、18世紀末には一定の資本主義経済が生まれていた。外交面では同じブルボン家の支配のもとで「家族協定」によってフランスとの共同歩調を取った。七年戦争ではフランスと同じくオーストリアを支援し、プロイセン・イギリスと戦ったが、新大陸でのフレンチ=インディアン戦争でフランスとともに敗れたため、フロリダをイギリスに奪われた。アメリカ独立戦争でもフランスとともに独立を支援し、イギリス海軍と戦い、このときはアメリカ大陸でフロリダを奪回するとともに地中海でミノルカ島を獲得した。
ナポレオンのスペイン征服
18世紀末、フランス革命の中からナポレオンが登場すると、スペインは当初は同盟を結びイギリスと戦った。しかし、1805年のトラファルガーの海戦での敗北は、大西洋でのスペイン海軍の後退をもたらし、ラテンアメリカの独立の動きを活発にさせるきっかけとなった。スペインのブルボン朝宮廷では当時、ナポレオンとの提携を巡って内紛が生じていた。その混乱に乗じてナポレオンはスペインの直接統治をもくろみ、1808年に腹心の将軍ミュラを派遣、フランス軍がマドリードに迫る中、5月2日から3日にかけてスペイン民衆が各地で蜂起した。マドリードでの蜂起はフランス軍によって鎮圧され、数百人が銃殺された。ゴヤが描いた『1808年5月3日』はこのときの状況を生々しく伝えている。
ナポレオンのスペイン遠征の背景 ナポレオンは1806年にイエナの戦いでプロイセン軍に勝利した後、残るイギリスを屈服させるため大陸封鎖令を出した。そのとき、イギリスの同盟国であったポルトガルが障害となるので、それを撃つ必要があったが、海軍力に劣るフランスがポルトガルを制圧するためには陸路を通る必要があった。そこでナポレオンは1807年、スペインの宰相ゴドイとフランス軍のスペイン通過を認めさせ、そのかわりにポルトガル制圧後にゴドイにその3分の1の領土を与えると約束した。しかし、ポルトガル征服にとどまらず、スペインをも併合しようと1808年春に軍隊を派遣してきた。スペインではカルロス4世とゴドイに対する反発が強まり、5月に民衆暴動「5月3日事件」(ゴヤが描いている)が起こって国王とゴドイは追放され、新国王フェルナンド7世が即位した。そのような混乱を見たナポレオンは、スペイン=ブルボン朝の廃位を決意した。 → スペインの反乱
ボナパルト王朝 ナポレオンはフェルナンド7世に退位を迫り、6月4日には自分の兄ジョゼフ=ボナパルトをスペイン王(スペイン語ではホセ1世、簒奪王といわれている)。ジョゼフ王はフランスのバイヨンヌで議会を開いて新王朝を承認させ、憲法(バイヨンヌ憲法)を制定し、フランスを手本とした自由主義・立憲王制国家の形を整えた。
スペイン最初の議会と憲法 それに対してスペインではフランス軍の支配の及ばない地域で抵抗組織として地域評議会をつくり、9月には中央評議会を組織した。しかし、これらは民衆運動を組織したものではなく、ナポレオンを悪魔的な無神論者として認めない教会の勢力がその中心であった。1810年には中央評議会はカディスに移り、そこで独自に議会(コルテス)を開催した。これはスペイン最初の近代的議会であり、1812年3月には立憲君主政体ではあるが、国民主権・三権分立などを規定したカディス憲法といわれる憲法を制定した。この憲法はスペイン=ブルボン朝の復活によって1814年に廃止されてしまうが、スペイン最初の憲法として、後の立憲革命でも意味を持つこととなるだけでなく、「自由主義の政治的モデル」としてポルトガルやイタリアにも大きな影響を与えた。
スペインの反乱=スペイン独立戦争
1808年5月2日・3日に反乱を起こしたスペインに対して、ナポレオンは6月に兄のジョゼフを国王とする王国として統治しようとしたが、民衆はそれ以降も抵抗を続けた。その戦いはスペインの反乱といわれるが、実態はスペイン独立戦争といって良いものであった。7月19日のバイレーンの戦いではフランスは大敗を喫し、ジョゼフはマドリードを脱出しなければならなくなった。そこでナポレオンは11月に自ら大軍を率いてスペインに侵攻、12月にマドリードに入城し、異端審問制や封建的諸権利の廃止など、解放者として振る舞った。ゲリラによる抵抗 ナポレオン軍に抵抗したのは、民衆が自発的に組織したゲリラ戦術であった。ゲリラ部隊はフランス軍占領地域で攪乱戦法に出てフランス軍を悩ませ、国王ジョゼフはついに全土を支配することができなかった。
1812年からナポレオンのロシア遠征が始まるとそちらに兵力を割かれたためフランス軍は苦戦に陥った。またウェリントンの率いるイギリスはポルトガルからスペインに進撃し、7月にフランス軍を破った。1813年、ナポレオンのロシアでの敗北とともにスペインのフランス軍も劣勢に陥り、6月にジョゼフ国王は国王を退いてフランスに退き、翌年6月までにスペインのフランス軍は完全に撤退した。
ラテンアメリカの独立運動開始
すでにアメリカ合衆国の独立によって、ラテンアメリカの独立の機運は生まれており、フランス革命期にフランス植民地であったハイチの独立が達成されていたが、その動きを一挙に高めたのはナポレオンのスペイン征服であった。1808年、ナポレオンのスペイン征服が伝わると、ラテンアメリカ植民地でも本国と同じく国王ジョゼフ(ホセ1世)を否認する評議会が各地に生まれた。独立運動をおもに担ったのはクリオーリョであり、メスティーソやインディオとの対立という要素を含みながら、独立をめざす動きを強めた。スペイン立憲革命
ブルボン朝の復活 ナポレオン没落後のウィーン体制は、ヨーロッパをフランス革命・ナポレオン戦争以前に戻そうという正統主義を掲げた。スペインでは復位したスペイン=ブルボン朝のフェルナンド7世が、1812年のカディス憲法をフランス風の自由主義に基づいているとして否定し、廃止した上で国王絶対王政を復活させた。しかしスペイン民衆の中には、自由を希求する要求が強く残っていた。ウィーン体制の動揺 1820年1月1日、カディス港でラテンアメリカの独立運動を鎮圧するために派遣される海軍の兵士が反乱を起こし、「カディス憲法」の復活を要求した。国王フェルディナンド7世はそれを承認し、スペイン立憲革命が成功した。これはウィーン体制の支配下における、自由主義と民族主義に大きな影響を与え、イタリアでのカルボナリの蜂起、ドイツのブルシェンシャフト、ロシアのデカブリストの反乱などが起こった。立憲主義と「カディス憲法」はその具体的な目標となった。
スペイン立憲革命は1820年から23年にかけて、自由主義改革を実現した後、フランス軍の介入で弾圧された。20年代の自由主義を求める決起はいずれも鎮圧されたが、それによってウィーン体制の矛盾をさらに深めていくこととなった。
フランスの介入 ウィーン体制を主導していたオーストリアのメッテルニヒはロシア、フランスなどの君主と神聖同盟を結成していた。その一角であるフランスのブルボン復古王政(ルイ18世)は神聖同盟の支援を受け、スペイン立憲革命に介入し、ラテンアメリカの独立運動を抑え、その支配を復活させようとしていた。
アメリカのモンロー宣言 ヨーロッパ大陸の強国がアメリカ大陸への支配を復活させることに対し、新興国で会ったアメリカ合衆国は強く警戒した。1823年にモンロー大統領が出したモンロー教書は、ヨーロッパ諸国をアメリカ大陸から排除するため相互不干渉を提言するとともに、アメリカ大陸を勢力圏とすることを狙ったものであった。を出して、スペインの動きを牽制したので、干渉を続けることは困難であった。また、イギリスは自由貿易圏を拡大することをねらい、フランス、スペインの大陸植民地が復活することに反対し、アメリカを支持した。このようにスペイン立憲革命はウィーン体制を大きく動揺させることとなった。
ラテンアメリカの独立 スペイン立憲革命でスペイン=ブルボン朝が一時的ながら倒れ、本国に自由主義政権が成立したことは、ラテンアメリカの独立運動にも大きな刺激を与えた。独立を求める動きは急速に活発となり、1824年にはシモン=ボリバルの率いるペルー軍がスペイン軍を破ったことで、ラテンアメリカの独立の大勢は決まった。スペインに残された植民地はキューバ、プエルトリコ、フィリピンのみとなった。
スペイン(7) 19世紀スペインの苦悩
19世紀スペインは絶対王政から立憲制に移行する過程で内戦が続いた。自由主義も力をつけ、1868年の九月革命では王政が倒れ、1873年には第一共和政が成立したが、翌年すぐに王政復古となった。しかし復活したスペイン=ブルボン朝国王の政治的実権は薄れ、立憲君主政のもとで政党政治が行われることとなった。
カルリスタ戦争
1833年、フェルナンド7世が死去、王妃マリア=クリスティーナが摂政となりわずか3歳の娘を即位させイサベル2世とした。これに対してフェルナンドの弟カルロスが、フランク王国以来のサリカ法典では女性の王位継承権は認められていないとして反乱を起こした。カルロスを支持する人々をカルリスタと言うのでこの内戦をカルリスタ戦争という。カルリスタに対抗するためマリア=クリスティーナは国内の自由主義者に近づいた。その支持者はクリスティーノスと言われた。こうして19世紀を通じ、<カルリスタ=保守>対<クリスティーノス=革新>という図式の内戦が繰り返される(第1次=1833~39、第2次=46~60、第3次=72~76)。前者には聖職者、農民の他にバスクとカタルーニャの反中央政府派も荷担したが、後者は軍隊、宮廷貴族、ブルジョワの支持を受け、ほぼ戦闘は後者の優位で進み、結局カルリスタは敗北した。カルリスタ戦争の過程で、国王は自由主義勢力を結ばざるを得なかったため、1837年には1812年憲法に近い憲法が制定され、国民主権のもとでの立憲制が実現するなど改革も行われたが、カルリスタの勢力が弱まると摂政マリア=クリスティーナは自由主義を抑圧して強権を振るおうとし、それに反発した軍隊蜂起(プロヌンシアミエント)が起きるということが繰り返された。また国王支持勢力も妥協的な穏健派と王政に批判的な進歩派に分裂して対立するようになった。
プロヌンシアミエント
近代スペインに特有な動きがプロヌンシアミエントである。軍事蜂起、蜂起宣言などと訳されることが多いが、スペインでたびたび繰り返された軍部クーデタのことを指している。スペインの軍隊は、ナポレオンとの戦争やカルリスタ戦争、植民地での民族独立運動の鎮圧(1859~60年のモロッコでのモロッコ戦争)などで鍛えられ、強大になっていたが、徴兵は不正に行われ、将校の数が兵士よりも多いという特殊な性格を持っていた。そして一つの政治勢力として国内の抗争に対応するために使われた。(引用)よく知られているように次のような仕組みで、事が周期的に起こった。亡命者、秘密結社、しばしば陰謀を企んでいる外国勢力は、それとなく一部の党派に後押しされ、また、政府の圧力を受けて合法的な手段を封じられたことを知って、一人の将軍を選び出す。彼は亡命中の、少なくとも逆境にある指導者である。それゆえに、クーデタは上陸した港か遠隔地で始まることになる。そこで、声明文が兵舎から出てくる軍隊に向けて読まれる。・・・あらかじめ工作していた他の駐留部隊に、同じ内容で「軍事蜂起を宣言する」よう強く求める。・・・<ピエール・ヴィラール『スペイン史』1992 白水社文庫クセジュ p.76>19世紀を通じて何度か軍事蜂起(プロヌンシアミエント)が起こされ、その大半は失敗している。1936年のフランコの挙兵はプロヌンシアミエントの最後で最大の、「成功した」例であった。
1868年 スペイン九月革命
イサベラ2世は1843年に成人して親政を行うことになったが、気分の赴くままに穏健派、進歩派の大臣の首をすげ替え、私生活も乱れていたため次第に役人、軍人から見放されるようになった。1868年9月、軍人のセラーノやプリムが進歩派とむすんでクーデターを決行し、女王イサベラ2世はフランスに亡命した。このプロヌンシアミエントで成立した自由主義政権は基本的人権の保障や男子普通選挙を導入するなどの改革を行った。翌69年6月には新憲法で国民主権に基づく立憲王政、二院制からなる議会制を定めた。この1868年のスペイン九月革命はいくつかの副産物を生んでいる。直接的には同年10月、スペイン植民地のキューバの独立戦争が始まったことである。これは「十年戦争」と言われ、スペインにとっての大きな負担として続く。
スペイン王位継承問題
スペイン九月革命のもう一つの副産物は、イサベル2世の亡命によって起こったスペイン王位継承問題をめぐってフランスとプロイセン王国が介入、両者の対立は国際問題化したことである。普仏戦争 王位継承者の候補としてプロイセンのホーエンツォレルン家家につながるレオポルト(ポルトガル王家とも血縁関係があり、カトリック信者だったので都合が良かった)の名が上がると、本人は乗り気ではなかったのに、プロイセン首相ビスマルクが強く説得、スペイン側も受けいれて一旦話しが成立した。それに対してフランスのナポレオン3世は、プロイセンの勢力がスペインに及んでフランスを挟撃するかたちになることを警戒し、強く反対した。16世紀のスペイン王カルロス1世が神聖ローマ帝国皇帝カール5世となってフランスに脅威をあたえフランソワ1世との間のイタリア戦争となったことの再現を恐れたのだった。1870年、ビスマルクはエムス電報事件によってドイツ・フランスの世論に刺激を与え、挑発されるかたちとなったナポレオン3世がプロイセンに宣戦布告し、普仏戦争が勃発した。
王政の混乱 普仏戦争の勃発でスペイン新国王の選任は難航し、ようやく71年1月、イタリア王ヴィットーリオ=エマヌエーレ2世の息子のアマディオを迎えることとなった。しかしそれに対して三度目のカルリスタの反乱が起こり、教会も信仰の自由を謳った憲法に反対を表明、内乱の状況が再発した。選挙では九月革命を推進した九月連合の自由主義派が勝ったが、指導者プリム将軍が暗殺され、国王アマディオも統治意欲を失い、73年2月王位を放棄してしまった。
第一共和政から立憲君主政へ
1873年2月、国王アマディオの退位に伴い、議会は共和政樹立を宣言し、6月に大統領を選出、ここにスペイン史上最初の共和国(第一共和政)が成立した。しかし、選挙で台頭したのは地方分権をかかげる連邦派だった。共和政は連邦制の早期実現を求める連邦主義者(カントナリスタ)の蜂起によって揺さぶられた。彼らはパリ=コミューンとバクーニン派の影響を受け第1インターナショナル=スペイン支部を結成していた。共和国政府は軍隊を動員して反乱を鎮圧したが、議会の不信任で大統領が辞任するなど混乱が続き、軍部独裁を目指す動きも出るなど、その政権は長続きせず、1874年12月、亡命先のパリからイサベル2世の息子アルフォンソ12世を迎え、第一共和政は1年半ほどので終わりを告げ、スペイン=ブルボン王朝の王政が復活した。スペインが再び共和政になるのは1930年である。復古後のスペイン王政はもはや絶対王政を行う権威はなく、実権を握ったカノバスのもとで、カルリスタ戦争とキューバ独立戦争(第1次)が終結し、1876年憲法の下で立憲君主政は確定し、保守党・自由党が生まれ、スペインにも議会制度と政党政治が定着することになった。しかし多くの農村では依然としてカシケといわれる政治ボスが選挙を左右する力を振るっていた。
カシケ
カシケ cacique とは、もともと16世紀に西インド諸島からスペインに伝えられた言葉で、酋長ないし親分といった意味である。スペインの南部の農村では、寄生地主の代理人が地方のボスとして一つの階層をなしていた。スペインでは1890年の選挙法改正で男性普通選挙権が認められたが、カシケの支配する地域では、ほとんどこのカシケが選挙民を操縦して行われた。(引用)例えば、ある村ではカシケは僧侶以外に読み書きできる唯一の人間であり、村の世話役であった。カシケは役人であることもあり、小地主であることもあり、商人であるあることもある。与党や富豪・地主などに頼まれたカシケは、選挙民に恐喝や圧迫を加えた。選挙当日には、車で投票場に運ばれた選挙民は、なんらかの隠し符号のついた投票用紙を配られる。後でカシケが開票を調べて、だれがどの候補者に投票したかを読み取る仕組みになっていたのである。ある地方では、選挙の「正確な」結果が判明するまでに八日を要したことがあるという。八日とは選挙詐欺のための取引きについやされたのである。<斎藤孝『スペイン戦争』1966 中公新書 p.11>
スペイン(8) 米西戦争の敗北
ブルボン朝立憲王政下のスペインは、1898年キューバの独立運動に介入したアメリカと戦い敗北した。そのためフィリピンなどの植民地を失いスペイン植民地帝国はほぼ崩壊した。この米西戦争の敗北は、かつてのスペイン帝国が完全に終わったことを意味し、スペイン人に強い衝撃を与え、「98年世代」といわれるスペインの危機を強く自覚した思想や文学も生まれた。一方では工業化の遅れは顕著であり、残された植民地モロッコに対する依存が高まっていく。
1898年 米西戦争の敗北
スペイン政府はそれを認めず弾圧を強化すると、カリブ海方面に進出を策していたアメリカ帝国主義が介入し、1898年2月のメイン号事件を口実に、1898年4月から米西戦争が開始された。現地の情勢は不利であったが、国内での反発を恐れたサガスタ首相は敗戦覚悟で戦争に踏み切り、はやり敗北した。この敗北は国民に「スペイン帝国の終焉」を自覚させ、スペインの知識人、ウナムーノ、オルテガ=イ=ガセットなどに大きな衝撃をあたえ、「スペインとは何か」を問う「1898年の世代」を生み出した。スペイン社会の動揺は……ヨーロッパが19世紀末の凡庸ながら華やいだ頽廃の日々を送っていた頃に表面化してきた。深刻な精神的な変化の到来を予想させる徴候は以前から数多くあったものの、変化が明確な形をとったのはようやく1898年の米西戦争における敗戦という体験を経て後のことであった。敗戦を境にそれまでの政府当局者の浮薄な楽観主義や、街頭で繰り広げられる安っぽい愛国精神の示威に代わって深刻な挫折感がスペイン全体を覆った。このときスペイン人の一部はこれでスペイン史に一段落がつき、次いでこれまた取るに足らない別の時代が始まるのだと単純に考えた。しかし、他方では祖国の現状に屈辱と恥辱を覚えたスペイン人もいた。こうした人々は民族主義の旗を高く掲げるか、あるいは国際的な革命運動の道をとるかその方法は異なるにせよ、スペインを断固変革せずには置かないことを固く心に誓った。祖国変革のためにとるべき道については彼らの意見はさまざまであったが、目の前の現状――そこでは政府をはじめ社会や国民生活全般がことごとく悪趣味と愚昧に毒され、欺瞞に満ち、マンネリ化し、怠惰に陥っていた――を放置すれば、スペインは必ずや滅亡に至るだろうという点では一致していた。<ビセンス・ビーベス/小林一宏訳『スペインー歴史的考察―』1962原著 1975 岩波書店刊 p.189-190>このときもちあがった疑問は「スペインとは何なのか」ということだった。それはカステーリャである、アフリカである、あるいは単なる空想の所産にすぎないなどの答えが出された。しかし敗戦を味わった悲劇の世代が一致して断言したのは、第一にこのときのスペインの実情は彼らの意にそぐわないものであり、次ぎになんとしてでもスペインのヨーロッパ化をはかる必要があるということである。しかし同時にスペインの未来図が、カステーリャ人、カタルーニャ人、さらにバスク人などで異なっていた。知識人の論争、文学や歴史学の中にも「今後スペインが国家として存続していくにはどうあるべきか」という点で見解の相違が明確になっていった。「1898年の世代」と言われた若い知識人が抱えた問題はそこにあった。
バルセロナの「悲劇の一週間」
米西戦争の敗北後も政党間の対立は続き、国王アルフォンソ13世の調停の場面が大きくなり、国王も積極的に政治に介入するようになった。それに対して特に工業化が進んだカタルーニャでは第1インターナショナル以来、アナキストの影響が強く、労働運動が先鋭化していた。1909年、スペインに残された植民地の一つモロッコで民族運動が高まり、反乱が起こった。保守党のマウラ首相は軍隊を動員してその鎮圧に命じたが、7月にスペイン(9) 第一次世界大戦とスペイン
スペインは第一次世界大戦では中立の立場を取り参戦しなかった。国内の工業化は進んだが、植民地モロッコの反乱、労働問題が深刻となり、その反動として1923年~1930年には王政のもとでのプリモ=デ=リベラの独裁的傾向の政治も登場した。一方、王政や独裁政治に反対し共和政を求める声が強まり、1931年にスペイン革命によってスペイン共和国(第二共和政)が誕生する。しかし、資本家・軍部と結んだ保守派と、労働者の支持する共和派の対立はなおも激しくなっていく。
中立策
スペインは第一次世界大戦では中立を宣言し、列強が総力戦を戦う間、モロッコの鉄鉱山開発を進めた。戦時好景気でインフレーションとなったが、賃金が追いつかず労働者・農民の生活は困窮した。そのため労働組合運動はさらに活発になり、社会労働党系のUGT、アナキスト系のCNTが力をつけてきた。ロシア革命の成功に刺激を受けた労働者は、1917年8月、ゼネストに打って出て共和政実現の政治要求を掲げて闘ったが、政府は戒厳令を布いて鎮圧した。ボリシェヴィズムの影響を受けた農村でも、1918~20年までスペイン南部で「ボリシェヴィキの三年」といわれる運動を展開した。1917~23年はスペイン立憲王政にとって危機的な状況となり、争乱が相次いでついには軍事独裁政権を出現させる。「スペイン風邪」は誤解 第一次世界大戦の末期の1918年に、「スペイン風邪」がヨーロッパの戦線でひろがり、さらに世界中に流行して約15万の死者が出た。そのれによって戦争の終結が早まったと言われている。この感染症は、現在ではインフルエンザであったことが判っており、当時から現在まで「スペイン風邪」といわれているが、実はスペインが発生源ではなかった。当時は戦争中であったので各国とも報道統制を行い、罹患者数を公表しなかったが、中立国であったスペインは報道規制を行っていなかったので、この新型インフルエンザがスペインを中心に流行している、と誤解されたのだった。実際には1918年3月にアメリカ・カンザス州陸軍キャンプで発生し、アメリカ軍によってヨーロッパ戦線にもたらされたものだった。<岡田晴恵『感染症は世界史を動かす』2006 p.212-214>
モロッコの反乱
スペインはジブラルタルの対岸のセウタを1580年以来、ポルトガルから継承して領土としていたが、1859~60年にセウタで境界紛争を口実にモロッコに出兵、モロッコ戦争(アフリカ戦争とも言う)を引き起こし、61年に通商条約を締結した。1904年にはフランスとの間で勢力圏を分割、北モロッコと西サハラを「スペイン領モロッコ」として支配していたが、1920年にリーフ地方の首長、アブデル=クリムがスペインに対する反乱を開始した。このリーフ戦争では、1921年7月のアヌアルの戦いで1万2千のスペイン軍が敗れ、シルベストレ将軍が殺されるという事態となった。アブデル=カリムは1923年にリーフ共和国の独立を宣言し、スペインのモロッコ支配は大きく揺らぐこととなった。プリモ=デ=リベラの軍事独裁
モロッコの危機の打破を国内に軍事政権を樹立することで打開しようとした軍人のプリモ=デ=リベラは1923年9月12日夜、カタルーニャに戒厳令を布き、臨時軍政府の樹立を宣言した。立憲君主政下の政府がテロリストと分離主義者を放置し、社会的混乱を招いたとして議会と政党、政府を非難し、憲法を停止して議会を解散するという強硬手段に出たのだったが、国王アルフォンソ13世はそれを容認し政府を守らなかった。こうして実質的な軍事独裁政権が成立した。この軍事独裁政権によってモロッコのアブデル=クリムが自立して建てたリーフ共和国に対する総攻撃をフランスと共同で展開し、1926年頃までにリーフ戦争を制圧した。しかし、この政権はわずかに職能代表制(コーポラティブ)国家を標榜しただけで、統一的な国家理念や独裁を支える国民組織、青少年組織などをもたず、リベラ自身も過渡的な独裁体制と考えていたので厳密にはファシズムとは言えなかった。それでも順調な経済成長を背景に長期政権となることができた。しかし、1926年になると独裁打倒の運動が始まり、共和主義者、社会主義者、労働組合の連携が生まれていった。知識人のウナムーノやオルテガ=イ=ガセットも独裁反対の声を上げた。1929年に起こった世界恐慌がスペインに及んだのは、1931年頃で、直接独裁政権に影響をあたえたわけではないが、世界的経済不安の中、1930年1月国王と軍の信任を失ったプリモ=デ=リベラは辞任した。
スペイン(10) 第二共和国とスペイン戦争
1931年のスペイン革命で共和政国家となったが、ファシズムが台頭、それに対抗して1936年2月に人民戦線内閣が成立した。同時に軍部の反乱が開始され、スペイン戦争(内戦)となる。イギリス・フランスが不干渉政策をとり、政府軍にはソ連と国際義勇兵が支援したが、ドイツ・イタリアが支援したフランコの率いる反乱軍が39年春までに全土を制圧した。その間フランコ独裁体制が成立、それが第二次世界大戦後にも続く。
1931年のスペイン革命
プリモ=デ=リベラ退陣後、国王アルフォンソ13世は国王親政体制を復活させようとしたが、すでに広範な王政反対、独裁政治反対の意識の高まりが進行していた。次第に焦点は立憲政治か共和政治か、という点に移った。1930年8月には、共和党・急進党・社会党・カタルーニャ党左派の指導者がサン=セバスティアンに集まり王政反対の革命委員会がつくられた。これはブルジョワ政党と社会主義穏健派が共和政実現を目指すと同時に、共産主義やアナーキストを押さえつけるための同盟として組織されたものであった。1931年4月、国王派が命運を賭して選挙に踏み切ると、農村の市町村選挙ではなおカシケの締め付けが強く、国王派が優勢だったが、マドリードでは50議席中30議席を共和派が占めるなど都市部では共和派が勝利を占めた。それをうけて4月14日には各地で共和国宣言が出され、国王アルフォンソ13世はあっけなく退位を表明、フランスに亡命した。このスペイン共和国は、1873~74年の第一共和政に対して第二共和政といわれている。
ファシズムの台頭
ヨーロッパは1929年の世界恐慌に巻き込まれ、ヴェルサイユ体制という第一次世界大戦後の国際秩序が崩壊した。その震源地はドイツであった。1933年に政権を獲得したヒトラーは10月に国際連盟を脱退し、1935年にはいるとザール編入、再軍備(徴兵制=義務兵役制復活)を立て続けに実行し、36年にはラインラント進駐を強行してヨーロッパの安定を脅かした。一方、イタリアではすでに20年代に登場していたムッソリーニは、1935年にエチオピア併合に乗り出していた。そしてアジアにおいては日本の軍部が独走して満州事変を起こして中国侵略を開始、国内では1936年2月の二・二六事件が起こった。この二・二六事件と同じ年にスペイン戦争が勃発している。このような世界的なファシズムの 台頭に対し、民主主義と自由、そして平和を守ろうという目的から、ブルジョワ共和派から労働者の社会主義運動までの幅広い反ファシズム勢力が団結して当たろうという人民戦線の運動がフランスやスペイン、その他で活発となってきた。それを受けて1935年にはコミンテルン第7回大会が人民戦線戦術をとることに転換し、共産党もそれに従った。
1936年のスペイン戦争は、1930年代の激しい世界情勢と1931年に始まったスペイン革命以降のスペインの激動と深く関わっている。以下、1931年のスペイン革命から、1936年のスペイン戦争までのスペインの動きをまとめると、次のようになる。
スペイン革命の苦悩
1931年にスペイン共和国が成立、スペイン革命が始まった。 6月の憲法制定議会選挙では共和派が多数を占めヴァイマル憲法 に範をとった共和国憲法が制定され、主権在民、戦争の放棄、国家と教会の分離、貴族の廃止、23歳以 上の男女普通選挙制度、一院制国会(コルテス)、カタルーニャの自治などを規定した。共和国政府は、信教と結社の自由、基本的人権保障、農地改革などを公約した。しかし、このころからおうやく世界恐慌の影響がスペインにおよび、スペイン経済は輸入超過、資本流出、通貨不安が深刻となった。第二共和政政府は内部の政治勢力間の対立とともにこの深刻な課題に対応しなければならなかった。政府は軍隊の将校の削減や教育を教会から切り離すための公費での学校建設などを進めたが、土地改革、農地解放には着手できなかった。
世界恐慌の波がスペインに及んできて、農村不況は深刻になり、不況が続く中、ストライキが続いていた。下層農民や労働者の間にアナーキストや共産党の影響が強まると、地主や資本家や教会は革命を恐れて、左派を抑えるための強力な政府の出現を望むようになった。そのような中で、「ファランヘ・イスパニョーラ」(後のファランヘ党)となど、ナチスを手本とした反共産主義、反議会主義、ユダヤ人排斥、軍国主義などをかかげたファシズム政党が台頭した。
暗い二年間
1933年11月の総選挙は23歳以上の男女普通選挙で行われたが、共和派は後退し、右派が勝利を占めた。1934~35年はファシストも入閣した右派内閣のもとで「暗い二年間」といわれる反動期となった。共産党やアナーキストに対してだけでなく、社会主義者や共和主義者にも弾圧が及んだので左派は危機感を抱き、統一戦線の結成を目指すようになった。1934年10月には、アストウリアスの労働者がファシストの暴力に対抗してゼネストに入り、自発的に武装蜂起するという「アストゥリアスの蜂起」が起こった。これはモロッコから動員された政府軍によって鎮圧されたが、スペイン人民戦線の成立の契機となった。1935年にはコミンテルン第7回大会がそれまでの方針を転換し、共産党に対しブルジョワ政党や社会主義者とも共闘して反ファシズム人民戦線を構築することを指示した。内戦の始まり
共和派と社会党、共産党、それにアナーキストの一部などの左派はファシズムの台頭に対抗するため1936年1月、スペイン人民戦線を結成した。2月に行われた総選挙では選挙協定を行って勝利し、人民戦線内閣が成立した。それに対して1936年7月、軍とファシストが各地で反乱を開始した。モロッコを拠点にフランコ将軍が反人民戦線政府の挙兵を宣言、本土に侵攻しスペイン内戦(戦争)が開始された。フランコ率いる反乱軍は、本土を北上し、スペイン西部を制圧したが、政府はバルセロナに移って抵抗し、スペインはほぼ東西で分断される内戦となった。スペイン戦争
フランコ軍に対してはヒトラーのナチスドイツとムッソリーニのファシスト党政権のイタリアが積極的に軍事支援を行った。政府もイギリス・フランスなど各国に支援を要請したが、ソ連がそれに答えて航空機や地上軍の支援を行ったが、イギリスはソ連と共闘することをきらい支援を拒否、フランス人民戦線のブルム内閣は、当初支援を決定したが、閣内での反対が強かったため、結局イギリスに同調して不干渉政策を取った。政府の不干渉政策に反発したイギリス・フランス・アメリカなどの社会主義者、自由主義者、共産党員などは個人の資格でスペイン支援に立ち上がり、国際義勇軍として政府軍を支援する動きが強まり、コミンテルンも義勇軍を募集し、国際旅団を結成して組織化した。このように、スペインの内戦は、単なる内戦にとどまらず、「スペイン戦争」という様相を呈していた。スペイン戦争は反乱を開始したフランコらの予測に反して長期化し、結局1939年春まで継続した。それは、ドイツ・イタリアがベルリン=ローマ枢軸を形成する契機となり、また特に再軍備を終えたドイツ軍にとってはその力を試す機会となり、第二次世界大戦の予行演習と言われる戦争となった。1937年4月26日のドイツ軍によるゲルニカ空爆は、第二次世界大戦でのロンドン、重慶、ドレスデン、東京、広島、長崎などと続く無差別戦略爆撃の最初の例となった。国際情勢が複雑に絡み合い、同時に人民戦線内部でも共産党と反共産党グループ、アナーキストなどの対立は「内戦の中の内戦」といわれるほど深刻な対立となった。
フランコ独裁政権
反乱軍を指揮したフランコは、ヒトラーとムッソリーニの支援を受けて最終的には1939年3月28日にマドリードを占領してスペイン戦争を反乱軍の勝利に終わらせ、人民戦線政府は亡命することとなった。戦争の過程ですでに1936年10月には国家主席として独裁的権力を獲得し、軍部とファランヘ党というファシスト、カトリック教会などを基盤としたフランコ体制を築き上げた。この体制は、ファシズムに近いが、ヒトラーやムッソリーニような強固な組織や国家理念をもつわけではなかった。しかし、フランコは第二次世界大戦では中立政策をとって注意深く巧妙に立ち回り、直接的な戦禍を避けることによって、独裁体制を維持することに成功した。スペイン(11) フランコ独裁体制
世界大戦中、中立の態度を保持したため、戦後もフランコの独裁体制は温存された。その死去によって1975年、ようやく独裁政権が終わり、立憲君主国として民主化が始まった。
戦後のフランコ体制
スペインでは戦前の1936年のスペイン内戦以来、フランコ独裁政権が続いていた。フランコはファランヘ党を基盤にファシズム体制を敷き、反対派を弾圧した。第二次世界大戦では一時ヒトラーの要請で義勇兵を派遣したが、ドイツの敗北後は路線を転換してローマ教皇やアメリカに接近して戦後も独裁支配を継続した。フランコ長期政権の存続理由
国際連合からはその政権としての正統性が否定されて加盟が認められず、国際的には孤立せざるを得なかった。また、国内では社会主義や労働運動はほぼ押さえ込み、ブルボン朝王政を復活させようとする運動に対しては、フランコは終身統領となり、その後継者に王家の後継者ファン=カルロスを指名するなどの巧妙な手段によって切り抜けた。また東西冷戦の時代となり、アメリカはスペインをヨーロッパにおける反共勢力に組み込もうという意図のもとにフランコ政権を公認し、それらが戦後の国際社会で、隣国のポルトガルのサラザール政権と共に長期独裁政権を存続させる要因となった。
NATO加盟は認められず しかし、対共産圏の軍事同盟である北大西洋条約機構(NATO)は「自由と人権の擁護」を掲げていたので、独裁国家スペインはNATO加盟国とは認められなかった。ただし、1953年にはアメリカと相互防衛協定を締結してその支援を受け、冷戦構造の中での西側諸国としての位置づけられた。
またフランコ政権はアメリカとの経済的結びつきを強め、 国内では大資本を保護して経済を成長させた。その結果、その在任中、大規模な反独裁運動は起こらなかったが、経済成長とともに政治的自由を求める市民層が成長し、彼らは次第に他の西欧諸国なみの自由や政治参加を求めるようになり、フランコ独裁体制を批判するようになった。
ポルトガルの変化 その動きは1968年に隣国ポルトガルの独裁者サラザールが引退し、1974年にポルトガル革命が起こり、民主化が開始されたことに刺激され、スペインでも民主化運動が始まった。
スペイン(12) スペインの民主化と現在
1975年にフランコ独裁体制が終わり、民主化が始まるとともにブルボン王家が復活。民主化、経済成長に勤めている。1982年には左派政権が生まれた。
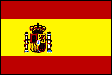 ポルトガルを除いたイベリア半島の多く範囲を占める国。面積は日本の約1.3倍で、人口は約4500万。首都はマドリード。現在は立憲君主政で、国民の大半はカトリックであるが、憲法上は信仰の自由は保障されている。
ポルトガルを除いたイベリア半島の多く範囲を占める国。面積は日本の約1.3倍で、人口は約4500万。首都はマドリード。現在は立憲君主政で、国民の大半はカトリックであるが、憲法上は信仰の自由は保障されている。フランコ死去と王政復帰
1975年にフランコが死去すると、11月に国王ファン=カルロス1世(1931年のスペイン革命で亡命したブルボン朝アルフォンソ13世の孫)が即位して王政を復活させた。ファン=カルロス1世は立憲君主制の下で民主化を認め、スアレス首相の下で改革が進んだ。共産党も合法化され、1977年には41年ぶりに総選挙が実施され、1978年には新憲法が成立した。現代のスペイン
1982年の総選挙では社会労働党が勝利して、43年ぶりとなる社会主義政権であるゴンザレス内閣が成立した。民主化の定着と、国内政治の安定を実現させた上で、1985年にはNATOに加盟、1986年にはポルトガルとともにヨーロッパ共同体(EC)に加盟した。2004年にはサパテロの率いる社会労働党(PSOE)による左派政権が成立した。国内にはバスク地方の独立運動があり、しばらくテロ活動もやんでいたが、2007年「バスク祖国と自由(ETA)」がふたたび過激な活動を宣言し、緊張が高まっている。また
News 闘牛離れ進むスペイン
スペインの国技ともいえる闘牛が、カタルーニャ州で禁止されることになった。かつてはスペイン各地に闘牛場があり、3月~10月のシーズンに、3人の正闘牛士が2回ずつ、6頭の雄牛と対決、赤い布で巧みに牛をかわし、最後は刺殺するという興行が行われていた。しかし、動物愛護団体の抗議が強まったことでスペイン国民の闘牛離れが始まっており、現在ではテレビ中継なども行われなくなっている。1991年にカナリア諸島で初めて闘牛が禁止され、2010年11月にカタルーニャ州でも、2012年から禁止することが決まったのだ。闘牛存続を求める人々は、闘牛はスペインの伝統的な芸術だ、として興行を続けることを主張しているが、州議会の採決でも禁止派が多数を占めた。「スペインといったら闘牛!」という私たちの常識は通用しなくなりつつあるようだ。









