イラン/イラン系民族
西アジアから中央アジアまで広く活動したインド=ヨーロッパ語族。アケメネス朝、パルティア、ササン朝の大帝国を成立させペルシアとも言われた。ゾロアスター教など独自の文明を発展させたが、7世紀にイスラーム化した。16世紀サファヴィー朝からはシーア派国家となり、20世紀にパフレヴィー朝が成立、1935年に国号をイランとした。第2次世界大戦前後から産油国として列強の介入が強まり、パフレヴィー朝の親欧米政策への民衆の反発を背景に1979年にイラン革命が起こり、イラン=イスラーム共和国と改称し、シーア派宗教主導の国家となった。現在は核武装をめぐり、アメリカなどとの対立を強めている。
- (1)古代のイラン系国家
- (2)イラン系民族のイスラーム化
- (3) イスラーム化後のイラン
- (4) シーア派国家の成立
- (5) 18~19世紀イランの混乱
- (6)20世紀前半 パフレヴィー朝
- (7)第二次世界大戦後のイラン
- (8)イラン革命
- (9)核開発から核合意へ
※イランの歴史の概要
イランとペルシア
イラン人はインド人と同じくインド=ヨーロッパ語族に属するアーリヤ人の一分派で、紀元前2千年紀に南ロシアのステップ地帯から南下し、イラン高原に入ったらしい。その過程でイラン高原西部のメディア人、東部のペルシア人などに分化した。後にペルシア人のアケメネス家が全イランを統一したので、イランとペルシアは同義語となった。世界史上は現在のイランだけではなく、中央アジア、西アジア、北インドにかけて広く活動していた民族であり、ゾロアスター教に代表される独自のイランの伝統文化の源流を成立させた。アケメネス朝とセレウコス朝
前6世紀からは、イラン高原南部のペールス地方を拠点としたペルシア人の国家であるアケメネス朝が有力となり、イラン高原からメソポタミア、小アジアを含む西アジア一帯に及ぶオリエント世界を統一して、世界帝国を作り上げた。この最初の世界帝国であるペルシア帝国は、エジプトを征服、中央アジア、インダス川流域を統治下に入れ、中央集権による皇帝専制国家を実現させた。前6世紀末からギリシアへの進出を図ったがペルシア戦争でギリシアのポリス連合軍に敗れて失敗し、前4世紀末にはアレクサンドロス大王の東方遠征によって征服されて消滅した。アレクサンドロスの帝国の成立によって、ギリシア文明とオリエント文明の融合したヘレニズムが生まれ、イランの伝統文化もその中に取り込まれていった。パルティアとササン朝
その後もヘレニズム諸国のセレウコス朝シリアの支配が続いたが、前3世紀にイラン高原北部の遊牧イラン人アルサケスが建てたパルティアが自立して、次第にヘレニズムの影響を脱しイラン文化を復興させた。パルティアは東方では大国クシャーナ朝と接し、西方では新たに起こったローマ帝国とも並び立つ事となり、東西交易路を押さえて繁栄した。しかし、その後はアルメニアをめぐってローマと激しく対立するようになり、次第に国力を衰退させていった。紀元後226年、農耕イラン人のササン朝ペルシアがパルティアに替わって西アジア全域を抑え、かつてのアケメネス朝の帝国支配とイランの伝統文化を再興した。ササン朝ペルシアもローマ帝国と西部国境で激しく争ったため、次第に国力が衰えた。このことが、アラビア半島に興ったイスラーム教の勢力が、西アジアに急速に広がる前提となった。イスラーム化以降のイラン
7世紀に東方に進出したイスラーム教は、正統カリフ時代の642年にニハーヴァンドの戦いでササン朝ペルシア軍を破り、それによってササン朝は急速に衰え、651年に滅亡、イラン高原はイスラーム化することとなった。イラン人はイスラーム帝国のアラブ人の支配者を受けることとなったが、その伝統的文化はイスラーム帝国下でも尊重され、イラン文化とイスラーム文化は融合しイラン=イスラーム文化が生み出された。その後もトルコ人のセルジューク朝、モンゴル人のイル=ハン国、ティムール朝といった他民族支配が続くが、それらのイスラーム教国でもイラン人は官僚などとして重用された。シーア派国家イラン
16世紀にイラン人の国家としてサファヴィー朝が成立するが、ここからはイスラーム教シーア派国家として独自の道を歩み、西のオスマン帝国、東のムガル帝国というスンナ派イスラーム教国と抗争を続ける。近代においては石油資源が発見されたことによって、イギリス・ロシアの帝国主義国家がイランに進出したため苦境に立たされたが、20世紀にパフレヴィー朝が独立を回復、1935年には国号をイランとした。パフレヴィー朝は、第二次世界大戦後に世俗化、欧米化を進めたが、それをアメリカへの従属政策であるとして反発したシーア派宗教指導者ホメイニらが1979年に決起し、イラン革命を起こし、パフレヴィー朝は倒され、シーア派主体のイスラーム宗教国家イラン=イスラーム共和国が成立、現在に至っている。イラン(1) 古代のイラン系国家
アケメネス朝ペルシア
イラン人はアッシリア帝国及びメディア王国の支配を受けていたが、前6世紀に自立してキュロス2世が前550年にメディアを滅ぼし、アケメネス朝ペルシアを建国、新バビロニア、エジプトを征服して西アジアに大帝国を建設した。その本拠地がイラン高原のファールス地方だったので、彼らはペルシア人とも言われた。ペルシア帝国はイラン高原とその周辺のメソポタミア、小アジア、エジプトなどの西アジア全体を支配する世界帝国として繁栄し、前6世紀末のダレイオス1世(大王)は都のペルセポリスとスサを結ぶ王の道を中心とした駅伝制を整備、全土を州に分けてサトラップを置き、中央から王の目、王の耳を派遣するなど中央集権支配を行い、全盛期となった。アケメネス朝の王はいずれもゾロアスター教を信奉したが、他の宗教(ユダヤ教など)にも寛容であった。しかし独自の文字を持つことはなく、王の業績を記した多数の石碑を遺しているが、それらはオリエント古来の楔形文字で記されている。民間では商業民族のアラム人が活動し、商取引ではアラム文字が使われていた。ダレイオス1世は、前492年からギリシア遠征を企てペルシア戦争を起こしたが、失敗した。次のクセルクセス1世も前480年から数度にわたって遠征軍を送ったが、ギリシアのアテネを中心としたポリス連合軍に敗れ、ギリシアを征服することはできなかった。アケメネス朝ペルシアはその後も西アジアに大きな勢力を維持し、ギリシアのペロポネソス戦争に介入したりしていたが、内紛が起こるなど次第に弱体化していった。
ヘレニズムの時代
前4世紀後半にはギリシア北方から興ったマケドニアのアレクサンドロスの侵攻を受け、前330年にペルシア帝国は滅亡した。アレクサンドロスの大帝国は前323年、大王が急死した後、ディアドコイと言われる後継者たちによる争いによって分裂、イラン高原を含む西アジアはセレウコス朝シリアが支配した。この国はヘレニズム三国の一つであり、ギリシア人(マケドニア人)が支配していたが、そのもとでギリシア人とイラン人の融合が進み、ヘレニズム文化が形成された。
イランの復興 パルティア
セレウコス朝の支配下にあったイラン高原北部の遊牧イラン人であるパルティア人が次第に自立の勢いを示し、前247年ごろパルティアを建国した。パルティアの王は、初めは「ギリシア人を愛するもの」という称号をもつなどヘレニズムの影響が強かったが、次第にゾロアスター教の信仰などのイラン文明を復興させていった。しかしパルティアはゾロアスター教を国教としたわけではなく太陽神を信仰するミトラ教なども行われた。パルティアが後半の都としたクテシフォンはティグリス河畔にあり、次のササン朝時代を通じて政治経済の中心となった。紀元後1~2世紀には、パルティアの東方にはクシャーナ朝のカニシカ王があらわれ、勢力は均衡した。一方西方では、地中海世界を統一したローマがオリエントにも進出する勢いを示すようになった。ローマ軍との戦いでは、前53年に侵攻したローマの将軍クラッススを破っている。その後も中間地帯であるアルメニアを巡ってローマと激しい抗争が続き、次第に国力を失わせ、衰退した。注意 セレウコス朝とパルティアの時代はイラン史から除外されることが多い アケメネス朝とササン朝の間に挟まれたセレウコス朝とパルティアはヘレニズム色が強く、イラン文明が衰えた時期とされることが多く、イラン史の中でも特異な時期として捉えられ、極端な場合はイラン史から除外されることもある。宮田律氏の『物語イランの歴史』(中公文庫)、最近の青木健氏の『ペルシア帝国』でもセレウコス朝とパルティアについてはほとんど記事がない。
イランの全盛期 ササン朝ペルシア
226年に農耕イラン人がササン朝ペルシアを建国した。ササン朝の成立事情は不明な点が多いが、初代アルデシール1世はアケメネス朝ペルシアの国家理念を受けつぎ、ゾロアスター教の主神アフラ=マズダの代理人として統治するという姿勢を復活させた。その立場からこの時代にゾロアスター教が国教として確立したと言うことができる。次のシャープール1世は、そのころバビロンに始まったマニ教の布教を許可し、一時ゾロアスター教は後退した。シャープール1世は260年のエデッサの戦いでローマ帝国皇帝ウァレリアヌスを捕虜としている。5世紀には中央アジアから遊牧民エフタルの侵入を受け、484年には敗れて一時衰えた。
6世紀のホスロー1世は、そのころ東方の中央アジアに興ったトルコ系の突厥と結んでエフタルを挟撃し、危機を脱した。さらにホスロー1世は西方のビザンツ帝国と互角に戦った。またこの時、聖典アヴェスターが編纂されるなど、ササン朝の文化が開花した。イラン文化はシルクロードを通じて、日本を含む東アジアにも影響を与えた。
中央アジアのイラン系民族
一方、モンゴル高原で活動していた月氏もイラン系とする説が強い。彼らは匈奴に追われて紀元前2世紀の前半に、パミール高原を超えて移住し、大月氏国を建てた。漢の武帝が匈奴を挟撃するために張騫を派遣した国である。この西トルキスタンからカスピ海東岸一帯の草原地帯ですでに活動したイラン系遊牧民族は月氏に押されて南下し、パルティアとともにインドに侵入した。彼らはインドではサカ(シャカ)族と言われている。なお、大月氏に支配されていたバクトリア地方の一部族であったクシャーナ人が自立し、1世紀に北インドに入ってクシャーナ朝を建てたが、彼らもイラン系と見られている。また中央アジアのソグディアナを拠点に5世紀ごろから活動が目立つようになるソグド人もイラン系である。彼らはオアシスの道(シルク=ロード、絹の道)での交易に従事し、唐の都長安でも活動していた。イラン(2) イラン系民族のイスラーム化
アラビア半島に起こったイスラーム教が波及し、7世紀後半からイラン系民族のイスラーム化が進んだ。
イスラーム化の開始
長期にわたるビザンツ帝国との抗争は次第にササン朝の国力を奪い、7世紀の前半、アラビア半島のアラブ人の中で起こったイスラーム教勢力がササン朝領に侵攻を開始、642年のニハーヴァントの戦いに敗れて急速に弱体化し、651年に滅亡した。それによってイラン人のイスラーム化が急激に進むこととなり、イランおよび西アジア史は大きく転換する。イラン人はササン朝の国教であったゾロアスター教徒が多かったが、彼らはイスラーム教徒から「啓典の民」として扱われた。イスラームの教えは階級や貧富の差を超えて「平等」と「統一」を説いたので、ササン朝の専制支配と階級支配のもとにあった多くのイラン人は、イスラームに改宗していった。ウマイヤ朝時代にアラビア語が帝国の公用語とされたため、ペルシア語にアラビア語の要素が入るようになり、文字もアラビア文字が使われるようになった。
シーア派とイラン ウマイヤ朝の成立に伴って、イスラーム教徒の中にカリフの地位をめぐって分派であるシーア派が生まれた。イランのムスリム(イスラーム教徒)のなかにはシーア派が多かったがその事情は、4代目正統カリフのアリーとムハンマドの娘ファーティマの間に生まれたフサインが、捕虜となったササン朝の王女と結婚したという伝説があったからであった。ゾロアスター教からイスラーム教に改宗したイラン人は、アリーの血統のなかにササン朝の王家の血が流れているとして、シーア派を支持したのだった。
イランにおけるイスラーム国家
750年のアッバース朝の成立にはホラーサーン地方のイラン人が大きな役割を果たし、大臣や官僚としてその政治を支える者も多かった。アッバース朝カリフもイラン人に大いに依存したので、首都をイランに近いバグダードに設け、ササン朝王宮の伝統を復活させた華麗なものとした。9世紀、アッバース朝が衰退すると、イラン人やトルコ人でアミールに任命されたものが地方王朝を樹立するようになり、イランではまず東部にターヒル朝、次いでサッファール朝が生まれ、中央アジアではサーマーン朝(9~10世紀)が登場、特にサーマーン朝はイラン高原も併合して最初の実質的な独立王朝となり999年まで続いた。一方、カスピ海南岸から起こったイラン系ブワイフ朝は946年、バグダードに入りアッバース朝カリフから大アミールの称号を与えられて軍事政権を樹立した。
イラン(3) イスラーム化後のイラン
9~15世紀、イスラーム化したトルコ系王朝、モンゴル系王朝の支配下で、イラン人は文化の担い手となり、イラン=イスラーム文化を開花させる。
トルコ系王朝・モンゴル系王朝とイラン人
9~10世紀にトルコ系民族がモンゴル高原周辺から移動して中央アジアに入って定住化すると、イラン人もトルコ語を話すなど中央アジアのトルコ化が進み、トルコ人支配層に同化してトルキスタンという呼称が成立した。こうしてイラン人はトルコ化したが、ガズナ朝やセルジューク朝などトルコ系国家でも重要な役割を果たした。その後イランは12世紀末から13世紀にかけて、北方のホラズム王国に支配され、次いでモンゴルのフラグの遠征によってイル=ハン国が成立するとその支配下に入った。15世紀は、中央アジアから起こったティムール朝の支配下に入った。イラン=イスラーム文化の発展
この間、イラン人は政治的には被支配民族に甘んじることとなったが、その文化的伝統から官僚や学者、芸術などでは依然として中心的な役割を果たし、イラン=イスラーム文化を生み出した。イスラーム化したイラン人は、イスラーム諸王朝のもとで、主として官僚やイスラーム法学者など知識人として遇された。それはイラン人はアケメネス朝以来の長い国家統治の経験を持ち、文化伝統を持っていたからであり、征服者であるアラブ人もイラン人をその方面で活用しようとした。同じくイスラーム化したトルコ人が、主として軍人(マムルーク)としてイスラーム諸王朝に活用されたのと好対照である。そのようなイラン人の例として、11世紀のトルコ系のセルジューク朝の宰相として活躍したニザーム=アルムルク、13世紀後半のイル=ハン国の政治家であり、『集史』を編纂した学者でもあったラシード=アッディーンらがあげられる。
イラン(4) シーア派国家の成立
16世紀、イスラーム神秘主義教団がイランを支配し、シーア派国家サファヴィー朝が成立する。
サファヴィー朝
ティムール朝(スンナ派)の衰退に従って、アゼルバイジャンで台頭したのがイスラーム神秘主義の中から生まれた神秘主義教団の一つのサファヴィー教団だった。サファヴィー教団は、小アジアのトルコ系遊牧民からなる騎馬部隊キジルバシュを軍事力としして急速に力を増し、イランに侵攻した。1501年、イランのタブリーズを征服した教団の教主イスマーイール1世はサファヴィー朝の建国を宣言し、イラン人の伝統的な君主の称号であるシャーを称した。その際、シーア派の分派である十二イマーム派を国教とすることを宣言した。教主であるイスマーイール1世は、十二イマーム派の信仰である「隠れイマーム」の代理人と称した。
それまでイラン人はイスラーム教のスンナ派が多数であったが、サファヴィー朝成立を機に、シーア派国家に転身した。また、当初の神秘主義教団としての性格は次第に薄れ、シーア派信仰による統治が強められていった。イマームに代わってイスラーム教徒を指導する存在としてアラブ人のシーア派イスラーム法学者であるウラマーが招かれ、シーア派の学校も多数作られるようになった。このようなサファヴィー朝のシーア派による国づくりは、隣接する有力なスンナ派のオスマン帝国やシャイバニ朝に対抗する意味もあった。
サファヴィー朝は、16世紀末から17世紀初頭のアッバース1世の頃、全盛期となりその新都イスファハーンは「世界の半分」と言われる繁栄を誇った。しかし、このころからポルトガルなどヨーロッパ人の勢力が西アジアに及び始めた。
イラン(5) 18世紀イランの混乱
18世紀にサファヴィー朝が衰退、トルコ人やアフガニスタン人が侵攻。1779年、トルコ系のガージャール朝が成立。しかし南下政策をとるロシア、インド確保をめざすイギリスがそれぞれイランに進出する。イラン人もタバコ=ボイコット運動などで抵抗し、1905年の立憲革命で立憲君主制国家となった。
アフガン人のイラン支配(1722~29)
サファヴィー朝はアッバース1世没後、シャーは政治を顧みずハーレムにこもり、アル中になる者もあらわれ、宦官が実権を握るようになった。まず、サファヴィー朝のシーア派信仰強制に反発したアフガニスタンのアフガン人ギルザイ族がカンダハールを占領。またヘラートでは同じアフガン人のアブダリ族が反乱を起こした。サファヴィー朝には反乱を鎮圧する力が無く、ギルザイ族のマフムードはアブダリ族の反乱を鎮圧した後、1722年に首都イスファハーンを包囲し、6ヶ月の攻撃の後に占領し約8万人を殺害した。マフムードはイラン王を称してスンナ派政権を樹立した。スンナ派の抑圧を避けるために、シーア派聖職者はオスマン帝国領のナジャフやカルバラーに移った(現在のイラクにシーア派が存在するのはこのためである)。アフガン人のイラン支配は全土には及ばず、サファヴィー朝の後継者タフマースプ2世を擁して抵抗を続けた。1726年、オスマン帝国が介入してイランに侵入し、同じスンナ派であることからアフガン人との間で和議を結びイランを分割支配することとなった。サファヴィー朝の再興(1729~36)
そのころタスマースプ2世はトルコ系のカージャール族の支援を受けていた。その中の一部族の中のナーディルが1729年にイスファハーンに進軍してアフガン勢力を追い出しタスマースプ2世を即位させ、サファヴィー朝を再興させた。しかし実権はアフガン人を撃退し、アゼルバイジャンなどでオスマン帝国軍を破ったナーディルが握った。アフシャール朝(1736~96)とザンド朝(1750~94)
ナーディルは1736年にサファヴィー朝のシャーを退位させ、ナーディル=シャーを名乗ってアフシャール朝を開いた。アフシャール朝では国教をスンナ派に転換させ、シーア派ウラマーを追放した。しかしその治世は戦乱が続いて国土が荒廃し、農民にも重税が課せられたので反発を受け、1747年にナーディルも殺害された。イランのスンナ派化も失敗し、民衆のシーア派信仰はそのまま続いた。その結果、アフガニスタンにはアフガン人がドゥッラーニー朝を自立させ、イランにはザンド朝が成立する。イランのザンド朝は一時、安定した支配を行うが、まもなくトルコ系のガージャール朝に滅ぼされる。ガージャール朝(1779~1925)
カスピ海沿岸に興ったトルコ系ガージャール族の族長アーガー=ムハンマドは1779年にガージャール朝を創始。イスファハーンを攻略し、1786年にテヘランを首都とした。ガージャール朝は1794年にザンド朝を、1796年にアフシャール朝を滅ぼし、イランはトルコ系の王朝によって統一された。日本では「カージャール」と表記されていたが、現在はペルシア語発音に従い、ガージャールと表記する。)ロシア・イギリスの侵略、始まる ガージャール朝の時代にはロシア、イギリスなど西欧諸国の侵出が始まり、とくに南下政策を強めたロシアとの2度にわたるイラン=ロシア戦争によって、カフカス地方のグルジア、アゼルバイジャン、東アルメニアなどを奪われた。また1828年のトルコマンチャーイ条約でロシアに不平等条約を強制された。またインドを支配するイギリスもイランを支配下におこうとして干渉を強め、1840年にイギリス=イラン通商条約を締結した。
ガージャール朝の内部では、1848年7月にはシーア派の分派バーブ教徒の反乱など不安定な状況が続くなか、19世紀末にイギリスの経済支配に反発するタバコ=ボイコット運動などの民族運動が起こり、ガージャール朝も1905年の立憲革命で立憲国家の形態をとることとなった。
しかし、ロシアとイギリスは、ドイツの西アジアへの進出に対抗するため、1907年に英露協商を締結し、ロシアが北部に、イギリスが東南部に互いに利権を認めたものであった。このようにガージャール朝のイランはヨーロッパ列強の力を背景にした進出によって翻弄される事態が続いた。
イラン(6) パフレヴィー朝イラン
20世紀初め、油田が発見され、イギリスが利権獲得。第一次世界大戦後、1921年にレザー=ハーンのクーデターでパフレヴィー朝が成立。1935年に国号をイランに変更した。
石油資源の発見
18世紀末からイランを支配したトルコ系のガージャール朝はロシアとイギリスの帝国主義諸国の侵略を受け、1907年に両国は英露協商で勢力圏を分割した。1908年にイラン南部のフーゼスタン州で最初の油田が発見され、翌年にはイギリス系のアングロ=イラニアン石油会社が設立され、その利権を所有した。イランは石油の産出地として注目されるようになり、さらに1913年、イギリス海軍が艦船の燃料を石炭から石油に変えたため、イギリスはイランへの支配を強めた。パフレヴィー朝
第一次世界大戦が始まるとオスマン帝国軍が侵入、ドイツ軍も諜報活動を展開し、イギリスも中立地帯に出兵した。これらの情勢にガージャール朝政府は対応出来ず、無政府状態が続く中、1921年にレザー=ハーンがクーデターを起こして実権を握り、1925年には自らシャー(国王)を称し、パフレヴィー朝を創始した。これはイギリスの意向があったといわれる。<宮田律『物語イランの歴史』2002 中公新書>国号をイランに変更
パフレヴィー朝は、1935年3月には正式な国号をイランとした。これはゾロアスター教の聖典アヴェスターからとったことばであった。イランは石油の産出国であったため、列強の関心を強めていた。第二次世界大戦中、パフレヴィー朝イランは首都テヘランを中立地帯として、北方の5州をソ連が、南方の諸州をイギリスが管理するという、南北分割下に置かれた。しかし、独ソ戦の開始によってイギリスとソ連は提携することとなり、連合国はイランを通ってソ連に援助物資を送って、その対独戦争を支援していた。1943年、アメリカのF=ローズヴェルト、イギリスのチャーチル、ソ連のスターリンの三巨頭がはじめて顔を合わせたテヘラン会談が、イランで開催されたのはそのような事情があった。
イラン(7) 第二次世界大戦後のイラン
第二次世界大戦後、パフレヴィー朝のモサデグ首相による石油国有化運動が進められたが、1953年にクーデターでモサデグ政権が倒され、パフレヴィー2世による上からの近代化策である白色革命が始まる。
モサデグの石油国有化政策
首相に就任したモサデグは1951年5月に石油国有化を断行し、中東で初めて植民地会社を追放し自国資源を自国が受益することに成功した。しかしモサデグ政権はイギリスによる国際市場でのイラン原油締めだしと内部対立のため、1953年8月19日にイラン=クーデターで倒され、パフレヴィー2世が復権し、石油資源も国際資本の合弁会社で管理されることになった。Episode イランを助けた日本の石油会社 -日章丸事件-
イランが石油国有化を宣言し、イギリスがイラン原油を世界市場から閉め出そうとしたとき、イランから原油を買い付けようとした日本人がいた。出光興産の出光佐三は、日本独自のエネルギー源確保は戦後日本の経済復興にとって不可欠であると考えた。そこで国際石油資本(メジャー)から閉め出され、格安でも原油の輸出先を探していたイラン国営石油会社と直接交渉し、両者は合意に達し契約を交わした。こうして出光佐三はタンカー日章丸をイランに派遣、1953年5月、当時シンガポールはイギリスが統治していたのでマラッカ海峡は通らず、スンダ海峡を経由して川崎港に帰ってきた。これは独立を回復した直後の日本と、真の独立を目指すイランの両国の心意気を示すものとして賞賛され、その後の日本とイランの友好な関係のきっかけとなった。<宮田律『物語イランの歴史』2002 中公新書 p.159-164>シャーによる白色革命
パフレヴィー朝シャーによる独裁政治を復活させたパフレヴィー2世は極端な親英米政策をとり、「白色革命」という急激な近代化政策を進めた。それは国民生活を犠牲にして、国際石油資本に屈服することを意味していたので、国民の信望を失っていった。イラン(8) イラン革命・イラン=イスラーム共和国
1979年にイラン革命によって十二イマーム派を国教とする宗教国家イラン=イスラーム共和国となった。80年代、隣国イラクとの戦争で疲弊したが、対米強硬路線を続け、核開発を主張している。
イラン革命
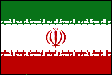 1979年2月、イスラーム教シーア派の指導者ホメイニの指導するイラン革命が起こり、パフレヴィー朝は倒れ、イラン=イスラーム共和国が成立した。
1979年2月、イスラーム教シーア派の指導者ホメイニの指導するイラン革命が起こり、パフレヴィー朝は倒れ、イラン=イスラーム共和国が成立した。イラン=イスラーム共和国は、大統領(初代はバニサドル)を公選する共和制国家であるが、革命指導者ホメイニの「ヴァラーヤテ=ファギーフ(イスラーム法学者による統治)」の思想によって主権は神(アッラー)にあるとされ、実際の国家の最高意志決定は、イスラーム教シーア派の十二イマーム派の聖職者から公選される専門家会議で選出される最高指導者があたる政教一致の国家体制をとっている。 → イランのシーア派
第2次石油危機
イランは当時、サウジアラビアに次ぐ世界2位の産油国であったが、1979年1月に国王が亡命すると、その保護のもとにあったメジャーズ(国際石油資本)は資源を残したまま撤退し、革命政権は石油国有化を実現させた。革命政権は資源保護を目的に原油輸出を停止し、OPECも同調して増産に慎重な姿勢を取ったため、世界的な原油不足となり、1973年の第4次中東戦争の時の第1次石油危機に次ぐ、第2次石油危機が起こった。アメリカとの関係悪化
革命直後の1979年、イランが亡命したパフレヴィー前国王の身柄引き渡しを要求したのに対してアメリカが拒否したため、イランの革命勢力はテヘランのアメリカ大使館を襲撃し大使以下を人質に立てこもるというアメリカ大使館人質事件が起こった。人質解放交渉は難航し、アメリカのカーター大統領はヘリコプター特殊部隊による救出作戦を決行したが失敗した。イラン=イラク戦争
ホメイニによるイスラーム信仰(シーア派)にもとづく厳しい統制がおこなわれる国家の出現は、西欧諸国大きな衝撃を与えた。しかし、この国家は、隣国イラクのサダム=フセインが革命に乗じて石油資源を狙って侵攻してきたため、1980年9月から88年に渡る長期間のイラン=イラク戦争に突入することになり、苦難が続くことになる。イランと関係が悪化していたアメリカは、革命の波及をおそれて、このときイラクを支援した。ホメイニ後のイラン
1989年にホメイニが死去してからは最高指導者はハメネイとなった。大統領は1997年の選挙で解放路線を掲げたハタミ(またはハーターミー)が当選し、イラン革命当時のような日常生活での宗教的な締め付けはかなり緩くなったと言われるが、依然としてイスラーム原理主義的な宗教理念を基本とした政治が行われている。イラン(9) 核開発から核合意へ
イラン=イスラーム共和国は2000年代に入っても対米強硬路線を続け、アメリカはイランが核開発を進めていると非難し経済封鎖に踏みきり、関係は更に悪化した。一時、核疑惑は解消に向かい、2015年にはイラン核合意が成立し、翌年アメリカは経済制裁を緩和した。しかし2018年、アメリカのトランプ政権が核合意から離脱したため、イランは核開発を拡大し、再び関係は悪化している。
イラン核開発とアメリカの経済封鎖
2002年にはアメリカのブッシュ(G.W.)大統領はイランがウラン濃縮施設を運営していると判明したとして、核開発を行う「悪の枢軸」の一つと名指して非難した。そのためイランとアメリカとの関係は極端に悪化した。2005年の大統領選挙では対米強硬論者、反西洋文明を訴えたアフマディネジャドが、穏健派ラフサンジャニを破って当選、新大統領はアメリカに対する警戒を強め、核開発をアメリカに対する平等な権利であると主張して推進しようとしている。ただし、イスラエルと異なり、核拡散防止条約(NPT)に留まって国際原子力機関(IAEA)の査察を受けいれることも表明し、イラン核開発問題は解決に向かう機運をみせた。その背景には2006年に始まったアメリカが主導する国連安保理決議にもとづく経済封鎖がイラン経済に打撃をあたえ、国民の中に対米強硬路線の転換、統制の緩和を支持する声が強まり、2013年8月に穏健派の新大統領ロウハニ師(聖職者)が当選した。国家の最高指導者は依然として反米姿勢が強いと言われるハメネイ師であり、対米関係の改善には困難が予想されたが、ロウハニ政権は積極的に交渉を行った。
イラン核合意
2015年7月14日、核保有国5ヵ国(アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国)とイランの核開発に関係深いドイツの6国およびEUと、イランとの間で、イランの核開発を制限することと見返りとしての経済制裁を解除する「包括的共同行動計画」を策定することで合意が成立した。この「イラン核合意」成立は、NPT(核不拡散条約)を実効のあるものとしたアメリカ大統領オバマの平和志向外交の成果として評価された。核合意に基づいてイランは核兵器に利用される高濃縮ウラン貯蔵量を10万トンから300キロに削減すること、高濃度ウランとプルトニウムの生産は15年間は行わないことなどの核能力削減の実施を約束、2016年1月にIAEA(国際原子力機関)がイランの核施設削減を確認したことを受け、アメリカやEUは金融制裁、イラン原油取引制限などの経済制裁を解除した。しかし、イランと厳しく対立するイスラエルはこの合意ではイランは制限されながら核開発を続けることが出来るし、弾道ミサイルの開発制限が盛り込まれていない、として反発した。
アメリカが離脱
2017年1月、アメリカ大統領にイスラエルと関係の深いトランプが就任したことから事態は一変した。トランプ政権は2018年5月8日にイラン核合意からの離脱を宣言、経済制裁の再開に踏み切った。同じ5月14日、アメリカ大使館をイェルサレムに移転している。イラン側も態度を硬化させ、2019年5月に核合意の一部履行停止を宣言し、核開発の事実上の拡大を表明した。イラン情勢は急速に緊迫し、トランプ政権が中東に空母を派遣、B52戦略爆撃機を投入してイランに軍事的圧力をかけると、6月20日、イラン革命防衛隊はアメリカ軍の無人機を撃墜したと発表、トランプ政権もただちに報復攻撃を承認して一触即発という危機になったが、このときはトランプ大統領が承認を撤回して衝突は回避された。
その前の5月~6月にかけて、ペルシア湾入口のホルムズ海峡で、6隻のタンカー(うち1隻は日本の海運会社が運航していた)が何者かに襲撃され損傷する事件が起き、日本でも第3次の石油危機になるのではないかという危惧が持たれた。しかしこの襲撃についてはイラン軍は関与を否定した。
日本の自衛隊派遣
日本政府は、イラン原油への依存度が高いことからホルムズ海峡の安全確保を最優先にしながら、イランとの長い友好関係もあり、一方でトランプ政権への協力の姿勢も見せなければならないという困難な立場に置かれた。安部首相は2019年6月12日にイランを訪問、イランのロウハニ大統領も12月20日に来日するなど活発な工作が行われ、両者の対立を回避が目指されたが、一方で12月27日、安倍内閣は自衛隊を中東に派遣することを閣議決定した。アメリカ軍、イラン革命防衛軍司令官を殺害
イラク戦争後もイラクに駐留を続けているアメリカ軍(およびイギリスなどの連合軍)は、2011年ごろからシリア・イラク国境地帯で出現したイスラーム過激集団イスラム国に対する鎮圧を行い、2017年ごろまでにほぼ制圧した。しかし、イラク国内にはシーア派も多く、その中の親イラン組織がイランと結んでアメリカ軍をしばしば攻撃することが続いた。それに対してトランプ大統領は2020年1月3日、イラン革命防衛軍のソレイマニ司令官をドローン攻撃で殺害した。アメリカの発表によるとソレイマニはそれまでの対アメリカ軍ミサイル攻撃の中心にいた司令官であるとしている。イラン国民の人気の高い軍人であったことから、イランの反米感情はさらに高まった。NewS 難航する間接協議
2021年、アメリカに成立した民主党バイデン政権は、トランプ共和党政権で悪化したイランとの関係修復に乗りだし、2021年4月からイラン合意復活のためのアメリカ=イランの間接協議(EU、英仏などが仲介)が始まった。しかし、アメリカの対イラン制裁事項は1500件に及んでおり、その一斉解除を要求するイランとの合意は困難ともされており、交渉は進捗していない。一方で制裁によって通貨価値が下落し物価騰貴などの経済低迷が続くイランにとっても外合意による制裁解除は不可欠の状況になっている。8月にはイランでは対米穏健派に代わって強硬派のライシ政権が成立、9月には国際原子力機関(IAEA)の各関連施設への立ち入りを拒否しており、間接協議は進んでいない。<2021.10.3 朝日新聞など>






