ロシア
ロシアの歴史の概略 9世紀のノルマン系ルーシの南下と東スラヴ人との同化によって形成された国家。一時モンゴルの支配を受けたが15世紀のモスクワ大公国の独立以来、東ヨーロッパの大国として成長し、現代では世界最初の社会主義国となった。
- (1)ロシア人、ロシア語とロシア暦
- (2)ロシア国家の形成
- (3)タタールのくびきとモスクワ大公国
- (4)ロマノフ朝の大国化(ロシア帝国)
- (5)近代ロシアの矛盾
- (6)ロシアの帝国主義
- (7)第一次世界大戦とロシア革命
- (8)ソ連邦・スターリン体制
- (9)ロシア連邦
ロシア(1) ロシア人、ロシア語とロシア暦
ロシア人は東スラヴ系のスラヴ人であるが、歴史過程のなかでゲルマン系、アジア系との融合が進み、現在のロシア人となっている。
ロシア人とロシア語
ロシア人とロシア語はインド=ヨーロッパ語系・スラヴ人の中の東スラヴ人に属している。しかし現在のロシアも含めてロシア国家を構成しているのは、ほぼ80%をしめるロシア人とアジア系などの民族であり、多民族国家である。またロシア人は現在のロシアだけでなく、ウクライナやカザフスタンにも多数居住している。ロシア語はスラヴ語の一つだが、語順がないことやBe動詞は省略が可能なこと、冠詞がないことなどきわめて自由な言語という特徴を持っている。その語彙にはギリシア・ローマ起源のものとタタール・トルコ起源のものが多い。ギリシア・ローマ出自の言葉(例えばツァーリ)が多いのは、ギリシア正教を受容したからである。また馬車の御者をヤムーシチクと言うが、それはモンゴル語の駅伝制度、ジャムチからきた言葉であるという。
なお、キエフ公国が没落し、その後多くの封建諸侯に分裂、やがてモスクワに中心が移りモスクワ大公国が台頭する過程で、東スラヴ人の言語的統一は失われ、モスクワ中心の大ロシア人、キエフ中心の小ロシア人(ウクライナ人)、西部のベロロシア人(ベラルーシ人)の三つに分かれた。
ロシア語を書き表す文字は、ロシア人がギリシア正教を受容してからキリル文字が使用されるようになり、現在に及んでいる。
ロシア暦
キリスト教改宗以前のルーシでは太陰太陽暦が用いられていたようで、その名残は三月を白樺月、五月を草月、七月を鎌月、十月を落葉月といったスラヴの古い月の名前に残っている。キリスト教受容と共に10世紀から太陽暦のユリウス暦を取り入れ、月の名前をローマ風にし、1週7日も受け容れた。紀元はビザンティン紀元で、これはローマ開市から754年目の年を天地創造から数えて5509年と見るものである。だから『原初年代記』(ロシア最古の歴史書)では、キリスト教受容の年(988年)は6496年と表記されている。当時西欧ではキリスト誕生紀元が一般化していたので、ルーシは暦の上で独自の世界をなすこととなった。また年のはじまりをローマからの伝統で3月1日としていたが、モスクワ大公イヴァン3世の治世の1492年に9月1日からとするように改められた。そして、西欧化に熱心であったピョートル1世(大帝)は、ロシア暦7208年12月31日の翌日を1700年1月1日とし、かつそれを年の初めとした。天地創造紀元をキリスト誕生紀元に改めたのであるが、しかしユリウス暦のままであった。18世紀末までに西欧新教国もローマ教皇グレゴリウス13世が創始したグレゴリウス暦が採用されると、正教の国ロシアのみは孤塁を守る形になったのであるが、そのためズレが生じ、ロシア暦は18世紀には11日、19世紀には12日、20世紀には13日、グレゴリウス暦より遅れることとなった。そのためロシア革命でのロシア暦二月革命は現行暦では三月革命、十月革命は十一月革命となる。革命後にグレゴリウス暦が採用され、1918年に同年1月31日の翌日を2月14日とされて現在に至っている。従って革命前の年代については注意を要する。以上の説明は<和田春樹『ロシア・ソ連』地域からの世界史11 1993 朝日新聞社刊 p.23>などによる。
ロシア(2) ロシア国家の形成
9世紀のノルマン系リューリクの率いたルーシが南下し、スラヴ人と同化して、ノヴゴロドに最初の国家をつくった。これがロシア国家の起源であるが、次いでさらに南下してキエフ公国が成立し、スラヴ化が進み、ギリシア正教に改宗する。それによってビザンツ帝国の後継国家としての性格が強くなる。
ロシア国家以前の状況
現在のロシアが、まだロシアと言われていなかった時代、現在の南ロシアの黒海北岸からカスピ海北岸の広大な草原には、スキタイ人が遊牧生活を送り、草原の道(ステップ=ロード)で東西交易のルートの一つとなっていた。古代ギリシア人はその地をスキュティアと呼んでおり、ヘロドトスの歴史にも情報が出てくる。しかし彼らの実態はよくわかっていない。1世紀のなかばごろ、中央アジアからフン人が移動してきて、さらに西に向かっていった。それに押されて草原の西にいた東ゴート族などのゲルマン人が移動を開始した。それが4世紀である。草原の北のドニェストル川とドニェプル川にはさまれた森林地帯にいたのがゲルマン人と同じインド=ヨーロッパ語族に属するスラヴ人であった。トルコ系民族の移住
6世紀ごろ、再び東方から民族移動の波が押し寄せ、トルコ系のハザール人がカスピ海北岸のヴォルガ川下流域に定住生活をはじめた。このハザール=カガン国は8世紀にイスラーム勢力に敗れ、イスラーム教を受容、商業活動を活発におこなって9世紀にはユダヤ教を受容した。さまざまな宗教が混在するロシアの歴史的背景の一つとして最近注目されている。また黒海北岸には同じくトルコ系のブルガール人がいたが、彼らはハザール人に圧迫されてバルカン半島に南下し、現在のブルガリアを建国した。なおその時ブルガール人の一部は分かれて北東に向かい、ヴォルガ川中流に移動してヴォルガ=ブルガール王国を建国した。この国は後にキプチャク=ハン国の支配を受けた後、自立してカザン=ハン国となった。このトルコ系民族はモンゴル人と同化してタタール人と言われるようになる。南ロシアの草原から中央アジアにかけてはトルコ系遊牧民の活動の舞台であった。ロシアの起源
第2次民族移動と言われるノルマン人の移動の一部として、9世紀の中ごろ、リューリクに率いられたノルマン系のルーシと言われた人々(彼らはヴァリャーグとも言われた)が、バルト海沿岸から内陸に入り、スラヴ人の居住地域に入って行き、862年にノヴゴロド国を建設した。ここからロシアが始まるとされており、ルーシから「ロシア」の名称が生まれたという。キエフ=ルーシ リューリックの死後、その一族オレーグはさらに南下して現在のドニェプル川中流域を支配して、882年にキエフを占領してキエフ公国をつくった。これによってノヴゴロドとキエフを南北に結ぶ広大な国家が生まれた。これは現在のロシアとウクライナを含む地域であり、ロシア史上は「キエフ=ロシア」と言われている。キエフ=ルーシのもとでノルマン系のルーシとスラヴ系のロシア人の同化が進んだ。
ただしノヴゴロド国もキエフ公国もロシアの歴史に加えられているが、現在の「大国ロシア」とは異なり、ノヴゴロド国時代もキエフ公国時代も一地方政権に過ぎないことに注意すること。ロシアという国号が正式に生まれるのは18世紀初めのピョートル1世の時代の「ロシア帝国」からであり、またソ連に継承される領域がロシア領となった。ピョートル1世の時、白・青・赤の三色旗が使われるようになった。スラヴ人と同化していった。
キエフ公国
キエフ公国は、リューリク以来の王を戴いていたので、リューリク朝ともいうが、そのもとでスラヴ化が進んだ。その最盛期の988年、キエフ大公ウラディミル1世はギリシア正教に改宗し、ビザンツ帝国の制度や文化を取り入れて中世国家としての形態を整えた。しかし、その社会は農民の農奴化が進み、大土地所有者となった諸侯が地方に分立する状態が続いた。キエフ公国はその後、南の黒海北岸に進出したトルコ系ポロヴェツ人の侵攻を受けたり、一族の内紛が起こってキエフの東方のウラディミルを都としたウラディミル大公国が分離するなど、弱体化した。そのような状況の下で13世紀のモンゴル軍の侵攻を受け、1240年に滅亡することとなった。
ロシア(3) タタールのくびきとモスクワ大公国
1240~1480年、タタールのくびきの時代が続く。ロシアの封建諸侯はその支配下にあったが、その中のモスクワ大公が次第に有力となり、1480年イヴァン3世の時に独立を達成した。16世紀後半にはイヴァン4世がツァーリを称し、農奴制を基盤としたツァーリズム体制をつくりあげた。
モンゴル軍の侵攻とタタールのくびき
モンゴル帝国のオゴタイ=ハンは、1237年にバトゥの指揮する大遠征軍をロシアに派遣した。この侵入はヨーロッパに大きな脅威となった。モンゴル軍は1240年にキエフ公国を滅ぼし、さらに1241年のワールシュタットの戦いでポーランドなどのキリスト教国連合軍を破った。しかしオゴタイ=ハンが病没したため、遠征はそこで中止され、バトゥは1243年には南ロシアにキプチャク=ハン国を建てた。モンゴルの支配は、納税を強制した他は、各地方政権の自治を認め、比較的緩やかな支配であった。同じころ、ノヴゴロド公アレクサンドル=ネフスキーは西方からの脅威であるスウェーデンやドイツ騎士団と戦って勝利している。むしろ西からの脅威の方が深刻であったのであり、そのためモンゴル人とは関係を良好に保とうとした。この1240年に始まるモンゴルの支配をロシア史では「タタールのくびき」と言い、1480年まで続く。モスクワ大公国
アレクサンドル=ネフスキーの子のダニールは1283年からモスクワを拠点とし、モスクワ公国となる。モスクワ公国は次第にキプチャク=ハン国からの自立(納税しないこと)をめざし、ハン国の弱体化もあって次第に力をつけていった。15世紀にモスクワ大公国といわれるようになり、そのイヴァン3世が1472年にビザンチン最後の皇帝の姪ソフィア(ゾエ)と結婚し、ビザンツ帝国の後継者としての権威を獲得した。またイヴァン3世は1480年にキプチャク=ハン国からの独立を果たし「タタールのくびき」を脱した。さらに地方政権を抑えてロシアの統一を達成し、近代のロシア国家の基礎を築いた。しかし独立を回復してからも、ポーランドやリトアニアなどの西側からの圧迫は続いていた。こうしてモスクワはロシアの中心としての地位を獲得、ローマ・コンスタンティノープルに次ぐ「第三のローマ」とさえ言われるようになった。ツァーリ国家の成立
モスクワ大公イヴァン4世は大貴族の勢力を抑えて、専制的な権力の集中に努め、1547年にツァーリを称する。ツァーリはイヴァン3世が一時的に用いていたが、ロシアの支配者の称号として正式に(恒常的に)用いられるようになったのはイヴァン4世からである。イヴァン4世は、オプリーチニナという親衛隊を組織し、残虐な手法により大貴族層を抑圧して恐怖政治を行い、雷帝(グローズヌイ)と言われた。これ以降のロシアの強大な皇帝専制政治をツァーリズムという。またヴォルガ流域のタタール人のカザン=ハン国、さらにアストラハン=ハン国などのアジア系国家を征服したが、ポーランド・スウェーデンとの戦争は長期にわたったが戦果を得ることができず、念願のバルト海進出はできなかった。ただその晩年にイェルマークが1581年から開始したシベリア遠征が行われ、ロシア商人が毛皮などを求めて東方進出の発端となった。
ボリス=ゴドゥノフ 1581年11月、イヴァン4世はふとした口論から皇太子を撲殺するという悲劇が起こった。1584年にイヴァン4世が死去すると、まもなくリューリク朝は断絶し、1598年に大貴族で親衛隊長だったボリス=ゴドゥノフがツァーリに選出されたが、貴族間の抗争が続いて混乱し「動乱の時代」となった。ポーランドの介入もあってモスクワは危機に陥ったが貴族連合がポーランド勢を撃退して、新たにミハイル=ロマノフをツァーリに選出し、ロマノフ朝が開始される。
ロシア(4) ロマノフ朝のもとでの大国化(ロシア帝国)
17世紀に始まるロマノフ朝は18世紀、ピョートル1世とエカチェリーナ2世というツァーリズム専制君主制の下で全盛期となり、領土を四方面に拡張、後のソ連邦、ロシア連邦の基盤を作った。
ロマノフ朝の成立
1613年に成立したロマノフ朝は、モスクワ大公国の貴族層が、イヴァン4世死後の動乱時代のポーランドなどの外国の干渉から国家を守るという意識で結束し、その共同の利害を代表するものとして全国会議でわずか16歳のミハイル=ロマノフが皇帝に選出されて始まった。貴族の共同統治という面が強かったが、17世紀中ごろの第2代アレクセイのとき、1670年に農民反乱ステンカ=ラージンの反乱を鎮圧して、農奴制の強化に成功し、また徐々に西欧的な国家機構の整備を進め、貴族世襲制の国から官僚制・常備軍に支えられた絶対主義国家へと変貌していった。またアレクセイの時にはリトアニアに奪われていたウクライナ(かつてのキエフ公国)の東部とキエフを奪還した。キエフはロシア国家の発祥の地であったので、ロシアはその故地を回復したことになるが、それだけに留まらず、先進的な文化を有し西側に開かれた都市を獲得したことはロシアの発展にとっては重要な意味があった。ピョートル1世
ピョートル1世(在位1682~1725)は17世紀末にツァーリとなり、自らヨーロッパ各国の視察を行い、積極的な西欧化政策を推進した。特に西欧の技術者を多数招聘し、産業の近代化に力を入れた。ロシアが西欧諸国に互していくためには、バルト海に進出する必要があると考え、バルト海沿岸に面して新都のペテルブルクを建設し1712年に遷都した。その間にバルト海の覇権をめぐって1700年からスウェーデンとの北方戦争を戦い、一時は敗北を喫したがそれを機に軍備を整え、ポルタヴァの戦いに勝利して1721年、ニスタットの和約で有利な講和を結んだ。その結果、ロシアは「バルト海の覇者」と言われるようになった。東方ではシベリア進出を推し進め、1689年に清の康煕帝との間でネルチンスク条約を締結した。これは清に有利なものであったが、初めてアジアにおける国境線の画定であった。またベーリングを派遣してカムチャツカ、アラスカ方面を探検させ、ロシアの東方進出の足がかりを作った。南方ではオスマン帝国からアゾフを獲得し、黒海方面への突破口としいわゆる南下政策を開始した。このピョートル大帝の時が実質的なロシアの出発点であり、後のロシア帝国の繁栄、それを領土的には継承したソ連邦、そして現在のロシア連邦のもととなったといえる。「ルーシ」に代わって「ロシア」が正式な国号となるのもこの時である。
ツァーリ専制政治の混乱
女帝エリザヴェータ 1725年にピョートル大帝が死去した後、ツァーリの継承での混乱が続いた。皇后のエカチェリーナ(1世)、孫のピョートル2世、姪のアンナと次々に交替し、さらにアンナの姪のアンナの子イヴァン6世が即位すると、わずか生後2ヶ月だったのでその生母のアンナが摂政となった。その間、ドイツ人の宮廷官僚が政治を主導するようになった。1741年11月、ピョートル1世の娘エリザヴェータはフランスとスウェーデンの公使と結び、近衛部隊を動かしてクーデタを断行、冬宮に入り摂政アンナを逮捕して即位した。貴族政治と農奴制の展開 エリザヴェータ女帝(在位1741~1761)は父のピョートル1世を模範とした絶対君主制を再建しようとして内閣制を廃止し、皇帝官房を設置して貴族政治に戻した。また製鉄業や酒造業などの商工業育成も図った。しかしツァーリ政治と貴族社会を支えるロシアの農奴制はこの時期にもっとも強まり、農奴に対する虐待は最悪の事態を招いた。
対外的には、オーストリア継承戦争(1740~1748)ではオーストリアのマリア=テレジアと同盟し、同じくオーストリア側に付いたイギリスがフランスと戦うにあたり援軍を送った。次の七年戦争(1756~1763)でもオーストリアを支援しプロイセンのフリードリヒ2世と戦った。
エカチェリーナのクーデタ 七年戦争の最中にエリザベータ女帝が死に、後継には姉の子がピョートル3世として即位した。ピョートルはプロイセンのフリードリヒ2世を尊敬していたので、オーストリアとの同盟を破棄したため七年戦争はプロイセン不利の情勢が一挙に逆転し、オーストリアの敗北で終わった。このような定見のないピョートル3世は人格的にも未熟なところがあり、1762年、その妻であったドイツのホルシュタイン家出身のエカチェリーナが宮廷官僚と近衛部隊を動員してクーデタを敢行、ピョートル3世を幽閉して女帝として即位した。
エカチェリーナ2世
エカチェリーナ2世(在位1762~1796)は啓蒙専制君主として改革や文化の保護にあたり、一方ではポーランド分割に加わるなどで領土を拡大した。アメリカの独立戦争に対しては武装中立同盟を提唱してその独立を助けた。この女王の時代はフランス革命、イギリスの産業革命が展開した時期であって、ロシアでも近代化を急がなければならない状況であったが、革命の勃発は避けねばならず、エカチェリーナはもっぱら上からの改革、つまり啓蒙専制君主としての改革を進めることとなった。外交面では1768年にオスマン帝国とのロシア=トルコ戦争(第1次)を開始し、1783年にクリム=ハン国併合、 した。また1772年に第1回ポーランド分割を主導して、領土の拡張を図った。1773年に大規模な農民反乱であるプガチョフの反乱が勃発したが、それを鎮圧した後はさらに反動的になる。ロシア(5) 近代ロシアの矛盾
19世紀のロシアはロマノフ朝のもと、保守反動の中心勢力となった。しかし国内では自由と民主化を求める運動も始まった。東方問題の対立から起こったクリミア戦争で敗北し、近代化をめざす上からの改革をおこなったが、それは不十分であり、間もなくツァーリ専制政府は再び膨張政策に転じ、国内矛盾を深めることになった。
アレクサンドル1世(在位1801~25年)
ナポレオンのモスクワ遠征を迎え撃ったロシアは大きな危機に陥ったが、粘り強い抵抗によって撃退に成功、アレクサンドル1世の評価は高まった。続いてアレクサンドル1世はウィーン会議に参加してナポレオン戦争後のヨーロッパ国際政治で活躍し、その優位な立場を利用してポーランド立憲王国の実質的な支配を獲得した。このウィーン体制の時期にはロシア・ロマノフ朝のツァーリズムは保守反動勢力の中心として、神聖同盟の盟主となり、ヨーロッパの民族運動、自由主義運動を弾圧して「ヨーロッパの憲兵」と呼ばれた。同時にイギリスが提唱した四国同盟にも加盟し、フランス包囲網の核となった。しかし、フランス革命とナポレオンの持ち込んだ自由主義と国民国家の概念はヨーロッパの東方にも波及して行き、ロシアもその影響を受けるようになった。この時期はロシアの膨張と国内矛盾が進行していた。デカブリストの反乱 自由主義、民族主義は貴族層にも影響を与えた。ナポレオン軍を追ってパリに入り、パリの自由な空気を知った青年将校を中心とした貴族の一部は1825年12月に、アレクサンドル1世が急逝しニコライ1世が慌ただしく即位した混乱に乗じて専制政治(ツァーリズム)を倒そうと反乱を起こした。このデカブリストの反乱は、民衆的な広がりがなく、鎮圧されてしまったが、ロシアの革命運動の出発点となった。
ニコライ1世(在位1825~55)
ニコライ1世はバルカン半島・黒海方面から地中海へ進出することによってヨーロッパ列強に互していくことを目指したが、他の列強との東方問題といわれる利害の対立が深刻になっていった。1821年に始まったギリシア独立戦争ではニコライ1世は南下のチャンスと捉えてギリシア支援に乗り出し、1827年、イギリス・フランスとの連合艦隊でオスマン艦隊をナヴァリノの海戦で破り、1829年、オスマン帝国とアドリアノープル条約を結んで黒海北岸を割譲させた。1830年のロンドン会議でギリシアの独立は認められ、オスマン帝国の権威は大きく低下、ロシアの南下の条件がそろった。エジプト=トルコ戦争 1831年に第1次エジプト=トルコ戦争が始まるとそれまでの敵対していたオスマン帝国の要請を受けてエジプトと戦った。その関係で1833年、ウンキャル=スケレッシ条約を結び黒海とダーダネルス=ボスフォラス海峡のロシア艦隊の航行権が認められ、他国の軍艦の通行は禁止された。1839年、第2次エジプト=トルコ戦争でもロシアはオスマン帝国を支援したが、ロシアの進出を警戒する列強によって1841年、5国海峡協定(ロシアの他にイギリス、フランス、オーストリア、プロイセン)が締結され、ウンキャル=スケレッシ条約は破棄されて海峡は再び閉鎖された。
西アジアへの侵出 西アジア方面ではカフカス地方からイラン方面に侵出を企て1804年、1826年にイラン=ロシア戦争を繰り返し、1828年に不平等条約トルコマンチャーイ条約を押しつけた。並行して1821年からのギリシア独立戦争を支援するとともに、1828年には露土戦争を再開してオスマン帝国と単独で戦った。
クリミア戦争 ヨーロッパ各地で起こった1848年革命によってウィーン体制は終わりを告げたが、ロシアはツァーリズムが存続する中、大国意識が次第に顕著になって行き、南下政策を強め、ロシアの膨張政策を警戒するイギリスとフランスとの対立が深刻化した。フランスのナポレオン3世がオスマン帝国にイェルサレムの聖地管理権を要求して認められたことにたいし、ニコライ1世は、オスマン帝国領内のギリシア正教徒の保護を理由に反発し、両者の対立は1853年にクリミア戦争となった。クリミア戦争の最中にニコライ1世は死去しアレクサンドル2世に代わった。
アレクサンドル2世(在位1855~81年)
クリミア戦争ではロシア軍の装備の遅れなどが明らかとなって英仏軍に敗れて、バルカンと黒海方面での南下政策は一時頓挫した。新皇帝アレクサンドル2世の課題はロシア内部の近代化と、バルカン方面に代わる、新たな膨張先であった。そのいずれもツァーリズムの専制政治を維持する上では不可欠と考えられた。しかし近代化はあくまで専制支配のためであったので「上から」なされるべきものであり、ツァーリの権威を高めるための膨張政策は続けなければならず、その矛先は中央アジア方面への侵出と東アジアへの侵出に向いていった。上からの改革 クリミア戦争の敗北によってロシアの後進性が改めて問われることになった。その答えがアレクサンドル2世の1861年、農奴解放令などの改革であった。この「上からの改革」によって、社会改革に向かったが、ツァーリズム体制内の改革には限界があった。
ナロードニキ運動 アナーキズム思想の影響を受けた知識人(インテリゲンツィア)は農村に入って社会の変革を目指すナロードニキ運動を始め、農村共同体であるミールに入り込んで運動したが、やがてその限界を感じ、一部には直接行動で政体を変換させようとするテロリズムに走るようになった。
露土戦争 1870年代、再び南下政策を強めたアレクサンドル2世は、1877年~78年、オスマン帝国との間でキリスト教徒の保護を口実に露土戦争を起こして勝利しサン=ステファノ条約でバルカンに大きな足がかりを作った。しかし、イギリス・オーストリアなどの反対を受け、1878年、ドイツのビスマルクが主催したベルリン会議での調停を受け入れ、ブルガリアの縮小など、バルカン半島方面への侵出は抑えられた。これ以降、バルカン方面における南下政策の性格は、スラヴ系諸国家を支援するというパン=スラヴ主義に転換させていく。
中央アジアへの侵出 オスマン帝国、イランと並んで中央アジアのアフガン王国にも盛んに介入した。ロシアの中央アジア侵出に対抗してイギリスもアフガニスタンに進出、2次に渡るアフガン戦争をへて、1879年にアフガニスタンを保護国化した。
東アジアへの侵出 ロシアの東アジア侵出は清との国境問題を新たな問題としてもたらした。東シベリア総督ムラヴィヨフは1858年の愛琿条約で黒竜江左岸を獲得し、さらにアロー戦争で清朝のイギリス・フランスとの講和を斡旋した見返りとして1860年、北京条約を締結して、沿海州の領有を認めさせた。これによってロシア領土は日本海岸に達し、ウラジヴォストークを建設し、日本海方面、さらに朝鮮半島と満州への進出の足場を築いた。1870年代には再びバルカン方面への進出をねらい露土戦争でオスマン帝国に勝利したが、ベルリン会議(1878)によって西欧列強の干渉を受けたために再び後退を余儀なくされ、替わって19世紀末には東アジアへの侵出に力点を置くようになり、1891年にモスクワとウラジヴォストークを結ぶシベリア鉄道の建設を開始した。それは、極東における日本との対立をもたらし、1904年の日露戦争へと向かい、結果的にロマノフ朝の動揺を招くこととなる。
文学・音楽の高揚と苦悩
19世紀はロシアの文学と音楽が一気に高揚し、文学ではプーシキン、トゥルゲーネフ、ドストエフスキー、トルストイ、チェーホフが活躍し、音楽ではムソログスキー、チャイコフスキー、ボロディンらが登場した。一時期に一定の地域でこれだけの世界的に著名な作家、作品が一斉に登場したのは希有のことである。その背景にはロシアの伝統を守る(スラヴ派)のか、あるいは近代化をめざす(西欧派)のか、という論争を体験した知識人の苦悩があった。改革に絶望した一部の知識人はアナーキズムやテロリズムに向かい、1881年には皇帝アレクサンドル2世がナロードニキの流れをくむテロリストに暗殺された。
ロシア(6) ロシアの帝国主義
農奴解放は一定の社会の近代化をもたらし、資本主義経済への転化をもたらした。しかしフランス資本の援助を受けた脆弱な体質であった。東方への進出は日本との新たな対立を生み出し、日露戦争となるが、戦争中にその矛盾が表面化し、第一次ロシア革命が起こる。
ロシア資本主義の形成
露土戦争後のベルリン会議でバルカン半島方面での南下政策をいったん収める形となったロシアは、再び方向を変えて東アジアでの勢力拡大に転じた。すでにウラジヴォストーク港を拠点に日本海方面、さらに満州から朝鮮半島への侵出の動きを示していたが、さらに東方進出の動脈として1891年にシベリア鉄道の建設を開始した。この鉄道はロシア資本主義の形成にとっても不可欠なものとなったが、フランス資本の援助を受けたものであった。ウラジヴォストークでのシベリア鉄道起工式に参加する途中、1891年、日本を訪問した皇太子ニコライ(後のニコライ2世)が日本人警官に襲われて怪我を負うという大津事件が起こっている。日本国内にロシアの東方侵出を強く警戒する世論が形成されていたためであった。ロシア社会主義の台頭
1870年代のインテリゲンツィアによる「ナロードニキ」運動から始まる。しかし、農奴解放令以降、保守化した農民はただちに革命運動に向かうことはなく、革命運動家は次第に絶望し、ニヒリズム(虚無主義)やテロリズムに走る。1881年には、皇帝アレクサンドル2世が「人民の意志」グループの女性革命家ベロフスカヤらに暗殺される事件が起き、革命運動は厳しく弾圧される。ナロードニキであったプレハーノフは1883年にマルクス主義をロシアに導入、1898年、レーニンなどとロシア社会民主労働党を結成し、社会主義革命をめざした。しかし、革命の路線を巡って、レーニンの指導するボリシェヴィキと、プレハーノフらの指導するメンシェヴィキは鋭く対立し、実質的に分裂してしまう。日露戦争と第一次ロシア革命
ロシアは、1894年に即位したニコライ2世のもとで、封建的な農村の制度や低い生産力、近代工業の未成熟、政治においてはツァーリズムと貴族制度といった古い体制のまま、西欧列強に対抗して帝国主義的な膨張政策を展開した。そのツァーリズム=ロシアのロシアの東アジア侵出の矛先は満州・朝鮮に向けられ、急速に大陸侵出をはかる日本、および満州での鉄道敷設などの利権を守ろうとするイギリスとの緊張を高めることとなった。朝鮮への影響力強める 1894年の日清戦争で清を破った日本は下関条約で清から遼東半島、台湾などを割譲させた。それに対してロシアはドイツ、フランスとともに三国干渉を行い、日本に遼東半島を還付させた。その見返りという形で、1896年6月、露清密約を結んで満州を横断する鉄道である東清鉄道の敷設権を認めさた。また、ロシアが朝鮮に対する影響力を強めると、日本はロシアと結ぶ閔氏を排除しようとして1895年に閔妃暗殺事件を起こし、かえって反日感情が強くなったため、朝鮮の親ロシア派が勢いを強めた。朝鮮国内に反日暴動が起きると、その混乱から保護するという名目で国王高宗をロシア公使館に移し、事実上の幽閉状態に置いた。
中国分割に参加 1898年のヨーロッパ列強による中国分割では、ロシアは旅順・大連の租借を認めさせ、海軍基地など東方進出の重要な足場とした。このような列強の侵略に反発した中国民衆が蜂起し、北京が占領されたことから義和団事件(北清事変)が起きると、ロシアも8ヵ国連合軍に加わって出兵し、北京議定書で軍隊の北京駐留権を得た。ロシアはこのとき満州に出兵し、事変が解決した後も撤兵せず、一気に勢力圏としようという動きを示した。
日露戦争 このようなロシアの東アジアでの侵出は、日本とイギリスを強く刺激した。イラン方面でもロシアと厳しく対立していたイギリスは、1902年1月30日に日英同盟の締結に踏み切った。ロシアと日本の対立は、ついに1904年に日露戦争の勃発となったが、ロシア帝国主義の膨張政策は民衆の犠牲の上で行われていたため、この戦争が第一次ロシア革命を勃発させる要因となった。
日露戦争は日本が旅順・大連を占領し、奉天での陸戦や日本海での海戦での勝利によって優位に進めたが、持久戦は両国の国力を消耗することとなり、アメリカの仲介で講和することとなり、1905年9月、ポーツマス条約を締結した。日本国内では勝利と宣伝され、また国際的にもアジアの新興国日本が、大国ロシアを破ったと受け止められた。しかし実態は痛み分けであり、両国ともこれ以上戦争を続けることは出来ない状況だった。また東アジアにおけるロシアの後退は明確であり、日本が覇権国家として登場し、またアメリカの侵出が顕著になるという戦後の状況の中で、こんどはロシアとイギリスが接近することとなり、両国は1907年に英露協商を結び、イラン・アフガニスタンでの勢力圏分割に合意した。
第一次ロシア革命 このような国内事情を無視した帝国主義政策の矛盾は早くも日露戦争中に爆発した。1905年1月、戦争による食糧不足に抗議したペテルブルクの市民・労働者に対して軍と警察が発砲するという血の日曜日事件をきっかけに、農民と労働者が蜂起してソヴィエトを樹立、第1次ロシア革命が始まった。皇帝はドゥーマ(国会)の開設などを約束して態勢を立て直し、反撃に移って革命運動を弾圧して専制政治を復活させた。
ストルイピンの政治 1906年に内閣を組織したストルイピンは、革命運動を抑えるためにミールの解体を強行し、その一方で再びバルカン方面への進出を企てたが、それは国内の不満を対外進出でそらそうという意図もあった。しかしバルカンではドイツ・オーストリアとの対立を深めて、危機はさらに深まっていった。
ロシア(7) 第一次世界大戦とロシア革命
19世紀末から帝国主義の矛盾が進行し、ロシアも第一次世界大戦の当事国となる。しかし戦争によって国内矛盾はさらに強まり、ついにロシア革命が勃発、社会主義政権が成立してソ連邦の一員としてのロシア共和国となる。
バルカン問題とロシア
日露戦争の敗北によって東アジア進出に頓挫したロシアは、再びバルカン半島方面での勢力拡大へと向かった。スラヴ系民族との連帯をかかげたパン=スラヴ主義を進めようとするロシアに対し、オーストリアはパン=ゲルマン主義を掲げ、またドイツもそれを支援したため、バルカン問題が深刻になった。こうしてドイツ・オーストリアとの対立が明確となったので、ロシアはそれまで中央アジアや東アジアで対立していたイギリスとの提携に転じ(英露協商)、またフランスとも秘密軍事同盟(露仏同盟)を結んだため、英仏露という三国協商(連合国)が形成された。また、日本とは日露戦争から一転して満州の利権を分割する日露協約を締結した。第一次世界大戦とロシア
ニコライ2世のツァーリ政府は帝国主義列強の世界分割協定に加わり、列強間の秘密軍事同盟を締結して勢力均衡を図ったが、一方の独・墺の三国同盟を軸とした陣営との対立は、ついに第一次世界大戦をもたらすこととなった。当時ロシアは労働者のゼネストが起こっており、国内の社会矛盾は深刻であったが、対外戦争で大衆の目を外に向けることでで沈静化を図ろうとした。1914年6月のサライェヴォ事件をうけてオーストリア=ハンガリー帝国がセルビアに宣戦布告すると、ロシアはただちに軍隊に動員をかけ、オーストリアを支援するドイツが動員を非難して最後通牒を発し、ロシアはそれに答えて8月1日にドイツに対しても宣戦布告をおこなった。こうして単なる地域紛争は一気に世界大戦へと拡大した。
しかし、ドイツの東部戦線での戦いではタンネンベルクの戦いで大敗し、ツァーリ政府の無能が明確になる。こうして戦争は長期化する中で、さらに民衆生活を圧迫し、ロシア社会の矛盾を深くして、1917年のペテルブルクの暴動をきっかけにロシア革命が勃発することとなる。
第2次ロシア革命
「第2次ロシア革命」とは、第一次世界大戦中の1917年に勃発した、帝政ロシアのロマノフ朝から、臨時政府の時期を経て、ボリシェヴィキによる社会主義政権の成立に至った一連の革命を言う。その前段階として、1905年の日露戦争のさなかに起こった第1次ロシア革命(単に第一革命ともいう)がおこり、動揺したロマノフ朝の専制政治(ツァーリズム)は懸命に革命勢力を弾圧していたが、第一次世界大戦の長期化はロシア社会の矛盾をさらに先鋭化させ、1917年ロシア暦2月(新暦3月)のペトログラードでの民衆が蜂起してロマノフ朝が倒れ、そこから第2次ロシア革命が急展開することとなった。ロシアの1917年は二度にわたる革命が展開された激動の都市なので、1年の動きをまとめておこう。1917年の動き
二月革命 1917年3月8日(ロシア暦2月23日)、二月革命(三月革命)でロマノフ朝の専制君主制が倒され(1917年3月15日にニコライ2世退位)てブルジョア主導の臨時政府が成立した。一方では革命派は労働者と兵士のソヴィエトを組織し、ロシアは二重権力の状況となった。レーニンの四月テーゼ 4月にレーニンが亡命地のスイスから封印列車で帰国し、1917年4月17日に四月テーゼを提起した。それは臨時政府に反対し、社会主義の段階的実現に向けて、「すべての権力をソヴィエトに」というスローガンととして、革命の方向性を明示し、レーニンの指導性を強めた。
ケレンスキー政権と七月暴動 6月に第1回の全ロシア=ソヴィエト会議が開催されたが、エスエルとメンシェヴィキが多数を占め、戦争継続を維持する臨時政府を支持したため、ボリシェヴィキとの対立は激しくなった。1917年7月に社会革命党(エス=エル)右派のケレンスキーが臨時政府の首相に就任して戦争を継続したことに対し、ボリシェヴィキが労働者の臨時政府反対デモを組織すると、ケレンスキー内閣は武力を行使してボリシェヴィキを弾圧、七月暴動となった。臨時政府はレーニンなど指導者を逮捕しようとしたので、レーニンは難を避けてフィンランドに亡命した。
コルニーロフの反乱 ボリシェヴィキを抑えたケレンスキー内閣であったが、今度は右派のコルニーロフ将軍が帝政復活をめざし反革命の反乱を起こし、危機となった。臨時政府側には反乱を鎮圧する力が無く、やむなくボリシェヴィキの力を借り、ようやくコルニーロフの反乱を鎮圧できた。その結果、ボリシェヴィキの発言力は増大し、レーニンも帰国して主導権を復活させた。
十月革命 ロシア暦10月、レーニンに指導されたボリシェヴィキは一挙に権力奪取を目指して武装蜂起し、ついに臨時政府を倒し、ケレンスキーは女装して国外に逃亡、十月革命(十一月革命)に成功した。ただちに第2回全ロシア=ソヴィエト会議を開催して、ソヴィエトがすべての権力を掌握することを宣言、同時に「平和についての布告」で交戦国すべてに即時講和を呼びかけ、「土地についての布告」で土地公有化の実施を宣言、世界最初の労働者階級が権力を握る社会主義政権が誕生した。狭い意味ではこの十月革命をロシア革命という場合もある。
1918~22年の動き
ボリシェヴィキ独裁の樹立 1918年1月、憲法制定議会が招集されたが、ボリシェヴィキはそこでは多数を占めることができなかった。議会制民主主義をブルジョワ権力の擬制であるとしたレーニンは実力で憲法制定議会を解散させ、ソヴィエトを最高機関とする労働者・兵士の政権を樹立し、ボリシェヴィキ以外の党派をほぼ追放し、ボリシェヴィキ独裁(プロレタリア独裁)体制を作り上げた。ロシア=ソヴィエト連邦社会主義共和国 1918年3月、ボリシェヴィキ独裁政権は、まず直面する課題である世界大戦でのドイツとの講和をブレスト=リトフスク条約で実現した。ロシアは大きな領土的譲歩を強いられ、また内部にもエスエル左派など講和に反対する勢力も強かったが、最終的にレーニンは革命を守るために講和に踏み切った。こうして国内の革命遂行に集中できる状況を作り出し、国内の封建的な社会関係の一掃に乗り出した。同年3月にボリシェヴィキは「ロシア共産党」と改称し、さらに首都をモスクワに移した。7月には憲法を制定してロシア=ソヴィエト連邦社会主義共和国を正式に発足させた。
内戦と干渉軍 それに対して反革命勢力は各地に反革命政権を樹立して内戦を仕掛けてきた。主な反革命政権には南ロシアでのデキーニン軍、シベリアでのコルチャーク軍、バルト沿岸でのユデーニッチ軍などがあり、これらはイギリスなどの諸国の援助を受けて革命政権打倒の軍事行動を展開した。これら白軍といわれた反革命軍との戦いのために、主としてトロツキーが中心となって赤軍といわれる革命軍が編成され、激しい内戦が戦われた。さらに資本主義(帝国主義)国のイギリス、フランス、アメリカ、日本などは直接的に対ソ干渉戦争を仕掛けてきた。1918年8月からのチェコ兵捕虜の救出を口実とした日本・アメリカを主力とするシベリア出兵は反革命軍と結びつき、赤軍・パルチザンと戦った。しかし反革命軍、干渉軍もロシアの民衆の支持を受けることはできず、革命軍は苦戦しながらも1920年末頃までにはほとんど撃退することに成功した。さらに1920年4月、ポーランドとの間で領土問題が発生し、ソヴィエト=ポーランド戦争が勃発し、ロシアはその領土の一部を放棄した。
戦時共産主義 1918年から1921年までの間、レーニンの指導するソヴィエト=ロシアのボリシェヴィキ政権は、「戦時共産主義」といわれる強制的な食料供給体制によって反革命軍や外国の干渉軍との戦いから革命を防衛しようとした。それは農民生活を犠牲にしながら革命政権の維持を図ろうとするもので、農民に対する食料の強制的提供を義務づけ、都市の食糧不足を解決しようとした。農民は強く反発し、反革命軍と結びつくこともあったが、ボリシェヴィキ政権はチェカという取締機関を設けて、それらの動きを反革命として押さえ込んだ。
コミンテルンの創設 1919年3月、激しい内戦と干渉戦争との戦いを続けながら、レーニンは革命成功の道は、ロシア以外でも労働者が蜂起し、革命を起こすことにあると考え、コミンテルンを設け、国際共産主義運動を追求しようとした。しかし、期待したドイツやハンガリーでの革命は次々と失敗し、レーニンはその面でも方針の転換に迫られることとなる。
ネップへの転換 戦時共産主義の矛盾は1921年3月のクロンシュタット反乱として現れた。レーニンは一連の反革命戦争、干渉戦争に勝利した後に大きな路線転換を決断し、新経済政策(ネップ)を打ち出した。これは一定程度の資本主義経済への復帰を認めるもので、それによって経済体制を立て直そうとしたものであった。そのようなボリシェヴィキ政権の変化は西欧との関係を回復させ、1921年にはまず英ソ通商協定が成立、さらに22年にはラパロ条約でドイツとの国交を回復し、国際的な認知を受けることとなった。
ソ連邦の成立
1922年12月30日にソヴィエト社会主義共和国連邦(ソ連邦、ソ連)が成立した。1917年の十月革命によって成立した新しい国家は、1922年の「ソヴィエト連邦」の成立までは一般に「ソヴィエト=ロシア(あるいはソヴィエト共和国)」という。ソヴィエト社会主義共和国連邦を構成したのは、1922年にはロシア=ソヴィエト連邦社会主義共和国、ベラルーシ、ウクライナ、ザカフカースの4国であった。ロシア=ソヴィエト連邦社会主義共和国(ロシア共和国)は、ソ連邦の全面積の4分の3、全人口の半分、資源の8割方を占める最大の連邦構成国であった。首都のモスクワ、大都市レニングラード(現サンクトペテルブルク)を含む、旧ロシア帝国以来のスラヴ人を主体とした国家であったが、共和国内の北カフカス地方や中央アジア、シベリアには、多くの自治国と自治区を含んでいた。
ロシア革命のもたらしたもの
このように、わずか一年の間に、封建社会の上に成り立っていた帝政を打倒し、一挙に社会主義権力の樹立にまで突き進んだのがロシア革命であったが、マルクス主義では資本主義社会の矛盾が必然的に社会主義を導くと考えられていたので、遅れたロシア社会が資本主義社会の成熟を待たずに社会主義化することに対し、当初から疑問視する考えもあった。そのような公式的な理解を超えて革命が進展したのであり、なによりも平和と農民の解放が実現したことは成果であったが、その反面、ソヴィエトを基盤とした社会主義国家においては議会政治や市民的自由はブルジョア的な無用物として排除された。レーニンはプロレタリア独裁は過渡的な国家形態であると言ったが、一党独裁が強化されるなかで党官僚制は肥大化、硬直化し、1925年以降のスターリン体制の独裁を生み出していくこととなる。スターリン独裁は社会主義の必然だったのか、それとも行き過ぎた変種であったのか。1991年、ソ連邦が解体し、ロシアは社会主義を放棄することとなったが、改めてロシア革命が目指したものは何だったのか、そこから生まれた「ソ連」がなぜ解体したのか、考えておく必要があろう。
ロシア(8) スターリン体制と第二次世界大戦
ロシアは1922年からソヴィエト連邦を構成する社会主義共和国となった。これ以降、1991年のソ連邦の解体までは、ロシア史はソ連の歴史と一体として歩むこととなる。
民族主義を克服して社会主義国家の建設に向かったソ連ではロシア人以外の人々も新国家の建設に参加したわけであったが、ソ連邦の構成原理は同時に「民族」ごとの共和国を認めざるを得なかった。インターナショナリズムに内包されたナショナリズムという矛盾はソ連の抱える問題として続き、結局は解決しきれないままにソ連は崩壊し、現代の旧ソ連圏諸国家間の対立へとつながっている。
スターリン体制
ソ連は1929年の世界恐慌に巻き込まれることなく社会主義経済体制を建設したが、その間レーニンの後継者となったスターリン(ロシア人ではなくグルジア人であった)が一国社会主義論をかかげ、世界革命論を主張したトロツキーなど反対派を排除、粛清して独裁体制を作りあげ、五カ年計画による社会主義建設を進めた。それは著しく工業重視に傾き、国内では食糧不足などの問題を生み出していたが、スターリン体制の独裁のもとで言論は封殺され、社会は次第に停滞していった。第二次世界大戦とロシア
社会主義国家ソ連の出現は、資本主義国家内の社会主義者や労働運動に大きな刺激となるとともに、国家権力と資本家階級はプロレタリア革命の波及という恐怖心を与えた。イタリアやドイツにおけるファシズムの台頭はそのような恐怖心を煽った政治運動であり、1930年代初頭までに大きな勢力となった。新たな領土的野心をあからさまにするファシズム国家に対し、イギリス・フランスが当初は融和的な姿勢を採ったのは、むしろ社会主義国ソ連の強大化をファシズム国家が抑えてくれるだろうという期待があったからと思われる。スターリンはミュンヘン会談での英仏の宥和政策に反発し、1939年8月23日、ヒトラーとの間で独ソ不可侵条約を締結し、その
しかし1941年6月、ヒトラーは不可侵条約を破棄してソ連に侵攻、独ソ戦が始まると、ソ連は一転してドイツとの「大祖国戦争」を多大な犠牲を払って戦うこととなった。同時にドイツが敵国となったことによりソ連は、アメリカ・イギリスとともに連合国の一員となった。日本とは中立条約を結んでいたが、米英の要請もあり、大戦終結直前に参戦、満州・千島に侵攻した。スターリン=ソ連はドイツ・日本との戦いに勝利したことによって、戦後の国際社会では世界の大国としての立場を確保し、戦後のアメリカとの対立に備えることができた。 → ソ連と第二次世界大戦
大戦中に発足した国際連合においても安全保障理事会の常任理事国となって、大国としての責任を持つ国家となった。
冷戦
第二次世界大戦後、ソ連は東ヨーロッパ諸国への影響力を強め、社会主義国家建設を進めていったため、資本主義陣営のアメリカ・イギリスは強く警戒することとなり、東西冷戦時代に突入した。ソ連はアメリカと対峙する軍事大国となり、核兵器開発や宇宙開発を競ったが、それは次第に経済・財政を圧迫するようになった。スターリン批判
1953年3月、スターリンが死去、その独裁体制の矛盾が表面化し、1956年、フルシチョフ政権によるスターリン批判を機にアメリカを主とする資本主義陣営との平和共存を模索する路線に転じた。その反面、社会主義国中国との関係が悪化し、中ソ対立が始まり、一時は武力衝突までおこった。その間、官僚的な共産党独裁体制のもと経済停滞が深刻となっていった。ロシアの停滞
1962年10月のキューバ危機の不手際などの責任をとらされて1964年10月にフルシチョフは解任され、その後は1982年まで、ブレジネフ体制と言われる時代が続いたが、その間、ソ連社会主義はますます官僚的、権威主義的になって行った。その中で言論や芸術の自由は制限され、長い停滞が続くことになった。一部の共産党幹部(ノーメンクラツーラ)が利権に群がる構造は抜き差しならない社会の閉塞状況を民衆に感じさせていった。ゴルバチョフの登場
長い停滞の時期を経て1985年に登場したゴルバチョフ政権は、ペレストロイカといわれた改革を進め、東欧社会主義圏の変動を呼び起こし、1989年には冷戦の終結をアメリカ大統領ブッシュとともに宣言するに至った。ゴルバチョフの登場は、ソ連社会でのグラスノスチをはじめとする改革を実現し、民主化を大きく進めたが、それは社会主義を放棄することとソ連邦を解体することを最初から目指したものではなかった。あくまでソ連の枠内での改革をめざしたが、そこで点火された火は、ソ連という連邦国家の中のロシア共和国(厳密にはまだ社会主義共和国であるが)との関係という最も国家の根源に関わる問題を焙りだすこととなった。
ソ連とロシアの関係 ロシア共和国はソ連を構成する一共和国であるが、外から見ていると「ソ連=ロシア」の一体として捉えられてきた。ソ連の解体という激変は、その関係を正しく理解していないと判り辛いものであった。ソ連とロシアの関係、ロシアのナショナリズムの台頭について、次の文が参考になろう。
(引用)ソ連邦におけるロシアの位置は、中心的な存在でありながら、同時に、独自の被害者意識をもつという逆説があった。ひとつには、バルト三国に比べれば生活水準が低く、文化・教育度も低いことへの不満と劣等感があり、また中央アジアなどの後進地域にたいしては、ロシアが損をしながら援助しているという被害者意識をもっていた。こうした背景から、連邦にたいしてロシア固有の利害を主張するロシア・ナショナリズムが登場した。和田春樹編『ロシア史』新版世界各国史22 山川出版社 p.409>
ロシア共和国の主権宣言
ソ連邦末期の1990年には、ソ連共産党のゴルバチョフは民主化を進めていたが、ソ連邦だけは維持しようとした。それに対してロシア共和国で台頭したエリツィンは、ロシアの主権国家としての自立を主張する「民主派」を主導し、鋭く対立するようになった。5月末にロシア共和国の人民代議員大会で、エリツィンが議長に選出されると、同6月12日、ロシア共和国人民代議員大会はほぼ満場一致で「主権宣言」を採択した。これによってなおもソ連邦を維持しようとする大統領ゴルバチョフが統治するソ連邦と、主権を宣言したエリツィンの主導するロシア共和国という二重国家の図式となり、混乱は深刻となった。ロシアに続いてソ連を構成する共和国でも主権宣言が相次いだ。しかし、そのロシア共和国の内部にも多数の民族地域があり、ソヴィエト連邦を苦しめたロシア自身が、内部の同種の問題に苦しめられるという「入れ子構造」状況があった。この段階では、ロシア自身がそのような内部問題を抱えていたため、一気にソ連を解体せよ、という主張にはならず、依然として併存状態が続いた。和田春樹編『同上書』p.410>
ところが、ソ連で1991年8月、ソ連共産党の保守派クーデタが起こったことで状況が一気に進んだ。保守派というのは連邦制の維持を主張する一部の古参幹部らのことで、ゴルバチョフがヤルタで夏期休暇中であったことを利用して政権を奪取しようとするものであったが、それに立ちはだかったのがモスクワのロシア共和国を握っていたエリツィンであった。エリツィンの活躍でクーデタが鎮圧されたことにより、ゴルバチョフからエリツィンへの政権移動が決定的になった。1991年末にゴルバチョフはソ連の解体の宣言に追いこまれることとなった。
「ロシアの日」 ロシア共和国は、ソ連が解体した後の1991年末に、内部の諸民族に自治共和国の地位を与えることで「ロシア連邦」とすることで内部の民族問題を一応克服した。それが現在の「ロシア」であるが、主権国家であることを宣言したこの1990年6月12日は、現在は「ロシアの日」として祝われている。
ロシア(9) ロシア連邦
1991年、ソ連邦が解体し、旧ソ連のロシア共和国が改称した。国連議席などはソ連を継承する。独立国家共同体(CIS)に属するが、冷戦終結後、二大国の相手国アメリカとは関係が悪化している。エリツィンは民主化を推進したが経済政策に失敗して退陣し、代わったプーチンのもとで豊富な石油資源などを基盤に経済の再建を進め、資本主義化を推進した。しかしその間に貧富の差が拡大し、プーチンの強権的な政治にも反発が強まっている。
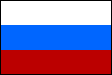
同じロシア語を用い、ロシア国家の起源の地であるキエフを含むウクライナの分離はロシアにとって大きな痛手であり、国内反対派も多かったが、旧ソ連の国連安保理の地位の継承と核兵器はロシアが継承することで、その分離を承認した。バルト三国を除く旧ソ連邦を構成していた諸国とは独立国家共同体を組織しているが、国境問題や人種問題で対立を含んでおり、結束は弱くなっている。
ロシア連邦国旗
国旗は旧ロシア帝国時代の白、青、赤の三色旗を復活させた。スラヴ系国家はロシアに倣ってこのような三色旗が多い。白は高貴、神、ベラルーシ(白ロシア)を、青は栄誉、皇帝、ウクライナ(小ロシア)を、赤は勇気、人民、ロシア(大ロシア)を表すとされる。資本主義導入の問題点
ロシア連邦はエリツィン大統領の下で、ソ連時代の社会主義体制は全く放棄し、資本主義経済と議会制民主主義国家として新たに出発したが、その急速な資本主義化は様々な矛盾を内包し、必ずしも順調に進んでいるとは言えず、特に新興企業の急激な成長の反面、インフレと社会保障などの切り捨てによって格差の拡大が進み、ソ連や共産党政治の復活を望む声も出ている。外交では1993年1月アメリカのブッシュ(父)大統領との間でSTART・Ⅱに調印した。その後も両国は友好関係を継続しているが、旧東欧諸国が次々とNATOやEUに加盟していくことに対してロシアは警戒心を持っており、またアメリカはロシアの人権問題を批判しており、時として関係が冷却することもある。
エリツィン政権の動揺
1993年にはエリツィン改革に反対派が最高会議ビルに立てこもるという事件が起き、エリツィンは武力を行使して反対派を排除した。同年12月の議会選挙では旧共産党勢力も台頭、政権運営は困難となった。また最大の問題は、ロシア連邦を構成する多数の共和国に連邦からの分離を求める民族運動が起こっていることで、エリツィン政権は強圧的な態度でそれらを抑圧している。特に1994年から激化したチェチェン紛争は独立派と半独立派の内戦が続き、独立派のテロをロシア軍が報復するという泥沼化の様相を呈している。エリツィンからプーチンへ
エリツィンは1996年に、決選投票でようやく勝利して大統領に再任されたが、それは民営化などの急速な資本主義化で台頭した富裕層や金融エリートと言われる人々の運動が有効だったと言われている。それでも1997年からは先進国首脳会議のサミットに参加し、G8のひとつに加えられた。しかし、エリツィンは建康不安から1999年に引退、2000年5月にプーチンが就任し、エリツィン路線の継承を鮮明にした。プーチンの膨張主義
プーチンは就任早々、ロシア連邦内のチェチェン共和国の分離運動を厳しく弾圧したほか、2008年8月、グルジア内の南オセチアが独立宣言をしたことからグルジア紛争が始まり、グルジア(ジョージア)内の親露派の南オセチアとアブハジアの分離運動を支援するために軍隊を派遣した。プーチンは2008年から大統領の三選を禁止する憲法に従い、大統領を辞したが、次期大統領には腹心のメドベージェフを指名、自らは首相として実権を保持した。そして、2012年には大統領の再任禁止は憲法に無いことから再び立候補して当選し、二期目の大統領として就任した。
クリミア併合と危機 2014年にはウクライナ領のクリミア半島で、ロシア系住民のロシアへの併合要求が高まるとそれを承認し、併合を強行した。さらにウクライナ東部のロシア系住民の分離独立も背後から支援するなど、膨張主義的な姿勢が目立っている。ウクライナに対しては、そのEUへの加盟に対して牽制する意味が強い。
ウクライナ側は強く反発し、クリミア危機といわれる衝突が始まった。また国際社会も強引なクリミア併合、さらにウクライナ東部への介入などを非難し、先進国首脳会議サミットへのロシアの参加を拒否した。ロシアはこのようにその強権的な体質から国際的な孤立を招いており、その強硬姿勢は日本との北方領土問題交渉にも影を落としている。
